
ちょっと面白いサイトを発見しました。
「~原」を「ばる」「はる」と読む地名
その方法も素晴らしい。
(1)日本語変換ソフトのATOK15の辞書から「固有地名」の品詞を持つ単語を辞書ユーティリティーを使って抜き出す。
(2)(1)の単語(約6万語)の中から、表記として「~原」、読みとして「~ばる・はる」を持つ単語を抜き出す。
(3)(2)で抜き出された地名が、どこの都道府県に属するかを、インターネットの検索エンジンで、表記と読みをANDで検索して調べる。
(4)(3)の結果、場所がわかった地名の正確な場所をインターネットの地図検索サービスで調べる。
その結果
全国で99箇所あり、そのうち何と97箇所が九州・沖縄であった。
最後の文字が原 に絞り込めば、九州のみです。
九州の分布地図をみると、弥生時代の遺跡、鉄器の分布に一致するのです。
糸島・博多、甘木、宇田、日向などです。
しかし、思いついた地名で 関ケ原(せきがはら)があった。
全て「ばる」と発音しますので、漢字が使えるようになった6世紀以後に自らの地名を付けたのでしょう。
氏姓制度で各地が一斉に名前を付ける時期があったと思いますが
しかし、何故?
・九州の遺跡のある地域に集中するのか?
・原(はら)を「ばる」と発音するのか?
・九州以外では、何故使われなかったのか?
日本神話に登場する 〇〇原の国と云えば、天上界で天照など神様が生活する「高天原」
こちらは、平安時代ですので 大和言葉で 「はら」と発音します。
原 の文字でイメージするのは 原っぱで、草原ですが、他に何か深い意味がありそうです。
原の漢字の成り立ちを調べてみると
「岩の穴から湧き出す泉」 源(みなもと)です。
高天原 も 高い所にある天上界の源
では、九州の〇〇原の地名が出来た時代は、「古事記」「日本書紀」で天照を主神とする
神道体制より、以前であるか?以後であるのか?
多分、九州の地名が先です。
次に大和朝廷は神道制度を作り始めた。
近畿、中国地方などで 原 と云う漢字を使う地名を禁止した。
九州で既にあった〇〇原の地名は 「ばる」に変更させた。
原という漢字は、早くから倭国に伝わった漢字のひとつ
みなもと と云う重い意味を含んでいる。
他にも 天、和、命など同じではないでしょうか。
大和朝廷のみが使える漢字にした。
ひょっとしたら 甘木市 も 天木市 を希望したかもしれませんね。
「~原」を「ばる」「はる」と読む地名
その方法も素晴らしい。
(1)日本語変換ソフトのATOK15の辞書から「固有地名」の品詞を持つ単語を辞書ユーティリティーを使って抜き出す。
(2)(1)の単語(約6万語)の中から、表記として「~原」、読みとして「~ばる・はる」を持つ単語を抜き出す。
(3)(2)で抜き出された地名が、どこの都道府県に属するかを、インターネットの検索エンジンで、表記と読みをANDで検索して調べる。
(4)(3)の結果、場所がわかった地名の正確な場所をインターネットの地図検索サービスで調べる。
その結果
全国で99箇所あり、そのうち何と97箇所が九州・沖縄であった。
最後の文字が原 に絞り込めば、九州のみです。
九州の分布地図をみると、弥生時代の遺跡、鉄器の分布に一致するのです。
糸島・博多、甘木、宇田、日向などです。
しかし、思いついた地名で 関ケ原(せきがはら)があった。
全て「ばる」と発音しますので、漢字が使えるようになった6世紀以後に自らの地名を付けたのでしょう。
氏姓制度で各地が一斉に名前を付ける時期があったと思いますが
しかし、何故?
・九州の遺跡のある地域に集中するのか?
・原(はら)を「ばる」と発音するのか?
・九州以外では、何故使われなかったのか?
日本神話に登場する 〇〇原の国と云えば、天上界で天照など神様が生活する「高天原」
こちらは、平安時代ですので 大和言葉で 「はら」と発音します。
原 の文字でイメージするのは 原っぱで、草原ですが、他に何か深い意味がありそうです。
原の漢字の成り立ちを調べてみると
「岩の穴から湧き出す泉」 源(みなもと)です。
高天原 も 高い所にある天上界の源
では、九州の〇〇原の地名が出来た時代は、「古事記」「日本書紀」で天照を主神とする
神道体制より、以前であるか?以後であるのか?
多分、九州の地名が先です。
次に大和朝廷は神道制度を作り始めた。
近畿、中国地方などで 原 と云う漢字を使う地名を禁止した。
九州で既にあった〇〇原の地名は 「ばる」に変更させた。
原という漢字は、早くから倭国に伝わった漢字のひとつ
みなもと と云う重い意味を含んでいる。
他にも 天、和、命など同じではないでしょうか。
大和朝廷のみが使える漢字にした。
ひょっとしたら 甘木市 も 天木市 を希望したかもしれませんね。










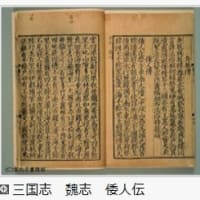
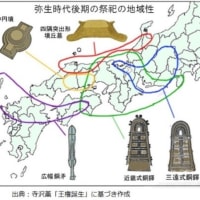


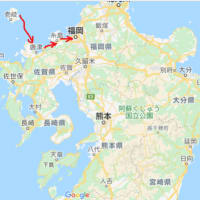

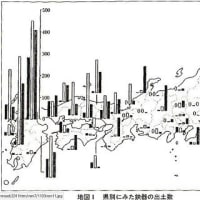


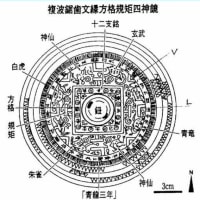
私は宮崎のアワキガハラで育ちました。
江田神社の氏子です。
宮崎にはニュウタバルや 原=バルという地名が多数あります。西都原=サイトバル 等
古事記に出てくる地名がそのまま残った不思議な所です。
宮崎神宮は地元民は「神武さん」と言います。