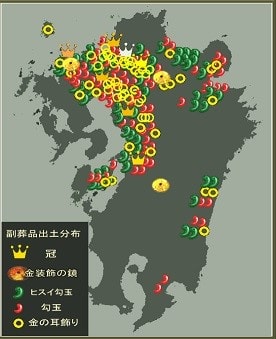「魏志倭人伝」に二度登場する奴国の謎 に続きます。

邪馬台国まで1万2千里
博多湾の奴国まで合計1万6百里
博多湾から南へ残り1400里で邪馬台国
そのどこかに卑弥呼の宮殿(千人の女性と暮らし、周囲が塀でかこまれ、武人は守衛)
その間(南北間)に21国
邪馬台国の南に狗奴国
と云う位置関係です。
の南に狗奴国(くなこく)がある。男子を王としている。
その官に狗古智卑狗がある。女王に属していない。
と最初に紹介されています。
最後の方に
倭の女王、卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼とは、まえまえから不和であった。
と王名が
狗奴国 男王卑弥弓呼、官 狗古智卑狗
邪馬台国 女王 卑弥呼、官 伊支馬(イシマ)
副 弥馬升(ミマシ)弥馬獲升(ミマカシ)奴佳鞮(ナカデ)
幾つかの疑問
1、卑弥呼と卑弥弓呼 名前が似ている。
2、奴国と狗奴国 名前が似ている。
3、狗古智卑狗 の 卑狗 は対馬国 一支国の官の名前
4、30の国がありながら敵対するする国同士が隣り合う。
考えられる事
元々、狗奴国があった。
祈祷師の女性が倭国の代表に選ばれた。
狗奴国の北部が邪馬台国となった、
男王の一族であった卑弥弓呼(彦)は女性の祈祷師卑弥呼を許せない。
対馬国 一支国の官は〇〇卑狗
副に卑奴母離(日守)も多く登場します。
狗古智卑狗の狗古智が名前で卑狗が官の呼び名
邪馬台国と投馬国の官、副の名前が特徴的です。
最初は祈祷して推薦された卑弥呼ですが
権力が増すとともに政治や外交に力を入れます。
ついに、親魏倭王の金印を得るまでに・・・
邪馬台国 VS 狗奴国 の戦争に発展
戦況は、なんと狗奴国優勢
卑弥呼は魏国に応援を依頼する状況まで・・・
30国をまとめる卑弥呼ですが、伊都国、奴国は
狗奴国の卑弥弓呼討伐には加勢しなかったのでしょう。
卑弥呼VS卑弥弓呼は一族の内乱だったからです。
卑弥呼死後は
卑弥弓呼VS伊都国、奴国でもめました。
たまたま、大陸から来ていた張政らが台与を支持する事で
もめ事がおさまった。

邪馬台国まで1万2千里
博多湾の奴国まで合計1万6百里
博多湾から南へ残り1400里で邪馬台国
そのどこかに卑弥呼の宮殿(千人の女性と暮らし、周囲が塀でかこまれ、武人は守衛)
その間(南北間)に21国
邪馬台国の南に狗奴国
と云う位置関係です。
の南に狗奴国(くなこく)がある。男子を王としている。
その官に狗古智卑狗がある。女王に属していない。
と最初に紹介されています。
最後の方に
倭の女王、卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼とは、まえまえから不和であった。
と王名が
狗奴国 男王卑弥弓呼、官 狗古智卑狗
邪馬台国 女王 卑弥呼、官 伊支馬(イシマ)
副 弥馬升(ミマシ)弥馬獲升(ミマカシ)奴佳鞮(ナカデ)
幾つかの疑問
1、卑弥呼と卑弥弓呼 名前が似ている。
2、奴国と狗奴国 名前が似ている。
3、狗古智卑狗 の 卑狗 は対馬国 一支国の官の名前
4、30の国がありながら敵対するする国同士が隣り合う。
考えられる事
元々、狗奴国があった。
祈祷師の女性が倭国の代表に選ばれた。
狗奴国の北部が邪馬台国となった、
男王の一族であった卑弥弓呼(彦)は女性の祈祷師卑弥呼を許せない。
対馬国 一支国の官は〇〇卑狗
副に卑奴母離(日守)も多く登場します。
狗古智卑狗の狗古智が名前で卑狗が官の呼び名
邪馬台国と投馬国の官、副の名前が特徴的です。
最初は祈祷して推薦された卑弥呼ですが
権力が増すとともに政治や外交に力を入れます。
ついに、親魏倭王の金印を得るまでに・・・
邪馬台国 VS 狗奴国 の戦争に発展
戦況は、なんと狗奴国優勢
卑弥呼は魏国に応援を依頼する状況まで・・・
30国をまとめる卑弥呼ですが、伊都国、奴国は
狗奴国の卑弥弓呼討伐には加勢しなかったのでしょう。
卑弥呼VS卑弥弓呼は一族の内乱だったからです。
卑弥呼死後は
卑弥弓呼VS伊都国、奴国でもめました。
たまたま、大陸から来ていた張政らが台与を支持する事で
もめ事がおさまった。