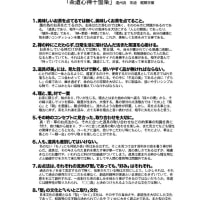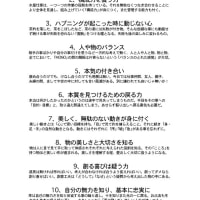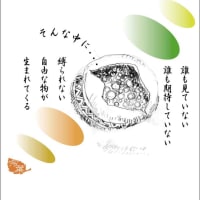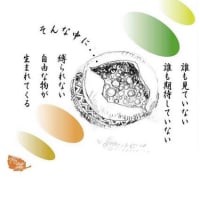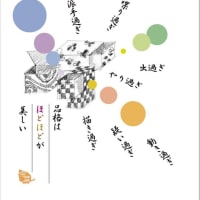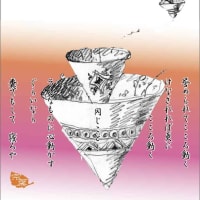●掛け物-1
利休居士が「南方録」に「掛物より第一の道具はなし、客・亭主共ニ茶の湯三昧の一心得道の物也、」おっしゃている様に、一席に於いて最重要ポイントであり、その日のテーマを決定するものが「掛物」であります。
極端な言い方ですが、このお茶で使う掛物は使用方法によって大きく分けて二つあり、それは「待合掛」にすべき物と「本席」で使える物に大別してよいでしょう。端的にいって今簡単に手に入る「絵」または「絵のはいいっている物(画讃物)」は一部を除いて「待合掛」といって「本席」すなわち茶席には不向きな物とするのが基本です。
そこに書かれている物はどんな掛物ですか、しっかり目的に合った意味合いの分かるものですか。ちょっとした知識で「恥」をかかず、お客に心遣いの出来る「茶の湯で使える掛物」を選ぶことが出来るようになるかと思います。
「むかしは絵を掛けて茶の湯をしていた」とおしゃる方、よくよく当時の会記(カイキ、茶会の道具を記録した物)をご覧下さい。「牧谿」「徐煕」「徽宗」などなど唐絵(カラエ、中国の宋から元時代が中心の絵画)あるいは禅機画といわれる物がほとんど、石州三百箇条に「台子には絵の…」といっているのも、これは全て唐絵、禅機画のことと考えるべきでしょう。
禅院での茶の湯には中国高僧の禅語を掛けることが多かったと思われ、一休から珠光へと伝わる「圓悟の墨跡」をはじめとして「無準師範」「虚堂智愚」「密庵咸傑」「古林清茂(茂古林)」らの「宋」「元」の中国僧、「兀庵普寧」「蘭渓道隆(隆蘭渓)」「一山一寧(寧一山)」など中国からの来日僧、「南浦紹明(大應國師)」「宗峰妙超(大燈國師)」「夢窓国師」「一休宗純」等日本の禅僧の物などが用いられていますが、「一行書」は一山一寧や兀庵普寧、夢窓国師、一休宗純などに散見する程度で「法語」「偈頌」がほとんどです。ただ、一行書は殊に一休が衆生のため難解な法語を示すより、その中の一行取りだし解くほうが容易であると考えよく用いられたと考えられますし後の茶の湯に大きな影響を与えます。一休の「諸悪莫作」「衆善奉行」(悪いことはするな、良いことをしなさいと言う意味)の一行書はあまりにも有名です。
ほかには字数の少ない物は「授号」「額字」という名前に関するもであったりします。また、「遺偈(ゆいげ、禅僧の遺言)」「尺牘(せきとく、禅僧の手紙)」「送別の語」などがあります。先の南方録の続きには「墨跡を第一とす」とあります。この時代までの墨跡はこれら、宋、元の中国僧、鎌倉、室町初期の禅僧の物を指しました。
ところが変革の人、利休が自らの師「春屋宗園(大徳寺111世)」の一行書を掛けるという事をします。在世の和尚の掛け物を掛けると言う事はそれまでになく同時代の「古渓宗陳(117世)」等から盛んになり茶の湯に掛ける為にしたためられるようになります。
万葉集や古今和歌集に始まる「古筆」は勅撰や私撰の和歌集を能筆かが書き留めた巻物、帖などを分断して掛け物とし鑑賞する物で「古筆切」と呼ぶのは分断した事による名称です。「寸松庵色紙」「継色紙」「八幡切」「石山切」「高野切」等があります。古筆切の書かれた年代としては10世紀から14世紀の所産であり、おいそれとは入手はおろか茶席で見かけることも稀でしょう。
「懐紙」はこの場合皆さんが茶席に持っていく物ではなく、文字通り懐中した日用の紙に、詩や歌を書き留め後に掛け物となった物です。藤原佐里の「詩懐紙」に始まり後鳥羽上皇の頃の「熊野懐紙」は高く評価されます。「懐紙」が「古筆切」より身近な気がするのは江戸時代に入り、作者として各歴代天皇の「御宸翰」をはじめ公家衆、更に僧侶や茶匠、数寄者にまでその範囲を広げるからなのです。紹鴎が「小倉色紙」を掛け利休もそれを模していますし、「熊野懐紙」に細川三斎が箱書きもしています。遠州は「寸松庵色紙」を盛んに用いています。
「消息」とは手紙のことですが、茶掛けに用いる場合、筆者としてまず「利休」を嚆矢としあとは尊敬に値する茶人であること条件で、内容としては茶に関する記述があり、和歌や俳句など入った物は喜ばれます。
「色紙」「短冊」も掛け物として用いられる物は「懐紙」などと同じ背景による物です、これらは「本席」より「待合掛」として真価を発揮する物が多いようです。
では何を掛けたら良いのか?というと、最初に求めるのであれば「禅語」といったところが茶席には無難です。
●掛け物-2
態度と申し上げたのは、席に入り先ず一番最初亭主より先に客が頭を下げ挨拶をする対象が掛物であります。これは単に「文字を鑑賞」するのではなく、語句を書かれた方そのものを軸を通して人格化し、本人を目の前にした気持ちで「挨拶」をする、という意味があります。
そういう訳で書いた人が「万人」とはいいませんが尊敬に値する人であることが大事なのです、単に「幾らで買った価値のある軸」なのではないのです。
よく「書」を嗜む方が、自分の書いた物、あるいは身内の書いた物を表具して人を招き、席に掛けるといったことを耳にします。しかしこれは「私に(身内に)頭を下げよ、尊敬しろ」と暗にいっているのも同じ事で甚だ不敬な事と言わなければなりません。「歌切」とは意味を異にします。
同じ様にコピーされた物、複製の軸を掛ける事、これっもやはり「勉強の為のお稽古」以外は避けなければなりません。コピーという物は、たとえどんなに有名な軸であってもまた、限定版であっても、コピーに人格はありません。ただしコピー技術の素晴らしさ、日本の技術革新に頭を下げさせたい方はどうぞご遠慮なく。
どんな方が書いた物にするか、あるいは書いていただくか、と言うことになります。とにかく「古いような字の書いた物があるから」といって掛けられる方もおられるようですが、前述したように人格を掛ける、といった意味もありますし、こと茶道に関する事ですから、茶道を「道」として導かれる方」「茶道を正しくお伝えになる方」などが、最もふさわしいように思われます。
茶の湯の礼法というのは元々中国の禅院で行われていた茶礼を道具と共にわが国に持ち込んだのが始まりとされていますし、侘び茶の祖ともいわれる村田珠光が、大徳寺一休禅師に参禅し、印可を受けるに当たり「圓語の墨跡」を賜り、これを掛け茶の湯をした、といったところから茶の湯と墨跡の関係が生まれたと考えられています。
その後茶の湯を志す者、茶の宗匠はことごとく大徳寺に参禅する事を慣わしとして、今に至っているのです。最初から「墨跡」を望むのも結構ですがまずは入門編として、たとえ末寺であっても大徳寺系のお寺を第一とし、次に同じ臨済派系の「妙心寺」や京都五山など茶の湯に関係の深い寺の物を掛けるとよいでしよう。
また後者である茶の宗匠方といえば、侘茶の祖「村田珠光」利休の師「武野紹鴎」茶聖「千利休」「利休七哲」「小堀遠州」「片桐石州」「元伯宗旦」「宗旦四天王」など、これらのものはまず入手はしにくい部類でしょう。時代を下がり、各歴代お家元や名だたる宗匠、数奇者などの物もやはり同様でしょう。現在のお家元や御先代のお軸ならば比較的手には入りやすいかとは思いますが、なかなか高価なものである事はいなめません。
ただ、「御家元の軸」があるからと言ってそれが決して頂点ではありません。歴代の御家元、宗匠、またそれらの方々が「師」として参禅された「禅僧」の方々の物、そういった物にこそ本来の伝統を背負った茶の湯の重みが出ることを忘れてはいけないと思います。(例えば濃茶の席など)そういった禅僧の書かれた「墨跡」であれば流儀を越えて尊敬に値する「茶の掛け物」ともいえるのではないでしょうか。
まずもって「大徳寺系の老師か和尚」のものといったところが恥を掻かずに済む線といえ、人格面からいっても無難なのではないでしょうか。
次に一番身近な大徳寺系の軸の落款や署名の見方を説明いたしましょう。大徳寺は臨済宗大徳寺派大本山であり山号を「龍宝山」といい、署名の仕方としては「現大徳」とあるのは管長を現わしますが、管長制になったのは明治にはいってからで、現在第十四代目の管長を勤められる福富雪底老師は新潟県西蒲原郡潟東村のご出身と伺っております。各塔頭のご住職はほとんど「紫野」「龍宝」を使われます。紫野は大徳寺のある所の地名で、龍宝は山号です。
一番多いのは「前大徳」で現代では末寺の住職に与えられる一種の位、称号、資格のようなものと考えるのが無難でしょう。大徳寺の僧侶の位には再住位・前住位・住持位・・・以下八位までありますが、この内「前住位」に当たるものです。この位を受けると、本山大徳寺にて一日だけ「大徳寺住職」になる「改衣式」を行い、方丈(導師)という役をして本尊と開山をはじめ各祖師に報告の法要をし一山の各住職に披露します。それ以後に、「前大徳」と書くことが許されます。ですから前の管長という意味ではありません、明治以降、管長は今まで十四人しかおりませんので悪しからず。
利休居士が「南方録」に「掛物より第一の道具はなし、客・亭主共ニ茶の湯三昧の一心得道の物也、」おっしゃている様に、一席に於いて最重要ポイントであり、その日のテーマを決定するものが「掛物」であります。
極端な言い方ですが、このお茶で使う掛物は使用方法によって大きく分けて二つあり、それは「待合掛」にすべき物と「本席」で使える物に大別してよいでしょう。端的にいって今簡単に手に入る「絵」または「絵のはいいっている物(画讃物)」は一部を除いて「待合掛」といって「本席」すなわち茶席には不向きな物とするのが基本です。
そこに書かれている物はどんな掛物ですか、しっかり目的に合った意味合いの分かるものですか。ちょっとした知識で「恥」をかかず、お客に心遣いの出来る「茶の湯で使える掛物」を選ぶことが出来るようになるかと思います。
「むかしは絵を掛けて茶の湯をしていた」とおしゃる方、よくよく当時の会記(カイキ、茶会の道具を記録した物)をご覧下さい。「牧谿」「徐煕」「徽宗」などなど唐絵(カラエ、中国の宋から元時代が中心の絵画)あるいは禅機画といわれる物がほとんど、石州三百箇条に「台子には絵の…」といっているのも、これは全て唐絵、禅機画のことと考えるべきでしょう。
禅院での茶の湯には中国高僧の禅語を掛けることが多かったと思われ、一休から珠光へと伝わる「圓悟の墨跡」をはじめとして「無準師範」「虚堂智愚」「密庵咸傑」「古林清茂(茂古林)」らの「宋」「元」の中国僧、「兀庵普寧」「蘭渓道隆(隆蘭渓)」「一山一寧(寧一山)」など中国からの来日僧、「南浦紹明(大應國師)」「宗峰妙超(大燈國師)」「夢窓国師」「一休宗純」等日本の禅僧の物などが用いられていますが、「一行書」は一山一寧や兀庵普寧、夢窓国師、一休宗純などに散見する程度で「法語」「偈頌」がほとんどです。ただ、一行書は殊に一休が衆生のため難解な法語を示すより、その中の一行取りだし解くほうが容易であると考えよく用いられたと考えられますし後の茶の湯に大きな影響を与えます。一休の「諸悪莫作」「衆善奉行」(悪いことはするな、良いことをしなさいと言う意味)の一行書はあまりにも有名です。
ほかには字数の少ない物は「授号」「額字」という名前に関するもであったりします。また、「遺偈(ゆいげ、禅僧の遺言)」「尺牘(せきとく、禅僧の手紙)」「送別の語」などがあります。先の南方録の続きには「墨跡を第一とす」とあります。この時代までの墨跡はこれら、宋、元の中国僧、鎌倉、室町初期の禅僧の物を指しました。
ところが変革の人、利休が自らの師「春屋宗園(大徳寺111世)」の一行書を掛けるという事をします。在世の和尚の掛け物を掛けると言う事はそれまでになく同時代の「古渓宗陳(117世)」等から盛んになり茶の湯に掛ける為にしたためられるようになります。
万葉集や古今和歌集に始まる「古筆」は勅撰や私撰の和歌集を能筆かが書き留めた巻物、帖などを分断して掛け物とし鑑賞する物で「古筆切」と呼ぶのは分断した事による名称です。「寸松庵色紙」「継色紙」「八幡切」「石山切」「高野切」等があります。古筆切の書かれた年代としては10世紀から14世紀の所産であり、おいそれとは入手はおろか茶席で見かけることも稀でしょう。
「懐紙」はこの場合皆さんが茶席に持っていく物ではなく、文字通り懐中した日用の紙に、詩や歌を書き留め後に掛け物となった物です。藤原佐里の「詩懐紙」に始まり後鳥羽上皇の頃の「熊野懐紙」は高く評価されます。「懐紙」が「古筆切」より身近な気がするのは江戸時代に入り、作者として各歴代天皇の「御宸翰」をはじめ公家衆、更に僧侶や茶匠、数寄者にまでその範囲を広げるからなのです。紹鴎が「小倉色紙」を掛け利休もそれを模していますし、「熊野懐紙」に細川三斎が箱書きもしています。遠州は「寸松庵色紙」を盛んに用いています。
「消息」とは手紙のことですが、茶掛けに用いる場合、筆者としてまず「利休」を嚆矢としあとは尊敬に値する茶人であること条件で、内容としては茶に関する記述があり、和歌や俳句など入った物は喜ばれます。
「色紙」「短冊」も掛け物として用いられる物は「懐紙」などと同じ背景による物です、これらは「本席」より「待合掛」として真価を発揮する物が多いようです。
では何を掛けたら良いのか?というと、最初に求めるのであれば「禅語」といったところが茶席には無難です。
●掛け物-2
態度と申し上げたのは、席に入り先ず一番最初亭主より先に客が頭を下げ挨拶をする対象が掛物であります。これは単に「文字を鑑賞」するのではなく、語句を書かれた方そのものを軸を通して人格化し、本人を目の前にした気持ちで「挨拶」をする、という意味があります。
そういう訳で書いた人が「万人」とはいいませんが尊敬に値する人であることが大事なのです、単に「幾らで買った価値のある軸」なのではないのです。
よく「書」を嗜む方が、自分の書いた物、あるいは身内の書いた物を表具して人を招き、席に掛けるといったことを耳にします。しかしこれは「私に(身内に)頭を下げよ、尊敬しろ」と暗にいっているのも同じ事で甚だ不敬な事と言わなければなりません。「歌切」とは意味を異にします。
同じ様にコピーされた物、複製の軸を掛ける事、これっもやはり「勉強の為のお稽古」以外は避けなければなりません。コピーという物は、たとえどんなに有名な軸であってもまた、限定版であっても、コピーに人格はありません。ただしコピー技術の素晴らしさ、日本の技術革新に頭を下げさせたい方はどうぞご遠慮なく。
どんな方が書いた物にするか、あるいは書いていただくか、と言うことになります。とにかく「古いような字の書いた物があるから」といって掛けられる方もおられるようですが、前述したように人格を掛ける、といった意味もありますし、こと茶道に関する事ですから、茶道を「道」として導かれる方」「茶道を正しくお伝えになる方」などが、最もふさわしいように思われます。
茶の湯の礼法というのは元々中国の禅院で行われていた茶礼を道具と共にわが国に持ち込んだのが始まりとされていますし、侘び茶の祖ともいわれる村田珠光が、大徳寺一休禅師に参禅し、印可を受けるに当たり「圓語の墨跡」を賜り、これを掛け茶の湯をした、といったところから茶の湯と墨跡の関係が生まれたと考えられています。
その後茶の湯を志す者、茶の宗匠はことごとく大徳寺に参禅する事を慣わしとして、今に至っているのです。最初から「墨跡」を望むのも結構ですがまずは入門編として、たとえ末寺であっても大徳寺系のお寺を第一とし、次に同じ臨済派系の「妙心寺」や京都五山など茶の湯に関係の深い寺の物を掛けるとよいでしよう。
また後者である茶の宗匠方といえば、侘茶の祖「村田珠光」利休の師「武野紹鴎」茶聖「千利休」「利休七哲」「小堀遠州」「片桐石州」「元伯宗旦」「宗旦四天王」など、これらのものはまず入手はしにくい部類でしょう。時代を下がり、各歴代お家元や名だたる宗匠、数奇者などの物もやはり同様でしょう。現在のお家元や御先代のお軸ならば比較的手には入りやすいかとは思いますが、なかなか高価なものである事はいなめません。
ただ、「御家元の軸」があるからと言ってそれが決して頂点ではありません。歴代の御家元、宗匠、またそれらの方々が「師」として参禅された「禅僧」の方々の物、そういった物にこそ本来の伝統を背負った茶の湯の重みが出ることを忘れてはいけないと思います。(例えば濃茶の席など)そういった禅僧の書かれた「墨跡」であれば流儀を越えて尊敬に値する「茶の掛け物」ともいえるのではないでしょうか。
まずもって「大徳寺系の老師か和尚」のものといったところが恥を掻かずに済む線といえ、人格面からいっても無難なのではないでしょうか。
次に一番身近な大徳寺系の軸の落款や署名の見方を説明いたしましょう。大徳寺は臨済宗大徳寺派大本山であり山号を「龍宝山」といい、署名の仕方としては「現大徳」とあるのは管長を現わしますが、管長制になったのは明治にはいってからで、現在第十四代目の管長を勤められる福富雪底老師は新潟県西蒲原郡潟東村のご出身と伺っております。各塔頭のご住職はほとんど「紫野」「龍宝」を使われます。紫野は大徳寺のある所の地名で、龍宝は山号です。
一番多いのは「前大徳」で現代では末寺の住職に与えられる一種の位、称号、資格のようなものと考えるのが無難でしょう。大徳寺の僧侶の位には再住位・前住位・住持位・・・以下八位までありますが、この内「前住位」に当たるものです。この位を受けると、本山大徳寺にて一日だけ「大徳寺住職」になる「改衣式」を行い、方丈(導師)という役をして本尊と開山をはじめ各祖師に報告の法要をし一山の各住職に披露します。それ以後に、「前大徳」と書くことが許されます。ですから前の管長という意味ではありません、明治以降、管長は今まで十四人しかおりませんので悪しからず。