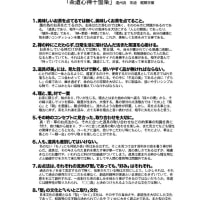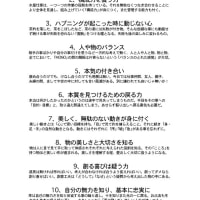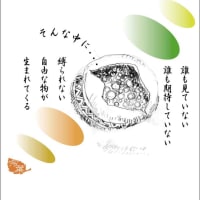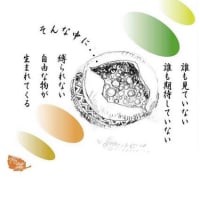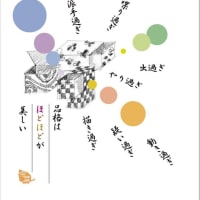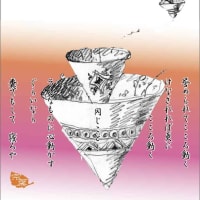茶の湯のそういった文化に批判的な人は(茶の湯をやっている人を含め)「茶杓本体」のみを論じようと躍起になり「中身が入れ替わってしまえば判らなくなる」とか「筒や箱だけ一人歩きする」などといった批判をしたりします。長い茶の湯の歴史の中には確かにそういったこともあったことは事実ですが、高度な茶人たちの茶事、茶会での会話の中には、拝見に出した茶杓の作者を隠し客に推理させる、などと言ったことも行われており、杓の特徴から作者や制作年代などを言い当てることも容易なのです。「そんなことはなかなか出来ない」と思われる向きもおありかとは思いますが、例えば裏千家の「淡々斎」「圓能斎」「玄々斎」の茶杓を言い当てるのはさして難しいことではないのではないですか?特徴をつかみさえすれば皆さんにもお出来になることです。
茶杓を論ずるとき多くの場合「茶杓の作者と茶杓」というう観点と「茶杓の真行草の格付けと使用方法」といった少し異なる観点で論じなければなりません。
前述の「象牙の茶杓」は「利休形」「珠徳形」「利休形に真塗りしたもの」のみが「真」の扱いをします。
唐物を原型とするという理由からでしょう「節無茶杓(長茶杓)」も「真」の扱いにします。
「行」にあたる茶杓は「元節」茶杓です。
「中節」の茶杓は「草の茶杓」という扱いですが「伝物」を除くすべての点前に使用する標準的なものとなります。江戸の初期までのものは保護のため「拭き漆」施してありますがそれ以外の「蒔絵」などの「塗りの茶杓」は「茶人」の手から「職人」の手に委ねられた物で「草の草」と言って良いでしょう。同様に「鼈甲」「その他の木製」も同様です。
象牙茶杓の中でも「薬匙」からの転用である「芋の子」茶杓や細工の入った「牙茶杓」は「草の茶杓」というより「茶箱用」として楽しむ意外には使用しません。たとえ「真の茶杓」より古いものであっても、「草の草」以上に番外的な扱いとなります。
「侘茶の道具としての茶杓(花入、蓋置)
木地の茶道具(水指、建水、等)」
竹で出来た「茶杓」「花入」「蓋置」は掛け軸と同様に「万人」とはいいませんが「尊敬に値する人の作」であることが必要なのです。わきまえた「茶人」なら決して手を出さないものと心得ておかれるべきでしょう。
「青竹の蓋置」と「木地曲の建水」の使い始めのエピソードには今に繋がる侘び茶の原点があります。
侘び茶の道具として珠光は青竹の蓋置を木地曲建水に仕組んで使用し、そのあと蓋置を建水の水に浸し持って帰り「再びこれらを使用しない」印として扱ったとのことです。「木地物の茶道具」の原則は「使いきり」と覚えていてください。侘び茶の道具というのは非常に厳しいものです。一つ間違えると「しぼたらしい」「貧乏臭い」物になりかねず、それと取り合わせる青竹や木地物の茶道具はことさら「使い切り」を求められます。
茶杓を論ずるとき多くの場合「茶杓の作者と茶杓」というう観点と「茶杓の真行草の格付けと使用方法」といった少し異なる観点で論じなければなりません。
前述の「象牙の茶杓」は「利休形」「珠徳形」「利休形に真塗りしたもの」のみが「真」の扱いをします。
唐物を原型とするという理由からでしょう「節無茶杓(長茶杓)」も「真」の扱いにします。
「行」にあたる茶杓は「元節」茶杓です。
「中節」の茶杓は「草の茶杓」という扱いですが「伝物」を除くすべての点前に使用する標準的なものとなります。江戸の初期までのものは保護のため「拭き漆」施してありますがそれ以外の「蒔絵」などの「塗りの茶杓」は「茶人」の手から「職人」の手に委ねられた物で「草の草」と言って良いでしょう。同様に「鼈甲」「その他の木製」も同様です。
象牙茶杓の中でも「薬匙」からの転用である「芋の子」茶杓や細工の入った「牙茶杓」は「草の茶杓」というより「茶箱用」として楽しむ意外には使用しません。たとえ「真の茶杓」より古いものであっても、「草の草」以上に番外的な扱いとなります。
「侘茶の道具としての茶杓(花入、蓋置)
木地の茶道具(水指、建水、等)」
竹で出来た「茶杓」「花入」「蓋置」は掛け軸と同様に「万人」とはいいませんが「尊敬に値する人の作」であることが必要なのです。わきまえた「茶人」なら決して手を出さないものと心得ておかれるべきでしょう。
「青竹の蓋置」と「木地曲の建水」の使い始めのエピソードには今に繋がる侘び茶の原点があります。
侘び茶の道具として珠光は青竹の蓋置を木地曲建水に仕組んで使用し、そのあと蓋置を建水の水に浸し持って帰り「再びこれらを使用しない」印として扱ったとのことです。「木地物の茶道具」の原則は「使いきり」と覚えていてください。侘び茶の道具というのは非常に厳しいものです。一つ間違えると「しぼたらしい」「貧乏臭い」物になりかねず、それと取り合わせる青竹や木地物の茶道具はことさら「使い切り」を求められます。