●花入-1
床の間の道具として掛物(軸)のつぎに上げられるのが「花入」です。床を飾るのは初座では軸であり後座は花入がその主役に代わります。花入を分類するのによく用いられるのが、「真行草」の格付けです。それぞれの花入が持つ歴史的背景、品格、雰囲気で分類されます、また花入の台である「薄板」の格を決定する目的もあります。
点前やお軸によってその使われ方が異なるのですが、前項でふれた点前と軸の関係のように、古い点前、格式のある台子、伝物の点前では「真」に近い花入が相応しいと考えられますし、侘茶、例えば名残の時期などの中置、窶れ風炉などを使った茶の湯では「草」に近い物が似合います。また、広間小間によっても使い分ける必要も出てきます。
個々の点前には、この花入と言う決まりはありませんが、全体の取り合わせとして、見合わすことが肝心です。
花入、軸に限らずこれから出てくる道具の話もそうですが、
「初座」で掛けられる軸に対し「後座」の花入の格を合わせる必要があります。その上で茶会などの「諸飾り」があります。
茶の湯では唐銅、胡銅と呼ばれるの花入は原料名、金属名としては「ブロンズ(青銅)」にあたります、その始まりは古く中国の「夏」や「殷」「周」時代の「青銅器」が始まりです。
当時は神に捧げる酒器の様な物だったようですが後世になって花器として使われ出したようです。やがて青銅器は殷代をピークとして漢の後期には著しく衰退するようになります。
かわってこの頃から焼かれ始める「青磁」は、唐代には「秘色(ひそく)青磁」が完成しますが花入に昇華するには若干の時間を要するようです。
やがて「宋」の時代に入ると青銅器の形状、雰囲気を目指した青磁が現れ(砧、天竜寺、七官など)元、明時代までつづき茶道で使われる花入の全盛時代を迎える事となります。
※室町時代にこれらの花入は「唐物」として茶の湯と共に我が国に招来する事となります。
いわばこの頃の時代までに日本へ伝来した唐物花入を「真」の扱いをする花入に当たります。
※一方、元のころ大成する「染付」「赤絵」は明代に盛んになりますが花入として日本への輸入が盛んになるのは江戸に入って「古染付」や「祥瑞」「呉須赤絵」と呼ばれる一群の茶道具としての注文品の輸入が始まってからの様です。
その他「高麗青磁」「交趾」「安南」や「オランダ」など唐物に準ずる物として同じ扱いをすると良いようです。
※唐物の中でも「釣船」の花入は一格落して「行」の格として扱うようです。
「七宝」「モール」の花入も「真」の部類です。
※準唐物である高麗物であっても「粉引「や「三島」などは「行」として扱いますし、いまどきの韓国製などの「高麗青磁」なども是に準じた方が良いでしょう。
※また青磁や染付のたぐいでも国産品である作家物などは稽古はともかく公の場所(茶会や茶事)では「行」として扱う方が無難であり奥床しいとも云えます。
※唐銅の花入は唐物と国物の差が判別しにくい所からとその品格からか「真」の花入として扱うことが多いのですが近世の作なら「行」に近い扱いもよろしいでしょう。
※「和物の施釉陶器」の花入を「行」の格で扱うのが基本です。ただし、和物施釉陶器の花入が登場するのは「唐物」の花入や後に説明する「焼締花入」に比べるとかなり遅れることとなります。
※「織部焼」の花入はまず見かけることがなく、古田織部の花入は「美濃伊賀」と呼ばれる新たな焼き物でそのイメージを開花させます。 ただ、その名の示すとおり伊賀焼に近い物として「草」に扱うほうが一般的です。
●花入-2
※「楽焼」の花入も釉は掛けてありますが「行」に扱う場合と時によっては「草」の花入として扱います。利休以降様々な形が有ります。
※掛花入(花入の上部に穿った穴が開いている。茶の湯が書院から草案へ移り「中釘」に掛けられるようにと鐶を付けた跡)としてこのような形式の嚆矢は「高麗筒」と呼ばれる「元」の時代の花入です。これは、かの「元寇」の際に火薬を入れる器として「南蛮粽」花入と共に玄界灘に沈んだ物が後に取り上げられ茶席に取り入れられた物です。この二点は「唐物」ではありますが、「草」に扱います。
※江戸時代に入り天才的感性を持って作陶を始め後の茶陶に大きな影響与える「仁清」が登場し豊かな表現力を駆使した造形で具象化したユニークな花入を数多く残し、後に京焼に受け継がれていきます。これら「色絵」の花入も「草」として扱う物かと思います。
「竹、籠、瓢」
※唐物の籠花入はその品格から自ずと事なるものとなります。大方、和物籠花入は風炉の時期だけですが唐物は炉の時期であってもまた「草」の花入れではありますが書院にもふさわしい花入として扱う事も有ります。
※「草」の花入の代表としてはやはり竹の花入でしょう。
利休は死までの一年間にも多くの竹の花入を切っていますし後世多くの茶人も花入を切っています。
これまでの花入と異なる点は「作り手が茶人」に移ったという点だと思います。茶人という工芸の素人が作り得る品物が一種の芸術品となった訳ですから秀吉が気に入らないのも尤もなことではあります。これは誰もがなし得たことではなく「利休」という侘び茶の大成者でなければ野にある竹を花入にしたものを何人も認めえなかったと思います。
最初の掛け物のときも書きましたが竹の花入も同じ様に「人格」を見出すための道具ですから職人が作ったものと異なる格調を備えた物なのです。お人が現れていなければ竹の花入としての意味はありません。
その誕生のときから竹の花入は「銘」とは切り離せないものなのです。
「竹」の花入はそれを切った人物によりやはり格調、格式を感じる物でしょう。
勿論、「台子」の点前には「真」の花入が相応しくはありますが、「行」の台子だからと言って「行」の花入は無理に用いませんし、「伝物」点前には「草」の花入を用いる場合もあります。
むしろこれらの手分けは、それぞれの花入の格に従い薄板といって花入に敷く板(風炉の敷板と区別する名称)が異なることによって大別されるからでしょう。
※「道具」としての花入はやはり、時代によってその重みを増します。「草」の花入である
「伊賀」「信楽」「美濃伊賀」「備前」などは桃山期の物が最も珍重され、格調高く扱われます。
※「古染付」「高麗青磁」「交趾」「安南」や「オランダ」など唐物に準ずる物で「真」として扱われますが、「唐銅」「青磁」物に比して些か軽く用いて「行」として扱っても構わないのではないでしょうか。
※「ガラス」などの物も最近は見かけることもありますが、見立ては見立て「草」として扱うべきでしょう。
板
「真」の花入には真塗の「矢筈板」、または「燕口板」を用います。板の縁が矢羽の後の部分のように∑状になっているものが矢筈板、上の部分が嘴の様に出ているものが燕口板です。現在出ているものは燕口板がほとんどですがが総称して「矢筈板」と呼んでいます。
燕口板の場合必ず広い方が上になるようにします。外に唐銅の鶴首などに「四方盆」や「曽呂利」の花入に添った「曽呂利盆」などを使う場合があります。盆に関しては石州三百箇条にも記述が有ります。
「行」の花入には塗の四角の蛤板を使います。板の縁が蛤のように⊃状になっているところからの名称です。塗は真塗、掻合、黒、溜塗なども問いません。
●花入-3
※「行」の花入には塗の四角の蛤板を使います。板の縁が蛤のように⊃状になっているところからの名称です。塗は真塗、掻合、黒、溜塗なども問いません。
※「草」の花入には木地で四角の「蛤板」か「丸香台」を使用します。焼締めの花入などは木地の方が似合います、が流儀により、どちらかを多用するようです。
「楽の花入」には丸香台も良いでしょう。なお一般にある「丸の蛤板」は用いません。
また、草の花入である「籠の花入」には板を敷きません。
これらの薄板はあくまで床の間が「畳床」の場合に限ります。「板床」に板は二重なりますので用いません。
板戸この場合、客が席入りする前にはしっとり濡らして花入を用います。
花入に入れる席中の茶花は、
栽培種ではなく自然を茶室に取り込むといった意味合いからまた、日本風省略の美、不足の美、といった美意識から極小数、一枝に花ひとつくらいのものを活けます。
利休さんも「(茶花は)一色か二色軽く活けたるがよし」と残されています。
くれぐれも「匂の強い花、けばけばしい花、名称の良くない花、実のなる花も避けます、しかし禁歌に歌われている花でも茶室に似あう花であれば上手に使い趣向を盛り上げる事も出来るでしょうが、あくまでも基本を守る事を旨とすべきでしょう。
床の間の道具として掛物(軸)のつぎに上げられるのが「花入」です。床を飾るのは初座では軸であり後座は花入がその主役に代わります。花入を分類するのによく用いられるのが、「真行草」の格付けです。それぞれの花入が持つ歴史的背景、品格、雰囲気で分類されます、また花入の台である「薄板」の格を決定する目的もあります。
点前やお軸によってその使われ方が異なるのですが、前項でふれた点前と軸の関係のように、古い点前、格式のある台子、伝物の点前では「真」に近い花入が相応しいと考えられますし、侘茶、例えば名残の時期などの中置、窶れ風炉などを使った茶の湯では「草」に近い物が似合います。また、広間小間によっても使い分ける必要も出てきます。
個々の点前には、この花入と言う決まりはありませんが、全体の取り合わせとして、見合わすことが肝心です。
花入、軸に限らずこれから出てくる道具の話もそうですが、
「初座」で掛けられる軸に対し「後座」の花入の格を合わせる必要があります。その上で茶会などの「諸飾り」があります。
茶の湯では唐銅、胡銅と呼ばれるの花入は原料名、金属名としては「ブロンズ(青銅)」にあたります、その始まりは古く中国の「夏」や「殷」「周」時代の「青銅器」が始まりです。
当時は神に捧げる酒器の様な物だったようですが後世になって花器として使われ出したようです。やがて青銅器は殷代をピークとして漢の後期には著しく衰退するようになります。
かわってこの頃から焼かれ始める「青磁」は、唐代には「秘色(ひそく)青磁」が完成しますが花入に昇華するには若干の時間を要するようです。
やがて「宋」の時代に入ると青銅器の形状、雰囲気を目指した青磁が現れ(砧、天竜寺、七官など)元、明時代までつづき茶道で使われる花入の全盛時代を迎える事となります。
※室町時代にこれらの花入は「唐物」として茶の湯と共に我が国に招来する事となります。
いわばこの頃の時代までに日本へ伝来した唐物花入を「真」の扱いをする花入に当たります。
※一方、元のころ大成する「染付」「赤絵」は明代に盛んになりますが花入として日本への輸入が盛んになるのは江戸に入って「古染付」や「祥瑞」「呉須赤絵」と呼ばれる一群の茶道具としての注文品の輸入が始まってからの様です。
その他「高麗青磁」「交趾」「安南」や「オランダ」など唐物に準ずる物として同じ扱いをすると良いようです。
※唐物の中でも「釣船」の花入は一格落して「行」の格として扱うようです。
「七宝」「モール」の花入も「真」の部類です。
※準唐物である高麗物であっても「粉引「や「三島」などは「行」として扱いますし、いまどきの韓国製などの「高麗青磁」なども是に準じた方が良いでしょう。
※また青磁や染付のたぐいでも国産品である作家物などは稽古はともかく公の場所(茶会や茶事)では「行」として扱う方が無難であり奥床しいとも云えます。
※唐銅の花入は唐物と国物の差が判別しにくい所からとその品格からか「真」の花入として扱うことが多いのですが近世の作なら「行」に近い扱いもよろしいでしょう。
※「和物の施釉陶器」の花入を「行」の格で扱うのが基本です。ただし、和物施釉陶器の花入が登場するのは「唐物」の花入や後に説明する「焼締花入」に比べるとかなり遅れることとなります。
※「織部焼」の花入はまず見かけることがなく、古田織部の花入は「美濃伊賀」と呼ばれる新たな焼き物でそのイメージを開花させます。 ただ、その名の示すとおり伊賀焼に近い物として「草」に扱うほうが一般的です。
●花入-2
※「楽焼」の花入も釉は掛けてありますが「行」に扱う場合と時によっては「草」の花入として扱います。利休以降様々な形が有ります。
※掛花入(花入の上部に穿った穴が開いている。茶の湯が書院から草案へ移り「中釘」に掛けられるようにと鐶を付けた跡)としてこのような形式の嚆矢は「高麗筒」と呼ばれる「元」の時代の花入です。これは、かの「元寇」の際に火薬を入れる器として「南蛮粽」花入と共に玄界灘に沈んだ物が後に取り上げられ茶席に取り入れられた物です。この二点は「唐物」ではありますが、「草」に扱います。
※江戸時代に入り天才的感性を持って作陶を始め後の茶陶に大きな影響与える「仁清」が登場し豊かな表現力を駆使した造形で具象化したユニークな花入を数多く残し、後に京焼に受け継がれていきます。これら「色絵」の花入も「草」として扱う物かと思います。
「竹、籠、瓢」
※唐物の籠花入はその品格から自ずと事なるものとなります。大方、和物籠花入は風炉の時期だけですが唐物は炉の時期であってもまた「草」の花入れではありますが書院にもふさわしい花入として扱う事も有ります。
※「草」の花入の代表としてはやはり竹の花入でしょう。
利休は死までの一年間にも多くの竹の花入を切っていますし後世多くの茶人も花入を切っています。
これまでの花入と異なる点は「作り手が茶人」に移ったという点だと思います。茶人という工芸の素人が作り得る品物が一種の芸術品となった訳ですから秀吉が気に入らないのも尤もなことではあります。これは誰もがなし得たことではなく「利休」という侘び茶の大成者でなければ野にある竹を花入にしたものを何人も認めえなかったと思います。
最初の掛け物のときも書きましたが竹の花入も同じ様に「人格」を見出すための道具ですから職人が作ったものと異なる格調を備えた物なのです。お人が現れていなければ竹の花入としての意味はありません。
その誕生のときから竹の花入は「銘」とは切り離せないものなのです。
「竹」の花入はそれを切った人物によりやはり格調、格式を感じる物でしょう。
勿論、「台子」の点前には「真」の花入が相応しくはありますが、「行」の台子だからと言って「行」の花入は無理に用いませんし、「伝物」点前には「草」の花入を用いる場合もあります。
むしろこれらの手分けは、それぞれの花入の格に従い薄板といって花入に敷く板(風炉の敷板と区別する名称)が異なることによって大別されるからでしょう。
※「道具」としての花入はやはり、時代によってその重みを増します。「草」の花入である
「伊賀」「信楽」「美濃伊賀」「備前」などは桃山期の物が最も珍重され、格調高く扱われます。
※「古染付」「高麗青磁」「交趾」「安南」や「オランダ」など唐物に準ずる物で「真」として扱われますが、「唐銅」「青磁」物に比して些か軽く用いて「行」として扱っても構わないのではないでしょうか。
※「ガラス」などの物も最近は見かけることもありますが、見立ては見立て「草」として扱うべきでしょう。
板
「真」の花入には真塗の「矢筈板」、または「燕口板」を用います。板の縁が矢羽の後の部分のように∑状になっているものが矢筈板、上の部分が嘴の様に出ているものが燕口板です。現在出ているものは燕口板がほとんどですがが総称して「矢筈板」と呼んでいます。
燕口板の場合必ず広い方が上になるようにします。外に唐銅の鶴首などに「四方盆」や「曽呂利」の花入に添った「曽呂利盆」などを使う場合があります。盆に関しては石州三百箇条にも記述が有ります。
「行」の花入には塗の四角の蛤板を使います。板の縁が蛤のように⊃状になっているところからの名称です。塗は真塗、掻合、黒、溜塗なども問いません。
●花入-3
※「行」の花入には塗の四角の蛤板を使います。板の縁が蛤のように⊃状になっているところからの名称です。塗は真塗、掻合、黒、溜塗なども問いません。
※「草」の花入には木地で四角の「蛤板」か「丸香台」を使用します。焼締めの花入などは木地の方が似合います、が流儀により、どちらかを多用するようです。
「楽の花入」には丸香台も良いでしょう。なお一般にある「丸の蛤板」は用いません。
また、草の花入である「籠の花入」には板を敷きません。
これらの薄板はあくまで床の間が「畳床」の場合に限ります。「板床」に板は二重なりますので用いません。
板戸この場合、客が席入りする前にはしっとり濡らして花入を用います。
花入に入れる席中の茶花は、
栽培種ではなく自然を茶室に取り込むといった意味合いからまた、日本風省略の美、不足の美、といった美意識から極小数、一枝に花ひとつくらいのものを活けます。
利休さんも「(茶花は)一色か二色軽く活けたるがよし」と残されています。
くれぐれも「匂の強い花、けばけばしい花、名称の良くない花、実のなる花も避けます、しかし禁歌に歌われている花でも茶室に似あう花であれば上手に使い趣向を盛り上げる事も出来るでしょうが、あくまでも基本を守る事を旨とすべきでしょう。













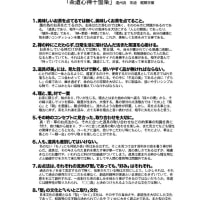
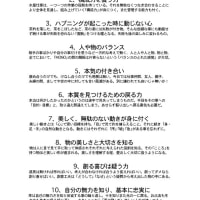
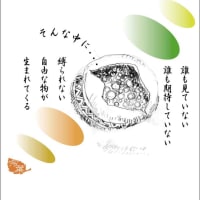

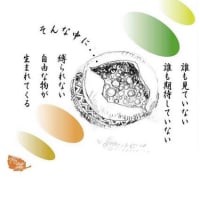
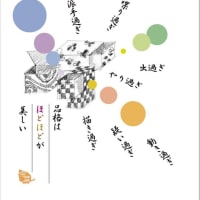
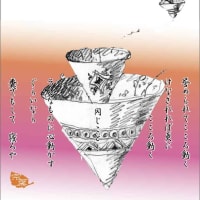
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます