自分に取って茶道とは何だろうか?茶道というには少々大袈裟であれば、茶の湯とはどんなものだろう。
茶人、茶の湯者、茶道家などと、大層な名で表さなくても、抹茶で人との混じり合いを大切に、日々の暮らしの中に、
茶と関わった時間を持ち、精神的にゆとりある落ち着いた環境をどう持つ事が出来るか。
今迄の歴史の中から、伝えられた幾人もの茶道家を手本とし、今の自分の身の丈にあった所で、考えをまとめてみよう。
●鎌倉時代に臨済の開祖栄西(1141〜1215)によって中国から伝わり歴代将軍と同様に暇を持て余し唐物を収集し、
殿中で立花、茶の湯を盛んに行う。義政の茶は水面に映った月を楽しむ境地で東山文化と言われる
●詫び茶の開祖と言われる村田珠光(1423〜1502)
八代将軍足利義政の時代、一休の純禅と深切に出合い、茶に禅味を加えた「月も雲間のなきはいやにて候」と、
完全な月よりも雲間に欠けた雲隠れのわびしい月にこそ茶の湯の高尚な美があると、心の茶を主張。
逆転の発想で、従来の禅林や殿中の茶とは一線を画するものであった。
珠光の茶はそれらと袂を分かち、民衆の共感を得て奈良流を形成。
国産の陶器や床の間を取り入れ、不足不完全という精神性の高い境地に茶の湯の美を見出そうと、
芸道としての茶の湯の発展を目指すがまだ観念的なもの。ここから心の茶が育って行く。
●戦国まっただ中室町末期武野紹鴎が珠光の茶を受け継ぐ
大徳寺の影響を受け「茶禅一味」や「一期一会」の理念で茶の湯の美を極め、様々な教養を積み、
その分野事との真髄を茶の湯に取り入れ、禅と和歌の精神を結実し、詫び茶を創出した。
武士や豪商の間に日本的な禅の一様態とも言える侘び茶を開花させ、
心の平穏を得ようと先達が長い年月をかけ深化させ、わび茶独自の流れを生じ我が国独自の精神文化、堺文化となる。
「仏心を伝え、心地の修行」と紹欧の茶を評する。
バブリーな境遇に安住するのではなく、「慎ましく」、「謙虚で」、「上品な」生き方に価値を見出す。
●藤原定家「詠歌大概之序」より
和歌を作る時に大切なのは、稽古である。いにしえの名歌を習い、名人を見習ってその真似をすること。
その主たる目的は、ただ形ばかりまねる事では無く、その人の心を学ぶことである。
それから、何をおいても作為が一番大切である。人と同じ事をするのではなく、一歩踏み出して自分を出す。
和歌で言えば人がまだ読んだ事の無い新鮮な情を求め詠む。これは茶の湯にも大切な事である。
この精神を茶の湯に取り入れた事により、わび茶の湯が本質を得て、形式を脱却し、生命を持った。
●芭蕉の不易流行について
「不易」とは、寂滅の永遠性を課題にしている。この風雅の精神を身に付け、本質を衝き、句を生み出すことで、
常なるもの、詰まり普遍性を追求したのである。
「流行」とは、自分を絶えず新しく変える努力をして、日々新しい自分となること、常に新鮮な作為を得て寂滅を捉え、
句に読み込むことである。簡単に言えば、無常という普遍の本質を探究することを、自分自身の人生の課題としていたのである。
芭蕉は世俗を離れて、生きながらに己を無にして自然と一体となることで、本物の自分を見出すことが出来たのである。
無を求めることもまた執着であるが、わびは無にあるのではなく、仏の道(禅)のあるがままの人生観にあるのである。
芭蕉は、仏法に開眼したことにより俳句に開眼し、「芭風」を興し得たのである。これは紹鴎の茶と同じ構図である。
紹鴎はわび茶によって、芭蕉は俳諧によって、直感的に奥深い小宇宙を探究し、宇宙の原理を発見したのである。
利休のわびさび
わび茶で求めるものは本来、世俗をはなれ、隠遁の世界で得られる心の静けさであるべきである。
しかし利休は信長や秀吉といった権力者の茶頭として、政治の中に我が身を置いた。
そして、最後迄天下人秀吉との葛藤に心をみだしている。その生き方は、心の静けさとはほど遠いものだった。
秀吉は統治の術の一環として茶の湯を利用し、利休と結んだ。これにより利休の発言力が伸長するが、
わび茶は、政治の道具にされ、その思想も干渉された。
「茶の湯の心を持つには、どうすれば良いのかを探る」
権威が廃れ、古い物差しが使い物にならなくなった時代、良く言えば自由、悪く言えば放埒な世の中、一体何が正しいのか、
自分で判断する基準がほしい。その基準の一つに「禅」があるが、やがて禅は形式主義、権威主義に落ち入る。
そこで、一休が禅宗の腐敗を痛罵して、自由な禅の在り方を主張。
我が国では人里離れ山中深く入り込み修行すると、普通の人には見えないものを心の目で見る事が出来るようになる。
この事は、根源的にして不変なるものを見る能力の事で、常なるものの本体の事で、
人間としてより良く生きようとする際の、私欲を捨てた仏の心、理念の事である。
人が良く生きようとすると、人生の意義や目標、そして価値判断の基準が必要になって来る。これが無ければ混乱するばかり。
価値基準と言ってもいろいろで、茶碗で言えば、道具としての「使用価値」、どれだけで売れるかという「取引の価値」、
そして鑑賞するための「美的価値」がある。秀吉も紹鴎も利休も追求したものは人生における美であろう。
人生は人それぞれで、何に価値を見出し、どれだけ深く生きたかが重要である。
禅とは一つの事物に精神を集中し、その真の姿を知ろうとする事で、知ったとしても心の平安が得られるだけで、
実益のある物ではない。コツコツと知識と実践を積み重ねて同じ事を深く行い、己を磨いてゆくと、やがて、
一つの知識と別の知識が融合するのであろう。悟ろうという気持から吹っ切れてこれを超え、昇華した所に、
新境地が出現し、物の本質を捉えて自然体を得、本物の名人、自由人になるのである。
茶の湯の世界でも「茶の湯者覚悟十体」に(我より上の人と知音するなり。人を見知りてともなうべし)
有能な人は多くの知識や人脈を持っている。彼らから学ぶべき事、得られる物は多い。
有能な人との繋がりが多ければ多い程、情報の質と量が増加する。
茶の湯者の心の変化
精神的な美を求める茶の湯者は、荘厳の美に満足しなかった、荘厳の美から吹っ切れた時、そこから一転して、
不要の美をそぎ落ししていく。そして荘厳の完璧な美の対極に位置する。簡素で静寂な、
自然に近い日本独特の美、いわば消極・否定の美の究極に、わび・さびの美を完成させたのである。
茶の湯における美の創造とは、具体的に何をする事かと言えば、
従来認識されていなかった新たな美を自ら発見し、茶室に再現する事なのである。
富貴の人がわび者の真似をして貧乏ぶるは「さばす」であって「さび」ではない。
茶の湯のさびは自然にさびるのがよいので、「さばす」であってはならない。
珠光の「心の文」より
一番いけないのは、己が心の我慢我執であり、これを抑えなくてはならない。
この様な心の有様は自然に身に付かないものであり、修行を積んで我慢我執を抑える心の師とならなければならない。
「我慢」と言う語は現代語の意と違い、慢心して我意を張ること、我が意を通すこと、思い上がりのことである。
わびの美とは、我が意を徹することではなく、自然の摂理との調和にこそある。
堕落、傲慢の心を戒めた、現代社会でも道徳規範の根元となり得る観念である。
紹鴎の茶の湯において一番大切な心は、和歌におけるわびと同じであり、茶の湯に具現化したことにある。
亭主はわびさびを身に付け、それを茶室で演出し、客はわびさびの感性を磨き、
これを感じ取る。わびとは不足を味わうこと、不自由な自由である。
「不足不自由の美」を味わうことで、亭主も客も普段は見えない宇宙の体系美を感じ、
神の声を聞き取ることが出来る境地に至るのである。
紹鴎のたどった軌跡は、旧来の社会制度もモラルも崩壊した自由社会への激動期の、
社会変動に対応する「自己改革運動」であるといえよう。個人や集団の欲望に基づく活動を制御しなければ、
健全な社会を保つことはできない。住み良く健全な、あるべき社会を実現し維持するには、
私利私欲にとらわれる己の弱さを捨て去るよう修行し、正義の精神を会得しなければならない。
その為の選択肢の一つとなるのが「わび」である。まるい豊かな心を持ち、実り多い人生を送って欲しいと願ったのだ。
わびと貧乏は違う
まず心の持ちようからして違う。わびはワビを追求し、その過程で何をなし得たかの過程である。
紹鴎の言うわびは、隠遁の心第一にわびて宇宙の究極に美を求め、閑寂を楽しむ心のあり方で、
心豊かな茶の湯の世界なのである。貧乏は夢を持てない。あるいは夢破れた、その結果のしがなさである。
本阿弥光悦は、利休を一応名人と認めながらも、権力と結んで、茶の湯を俗化させたと批判している。
利休が創造したのは、冬の枯れ木に美的価値を置いて我が茶風とする、ものに立脚した美である。
紹鴎の茶の湯の心は、虚飾を取り去った誠である。これは、人の生活の規範となすべきもので、
成熟した現代社会を健全に守るためには忘れてはならない。欧米人もこれを持ってはいるが、
ともすれば自己主張のハッキリした、外向的な開拓魂の陰に隠れてしまいがちである。
ある種内省的な世界で、ハッキリしない中庸さに真実を求める人生観である。これは芭蕉のわびとも共通する。
珠光の茶の湯の真髄を知るには、一休から与えられ、「不法も茶の湯の中にある」
と悟った園悟墨蹟の文面に籠められていた深い意味こそが重要なのである。要するに珠光が遺言した茶の湯の奥義とは、
ものへの執着からの解放なのである。しかし、利休は物や珠光の嗜好に執着していたようである。
利休のわびは冬から春を想起するところにあるのではない。実際の利休の審美眼は、
春の雪解けに象徴される生命の躍動などというものとは真逆の、黒茶碗の黒、利休鼠のネズミ色など、
墨の濃淡の様な枯れたものに美を見出していた。
紹鴎が禅の実践や和歌を基本に外来文化の和洋化を図ったのに対し、利休・宗二は外来文化を崇拝し、
儒教を基本に漢詩や水墨画を取り入れたのである。
利休は秀吉の茶頭であり、秀吉と利休とは主従の関係にあった。殿中にあって利休が、
秀吉の立場に配慮することなく茶人として茶の湯上の真念を貫くことは、もとより無理なことだったのである。
利休は己の美学を以って茶風を興そうとしていたが、従来、茶の湯で重要な要素は一、目利き・一、
作分(創意工夫)・一、手柄(功績)・一、心の働きなどであったが、利休の心の働きは、機知、
機転の類に基軸を置いていたのである。
「山上宗二記」によれば、
利休は名人なれば、山を谷、西を東と、茶の湯の法を破り、自由せられても、面白し。
平人それを其の侭似せたらば、茶の湯にては在るまじきぞ。とあり、利休が形式を破った茶を好んでいたのは確かなのである。
利休の師 武野紹鴎
武野宗延著 武野紹鴎研究所より抜粋
私は、利休百首よりの「降らずとも雨の用意」を茶の湯の心の働きの元としている。前もっての準備、
何かのことがあっても慌てることなく、自分を守ることができれば、相手の身にもなれる優しさが生まれるのではないか?
わびさびは、道具などには言うにおよばず、仕草や、心の働きの中にも取り入れ、我欲をおさえ、
「禅」の修行までは行かなくても、誰かのために、何のための茶会かを催すことに心がけたい。
茶会の目的 ①感謝へのお招き ②コミュニケーション
茶の湯の様式 ①濃茶(式的要素で心大らかに)食事(腹8分目)薄茶(身体共に楽しみ遊ぶ)
狙いところ ①茶のわび美を何処で表すか ②形式のオリジナル化 ③創意工夫な作品のお披露目
梶間 宗葉の茶の湯感
茶人、茶の湯者、茶道家などと、大層な名で表さなくても、抹茶で人との混じり合いを大切に、日々の暮らしの中に、
茶と関わった時間を持ち、精神的にゆとりある落ち着いた環境をどう持つ事が出来るか。
今迄の歴史の中から、伝えられた幾人もの茶道家を手本とし、今の自分の身の丈にあった所で、考えをまとめてみよう。
●鎌倉時代に臨済の開祖栄西(1141〜1215)によって中国から伝わり歴代将軍と同様に暇を持て余し唐物を収集し、
殿中で立花、茶の湯を盛んに行う。義政の茶は水面に映った月を楽しむ境地で東山文化と言われる
●詫び茶の開祖と言われる村田珠光(1423〜1502)
八代将軍足利義政の時代、一休の純禅と深切に出合い、茶に禅味を加えた「月も雲間のなきはいやにて候」と、
完全な月よりも雲間に欠けた雲隠れのわびしい月にこそ茶の湯の高尚な美があると、心の茶を主張。
逆転の発想で、従来の禅林や殿中の茶とは一線を画するものであった。
珠光の茶はそれらと袂を分かち、民衆の共感を得て奈良流を形成。
国産の陶器や床の間を取り入れ、不足不完全という精神性の高い境地に茶の湯の美を見出そうと、
芸道としての茶の湯の発展を目指すがまだ観念的なもの。ここから心の茶が育って行く。
●戦国まっただ中室町末期武野紹鴎が珠光の茶を受け継ぐ
大徳寺の影響を受け「茶禅一味」や「一期一会」の理念で茶の湯の美を極め、様々な教養を積み、
その分野事との真髄を茶の湯に取り入れ、禅と和歌の精神を結実し、詫び茶を創出した。
武士や豪商の間に日本的な禅の一様態とも言える侘び茶を開花させ、
心の平穏を得ようと先達が長い年月をかけ深化させ、わび茶独自の流れを生じ我が国独自の精神文化、堺文化となる。
「仏心を伝え、心地の修行」と紹欧の茶を評する。
バブリーな境遇に安住するのではなく、「慎ましく」、「謙虚で」、「上品な」生き方に価値を見出す。
●藤原定家「詠歌大概之序」より
和歌を作る時に大切なのは、稽古である。いにしえの名歌を習い、名人を見習ってその真似をすること。
その主たる目的は、ただ形ばかりまねる事では無く、その人の心を学ぶことである。
それから、何をおいても作為が一番大切である。人と同じ事をするのではなく、一歩踏み出して自分を出す。
和歌で言えば人がまだ読んだ事の無い新鮮な情を求め詠む。これは茶の湯にも大切な事である。
この精神を茶の湯に取り入れた事により、わび茶の湯が本質を得て、形式を脱却し、生命を持った。
●芭蕉の不易流行について
「不易」とは、寂滅の永遠性を課題にしている。この風雅の精神を身に付け、本質を衝き、句を生み出すことで、
常なるもの、詰まり普遍性を追求したのである。
「流行」とは、自分を絶えず新しく変える努力をして、日々新しい自分となること、常に新鮮な作為を得て寂滅を捉え、
句に読み込むことである。簡単に言えば、無常という普遍の本質を探究することを、自分自身の人生の課題としていたのである。
芭蕉は世俗を離れて、生きながらに己を無にして自然と一体となることで、本物の自分を見出すことが出来たのである。
無を求めることもまた執着であるが、わびは無にあるのではなく、仏の道(禅)のあるがままの人生観にあるのである。
芭蕉は、仏法に開眼したことにより俳句に開眼し、「芭風」を興し得たのである。これは紹鴎の茶と同じ構図である。
紹鴎はわび茶によって、芭蕉は俳諧によって、直感的に奥深い小宇宙を探究し、宇宙の原理を発見したのである。
利休のわびさび
わび茶で求めるものは本来、世俗をはなれ、隠遁の世界で得られる心の静けさであるべきである。
しかし利休は信長や秀吉といった権力者の茶頭として、政治の中に我が身を置いた。
そして、最後迄天下人秀吉との葛藤に心をみだしている。その生き方は、心の静けさとはほど遠いものだった。
秀吉は統治の術の一環として茶の湯を利用し、利休と結んだ。これにより利休の発言力が伸長するが、
わび茶は、政治の道具にされ、その思想も干渉された。
「茶の湯の心を持つには、どうすれば良いのかを探る」
権威が廃れ、古い物差しが使い物にならなくなった時代、良く言えば自由、悪く言えば放埒な世の中、一体何が正しいのか、
自分で判断する基準がほしい。その基準の一つに「禅」があるが、やがて禅は形式主義、権威主義に落ち入る。
そこで、一休が禅宗の腐敗を痛罵して、自由な禅の在り方を主張。
我が国では人里離れ山中深く入り込み修行すると、普通の人には見えないものを心の目で見る事が出来るようになる。
この事は、根源的にして不変なるものを見る能力の事で、常なるものの本体の事で、
人間としてより良く生きようとする際の、私欲を捨てた仏の心、理念の事である。
人が良く生きようとすると、人生の意義や目標、そして価値判断の基準が必要になって来る。これが無ければ混乱するばかり。
価値基準と言ってもいろいろで、茶碗で言えば、道具としての「使用価値」、どれだけで売れるかという「取引の価値」、
そして鑑賞するための「美的価値」がある。秀吉も紹鴎も利休も追求したものは人生における美であろう。
人生は人それぞれで、何に価値を見出し、どれだけ深く生きたかが重要である。
禅とは一つの事物に精神を集中し、その真の姿を知ろうとする事で、知ったとしても心の平安が得られるだけで、
実益のある物ではない。コツコツと知識と実践を積み重ねて同じ事を深く行い、己を磨いてゆくと、やがて、
一つの知識と別の知識が融合するのであろう。悟ろうという気持から吹っ切れてこれを超え、昇華した所に、
新境地が出現し、物の本質を捉えて自然体を得、本物の名人、自由人になるのである。
茶の湯の世界でも「茶の湯者覚悟十体」に(我より上の人と知音するなり。人を見知りてともなうべし)
有能な人は多くの知識や人脈を持っている。彼らから学ぶべき事、得られる物は多い。
有能な人との繋がりが多ければ多い程、情報の質と量が増加する。
茶の湯者の心の変化
精神的な美を求める茶の湯者は、荘厳の美に満足しなかった、荘厳の美から吹っ切れた時、そこから一転して、
不要の美をそぎ落ししていく。そして荘厳の完璧な美の対極に位置する。簡素で静寂な、
自然に近い日本独特の美、いわば消極・否定の美の究極に、わび・さびの美を完成させたのである。
茶の湯における美の創造とは、具体的に何をする事かと言えば、
従来認識されていなかった新たな美を自ら発見し、茶室に再現する事なのである。
富貴の人がわび者の真似をして貧乏ぶるは「さばす」であって「さび」ではない。
茶の湯のさびは自然にさびるのがよいので、「さばす」であってはならない。
珠光の「心の文」より
一番いけないのは、己が心の我慢我執であり、これを抑えなくてはならない。
この様な心の有様は自然に身に付かないものであり、修行を積んで我慢我執を抑える心の師とならなければならない。
「我慢」と言う語は現代語の意と違い、慢心して我意を張ること、我が意を通すこと、思い上がりのことである。
わびの美とは、我が意を徹することではなく、自然の摂理との調和にこそある。
堕落、傲慢の心を戒めた、現代社会でも道徳規範の根元となり得る観念である。
紹鴎の茶の湯において一番大切な心は、和歌におけるわびと同じであり、茶の湯に具現化したことにある。
亭主はわびさびを身に付け、それを茶室で演出し、客はわびさびの感性を磨き、
これを感じ取る。わびとは不足を味わうこと、不自由な自由である。
「不足不自由の美」を味わうことで、亭主も客も普段は見えない宇宙の体系美を感じ、
神の声を聞き取ることが出来る境地に至るのである。
紹鴎のたどった軌跡は、旧来の社会制度もモラルも崩壊した自由社会への激動期の、
社会変動に対応する「自己改革運動」であるといえよう。個人や集団の欲望に基づく活動を制御しなければ、
健全な社会を保つことはできない。住み良く健全な、あるべき社会を実現し維持するには、
私利私欲にとらわれる己の弱さを捨て去るよう修行し、正義の精神を会得しなければならない。
その為の選択肢の一つとなるのが「わび」である。まるい豊かな心を持ち、実り多い人生を送って欲しいと願ったのだ。
わびと貧乏は違う
まず心の持ちようからして違う。わびはワビを追求し、その過程で何をなし得たかの過程である。
紹鴎の言うわびは、隠遁の心第一にわびて宇宙の究極に美を求め、閑寂を楽しむ心のあり方で、
心豊かな茶の湯の世界なのである。貧乏は夢を持てない。あるいは夢破れた、その結果のしがなさである。
本阿弥光悦は、利休を一応名人と認めながらも、権力と結んで、茶の湯を俗化させたと批判している。
利休が創造したのは、冬の枯れ木に美的価値を置いて我が茶風とする、ものに立脚した美である。
紹鴎の茶の湯の心は、虚飾を取り去った誠である。これは、人の生活の規範となすべきもので、
成熟した現代社会を健全に守るためには忘れてはならない。欧米人もこれを持ってはいるが、
ともすれば自己主張のハッキリした、外向的な開拓魂の陰に隠れてしまいがちである。
ある種内省的な世界で、ハッキリしない中庸さに真実を求める人生観である。これは芭蕉のわびとも共通する。
珠光の茶の湯の真髄を知るには、一休から与えられ、「不法も茶の湯の中にある」
と悟った園悟墨蹟の文面に籠められていた深い意味こそが重要なのである。要するに珠光が遺言した茶の湯の奥義とは、
ものへの執着からの解放なのである。しかし、利休は物や珠光の嗜好に執着していたようである。
利休のわびは冬から春を想起するところにあるのではない。実際の利休の審美眼は、
春の雪解けに象徴される生命の躍動などというものとは真逆の、黒茶碗の黒、利休鼠のネズミ色など、
墨の濃淡の様な枯れたものに美を見出していた。
紹鴎が禅の実践や和歌を基本に外来文化の和洋化を図ったのに対し、利休・宗二は外来文化を崇拝し、
儒教を基本に漢詩や水墨画を取り入れたのである。
利休は秀吉の茶頭であり、秀吉と利休とは主従の関係にあった。殿中にあって利休が、
秀吉の立場に配慮することなく茶人として茶の湯上の真念を貫くことは、もとより無理なことだったのである。
利休は己の美学を以って茶風を興そうとしていたが、従来、茶の湯で重要な要素は一、目利き・一、
作分(創意工夫)・一、手柄(功績)・一、心の働きなどであったが、利休の心の働きは、機知、
機転の類に基軸を置いていたのである。
「山上宗二記」によれば、
利休は名人なれば、山を谷、西を東と、茶の湯の法を破り、自由せられても、面白し。
平人それを其の侭似せたらば、茶の湯にては在るまじきぞ。とあり、利休が形式を破った茶を好んでいたのは確かなのである。
利休の師 武野紹鴎
武野宗延著 武野紹鴎研究所より抜粋
私は、利休百首よりの「降らずとも雨の用意」を茶の湯の心の働きの元としている。前もっての準備、
何かのことがあっても慌てることなく、自分を守ることができれば、相手の身にもなれる優しさが生まれるのではないか?
わびさびは、道具などには言うにおよばず、仕草や、心の働きの中にも取り入れ、我欲をおさえ、
「禅」の修行までは行かなくても、誰かのために、何のための茶会かを催すことに心がけたい。
茶会の目的 ①感謝へのお招き ②コミュニケーション
茶の湯の様式 ①濃茶(式的要素で心大らかに)食事(腹8分目)薄茶(身体共に楽しみ遊ぶ)
狙いところ ①茶のわび美を何処で表すか ②形式のオリジナル化 ③創意工夫な作品のお披露目
梶間 宗葉の茶の湯感













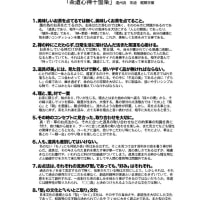
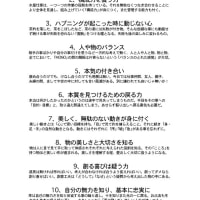
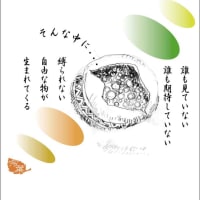

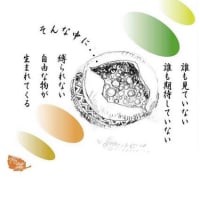
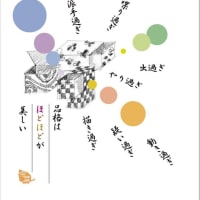
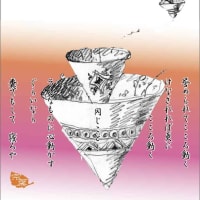
日本の実家では、反発して全くせず、こちらに来てから、すっかりはまってしまいました。現在、奥伝をかじり始めたところです。
貴殿のブログは、とても明解で、ときに寛容でやさしく、でも厳しさは的を得ており、すっかり魅了されてしまいました。今日初めて何件か読ませていただき、坦々とした口調も、大好きになりました。
初めから、じっくり読ませていただきますね!