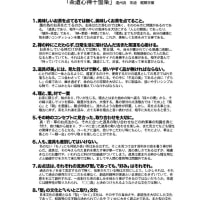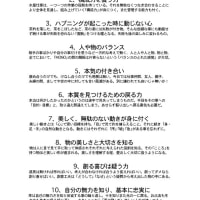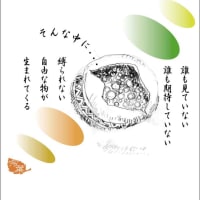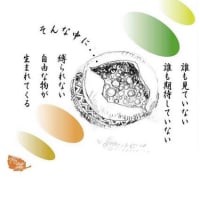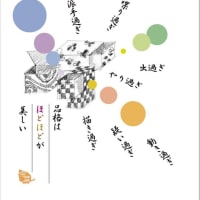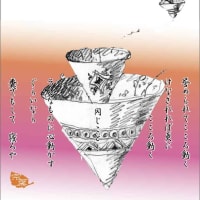宮本武蔵の最晩年に書かれた「五輪書」を皆木和義が観見の一振り 駒草出版より抜粋。
武蔵は全ての発想を兵法へと発展・進化させた。
私は趣味の段階ではあるが、茶の湯を兵法に置き換えたならば、茶法と考える事が出来るのではないか。
前回の内田樹氏の武道の技とお茶の点前を置き換えてみた。
今回は武蔵の生きざまと茶道との一致する部分を見つけ出し、自分への糧と為し「老計」への指針となす。
●武蔵は、「五輪書」全体を通して、勝つための五つの要諦を記している。
一、相手の心と相手の動きを見抜く観察力、洞察力の鋭さ
二、剣の技量の卓越さと敏捷さ
三、相手に勝つための仕掛けづくり
四、情報収集力
五、志と勝利へのあくなき執念
60回余りの不敗の理由は、実践の修行の中から「相手の心を見抜く術」を身につけた。
「火の巻」の教えの中の「敵になる」とは、現代で言えば、
「顧客の立場に立つ」顧客の心になり切る」という事であり、現代の経営の基本である。
茶道では、勝つ、とう言うのは、美味しくお茶を飲んで頂くためのあらゆる条件を指すとする。
相手の喜びそうな事、お茶道具やビックリさす仕掛け等は、相手を良く前もって知らなければ
タイムリーなものにならない。お茶事での会席で相手の嫌いなモノを出してはお話しにならん。
技は美しさの中に、間や残心、守・破・離の動作と心のゆとり持つ事が勝つための一つになる。
●「独行道」は、晩年の心境を書き込んでいる。
武蔵が自身の心を冷徹に管理するための必須の項目だった。
そもそも、自己管理が出来ない人間には、初めから戦う資格などないのだ。
一、世々の道を 背く事なし
一、身に楽しみを たくまず
一、よろずに依怙(えこ=不公平)の心なし
一、身を浅く思い 世を深く思う
一、一生の間 欲心思わず
一、我事において 後悔せず
一、善悪に他を妬(ね)む心なし
一、いずれの道にも 別れを悲しまず
一、自他ともに 恨みかこつ心なし
一、恋慕の道 思いよる心なし
一、もの事に すき好む事なし
一、私宅において 望む心なし
一、身一つに 美食を好まず
一、末々代物なる古き道具 所持せず
一、我が身に至り 物忌みする事なし
一、兵具は格別 よの道具たしなまず
一、道においては 死をいとわず思う
一、老身に財宝所持 もちゆる心なし
一、仏心は貴し 仏心をたのまず
一、身を捨てても 名利は捨てず
一、常に兵法の道を 離れず
だから兵法は、物事の本質をしっかりととらえた上で、真っ直ぐで純真な心で実践しなければならない。
茶道では、剣、茶に限らずここまで自分を管理する事が出来ればただひたすら「独座観念」
●武蔵は相手を観察する事に関して「観の目つよく、見の目よわく」と言っている。
一事で言えば、「目で見るよりも心で見よ」という意味。
戦いの目配りにおいて物事の本質(相手の心も含めて)、真理を深く広く冷静に心で見極める事を第一にしている。
姿、形、挙動などの表面の動きや現象を見ながら、心の目でより強く見るのである。目先の太刀や敵の動きなどにとらわれてはならない。
茶道では、お点前の仕草を目で見て、その日のお道具などを観の目でとらえ、亭主のこころ尽くしを五管で受け取る。
●将棋の大山名人はマンネリという知らず知らずのうちに忍び寄って来た自分の心の中の大敵を倒した。
対戦相手を含めいろいろな事に慣れることから、心の中にマンネリズムが蔓延して行く。
これが無意識のうちに、見えない敵となり、スランプの元凶の一つになっていく。
こういう場合は心機一転、全て過去の常識を捨てて、新人になる。つまり、自分をまっさらに純粋化することが、
自分の心の中の邪心を払い、新たな良い運を作る事になる。皆木さん何故か武蔵から大山氏へ何せ武蔵は負けた事がないんで・・・
茶道では、というか、もの事全てに於いて、経験があっての挑戦の始まりだろう。
大山氏のレベルまで達した事のない我々には捨てる物さえまだ出来てはいない。
が・・・スランプという大袈裟なものではなく、ただ「できな〜〜〜イ」と思う事は何時も感じる。
そういう場合には、くさるのではなく、今この状態が俺の実力。何らかの努力をしていると思えるならば(何もしていなければ問題外)、
焦らず、その内上手くなるだろうと自分の心の中の負の部分を追い出そう。
●五輪書は1645年5月、死の間際まで筆を取り続けた武蔵の勝つための実践兵法書である。この道を学ぶための九つの方法論。
兵法行道九箇条
一、邪心を持ってはならないこと
二、二天一流の兵法の道を実践的に鍛錬すること
三、剣だけでなく、多くの他の芸術、文化に触れること
四、自分の道だけでなく、ほかの仕事や職業の道を知ること
五、合理的にもの事の利害得失を判断すること
六、あらゆることについて、本質を見抜く目を養うこと
七、目に見えないものであっても、直観によって悟り得るように
すること
八、どんな些細なことにも真剣に、しかも慎重に注意すること
九、兵法の道において役に立たない無駄なことはしないこと
そして、ありとあらゆるすべてのことが、兵法の真理を極めるという一点に有り、これに向かって一意専心、鍛錬して、
この真理を会得するならば、百戦百勝であるという。決して途中の過程を飛ばしてはいけないのだ。
茶道では、客の相手に邪な考えで接することの無いように心を鍛え、茶道は総合芸術と言われるものであるから、
自分のやっていることが無駄にはならず、必ずそれを活かすチャンスに巡り会う。
合った物を逃がさないためにも本質を見抜く観の目をしっかり育てておこう。
三種混合ワクチンではないが人生においての味つけとして、自分の好きなこと3つを取り入れることで、
お互いに影響しあい上手く回転することが出来る。三種の中に取り入れる大枠は、
「文科系・趣味」「スポーツ・武道」「楽器演奏」「アート・芸術」などで、より深い茶道になると思うのだが!
●石舟斎は儒教の基本的な徳目である「五常」にその道を求めた。「五常」とは人が常に守り、行うべき五種の道、
すなわち仁・義・礼・智・信である。仁は、慈悲・慈愛の心。義は正義を貫き通す心。礼は、礼節を重んじ、人を敬う道。
智は、道理・真理を正しく把握する知恵を働かせること。信は、誠意・真心・信頼の心。
この道がなきがゆえに、また微弱になっているが故に人の心も乱れておかしくなるのだ。
茶道では、柳生の兵法道、哲学と命のやり取りはないが、行き着く所は同じだ。
「茶の五常」を考えるに千家なら「和・敬・清・寂」遠州流なら「勤・謹・和・緩」さしずめ私なら「和・美・創・楽・慎」
●兵法とは絶対に勝つことである。これを事業や仕事に置き換えたら、顧客の満足・喜び・感動を獲得することである。
さらに、自分が人生という兵法の道場で修行を積み、勝ち取った「心」が大きければ大きいほど、
深ければ深いほど自分の器は大きくなり、人格が高まり、兵法の至極に近づく。
武蔵は兵法の理の仕事も含め、いろいろな諸芸に応用して、深め、広げて行くことが改めて大切だと強く思った。
そうする事によって、兵法と諸々の仕事や諸芸の双方向から、今の殻を外から内からうちつけていけば、倅啄同時で兵法の道が極められるはずである。
茶道では、というより、茶道も同じような茶法を持って道を切り開いて行くのでしょう。今の茶道に於いて問題となっているのは何なのか、
この辺りをクリアーしなければ解決を見ることは出来ないし、指導者側だけが躍起になっても問題は無くすることは出来ない。
殻の内外同時に声を上げよう。
●武蔵は、南宋の哲人官史であった朱新仲の「人生の五計」を改めて自分に当てはめての5つの計画
第一、「生計」我、如何に生くべきか 天から授かった使命を考え
第二、「身計」如何に身を立てるか 社会にどのように貢献するか
第三、「家計」如何に家と家庭を正しく営んで行くか
第四、「老計」如何に老い、老後を充実させていくか
第五、「死計」如何に死すべきか 死を前向きにどう受け入れて行
くか
茶道では、生まれた時からお茶に携わっていないので、私のお茶に関わった人生を五計で言えば、使命までもいかないが「生計」では、
男のための茶、男性だから出来るお茶、男性だからやって欲しいお茶との関わりを稽古する場をつくること。ここで目標は定まる。
「身計」では生計で立てた「男の茶道塾」から、お茶のある人生が如何に潤いのある生活となることを知ってもらう。
「家計」では男女に関わらず心葉会という仲間つくりを行う。
「老計」まさに、今の私の環境。茶に感心のある人なら誰でも参加することが出来る、もっとオープンな会に発展させ、
お茶のある充実した人生を知ってもらうこと。「死計」我一人座して飲む!な〜〜〜んて言うのはヤダ!
茶の湯は目標ではなく、お茶を活かして人の為になることを主眼に置く手段として活かそう。
今は、北海道子供ホスピスサポートに参加し自分は何が出来るのだろうと模索中!計画したらまず実行!
●生きざまの反省
一、自分の「生」をひたむきに誠実に尽くしているか。
二、自分の心・魂を常に磨き、浄化・純化・深化させているか。
三、世のため、人のために、自分の出来ることを通して、一隅を
照らしているか。
太陽に慣れなくてもいいから、自分の力で明るく照らすホタルであれ。「自分はこれだけのことをして死のう」という気概こそが大切だ。
「老いるは嘆くに足らず、嘆くべきは 老いて虚しく生きるなり」
結び
「我、茶の心を持って 生きぬく」
武蔵は全ての発想を兵法へと発展・進化させた。
私は趣味の段階ではあるが、茶の湯を兵法に置き換えたならば、茶法と考える事が出来るのではないか。
前回の内田樹氏の武道の技とお茶の点前を置き換えてみた。
今回は武蔵の生きざまと茶道との一致する部分を見つけ出し、自分への糧と為し「老計」への指針となす。
●武蔵は、「五輪書」全体を通して、勝つための五つの要諦を記している。
一、相手の心と相手の動きを見抜く観察力、洞察力の鋭さ
二、剣の技量の卓越さと敏捷さ
三、相手に勝つための仕掛けづくり
四、情報収集力
五、志と勝利へのあくなき執念
60回余りの不敗の理由は、実践の修行の中から「相手の心を見抜く術」を身につけた。
「火の巻」の教えの中の「敵になる」とは、現代で言えば、
「顧客の立場に立つ」顧客の心になり切る」という事であり、現代の経営の基本である。
茶道では、勝つ、とう言うのは、美味しくお茶を飲んで頂くためのあらゆる条件を指すとする。
相手の喜びそうな事、お茶道具やビックリさす仕掛け等は、相手を良く前もって知らなければ
タイムリーなものにならない。お茶事での会席で相手の嫌いなモノを出してはお話しにならん。
技は美しさの中に、間や残心、守・破・離の動作と心のゆとり持つ事が勝つための一つになる。
●「独行道」は、晩年の心境を書き込んでいる。
武蔵が自身の心を冷徹に管理するための必須の項目だった。
そもそも、自己管理が出来ない人間には、初めから戦う資格などないのだ。
一、世々の道を 背く事なし
一、身に楽しみを たくまず
一、よろずに依怙(えこ=不公平)の心なし
一、身を浅く思い 世を深く思う
一、一生の間 欲心思わず
一、我事において 後悔せず
一、善悪に他を妬(ね)む心なし
一、いずれの道にも 別れを悲しまず
一、自他ともに 恨みかこつ心なし
一、恋慕の道 思いよる心なし
一、もの事に すき好む事なし
一、私宅において 望む心なし
一、身一つに 美食を好まず
一、末々代物なる古き道具 所持せず
一、我が身に至り 物忌みする事なし
一、兵具は格別 よの道具たしなまず
一、道においては 死をいとわず思う
一、老身に財宝所持 もちゆる心なし
一、仏心は貴し 仏心をたのまず
一、身を捨てても 名利は捨てず
一、常に兵法の道を 離れず
だから兵法は、物事の本質をしっかりととらえた上で、真っ直ぐで純真な心で実践しなければならない。
茶道では、剣、茶に限らずここまで自分を管理する事が出来ればただひたすら「独座観念」
●武蔵は相手を観察する事に関して「観の目つよく、見の目よわく」と言っている。
一事で言えば、「目で見るよりも心で見よ」という意味。
戦いの目配りにおいて物事の本質(相手の心も含めて)、真理を深く広く冷静に心で見極める事を第一にしている。
姿、形、挙動などの表面の動きや現象を見ながら、心の目でより強く見るのである。目先の太刀や敵の動きなどにとらわれてはならない。
茶道では、お点前の仕草を目で見て、その日のお道具などを観の目でとらえ、亭主のこころ尽くしを五管で受け取る。
●将棋の大山名人はマンネリという知らず知らずのうちに忍び寄って来た自分の心の中の大敵を倒した。
対戦相手を含めいろいろな事に慣れることから、心の中にマンネリズムが蔓延して行く。
これが無意識のうちに、見えない敵となり、スランプの元凶の一つになっていく。
こういう場合は心機一転、全て過去の常識を捨てて、新人になる。つまり、自分をまっさらに純粋化することが、
自分の心の中の邪心を払い、新たな良い運を作る事になる。皆木さん何故か武蔵から大山氏へ何せ武蔵は負けた事がないんで・・・
茶道では、というか、もの事全てに於いて、経験があっての挑戦の始まりだろう。
大山氏のレベルまで達した事のない我々には捨てる物さえまだ出来てはいない。
が・・・スランプという大袈裟なものではなく、ただ「できな〜〜〜イ」と思う事は何時も感じる。
そういう場合には、くさるのではなく、今この状態が俺の実力。何らかの努力をしていると思えるならば(何もしていなければ問題外)、
焦らず、その内上手くなるだろうと自分の心の中の負の部分を追い出そう。
●五輪書は1645年5月、死の間際まで筆を取り続けた武蔵の勝つための実践兵法書である。この道を学ぶための九つの方法論。
兵法行道九箇条
一、邪心を持ってはならないこと
二、二天一流の兵法の道を実践的に鍛錬すること
三、剣だけでなく、多くの他の芸術、文化に触れること
四、自分の道だけでなく、ほかの仕事や職業の道を知ること
五、合理的にもの事の利害得失を判断すること
六、あらゆることについて、本質を見抜く目を養うこと
七、目に見えないものであっても、直観によって悟り得るように
すること
八、どんな些細なことにも真剣に、しかも慎重に注意すること
九、兵法の道において役に立たない無駄なことはしないこと
そして、ありとあらゆるすべてのことが、兵法の真理を極めるという一点に有り、これに向かって一意専心、鍛錬して、
この真理を会得するならば、百戦百勝であるという。決して途中の過程を飛ばしてはいけないのだ。
茶道では、客の相手に邪な考えで接することの無いように心を鍛え、茶道は総合芸術と言われるものであるから、
自分のやっていることが無駄にはならず、必ずそれを活かすチャンスに巡り会う。
合った物を逃がさないためにも本質を見抜く観の目をしっかり育てておこう。
三種混合ワクチンではないが人生においての味つけとして、自分の好きなこと3つを取り入れることで、
お互いに影響しあい上手く回転することが出来る。三種の中に取り入れる大枠は、
「文科系・趣味」「スポーツ・武道」「楽器演奏」「アート・芸術」などで、より深い茶道になると思うのだが!
●石舟斎は儒教の基本的な徳目である「五常」にその道を求めた。「五常」とは人が常に守り、行うべき五種の道、
すなわち仁・義・礼・智・信である。仁は、慈悲・慈愛の心。義は正義を貫き通す心。礼は、礼節を重んじ、人を敬う道。
智は、道理・真理を正しく把握する知恵を働かせること。信は、誠意・真心・信頼の心。
この道がなきがゆえに、また微弱になっているが故に人の心も乱れておかしくなるのだ。
茶道では、柳生の兵法道、哲学と命のやり取りはないが、行き着く所は同じだ。
「茶の五常」を考えるに千家なら「和・敬・清・寂」遠州流なら「勤・謹・和・緩」さしずめ私なら「和・美・創・楽・慎」
●兵法とは絶対に勝つことである。これを事業や仕事に置き換えたら、顧客の満足・喜び・感動を獲得することである。
さらに、自分が人生という兵法の道場で修行を積み、勝ち取った「心」が大きければ大きいほど、
深ければ深いほど自分の器は大きくなり、人格が高まり、兵法の至極に近づく。
武蔵は兵法の理の仕事も含め、いろいろな諸芸に応用して、深め、広げて行くことが改めて大切だと強く思った。
そうする事によって、兵法と諸々の仕事や諸芸の双方向から、今の殻を外から内からうちつけていけば、倅啄同時で兵法の道が極められるはずである。
茶道では、というより、茶道も同じような茶法を持って道を切り開いて行くのでしょう。今の茶道に於いて問題となっているのは何なのか、
この辺りをクリアーしなければ解決を見ることは出来ないし、指導者側だけが躍起になっても問題は無くすることは出来ない。
殻の内外同時に声を上げよう。
●武蔵は、南宋の哲人官史であった朱新仲の「人生の五計」を改めて自分に当てはめての5つの計画
第一、「生計」我、如何に生くべきか 天から授かった使命を考え
第二、「身計」如何に身を立てるか 社会にどのように貢献するか
第三、「家計」如何に家と家庭を正しく営んで行くか
第四、「老計」如何に老い、老後を充実させていくか
第五、「死計」如何に死すべきか 死を前向きにどう受け入れて行
くか
茶道では、生まれた時からお茶に携わっていないので、私のお茶に関わった人生を五計で言えば、使命までもいかないが「生計」では、
男のための茶、男性だから出来るお茶、男性だからやって欲しいお茶との関わりを稽古する場をつくること。ここで目標は定まる。
「身計」では生計で立てた「男の茶道塾」から、お茶のある人生が如何に潤いのある生活となることを知ってもらう。
「家計」では男女に関わらず心葉会という仲間つくりを行う。
「老計」まさに、今の私の環境。茶に感心のある人なら誰でも参加することが出来る、もっとオープンな会に発展させ、
お茶のある充実した人生を知ってもらうこと。「死計」我一人座して飲む!な〜〜〜んて言うのはヤダ!
茶の湯は目標ではなく、お茶を活かして人の為になることを主眼に置く手段として活かそう。
今は、北海道子供ホスピスサポートに参加し自分は何が出来るのだろうと模索中!計画したらまず実行!
●生きざまの反省
一、自分の「生」をひたむきに誠実に尽くしているか。
二、自分の心・魂を常に磨き、浄化・純化・深化させているか。
三、世のため、人のために、自分の出来ることを通して、一隅を
照らしているか。
太陽に慣れなくてもいいから、自分の力で明るく照らすホタルであれ。「自分はこれだけのことをして死のう」という気概こそが大切だ。
「老いるは嘆くに足らず、嘆くべきは 老いて虚しく生きるなり」
結び
「我、茶の心を持って 生きぬく」