 今から、期待と緊張に胸を膨らませながら市民会館での管弦楽とソリスト、合唱団の総練習に行ってきます。
今から、期待と緊張に胸を膨らませながら市民会館での管弦楽とソリスト、合唱団の総練習に行ってきます。音あわせとも言います。
 下の文章は、2000年の高槻市民合唱団の第九演奏会の様子です。
下の文章は、2000年の高槻市民合唱団の第九演奏会の様子です。当時、社会風潮がこれほど変化すると想像できたでしょうか?
あの頃は、将来にたいする希望と夢にあふれていました。
期待したような変化はあらわれず、嫌な風潮となってきています。
指導された合唱指揮者の大谷先生が言われた言葉、
「ベートーベンの生きた当時の社会のことをもう一度かんがえてみて、想像してみてください。」
「友愛、平等、平和。こういう社会を望んだベートーベン。人は平等なんだ。そうじゃないか!」
「折しも起こったフランス革命。ベートーベンの気持ちを考えたらもう少し歌い方も違ってくるはずです。」
「皆さん、もう少し大げさな位、情熱的に歌いましょう
 」
」 現実の日本は、様変わりして大きく舵を切り直していっています。
現実の日本は、様変わりして大きく舵を切り直していっています。風信子の気持ちも
 の頃とは違ってきています。
の頃とは違ってきています。今年の大谷先生の指導で一番、こころに響いた教えでした。
 さあ、16時には外出します。
さあ、16時には外出します。大谷先生も来て下さってると嬉しいな。

| 「オーケストラ、少しテンポを早くして」 指揮台の上にかがみこむようにしてタクトを振りつつ、手塚幸紀(ゆきのり)は明晰な声で指示を出した。 オーケストラの奏者は、指揮者の方を見ていない風に、集中して譜面を追っているもようにみえる。だが、ややうつむいた額(ひたい)あるいは、前髪か眉のあたりに、指揮棒が微かに上下するのを捉えているに違いない。 つまり、もっと演奏を速くしたいという指揮者の気持ちは、十分に伝わっていたはずだ。素人の合唱団員でさえ、楽譜を眼で追いながら、掲げた楽譜の上あたりで、それを感じているものなのであるから。 にもかかわらず、変化はなかった。その夜、高槻混声合唱団の一員として参加していた海耶(みや)は戸惑った。 大阪フィルハーモニー交響楽団は、指揮棒の動きを、あえて無視していたとしか思えない。指揮にくらべて僅かに演奏が遅れている。弦楽器の、そのロー・テンポは、さっきから海耶(みや)の気持ちををじりじりさせていた。 息切れしそうなゆるやかさ。だが、指示を受けたオーケストラが、ゆっくりしたテンポを。軌道修正してゆくようには思えなかった。執拗に同じテンポ。ゆるぎないテンポ。 気色ばむと、顔面から湯気たつような怒気をあらわにする指揮者と、じっとこらえて面(おもて)に変化のない指揮者がいるとすると手塚幸紀は後者である。むしろ、コーラスを指導していても飄々(ひょうひょう)としたのびやかさがあった。首をふって落胆を示すより、持ち上げてから落ちをつけて笑わせるタイプなのだ。 自信のない、あるいは水準に達していない合唱団を目のまえにしても 「決して悪くはないですよ、決して。まだ十分になんとかなるでしょう。少なくとも、本番までには」と情けをかけてくれる寛容さがあった。 その手塚の顔に徹かな苦衷(くちゅう)が滲(にじ)んだ。意のままにならぬオーケストラがいた。だが、時間がもうない。今夜のオケ合わせを、わずか一時間ほどで終わらせると、素人合唱団は明日が本番なのだ。指導すべきは合唱団で、オーケストラではない。 今までピアノのみで練習してきた200人のコーラス集団が、今夜、当日と同じ舞台(市民会館)に立っている。これを、オーケストラと引き合わせて練習し、慣れさせ曲の感じをつかませるというのが、今夜の目的である。 手塚の様子は、連結客車を牽引(けんいん)する蒸気機関車が、あえぎつつ懸命に峠を越えようとしているようであった。必死に奮闘しながら、けっして表情を崩さずに指揮を続ける指揮者。 しばらくのあいだ、緊迫(きんぱく)した空気が流れた。明日の演奏曲目はベートーベンの「第九」である。 大阪フィルハーモニーがベートーベンの『第九』を常任指揮者・朝比奈隆との共演で、200回目の演奏をして話題になったのは、平成3年の12月29日であった。その後も師走の恒例として、朝比奈が『第九』を振る習慣は続いている。平成7年の今年も大阪フィルと朝比奈の演奏会の日程を、海耶(みや)は新聞紙上でみていた。 朝比奈カラーのテンポの遅い『第九』は評判が高い。その馴染んだ色を雰囲気を崩すことを、楽団は拒否しているのではないか。しかし、手塚幸紀だとて、72年から82年までの10年間を大阪フィルハーモニー交響楽団の指揮者として過ごした実績があった。今夜は客演とはいえ、まったくの赤の他人ではないのだ。 指揮者と奏者のしのぎをけずる駆け引きは、常に演奏にはつきものらしい。27歳の小沢征爾がNHK交響楽団の指揮者に就任したのは昭和37年の6月、半年後の12月には小沢ボイコットがおきている。オーケストラは容易なことでは、手綱(たづな)を操れぬようだ。 『第九』の場合、200人の合唱団が舞台に登場するのは、ふつう第3楽章が終わってすぐである。今夜の練習でも、そのつもりで上手と下手の両方からしずしずと現われるところから始まった。 魅惑の第4楽章。わずか、15分足らずの合唱だが、すべての人が胸を轟かせて今夜の練習を楽しみにしていた。すでに第1楽章から第3楽章までの演奏練習は終わっている。 気灘しいオーケストラ団員と指揮者は、市民会館での夕方まで続いた練習で、どう折り合いをつけていったのだろうか。第3楽章の非常に美しいアダージョを、愛惜するがゆえにも心を込めて、朝比奈隆は限りなくゆっくりと演奏するというが・・・。 夜に入って、4人のソリストと200人のコーラスとのオケ合わせ。オーケストラの間に疲労が色濃く漂わずにいるのが不思議なくらいである。音楽が人の心を高揚させてそんな影を消してしまっているのだろうか。 明日の朝には、本番を前に総練習するゲネプロがある。ゲネプロとは本番とまったく同じ進行で練習するこである。つまり、たった2回の合同練習で、本番を迎えるわけである。その緊張感は演奏家とはいえ同じことだろうに。 手塚幸紀は指揮者というより、俳諧師(はいかいし)のような風貌である。本番指揮者として、高槻混声合唱団の練習に臨んだのはこれまでに2回。諧謔(かいぎゃく)に満ちた語り口は皆の緊張感をやわらげ安心を与えていた。 「なかなかいいですよ。うん、本番までにはもうちょっとマシなものに仕上がると思いますよ。大丈夫、安心してくだすって結構です」 そんなユーモアを解する手塚は思案のすえに、やがてきっぱりと言った。(テンポアップの指示は、すでに2回出されていた) 「よろしい。オーケストラには、テンポをこれ以上早くする気がない。ないのですね。解りました。それでいきましょう」 えっ…。と海耶(みや)達は、驚いて、思わず手塚の顔をみつめた。皆、固唾を飲んでいる。指揮者はオーケストラに屈したのか? 手塚は、合唱側の方へすかさず顔を振り上げて、 「しかし、コーラス。コーラスは私の指揮どうりに歌ってください。私の指揮棒を見て。オーケストラの演奏に合わせないで。オーケストラの音に引きずられることなく、私の方を見て歌ってください」 合唱団員の間に動揺のざわめきが起こった。手塚は、あぜんとする合唱団の方をなだめるように見て言う。 「大丈夫。大丈夫です。指揮をみて歌って。もともと暗譜なんだから、皆さん、私の顔をみるのになんの苦労もないはずです。コーラスから半拍遅れてオーケストラの音が入ってきます。先にでたコーラスの音の上にすぐに冠さってゆくので、まったく問題ありません。安心して歌ってください。ただ、、オーケストラにあわせちゃ駄目です。絶対に僕に合わせて。大丈夫だから」 ああ、なんということだろう。いつものことながら、悠長ともいえる練習を重ねてきたコーラスは本番前に毎回、度肝(どぎも)を抜かれるようなことを体験することになる。 しかしながら、半拍のずれは私にも、じれったかったのであるから、迷いながら歌うより手塚に従う方が楽である。不安に思いながらもホッとする。 楽譜どおりに歌うといいながら、音符による演奏上の規定が、かくも柔軟性を持ち、指揮者の曲の解釈によってずいぶんなテンポの幅があるなどとは、コーラスを始めるまで知らなかった。 海耶(みや)は、残念なことに1度も、朝比奈隆の指揮に聞きほれたことはない。ただ、「美しさに陶酔するうちに段段テンポは遅くなるものです」と言う彼の談話をどこかで読んだことはある。 敬愛する指揮者と200回以上おなじ曲目を演奏していって(たった1回の演奏会の為に、ソリストは、なんと200回は練習すると聞いた。おそらくオーケストラも…)、その染みこんだ演奏は不動のものとして存在するものであろう。そう考えるとオーケストラの妥協の限りが、あの半拍のずれとなってあらわれているのやもしれず。 心の動揺をなだめながら私は思い出した。 平成4年の高槻混声合唱団は、モーッアルトの作品『レクイエム』を上演した。 私にとっては、前年のヘンデル『メサイア』に続いての参加である。 初見の楽譜は、高低なだらかで比較的に歌いやすかったが、半年で20数回の練習では、素人の悲しさでまったく覚束無(おぼつかな)いと思った。 そこで、半年間は仕事から戻ると、料理をしながら1度、寝るまでに布団のなかでもう1度、と、とにかく毎日CDを聞くことに努めた。 これは偶然に手にしたカール・ベームの演奏である。やがて、カール・ベームの演奏は、心地よく私のものとなっていった。 練習はおおよそ平均律で覚えて歌ってゆく。家での試聴とあまりへだたりがなく、あまり違和感がなかった。 さあ、そこで。本番での演奏と指揮者はテレマン室内管弦楽団と延原武春である。両者は子飼(こが)いの朗党(ろうとう)と頭領(とうりょう)といった関係で、楽団は指揮者に従順(じゅうじゅん)である。 始めに軽く流して、お互いを知ろうとする。そのすべり出しから、私は反発を覚えた。耐え難い苦痛がキリキリと胸を襲ったのは、余韻をすべて取り払った歌い方を強制されたからである。 事前の練習では、 「おそらく、節ごとの歌い終わりは練習のときよりは、かなり流したものになるでしょう抒情(じょじょう)的な息の長い、歌い方が普通ですので、皆さんは伸ばしすぎて息が苦しくなるかも知れません」ということだった。 ところがどっこい、芸術家膚(はだ)の彼の解釈は、進歩派なのかどうか、思いきりよく、音の最後を切り捨てるものであった。しかし、どれだけユニークな解釈を指揮者がしたとしても、コーラスは従わなければならない。 なんという酔狂(すいきょう)さだろう。情けない思いをしながら、泣く泣く指示どうり歌うつらさといったらなかった。落胆と失望が、海耶(みや)の心を覆(おお)った。 「今まで、何の為に練習してきたのだろう・・・」 あくまでも素人の海耶に天才、延原武春の指揮の意図や解釈はわかるはずもないのだが、進む方向で舵を取られっぱなしというのは、大層、苦痛なものである。 「ちよっとどうにかして欲しいわ」という周囲のつぶやきで、大方の人の不満を知った。だが、どうしょうもない。指揮者の希望どおりに飛ぶような早さのテンポで演奏会は終わった。 こんな、猛然たる不興(ふきょう)を味あわせた相手にたいして、海耶(みや)は呪った。 『この偏屈な指揮者、延原武春の演奏会には絶対に足を運ばないぞ、誓って!』 音楽への理解など、たかだかしれた私の脳髄にさえ、予想を越えた演奏の幅にはこれほどの抵抗を覚えるものである。 音楽への思い入れも深く、日々、技を磨くことを目標にしている集団にとって、指揮者との葛藤(かっこう)は譲れぬ線をどう守るかということに尽きるのかもしれない。 さて、波乱を含んだ演奏会はおおむね好評のうちに終わった。手塚幸紀はうまくまとめあげて、高槻混声合唱団に昔より上手になったという評価さえ与えた。 海耶(みや)は満足だった。たくさんの友人に声を掛けて、ともに初めての『第九』を歌いあげるという夢をかなえたのだ。12月には皆で『Ⅰ万人の第九』に参加して、大阪城ホールで思いっきり歌った。 それから4年が過ぎた。今年のコーラスの練習指導者は語る。 「いい、テンポは生き物だということを忘れないで。ずうっと3拍子だからといって、始めから終わりまで同じ調子でテンポが続くとは限らないよ。テンポは息をしているんだよ。早くなったり遅くなったり。指揮者の気持ちしだいで変化してゆくんだ。だから、できるだけ指揮者をみて。できるだけ楽譜から目をあげて、指揮者の変化についていってね」 世紀末の今年は、年末恒例のベートーベン『第九』の演奏も、カウントダウンなどで、ひときわ華やかに奏でられることであろう。もちろん、人類愛を歌いあげたシラーの歌詩によって、新世紀を迎えるにふさわしい曲として年頭も高らかに謡いあげられ、そののちも『歓喜』で明け暮れる1年になることであろう。 海耶(みや)は、『第九』に聞き入るとき必ず第1楽章から第2、第3、第4楽章をていねいに楽しみつつ鑑賞してゆくようになった。 音楽は聴くことを重ねることによって、どんどん魅力に引き込まれてゆくものだ。変われば変わるものだ、高校の頃にはレコードを掛けたときは、すぐに飽きてしまって針を第4楽章「合唱」まで飛ばしてしまっていた。出だしと 歓びの唱 だけを聴いて、あとは退屈なもんだと感じていた。 ところが、 「皆さんは、第3楽章を眠たくなる、なくてもよさそううなどというけれど、ベートーベンの『第九』なかで一番美しい旋律を持っているのが、第3楽章なのですよ。だから僕は、あの第3楽章こそ、力いっぱい演奏するんです」 と、マエストロ朝比奈隆が語ったということを読んで、我慢してじっと聴くことにした。すると、よさがわかってきたのである。夜ごと、布団のなかで70分を聴く。本当はコーラス部分を覚える為に聴くはずであるが、最初から聴く。やがて私の脳味噌になんらかの窯変(ようへん)が起こってきて、深い愛着が沸いてきたのだ。 最後に、音楽の歓びは人間の感情の一番底のほうにあるものだという。わたしは、たくさんの音楽家の啓 の言葉に感動しながら21世紀も歌っていきたい。 小沢 「音楽はまず声から出発するんだ。全部の楽器は全部人間の声の代理なんだ」 レオナード・バーンスタイン「音楽を作るのは魂であり、集中力だ」 作者:海耶(みや)の後付。 この作品は、師匠、中浜みのる主宰する創作誌『風』に載せたものです。 この時点では、指揮者・朝比奈隆さんは存命中でした。昂揚した気分で、 ミレミアムの年に書いたのでした。 マエストロ朝比奈隆の演奏会へ行くチャンスはありませんでしたが、その CDを購入しました。そして、カラヤンや、小澤征爾などの4枚ほどのCDで 『第九』 の演奏の聞き比べをしました。 驚くほど、皆、演奏のテンポが違うのでした。 朝比奈隆さんのご冥福をお祈りします。 |
 他の風信子のツイッターまとめ。(ツイログ)
他の風信子のツイッターまとめ。(ツイログ) http://twilog.org/hyacinth_haru
http://twilog.org/hyacinth_haru| 日常のことツイッターでつぶやき中。 | 大阪府ブログランキング | 高槻情報人気ランキング |
 Twitterブログパーツ Twitterブログパーツ |  | |
 よかったらクリックお願いします。
よかったらクリックお願いします。














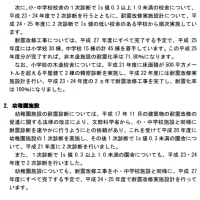
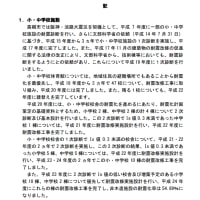
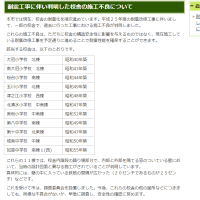


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます