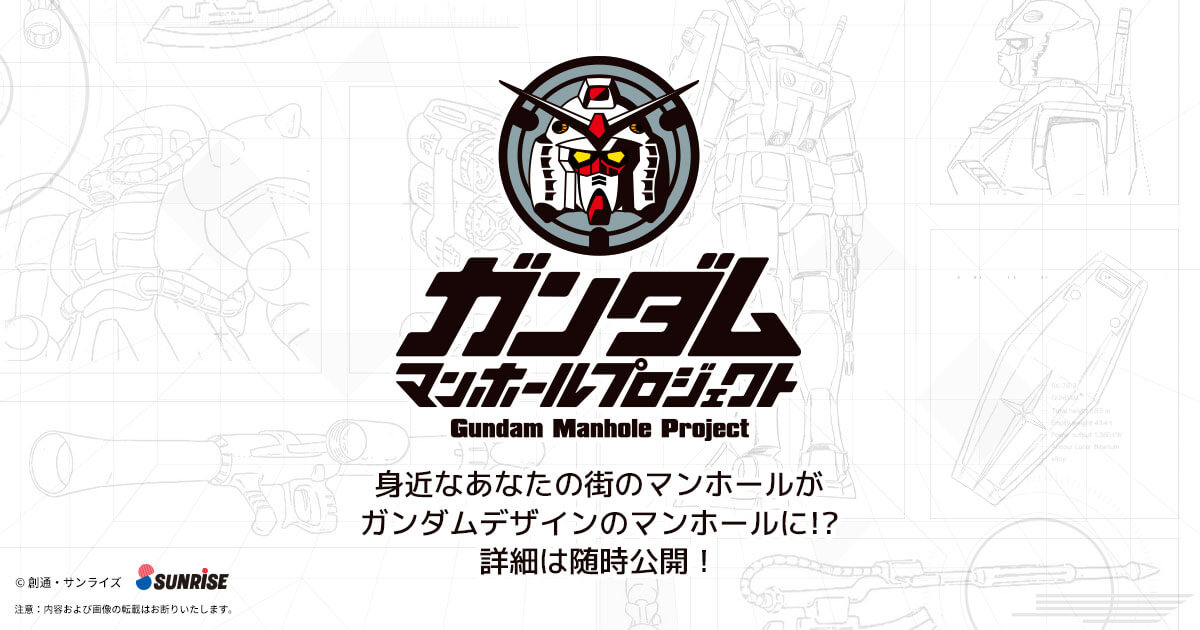展示方式が面白い。
スロープからも見えるが、望遠鏡がほしいところだ。
昔の道具が数多く収められていた。
剥製も多く見ごたえがあった。野鳥や虫まで。豊田で見ることのできるものが集められてる。
実際見たことのあるものは、猪、鹿、カモシカ、ニホンザル、オコジョ、タヌキ、フクロウ、オオタカ、もろもろ。クマはここらではたまに目撃情報が出るぐらいで、マムシに注意のほうがまだ身近。
地域の略ジオラマがあった。よく表現で来てる。手前が愛環の升塚車庫があって、奥に行くほど三河高原になる。最奥に風車発電が3本ほどたってるのだが、あんなん豊田市にあったっけ?謎が深まる。
検索してみた。
今年の正月のスキー場に行く途中にある。面の木の道路からだいぶ離れてるので見たことなかったんだ。おまけに『風力発電所へ行く道は、現在通行止となっております。通行止め解除時期は未定です。予めご了承ください。 』そりゃあ知られることはない。
というかあそこ、北設楽郡じゃないのか?豊田市ちょっと広すぎないか?
あそこ『クルマの街・豊田』『工員の街・トヨタ』という感じがちょっとまるでなさすぎてヤバイ。
2階は図書コーナーと売店とカフェ。
豊田市には昔話のいわれの地が、自分が知るだけでも5つは知ってます。もっとあると思います。『豊田の昔話』という本は無いので、せめて『愛知県の昔話』の本ぐらいは置いていてほしいです。昔話は子供にとって歴史を知る最初の入り口なので。
豊田市からの出土品、出品が多いが、町名で書かれても、橋の名で書かれても、地域が広い豊田市だけに、場所がピンとこない。次は地図も持っていこう。
信長公の肖像画(コピー)が見当たらなかった。またオリジナルの測量手帳も売ってなかった。残念。
実は先週もここに来てる。竣工後のダメ工事(竣工検査後手直し工事)の為に3日間休みだったらしい。がっくりして帰った。
今日は『升塚味噌』さんが屋外で五平餅を出品していた。
地元の味噌屋さん。会社名は『のだみそ』だったかな?確か豊田市のふるさと納税にも選ばれてる。
今は赤味噌だけじゃなく、田舎味噌みたいのも作ってる。豊田市は市外からの流入が多く、笑いながら「赤味噌辛くて食えない」とかほざく人まで出る始末。ジモティがそれ聞くとイラっとする。そのせいか食堂とかだと赤味噌と田舎味噌の味噌汁を選べることができるところがあったりする。そんなことから最近はいろんな味噌を作って、生き残りをかけてるみたい。
赤味噌とかここらでは岡崎市の八帖町で作る、『八丁味噌』が有名。カクキューさんとマルヤさんのところ。
『升塚味噌』さんところは、八丁と同じ製法で、樽の上に石を積む、樽石造りで本格的。八帖にないので八丁味噌は名乗れないが、八丁と同じような味。
豊田市でナンバーワンの味噌。
その味噌ががかかってる五平餅を食べる。
普段食べる、甘み強めを感じる赤味噌ではなく、さらに赤味噌感が強い。
これがまた、でらい、うまい。
「どこかに出店してたらまた食べたい。」と思うほど。
実は五平餅、長野・岐阜を中心として、南は愛知・静岡・神奈川、北は富山あたりまで食される。(神奈川は範囲外と思っていたのだが、一度食べたことがある。山梨は行ったことがない。石川とか新潟でも食というのもされてそうなのだが、今のところ食べたことがない。)
広域のもので、地方ごとに形状も違えば、餅の突き方の荒さも違えば、掛けるものがほぼ地方特色のある味噌なんだが、味噌の味が全く違う。たまに団子のアンみたいのがかかってるということもある。荒く突かれた、つぶれた丸餅に砂糖醤油がかかってたというのもあった。正直、五平餅の定義がよくわからない。
非常に地方特色が出てる食べもので、中部地方を旅行した時、『五平餅』のワードでを見るたびに食べるようにしてる。
今、気が付いたが、五平餅マニアだな。
喜多町にあったらしい建物。高校の頃、街中ぶらぶらしながら帰っていたので、なんとなく移設前のこの蔵をどこかで見た覚えがある。
お寺の横あたりだったかな?引き車の蔵と勘違いしてるかも。
かやぶき屋根の資料として撮影。
かやが2層というのを初めて知った。密度の高いのは稲の茎。荒いほうは薄(すすき)のようだ。
うちの祖母の在所はカニ家(漢字は不明)というのだが、祖母の在所が、昔かやぶき屋根だった。子供の頃に一度連れて行ってもらった時は、まだかやぶきだったのだが、そのうち流行のトタンぶきになっていた。
興味の元をなんとなく思い出して。