少し前ですが、2月17日の東京新聞「こちら特報部」に面白い記事がでていました。
小中学校の教科書から「鎖国」という言葉が消え、「幕府の対外政策」に変更されるそうです。何故か?
以下記事抜粋させていただきます。改行など少しだけ編集しました。

写真:東京新聞2017年2月17日
江戸時代は「鎖国」じゃなかった!?
東京新聞2017年2月17日
(前略)
文部科学省教育過程課の担当者は、
「学術研究が進展し、実態として対外的に交易の窓口があり、通商などを行っていたことが明らかになってきた。また『鎖国』という表現を当時の幕府は使っていなかった」
と理由を説明した。
(中略)
「鎖国という言説」の著者で熊本県立大の大島明秀准教授(洋学史)によると、「鎖国」という言葉の由来は、17世紀末に長崎・出島で勤務したドイツ人医師、エンゲルベルト・ケンペルが記した論文にあるという。
その表題を、蘭学者の志筑忠雄が1801年に「鎖国論」と訳した。もとの表題は長く、そのまま訳すと「今の日本人全国を鎖(とざ)して国民をして国中国外に限らず敢えて異域の人と通商せらざらしむ事、実に所益なるに与れりや否やの論」だったという。
大政奉還の66年前だ。その後、「鎖国」が使われることは少なく、江戸時代後期になっても、それほど浸透していなかったらしい。
頻繁に使われるようになったのは明治20年代からだという。同40年代には尋常小学校の教科書に「鎖国」が登場する。
大島氏は
「明治政府が『非文明的な江戸時代』と批難する文脈で使われるようになった」
と解説する。つまり、政治的に利用されたわけだ。
大島氏は、
「『鎖国』は便利な言葉だが、孤立して閉ざしていた、というイメージが強すぎた」
と指摘する。小中学校の教育で使わないことを支持しつつ、
「だからといってグローバルだったという話ではない。キリスト教弾圧があり、厳しい出入国管理があった。交流があったことをクローズアップするだけの教育ではいけない」
と注文をつける。
立教大の荒野泰典名誉教授(近世日本史)は、
「30年来のわれわれの主張が通った」と評価する。江戸時代、薩摩や松前など「四つの口」で交易をしていたことを挙げ、
「江戸時代も東アジアとの国際関係を持っていた。実態としては鎖国ではなかった」
として「鎖国観」の打破を提唱してきたという。
一方で、教科書から「鎖国」を完全に消すことには懸念を抱く。
「明治政府は、外国への開港が間違いではなかったことや、政権を取ったことの正当性を示すために『鎖国』という言葉を利用した。どのように語られ続けてきたかも、歴史事実として残さなければならない」と訴える。
(後略)
東京新聞2017年2月17日
(前略)
文部科学省教育過程課の担当者は、
「学術研究が進展し、実態として対外的に交易の窓口があり、通商などを行っていたことが明らかになってきた。また『鎖国』という表現を当時の幕府は使っていなかった」
と理由を説明した。
(中略)
「鎖国という言説」の著者で熊本県立大の大島明秀准教授(洋学史)によると、「鎖国」という言葉の由来は、17世紀末に長崎・出島で勤務したドイツ人医師、エンゲルベルト・ケンペルが記した論文にあるという。
その表題を、蘭学者の志筑忠雄が1801年に「鎖国論」と訳した。もとの表題は長く、そのまま訳すと「今の日本人全国を鎖(とざ)して国民をして国中国外に限らず敢えて異域の人と通商せらざらしむ事、実に所益なるに与れりや否やの論」だったという。
大政奉還の66年前だ。その後、「鎖国」が使われることは少なく、江戸時代後期になっても、それほど浸透していなかったらしい。
頻繁に使われるようになったのは明治20年代からだという。同40年代には尋常小学校の教科書に「鎖国」が登場する。
大島氏は
「明治政府が『非文明的な江戸時代』と批難する文脈で使われるようになった」
と解説する。つまり、政治的に利用されたわけだ。
大島氏は、
「『鎖国』は便利な言葉だが、孤立して閉ざしていた、というイメージが強すぎた」
と指摘する。小中学校の教育で使わないことを支持しつつ、
「だからといってグローバルだったという話ではない。キリスト教弾圧があり、厳しい出入国管理があった。交流があったことをクローズアップするだけの教育ではいけない」
と注文をつける。
立教大の荒野泰典名誉教授(近世日本史)は、
「30年来のわれわれの主張が通った」と評価する。江戸時代、薩摩や松前など「四つの口」で交易をしていたことを挙げ、
「江戸時代も東アジアとの国際関係を持っていた。実態としては鎖国ではなかった」
として「鎖国観」の打破を提唱してきたという。
一方で、教科書から「鎖国」を完全に消すことには懸念を抱く。
「明治政府は、外国への開港が間違いではなかったことや、政権を取ったことの正当性を示すために『鎖国』という言葉を利用した。どのように語られ続けてきたかも、歴史事実として残さなければならない」と訴える。
(後略)
「勝てば官軍、負ければ賊軍」といいますが、勝ったものは言いたい放題。
『鎖国』なんて言葉、江戸時代は使われていなかったのですね。知らなかった…。
江戸時代は、厳しい出入国の規制はあったにせよ、なんだかんだで、260年間も平和をたもち、独自の江戸文化を作り上げてきました。
(今、日本の文化を紹介する「日本すごい」系のテレビ番組が大流行ですが、それもまた、平和だった江戸時代の賜物だと思います。)
明治もだいぶたってから、ほとんどの人が知らない江戸時代の翻訳本を引っ張り出してきて、『鎖国』という言葉をピックアップして、過去の政権を批判するあたり、明治政府の徳川に対するプロパガンダだったのか。
当時の庶民の目線だと、徳川の時代を懐かしむ声も多かったのかもしれませんね。
徴兵制もはじまって、農民だろうがなんだろうが、日清日露と戦場に行かされ、散々だったでしょうし。
そういう国民の不満や批判を押さえ込むためにも、今話題?の国家の危機には忠誠を尽くせという教育勅語や、戦死したら神として祀る靖国神社など、いろいろなプロバガンダが、明治政府によって作られてきたのかなと思います。
「非文明的な江戸時代」と批難する意味で使った『鎖国』もその一環だったのだと思います。
★関連記事
洗脳的教育勅語
★3月31日追記
最終的に「鎖国」という言葉はこれからも使われることになりました。
だとしたら、逆に「鎖国」という言葉の成り立ちや、明治政府の立場など、全体像を説明した上で使ってほしいなと思いました。
→「聖徳太子」「鎖国」復活へ 指導要領改訂案を修正(ハフィントンポスト-2017/03/19)
だとしたら、逆に「鎖国」という言葉の成り立ちや、明治政府の立場など、全体像を説明した上で使ってほしいなと思いました。
→「聖徳太子」「鎖国」復活へ 指導要領改訂案を修正(ハフィントンポスト-2017/03/19)


















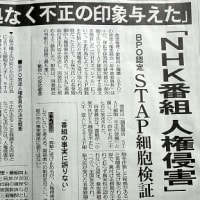






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます