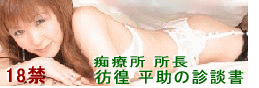乳がんの手術で乳房を残す「乳房温存療法」について、厚生労働省研究班は初の指針をまとめた。
温存療法は現在、乳がん手術の第1位の選択肢だが、施設により実施率が大きく異なる、放射線治療医など専門医抜きで実施している施設がある、などの問題を抱える。
指針の徹底で、施設間格差を縮め、全体の水準向上を目指す。
乳がんは日本人女性が最も多くかかるがんで、毎年約3万5千人が新たに患者となっている。
腫瘍の周りを切りすぎると乳房の形が悪くなりQOL(生活の質)が下がるが、切除が不十分だと再発率が高くなる。
日本乳癌学会によると、温存療法は80年代後半から広まり、03年に全摘手術を抜いた。
指針では、切除後も乳房の形を大きく損なわないなら腫瘍の大きさが4センチまで温存療法が許されるとした。
また腫瘍が複数あっても、近くに二つある場合で安全性が保てると判断されれば、温存の適応とした。
温存療法の場合、切除後、残された乳房に放射線を当てて再発を防ぐ。
指針では、日本放射線腫瘍学会に属する医師や技師が少なくとも1人、勤務していることを実施施設に求めた。
手術前に抗がん剤を使い、腫瘍を縮小することも推奨した。
温存療法に関しては、3センチまでの腫瘍を適応とするなどとした乳癌学会の99年の指針があるが、医療の進歩を反映するとともに、問題点の解消を狙った。
新指針をまとめた霞富士雄・癌研有明病院乳腺科部長は「実際に温存療法の適応となるのは60%台だろう。指針は強制ではないが、科学的根拠に基づいた診療をして欲しい」と話す。
指針は医師向けと患者向けがある。それぞれ各1部を乳癌学会の認定医に配り、近く出版もする予定。
(朝日新聞 記事参考)