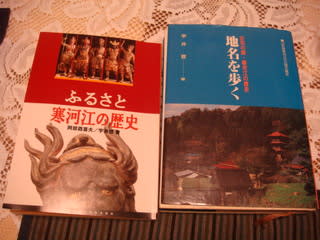
「ふるさと・寒河江の歴史」&「出羽の国・寒河江の歴史・地名を歩く」
一昨日 本屋のふるさとコーナーのような所で 偶然一冊の小冊子を見つけた
「ふるさと・寒河江の歴史」という本だ
昨年の7月 寒河江市教育委員会が出版
この本の中に「寒河江の地名」の由来について
面白い記事が載っていたので 少し紹介してみたい
寒河江という町の難しい名前の由来については
昔からいろいろな諸説があった
朝鮮から来た名前だとか いや アイヌ語だとか
その他もろもろ・・・・・・・・・・
だがどれひとつとして あまり裏づけのある説ではなかった
寒河江という地名は 4世紀~7世紀ごろ稲作と一緒に大陸からやって来た
渡来人(朝鮮人)と深くかかわっているようだ
奈良時代 稲作農業の先進地域から計画的な移民が
大和朝廷の手によって行われたようだ
まず 寒河江を寒河と江の二つに分けて考えてみると
寒河は寒川と書いても同じでこの地名は
全国で九州から北は秋田まで20箇所もあるようだ
現在の神奈川県に相模国寒川(寒川市)というところがある
出羽の国への移民は 関東の寒川地方の人々が植民して
自分たちの住むところに 故郷の地名をつけた場合が多いと思われる と書いてある
こうした関東地方の農民が出羽国に移民して 定住するようになったのが
われわれの住む寒河江であったろうと考えられる
次に なぜ寒川の下に江が付いたのだろうか・・・・・・?
それは 南に最上川 北に寒河江川(当時は寒河江川とは言わなかった)があって
寒河江川の旧河道の沼川が西から東に流れ 寒河江にそそいでいた
雨期に入ると 氾濫してあたり一面水浸しとなった
水の引いた後には いたるところ多くの入り江が出来た
寒川から移民して来た人達が住んでいた辺りも入り江が多かったから
初めは「寒川の江」と読んでいたのが
次第に「さがえ」と呼ぶようになったのであろう・・・・・・・・・・
因みに寒河江の地名が文書に出てきたのは 平安の末だが
それより以前の11世紀の中ごろには既に
藤原氏の荘園として成立していたといわれており
つまりは900年も前に 地名 荘園名として呼ばれていたことになる
このように寒河江の地名は
古墳時代に始まった開拓史と 深くかかわり合いを持っていたのである
・・・・・・・・のようなことが この本に書かれていた
なんとなく裏づけのしっかりとした 説のような気がする
ところで 話を最初に戻して
現在の神奈川県 相模国には朝鮮半島からの渡来人が多い
さがみ(相模)という地名は当時の渡来人が暮らした村を
「サガ」といったことに起因し
ここから派生した言葉が サガ(寒川)神社やサムカワ(寒川 寒河)などの地名として
残っているといわれている
・・・・・・・・・・・・・・・・だとしたら
現在の寒河江市民のルーツは・・・・・・・?
朝鮮半島までさかのぼっていく壮大なスケールを持っているような気がする
そうしてみると 一番はじめに書いた
朝鮮から来た名前・・・・・・・・・・まさにこれが正解だった




















私は本を読む機会なく、只ひたすら書きまくっているだけです。
さて 手持ちの「 地名を歩く 」を出版する時に、 座談会に出席しました。271ページに載ってます。 親父にお使いある事はこんな時ぐらいです。
温故知新・・・・故きを温ねて新しきを知れば以て師たるべし
諺通り 身の回りのすべての物事の価値を計る物差しとして 歴史に学ぶことが多々あります
バブル時代 土地はいつまで経っても右肩上がりのカーブを描き 値上がり続けるものと信じ込ませ 人々の購買欲を煽り立てました
・・・・・・・・・・・・
しかし 現在では 土地の値段は当時の半分ほどに値下がりしてしまいました
このように 人間が故意に造り上げた物事は
仮に長く歴史に残っても
後世 何事も歴史がその価値を正しく再評価して来ました
それ故 歴史を遡ることに興味が尽きません
寒河江の市街地や 農村地帯を歩いていても 歴史を考えると 何故か楽しくて ワクワク・ドキドキ・ソワソワ・・・・・・・
「地名を歩く」 271ページ
読みましたァ~~・・・・・・・!!!!
以前からこの本の{新町というところ」
を面白く何度も繰り返し読んでいましたが
kさんが座談会に出席していたとを初めて知りました
お互いの趣味が又ひとつ増えたようで これもまたなにかの「縁」があったのだろうと思いました
今後ともよろしく・・・・・