
プロジェクトの現調・ヒアリングで奈良に行き、その帰りに京都でプライベートの同窓会に合流した。苦楽を共にした日本各地から仲間が集まり紅葉真っ盛りの京都で笑顔を共にした。仕事で何度か京都に足を運んだことがあるが、いつもスタッフは東京の者ばかりで、ホントの京都の醍醐味までは知ることができない。今回は京都の地元の方がいろいろとアレンジしてくれたので、もうひとつ踏み込んだ京都を知ることができた。
関西圏は一般的に紹介者経由でないとなかなか入りづらいお店が多い。東京でも敷居が高いお店は同じだが、徹底しているという意味では関西圏のほうが上だ。その中でも京都というエリアは特別な気がする。“京都”の本当の楽しさを満喫するには、やはりよそ者が入り込みにくいところに文化があるような気がしてならない。
閉鎖的と一言で片付けると悪く取られがちだが、そこにはヨーロッパなどの国々と共通した人々の深みを感じる。これは差別とかではないが、人には楽しむことができる空間がそれぞれにある。大声張り上げることが楽しい人、静かに飲んでることが楽しい人。お店にはお店の演出と雰囲気があり、その雰囲気を創るのもお客様であったりするわけだ。お客さんを取捨選択する権利もお店側にもあるわけだ。
お金があれば何処にでも入れるという価値観はあまり好ましいとは思えない。しかしながら、店側も売上を考えるとお金をもっていればまあいいかって妥協しつつウエルカムを装ったりすることがある。
最低必要条件としてお店に入るにはお金が必要だが、それ以外にも人として何かがないと入れないお店。コネだとか紹介者がないと入れないというのはお店側の手段の話で、そんなことはたいした問題じゃないような気もする。そんなお店が多い京都はほんとうの遊びができる街じゃないかと思ったりする。
建築雑誌などでも紹介されていた鴨川沿いにある “The River Oriental” ちゃんと予約すれば誰でも入りやすいお店だ。鴨川を眺めながら一杯飲む。インテリアも相手との距離感を縮める演出がされていて、より相手のことをより深く理解しあえたりする雰囲気だ。
関西圏は一般的に紹介者経由でないとなかなか入りづらいお店が多い。東京でも敷居が高いお店は同じだが、徹底しているという意味では関西圏のほうが上だ。その中でも京都というエリアは特別な気がする。“京都”の本当の楽しさを満喫するには、やはりよそ者が入り込みにくいところに文化があるような気がしてならない。
閉鎖的と一言で片付けると悪く取られがちだが、そこにはヨーロッパなどの国々と共通した人々の深みを感じる。これは差別とかではないが、人には楽しむことができる空間がそれぞれにある。大声張り上げることが楽しい人、静かに飲んでることが楽しい人。お店にはお店の演出と雰囲気があり、その雰囲気を創るのもお客様であったりするわけだ。お客さんを取捨選択する権利もお店側にもあるわけだ。
お金があれば何処にでも入れるという価値観はあまり好ましいとは思えない。しかしながら、店側も売上を考えるとお金をもっていればまあいいかって妥協しつつウエルカムを装ったりすることがある。
最低必要条件としてお店に入るにはお金が必要だが、それ以外にも人として何かがないと入れないお店。コネだとか紹介者がないと入れないというのはお店側の手段の話で、そんなことはたいした問題じゃないような気もする。そんなお店が多い京都はほんとうの遊びができる街じゃないかと思ったりする。
建築雑誌などでも紹介されていた鴨川沿いにある “The River Oriental” ちゃんと予約すれば誰でも入りやすいお店だ。鴨川を眺めながら一杯飲む。インテリアも相手との距離感を縮める演出がされていて、より相手のことをより深く理解しあえたりする雰囲気だ。



















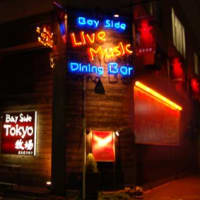
京都は大好きなところです。
比較的私の住んでいるところに近いこともあり・・・
確かに京都のお店は入りにくい雰囲気があります。
よく一般的に言う「間口が狭い」というのが、独特の雰囲気ですね。
私が京都によく行く理由は、妻との共通の趣味で寺社仏閣めぐり、父の仕事の関係で骨董の買出し、それにおいしいものを頂に行くためです。
特に、「おいしいもの」に関しては、京都で「はずれ」にあったことはありません。
いつも思うのですが、さすが日本料理人が修行に来る場だと思います。
たぶん、住んでいる人たちの舌が肥えているのでしょう。
「さば寿司」という京都名物をご存知でしょうか?
私はこれが大好物です。
昔は「ひかりもの」がとても嫌いだったのですが、京都のは全然違います。
なかでも、祇園の「いずう」と言うお店は最高です。
けれどその店はgreenpapperさんのいう、「入りにくいお店」なんですよ。
特に高級そうではないのですが、どちらかというと、「きたないすし屋」です。
(お店の人ごめんなさい・・)
テレビや雑誌でもよく紹介されるのですが、店が見つけにくく、また、店の前で躊躇する人が多いそうです。
ここの寿司は大手の百貨店でも売られているのですが、買ってみたら味が変わっていました。
この店で食べないと、本当のおいしさがわかりません。
私のお勧めは、実は「さば寿司」ではなく、夏限定の「はも寿司」です。残念ながら今の時期はありませんが、「京都のはも」は最高ですね!
それではまた!
京都に近いというのはうらやましいですね。
いつも入りやすいお店のことばかり考えていると
入り難いお店の価値観がボケてきます。
自分を戒めなきゃいけないですね。
お店はお客様との出会いの場であり
劇場で会ったりするわけですから
流れる時間の中で緊張感がなきゃいけないのかなって
そんな風に思ったりするわけです。
感動は緊張の中から生まれてきたりするわけですから
緊張感を演出しなければいけないときもありますね。
ハモは食べたことないです。
来年トライしますね。