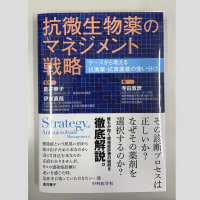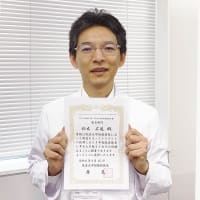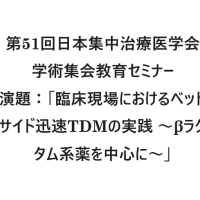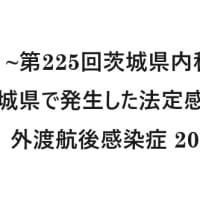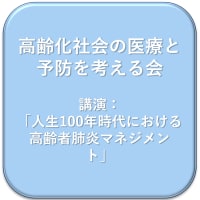日本小児感染症学会
要点
1 BQ. 先天梅毒の疾患概略は?
先天梅毒(Congenital Syphilis: CS)は、梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum: TP)が、胎 盤を通過して母体から胎児に感染する多臓器の慢性感染症
妊婦の梅毒感染例は、妊娠の有無が報告 項目になった 2019 年以降、毎年 200 例前後(全女性症例の 7‒9%)報告されており、先天梅毒の 年間報告数も 20 例前後報告。近年、大幅に増加傾向
【先天梅毒の届出基準】 下記のいずれに該当する場合
ア.母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合 イ.児の血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く超えて持続する場合 ウ.児の TP を抗原とする IgM 抗体陽性 エ.早期先天梅毒の症状を呈する場合 オ.晩期先天梅毒の症状を呈する場合
CQ1. 先天梅毒を疑う契機となる臨床所見は何か?
母体の感染歴があれば疑いは明らかである。一方で出生した時点では、先天梅毒患者の 6 割以上は 無症候あるいは所見が軽微であり、先天感染症に共通する症状や所見である胎内発育不全などから、 TORCH(Toxoplasmosis、Others、Rubella、Cytomegalovirus、Herpes simplex virus)症候 群の一つとして積極的に除外する必要がある。出生後は乳児期早期に症状が徐々に顕在化するため、先 天梅毒に比較的特徴的な所見である皮膚病変や鼻炎、貧血や血小板減少をもって疑う必要がある。この ように、臨床症状や所見のみから先天梅毒を診断することは困難なこともあるが、最終的な診断は母体お よび児の臨床経過に加え検査所見を踏まえ、総合的に早期に判断することが重要である
出生児において先天梅毒の臨床症状は、早期先天梅毒と晩期先天梅毒で大きく分けて考える。早期先 天梅毒は 2 歳未満に発症した臨床症状によって、晩期先天梅毒は 2 歳以上に発症した臨床症状によって 定義される
CQ2. 先天梅毒の検査は何があるか?
病変から直接同定する方法と、血清抗体価を測定し間接的に同定する方法がある。血清抗体価は非 特異的検査(rapid plasma regain: RPR)と梅毒特異的検査(TP hemagglutination: TPHA、TP latex agglutination: TPLA、fluorescent treponemal antibody absorption: FTA-ABS)がある。 母体と児の RPR を比較するとき、治療効果判定目的に RPR を連続測定する場合には必ず同じ検査試薬 を用いた検査方法を使用すべきである。
IgM は移行抗体ではないため、FTA-ABS-IgM の測定は、CS の診断の一助となりうる。ただ し通常 FTA-ABS の検査オーダーでは、IgG しか測定されないため、IgM の測定を目的とするコメントを 付与する必要があり、FTA-ABS-IgM は保険未収載検査である。
CQ3. 先天梅毒の治療適応はどのように判断するか?
[推奨] 児の先天梅毒を疑う身体所見の有無、児の RPR と出産時の母体の RPR の値の比較、母体の梅毒の 感染歴と治療歴を考慮し判断する。
① CS を疑う身体所見がある場合、②出産時 の児の RPR が出産時の母体の RPR よりも倍数希釈法で 4 倍以上高い場合(自動化法では 2 倍以上 を目安)、また、実施可能な施設は限られるが③胎盤・臍帯・病変部・体液などの暗視野顕微鏡または 特殊染色による鏡検や PCR 検査(保険未収載)陽性の場合、以上①~③のいずれかを認める場合は、 CS の可能性は非常に高い(proven or highly probable)と考える。この場合は、髄液検査(RPR、 細胞数、蛋白、など)、血液検査(RPR、TPHA、FTS-ABS-IgM(保険未収載)、などの血清学的 検査の他に、白血球分画、血小板数、など)、長管骨 X 線撮影検査(上肢、下肢)および CS 症状に 対する検査(眼底検査、聴力検査、腹部超音波検査、頭部画像検査、など)を実施し、10 日間のベ ンジルペニシリンカリウム(ペニシリン G カリウム®)の静注治療を行う。
CQ4. 先天梅毒児に対する有効な治療は何か?
[推奨] ベンジルペニシリンカリウム(ペニシリン G カリウム®)の 10 日間静注あるいはベンジルペニシリンベン ザチン(ステルイズ®)の単回筋注を行う
CQ5. 先天梅毒児のフォローアップに必要な項目は何か?(感染対策を含めて) [推奨] ・生後 2、4、6、12 か月に成長・発達や病変ごとの評価を行う。 ・血清学的検査は陰性になるまで 2‒3 か月ごとに評価する。
・出生時に児 RPR 陰性の場合、生後 3 か月で再検し、陰性であればフォローを終了する。 ・RPR が生後 6‒12 か月でも上昇する場合や低下しない場合には、髄液を含めた再評価を行い、ベン ジルペニシリンカリウム(ペニシリン G カリウム®)による 10 日間の治療を検討する。