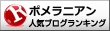母の日ガ第二日曜日なのに、なぜか父の日が第三日曜日になっちゃって、
母の日が先にありきで、あとから取ってつけたように・・
父の日ができいまだに定着しない現実を見ても、女性優位時代は明らかで、
女房関白という言葉はないが、かかあ天下は永久に不滅だ。
一時期は、ぬれ落ち葉や、座布団亭主などと小馬鹿にした言葉が年末大賞で選ばれ、
いまや男の願望にもほど遠い権威のなさだが、でも・オトウサンは、
物価高と戦いながら一家繁栄のために懸命に頑張っているんだぞぅ!!。
普段から距離感のあるお父さんも最近では家族が一緒の時間を過ごす
家族全員参加のイベントが各遊園地等々集いの広場でも、
父親の存在感を家族にアピ-ルする催し参加はチョッピリ嬉しいネ。
頑張ってください・・・オ ト ウ さん・・
お父さんへ・・・・