
念願の世界遺産、白川郷合掌造り集落に行きました。
大野郡白川村と高山市荘川町(旧荘川村)および高山市清見町(旧清見村)の一部に当たるそうで、白川村を「下白川郷」、他を「上白川郷」と呼ぶそうですが、今では白川村のみを指すようです。
白川郷の荻町地区は合掌造りの集落となっています。
1995年には富山県の五箇山(相倉地区、菅沼地区)と共に白川郷・五箇山の合掌造り集落として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。
白川郷の荻町地区は合掌造りの集落となっています。
1995年には富山県の五箇山(相倉地区、菅沼地区)と共に白川郷・五箇山の合掌造り集落として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。






明善寺鐘楼門
屋根は茅葺き。
1階に板庇(ひさし)をつけた珍しい建築物。加藤定七により、延べ人数1425人を要して建てたと伝えられているそうです。
梵鐘(ぼんしょう)は第二次大戦中に供出されたため、現在のものは戦後に鋳金工芸作家の中村義一氏(高岡市)によって作られたもの。

明善寺
庫裏と鐘楼門は県の重要文化財となっています。
見学料大人300円(2016年5月現在)

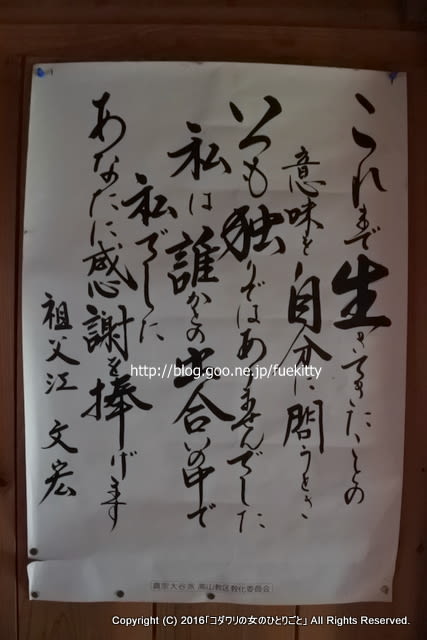

県の重要文化財の庫裏
明善寺庫裡郷土館
江戸時代末(1817年頃)に、高山の大工副棟梁与四郎によって建てられ客間のことである、「でい」が「口のでい」「奥のでい」と3室に分かれており、南側と表側の一部が庭に面して回廊になっているのが大きな特徴。
江戸時代末(1817年頃)に、高山の大工副棟梁与四郎によって建てられ客間のことである、「でい」が「口のでい」「奥のでい」と3室に分かれており、南側と表側の一部が庭に面して回廊になっているのが大きな特徴。





明善寺本堂
写真は本堂ではなく本堂の手前のお部屋です。本堂も見学しているのに写真がありませんでした。
本堂は北に縁があり、南側奥が花立部屋、北側は半鐘部屋、東奥側には後堂、中央部は2間で手前に外陣、その奥に一段高くして内陣があります。向拝の龍頭の彫刻がみごと。
写真は本堂ではなく本堂の手前のお部屋です。本堂も見学しているのに写真がありませんでした。
本堂は北に縁があり、南側奥が花立部屋、北側は半鐘部屋、東奥側には後堂、中央部は2間で手前に外陣、その奥に一段高くして内陣があります。向拝の龍頭の彫刻がみごと。






レンタサイクルの看板が可愛い。
確かに。意外と広いのでレンタサイクルがあると隈なく見学できるかもしれません。
















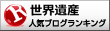











![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46c9f17b.96636b97.46c9f17c.83c810c6/?me_id=1423177&item_id=10000027&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ftwgtea%2Fcabinet%2Fimgrc0120778920.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)










