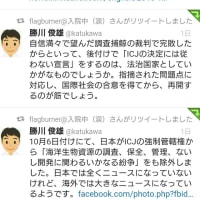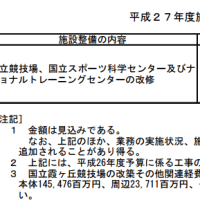何か知らないけど、「教育における機会の平等を追い求めるな」とのたまってる人がいた模様。
・「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう(2011年5月2日 BLOGOS)
BLOGOS といえば、天下の池田 信夫教授や佐藤 優氏などの(イカれた)論説が読めることから極一部の好事家(?)から熱烈な支持を受けている「ネット上の論壇誌」。
俺も時々 BLOGOS の論説を読んで鼻で笑っているが、wasting time? という HN の筆者による上の論説はあまりにも酷いので突っ込んでおくことにした。
この論説の冒頭、筆者は英国において長年 "Social Mobility"(社会流動性:元は社会学の用語らしい)向上が求められてると述べていた。
その一方、英国の実態はそれと程遠い、と切り返しつつ、優生主義全開な筆者の個人 blog(ややこしい)の過去記事(2011年2月13日付)を紹介していた[おまけ1参照]。
こっちも相当危険なのだが・・・。
この後、BLOGOS の記事は、英国の Civitas というシンクタンクに所属する Peter Robert SAUNDERS 氏による、telegraph.co.uk 2011年2月8日分の論説(2010年6月に SAUNDERS 氏が公開した『Social Mobility Myths』という本から引用してる)を引き合いに自説を展開していた。
・Must all students now pass the Nick Clegg test?(2011年2月8日 telegraph.co.uk)
上の記事から、筆者は"Social Mobility"が改善しなかったという研究結果を紹介してたのだが・・・。
以下、2011年5月2日分 BLOGOS『「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう~』から、telegraph.co.uk の記事に関する説明部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
イギリスは“Social Mobility”を実現するために教育分野でいろんな方策をとってきた。
しかし、成果はなかった。
また、スウェーデンでも学校選択制を導入しても廃止した場合でも、また国が教育に対する支出をいくらにしようとも“Social Mobility”は改善しなかった[おまけ2参照]。
(以下略)
---- 引用以上 ----
実の所、SAUNDERS 氏の論説ってのは、Nick GLEGG 英国副首相が打ち出してる教育制度修正案(特に高等教育)への非難、っつー意味もあるんだよな。
とはいえ、これについて説明すると本題から逸れまくるのでパス(笑)。
で、BLOGOS の記事では、SAUNDERS 氏の論説で紹介されてた研究から色々不思議な論を展開していた。
以下、2011年5月2日分 BLOGOS『「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう~』から、筆者の論を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
1. 左派にとって。
機会の均等を実現しても、結果は変わらない。
結局、低所得者層の子供は低所得者層に落ち着いてしまう。
であるならば、人間の能力に対する課税の意味も含めて所得の再分配をさらに推し進めるべきではないか?という主張を彼らはもっとすべきではないだろうか?(まあ、こんな主張をしても受け入れる人は少ないだろうけど・・・)
2. 上記の研究によれば、教育への投資はあまり意味がない。
制度をいじることもあまり意味がないという。
しかし、教育以外の政策が“social Mobility”に大きな影響を与えている可能性はあるのではないか?
生活保護世帯に生まれた子供が親が働かずに生活保護に頼って生きている姿を見て育ち働くことが当然とは思わずに、自分が大人になると同じように生活保護を受ける可能性が高いように。(いわゆる貧困の罠)
そういった誤った過度な社会福祉制度こそ改めるべきではないだろうか?
3. 成功のための基準を学歴で捉えているからおかしいのではないだろうか?
よりよい学歴を手に入れれば成功する。だから、学問をせよ。
と言う信仰は本当に正しいのだろうか?
(以下略)
---- 引用以上 ----
・・・低所得者層の子どもに限らず高所得者層の子どもも普通に低所得者層に行く可能性は(高等教育を受けても)あると思うが。
それに、生活保護や社会保障制度を「貧困の罠」の一環として敵視する意味がわかんない。
まさか、筆者は生活保護を削減すれば "Social Mobility"が向上するとでも本気で思ってるんじゃ?
なお、「貧困の罠」に関する議論は以下参照(手抜き)
・学習会報告「貧困の罠」 -セーフティネットの課題から地域自治の視点で考える-(2008年7月20日 東京生活者ネットワーク;.pdfファイル)
そして、筆者は、この論説を妙な言葉で〆ていた。
以下、2011年5月2日分 BLOGOS『「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう~』から、最後のオチを(略
---- 以下引用 ----
(中略)
機会の平等に過度に期待しすぎ、それを国家主導で過剰に推し進めようという主張は疑問だ。
それはあまり効果がないようだ。
その上、その基準がなぜ学歴や所得である必要があるのだろうか?
人間に一番大切なことは幸せに生きていくことなんだから。
それはお金では買えないものである。
---- 引用以上 ----
この筆者は、(教育における)機会の平等が保障されている社会制度を否定したいようだ。
それが行きつく所は、「百姓の子は百姓」という社会制度なのだが・・・。
それはそうと。
今回ネタにした記事の筆者である wasting time? に対して一言言っておきたい。
『今度から、"wasting time" という名前にしたら?』
おまけ:筆者である wasting time? の 2011年2月13日分個人blog の記事。
・所得格差が遺伝するのではない能力が遺伝する(2011年2月13日 ロンドンで怠惰な生活を送りながら日本を思ふ)
ここでは、Nicolas Greg MANKIW 氏の blog 記事(ややこしい)をネタにしつつ、親の能力が子どもに遺伝すると(多分得意げに)述べていた。
そして、(個人 blog の記事では英国を対象にしてるが)貧困層の子ども達が持つ能力の高さに疑問を呈していた。
以下、2011年2月13日分ロンドンで(略)『所得格差が~』から、問題の部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
こういった能力が遺伝するという大切な要素をあまり語らず、多くの人が「より機会の平等を」といい、納得してしまう。
それに反論するのも難しい。
しかし、その行き着く先は結果の平等だろう。
なぜなら究極的にスタート条件を同じにするならばすべての子供を親から引き離して施設にでもぶち込まなければいけないからだ。
それは何を意味するだろうか?
能力と努力だけがすべてを支配するギスギスとした競争社会であり、多様な家庭で育った多様な人材が生まれてくる多様性のある社会では決してない。
そんなことは容易に想像できる。
また、より良い教育やちょっと変わった(?)教育をしていこうと考えている親の教育の自由を奪うことでもあるはずだ。
イギリスでも貧困層の家庭の子供にもっと機会をという声は大きい。
しかし、誤解を恐れず言えば、貧困層の子供の多くは能力が残念ながら一部の例外を除けば低い可能性は高い。
そこになんでもかんでも税金をつぎ込むことは決して正しくないだろう。
効率性の観点からもおかしいだろうし、中流家庭の子供との比較感からの公平性の観点からもおかしいはずだ。
(以下略)
---- 引用以上 ----
いや、親の能力が子どもに遺伝する(低い→低い、高い→高い)とは限らないからさ・・・。
つーか、どこの優生学だ(毒)
おまけ2:『Social Mobility Myths』では、2005年に Institute for Public Policy Research が出したレビュー誌こと『Maintaining Momentum: Promoting social mobility and life chances from early years to adulthood』内に掲載された Gøsta Esping-ANDERSEN 氏の『Social inheritance and equal opportunities policies』を結構引用している。
BLOGOS の記事のまとめ方だと少しわかりづらいか。
なお、Civitas では、何故か『Social Mobility Myths』の全文が読めるようになっている・・・。
・Social Mobility Myths(2010年6月?日 Civitas;.pdfファイル@保存はお早めに)
また、英国における "Social Mobility" 向上の成果がないってのは、今年3月に OECD が出した報告書でも指摘されてる。
・Obstacles to social mobility weaken equal opportunities and economic growth, says OECD study(2011年2月10日 OECD)
OECD の報告書では、早期教育の段階で学力に応じてクラス分けをすると "Social Mobility" 低下を招くと指摘されてるが・・・。
・「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう(2011年5月2日 BLOGOS)
BLOGOS といえば、天下の池田 信夫教授や佐藤 優氏などの(イカれた)論説が読めることから極一部の好事家(?)から熱烈な支持を受けている「ネット上の論壇誌」。
俺も時々 BLOGOS の論説を読んで鼻で笑っているが、wasting time? という HN の筆者による上の論説はあまりにも酷いので突っ込んでおくことにした。
この論説の冒頭、筆者は英国において長年 "Social Mobility"(社会流動性:元は社会学の用語らしい)向上が求められてると述べていた。
その一方、英国の実態はそれと程遠い、と切り返しつつ、優生主義全開な筆者の個人 blog(ややこしい)の過去記事(2011年2月13日付)を紹介していた[おまけ1参照]。
こっちも相当危険なのだが・・・。
この後、BLOGOS の記事は、英国の Civitas というシンクタンクに所属する Peter Robert SAUNDERS 氏による、telegraph.co.uk 2011年2月8日分の論説(2010年6月に SAUNDERS 氏が公開した『Social Mobility Myths』という本から引用してる)を引き合いに自説を展開していた。
・Must all students now pass the Nick Clegg test?(2011年2月8日 telegraph.co.uk)
上の記事から、筆者は"Social Mobility"が改善しなかったという研究結果を紹介してたのだが・・・。
以下、2011年5月2日分 BLOGOS『「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう~』から、telegraph.co.uk の記事に関する説明部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
イギリスは“Social Mobility”を実現するために教育分野でいろんな方策をとってきた。
しかし、成果はなかった。
また、スウェーデンでも学校選択制を導入しても廃止した場合でも、また国が教育に対する支出をいくらにしようとも“Social Mobility”は改善しなかった[おまけ2参照]。
(以下略)
---- 引用以上 ----
実の所、SAUNDERS 氏の論説ってのは、Nick GLEGG 英国副首相が打ち出してる教育制度修正案(特に高等教育)への非難、っつー意味もあるんだよな。
とはいえ、これについて説明すると本題から逸れまくるのでパス(笑)。
で、BLOGOS の記事では、SAUNDERS 氏の論説で紹介されてた研究から色々不思議な論を展開していた。
以下、2011年5月2日分 BLOGOS『「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう~』から、筆者の論を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
1. 左派にとって。
機会の均等を実現しても、結果は変わらない。
結局、低所得者層の子供は低所得者層に落ち着いてしまう。
であるならば、人間の能力に対する課税の意味も含めて所得の再分配をさらに推し進めるべきではないか?という主張を彼らはもっとすべきではないだろうか?(まあ、こんな主張をしても受け入れる人は少ないだろうけど・・・)
2. 上記の研究によれば、教育への投資はあまり意味がない。
制度をいじることもあまり意味がないという。
しかし、教育以外の政策が“social Mobility”に大きな影響を与えている可能性はあるのではないか?
生活保護世帯に生まれた子供が親が働かずに生活保護に頼って生きている姿を見て育ち働くことが当然とは思わずに、自分が大人になると同じように生活保護を受ける可能性が高いように。(いわゆる貧困の罠)
そういった誤った過度な社会福祉制度こそ改めるべきではないだろうか?
3. 成功のための基準を学歴で捉えているからおかしいのではないだろうか?
よりよい学歴を手に入れれば成功する。だから、学問をせよ。
と言う信仰は本当に正しいのだろうか?
(以下略)
---- 引用以上 ----
・・・低所得者層の子どもに限らず高所得者層の子どもも普通に低所得者層に行く可能性は(高等教育を受けても)あると思うが。
それに、生活保護や社会保障制度を「貧困の罠」の一環として敵視する意味がわかんない。
まさか、筆者は生活保護を削減すれば "Social Mobility"が向上するとでも本気で思ってるんじゃ?
なお、「貧困の罠」に関する議論は以下参照(手抜き)
・学習会報告「貧困の罠」 -セーフティネットの課題から地域自治の視点で考える-(2008年7月20日 東京生活者ネットワーク;.pdfファイル)
そして、筆者は、この論説を妙な言葉で〆ていた。
以下、2011年5月2日分 BLOGOS『「機会の平等」という幻想を追い求めるのはやめよう~』から、最後のオチを(略
---- 以下引用 ----
(中略)
機会の平等に過度に期待しすぎ、それを国家主導で過剰に推し進めようという主張は疑問だ。
それはあまり効果がないようだ。
その上、その基準がなぜ学歴や所得である必要があるのだろうか?
人間に一番大切なことは幸せに生きていくことなんだから。
それはお金では買えないものである。
---- 引用以上 ----
この筆者は、(教育における)機会の平等が保障されている社会制度を否定したいようだ。
それが行きつく所は、「百姓の子は百姓」という社会制度なのだが・・・。
それはそうと。
今回ネタにした記事の筆者である wasting time? に対して一言言っておきたい。
『今度から、"wasting time" という名前にしたら?』
おまけ:筆者である wasting time? の 2011年2月13日分個人blog の記事。
・所得格差が遺伝するのではない能力が遺伝する(2011年2月13日 ロンドンで怠惰な生活を送りながら日本を思ふ)
ここでは、Nicolas Greg MANKIW 氏の blog 記事(ややこしい)をネタにしつつ、親の能力が子どもに遺伝すると(多分得意げに)述べていた。
そして、(個人 blog の記事では英国を対象にしてるが)貧困層の子ども達が持つ能力の高さに疑問を呈していた。
以下、2011年2月13日分ロンドンで(略)『所得格差が~』から、問題の部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
こういった能力が遺伝するという大切な要素をあまり語らず、多くの人が「より機会の平等を」といい、納得してしまう。
それに反論するのも難しい。
しかし、その行き着く先は結果の平等だろう。
なぜなら究極的にスタート条件を同じにするならばすべての子供を親から引き離して施設にでもぶち込まなければいけないからだ。
それは何を意味するだろうか?
能力と努力だけがすべてを支配するギスギスとした競争社会であり、多様な家庭で育った多様な人材が生まれてくる多様性のある社会では決してない。
そんなことは容易に想像できる。
また、より良い教育やちょっと変わった(?)教育をしていこうと考えている親の教育の自由を奪うことでもあるはずだ。
イギリスでも貧困層の家庭の子供にもっと機会をという声は大きい。
しかし、誤解を恐れず言えば、貧困層の子供の多くは能力が残念ながら一部の例外を除けば低い可能性は高い。
そこになんでもかんでも税金をつぎ込むことは決して正しくないだろう。
効率性の観点からもおかしいだろうし、中流家庭の子供との比較感からの公平性の観点からもおかしいはずだ。
(以下略)
---- 引用以上 ----
いや、親の能力が子どもに遺伝する(低い→低い、高い→高い)とは限らないからさ・・・。
つーか、どこの優生学だ(毒)
おまけ2:『Social Mobility Myths』では、2005年に Institute for Public Policy Research が出したレビュー誌こと『Maintaining Momentum: Promoting social mobility and life chances from early years to adulthood』内に掲載された Gøsta Esping-ANDERSEN 氏の『Social inheritance and equal opportunities policies』を結構引用している。
BLOGOS の記事のまとめ方だと少しわかりづらいか。
なお、Civitas では、何故か『Social Mobility Myths』の全文が読めるようになっている・・・。
・Social Mobility Myths(2010年6月?日 Civitas;.pdfファイル@保存はお早めに)
また、英国における "Social Mobility" 向上の成果がないってのは、今年3月に OECD が出した報告書でも指摘されてる。
・Obstacles to social mobility weaken equal opportunities and economic growth, says OECD study(2011年2月10日 OECD)
OECD の報告書では、早期教育の段階で学力に応じてクラス分けをすると "Social Mobility" 低下を招くと指摘されてるが・・・。