
お嫁ちゃん手作りの「ポットン落とし」
レンゲを上手に使えるまで成長しました😀

以前送ってくれた動画はこの容器に入れるのを楽しそうにしていただけなのに、今回の動画は成長を感じます😆
まだ2回しか会えていませんが、その成長に目を細めてしまう自分がいます😊
では今日のブログは以前調べたことです。
闘争・逃走反応(fight-or-flight response)とは動物が示す恐怖への反応(emergency reaction)である(1)。これに強く関わるカテコールアミンで、神経科学においては主に神経伝達物質として機能するドーパミン、ノルアドレナリン(またはノルエピネフリン)、アドレナリン(またはエピネフリン)の3つを指す(2) (3)。カテコールアミンは副腎髄質や交感神経、脳細胞から分泌され、血圧上昇、発汗、血糖上昇、覚醒、血液凝固系の亢進等の変化をもたらす。この作用により心臓や脳、筋肉への酸素やエネルギー供給を増加させたり、けがをした場合の出血を最小限にとどめたりする。ただ、これが長時間分泌されると過度のストレスとなり、また成長を妨げる原因にもなるので、普段は多く分泌されることはない。
このホルモンであるが、軽く触れる事により抑制され、強い刺激で増加する。なので子どもにやさしく触れることでこのホルモンは抑制され、安心した成長を助けることとなる(4)。
医療の原点は「手当て」である。痛いところに手を当てるところから始まった。これは古今東西いずれも同じだ。この「手当て」なる行為は医師や医療に携わる人の専売特許ではない。親御さんが常日頃から子どもにしている事だ。ここに書いた神経科学の分野からも、優しく触れることが子どものストレスの解放にどれだけ大切な事かわかるのではないだろうか。ほとんどの親御さんがすでに子どもの安全基地になっていると思う。だからこれからもしっかり子どもに触れて、安心できる場所で居続けてもらいたいと老婆心ながら切に思う次第である。
(1)
アメリカのウォルター・B・キャノンがホメオスタシス(恒常性)の中で提唱した防衛反応の一種。闘争・逃走反応(fight-or-flight response)はストレス反応として捉えることができ、不安や恐怖、交感神経系の興奮などの心理的・生理的な反応が生じる。「闘うか逃げるか反応」とも呼ぶ。
(2)
カテコールアミンとは本来カテコール基とアミノ基をもつ化合物であるが、神経科学においては主に神経伝達物質として機能するドーパミン、ノルアドレナリン(またはノルエピネフリン)、アドレナリン(またはエピネフリン)の3つを指す。
(3)
カテコールアミン(catecholamine)とは、副腎から合成・分泌される神経伝達物質の総称である。
(4)
「皮膚刺激と心身の健康」
心身健康科学10巻1号2014年










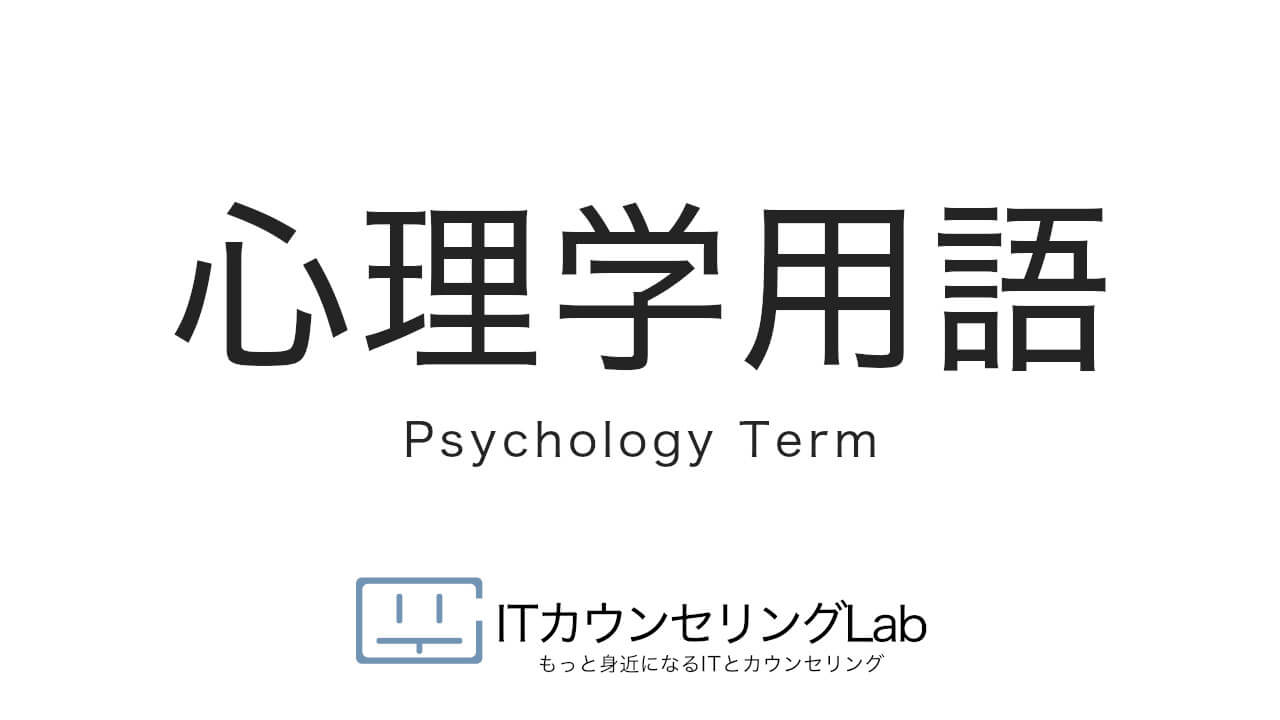
![カテコールアミン | 看護師の用語辞典 | 看護roo![カンゴルー]](https://www.kango-roo.com/kangoroo.png)











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます