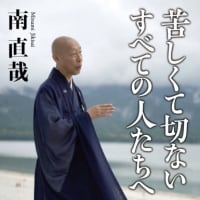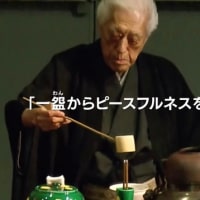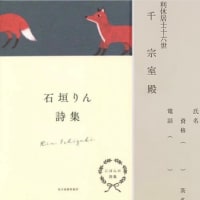もう随分昔のことになりますが、毎晩夫婦で声を合わせて、子守唄を歌っていたのを思い出しました。
双子の娘たちを寝かしつけるのは、片方ずつ担当で抱っこをして、夫婦で共同作業をすることになるのです。
家のなかで声を合わせて歌うことなど、それまでなかっただけに、私は歌っていて不思議と気持ちが落ち着くのを感じました。子育てがあまりにも大変で、その当時の記憶がほとんど飛んでいるという妻にとっては、信じ難いほどお気楽な話でしょう。
主に歌っていたのが「ゆりかごの唄」で、四番の「ゆりかごのゆめに/きいろい月がかかるよ/ねんねこねんねこねんねこよ」のくだりは、遠い異国で夢を見るような気持ちにさせられます。
ここで娘たちがおとなしく寝付く訳ではないので、一番の「ゆりかごのうたを/カナリアがうたうよ」に戻って、ひたすらリピートする、親にとっても催眠効果が非常に高いひとときでした。
こんなことを思い出したのは、先日の「天声人語」に子守唄について触れていて、いろいろなことを考えさせられたからです。長くなりますが引用します。
なぜ、人は子守唄を歌うのかーー。 鵜野さん(『世界子守唄紀行』著者ー引用者注)は世界各地をめぐりながら、そんな問いを考えてきた。もちろん、子どもを寝かしつける歌なのだが、果たしてそれだけだろうかと。
実際に子守唄といっても、「竹田の子守唄」やシューベルトの〈ねむれ ねむれ 母の胸に〉のような、郷愁を誘う曲ばかりではない。アフリカには、激しく太鼓を打ち鳴らす子守唄があるし、いくつかの国では子どもを怖がらせる歌詞もあるそうだ。
気づいたのは、子守唄が弔いの歌と似ていることだった。 他界した親しい人に歌うのも、幼き子に歌うのも、返事をしない魂に向け、思いを届けようとする行為にほかならない。それは無意識であれ、歌い手の心も癒やしている。
ひょっとすると、まどろみのなかで耳にした遠い調べは、かけがえのないメロディーであったのかもしれない。鵜野さんは言う。「へこたれそうなとき、人を支えてくれる力が、子守唄にはあるのでしょう」(「天声人語」2023.11.18)
私が子守唄を歌っていた頃、実母は入退院を繰り返しており、子育てに参加したくてもできない状態でした。義母が遠くから週一回訪ねて来て、買い物やら洗濯やらを手伝ってくれるのですが、私が帰宅する頃にはもう実家に帰っていて、お礼を言うこともできないような有様でした。
そう言えば、慣れない子守唄を精一杯歌うとき、遠いどこかに届けという思いがこもっていたと思います。弔いの歌ではないのですが、それは入院中の母や、お礼も言えない義母に向けていたのかもしれません。疲労困憊で記憶すら飛んでしまう妻に対しては、もちろん励ますように声をそろえていました。
そんなこともあって「返事をしない魂に向け、思いを届けようとする行為」という表現が、そのままあの頃の記憶に繋がるのです。そして、あの歌が娘たちを支える力になるかもしれないと思うと、ずっと遅れてこだまが返ってくる様子を連想します。
思い返せば、歌を歌うことで一番癒されていたのは、そんなことでしか子育てに参加できない私であり、それは妻にとっては割に合わない話だと思うのですが。