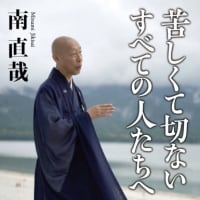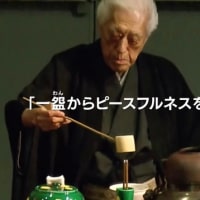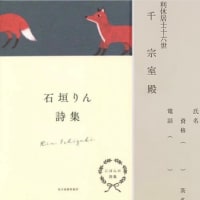中村哲さんの著書『医者、用水路を拓く』(石風社、2007年)は、ペシャワール会医療サービス(PMS)とアフガンの労働者たちが、さまざまな困難を乗り越えて用水路を拓くまでの6年間の記録です。
そのなかで、粛然とした思いで読まざるを得ないくだりが、中村さんの当時まだ十歳であった次男の死に至るまでの過程です。2001年6月にその子が脳腫瘍と診断されたとき、中村さん自身が脳神経の専門医であるにもかかわらず、アフガニスタンでの活動を続けざるを得ませんでした。2002年12月に様態が急変したため、中村さんは急きょ帰国することになります。
四肢の麻痺で体を動かせないその子は、中村さんの顔を見て「お帰りなさい!」と明るく目を輝かせます。しかし、やがて関節痛が高じて、普通の鎮痛剤が効かなくなり、我慢強い子が七転八倒するようになります。中村さんは日本では入手しづらいサリドマイドを、ペシャワールまでとんぼ返りしてまで手に入れようと考えます。PMSの仲間や他の医師の助けでようやく薬を手に入れたのが、その子の亡くなる2週間前でした。
息子の死に際し、「アフガニスタンの現地の今後も考え、情を殺して冷静に対処せねばならない」と考える中村さんは、その翌朝の様子を次のように記しています。
翌朝、庭を眺めてみると、冬枯れの木立の中に一本、小春日の陽光を浴び、輝くような青葉の肉桂の樹が屹立している。死んだ子と同じ樹齢で、生まれた頃、野鳥が運んで自生したものらしい。常々、「お前と同じ歳だ」と言ってきたのを思い出して、初めて涙があふれてきた。そのとき、ふと心によぎったのは、旱魃の中で若い母親が病気のわが子を抱きしめ、時には何日も歩いて診療所にたどり着く姿であった。たいていは助からなかった。外来で待つ間に母親の胸の中で体が冷えて死んでゆく場面は、珍しくなかったのである。
中村さんは我が子の死に接し、「空爆と飢餓で犠牲になった子の親たちの気持ちが、いっそう分かるようになった」と語るのです。
息子の死と、アフガニスタンの診療所外来で息をひきとる幼い子の死とを重ね合わせて、なおみずからをアフガニスタン支援に駆り立てようとする、志の高さに圧倒されます。