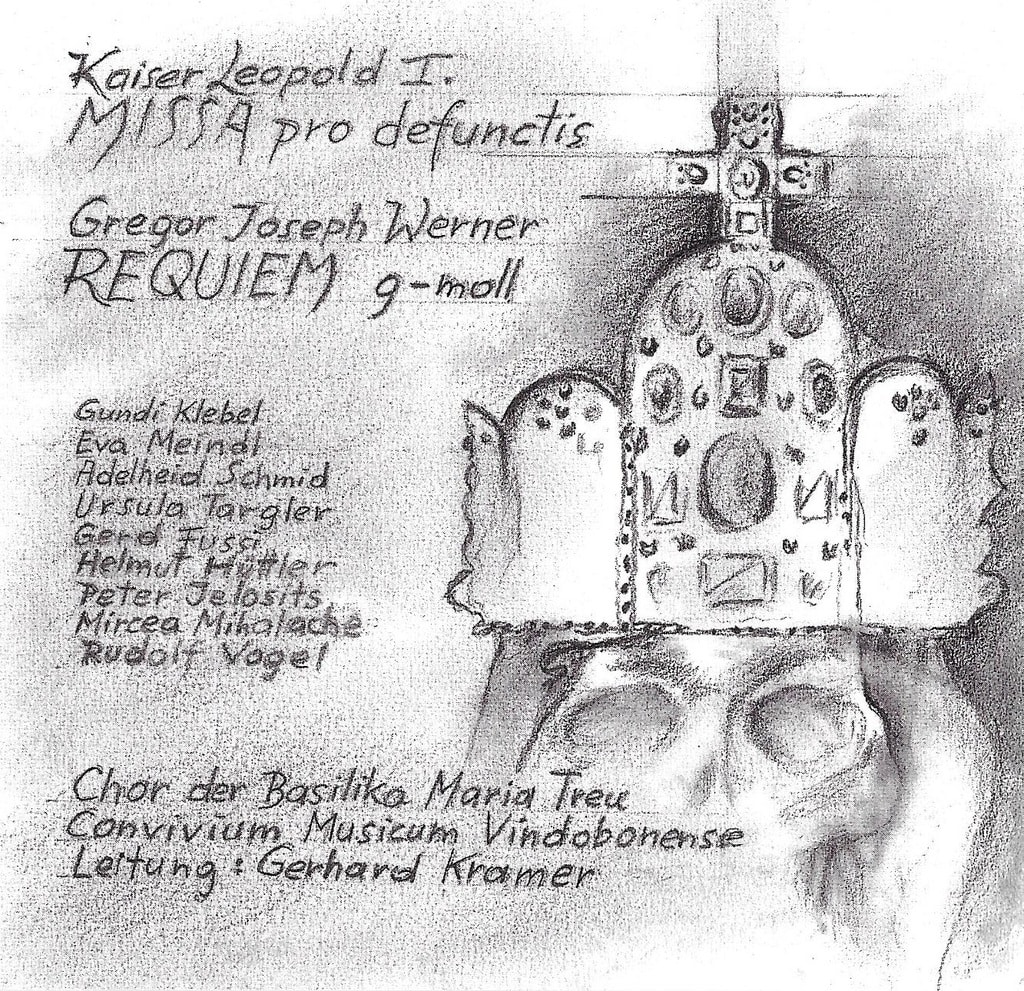Original text in Umbrian dialect: 邦訳(黒田正利による)
Altissimu, omnipotente bon Signore, いとも高く、万能にして、恵み深き主よ
Tue so le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
賛美、栄光、ほまれ、すべての恵みは主のものなれ
Ad Te solo, Altissimo, se konfano, いと高き主よ、こはみな主のものにして、
et nullu homo ène dignu te mentouare. 人はそのみ名を呼ぶにも足らず
Laudato si, mi Signore cum tucte le Tue creature,
ほむべきかな、主よ、主のつくりませる物みなと、
spetialmente messor lo frate Sole, ことに昼を与へわれらを照り輝かす
lo qual è iorno, et allumini noi per lui. はらから太陽と。
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 日は美しく眩しきまでに照り渡る、
de Te, Altissimo, porta significatione. かれこそは主の御姿、ああ高きにいます主よ
Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
ほむべきかな、わが主よ、わがはらから月は星は、
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.主はこれをみ空に作りたまひ、すみて貴く美はし
Laudato si, mi Signore, per frate Uento. ほむべきかな、わが主よ、風は、
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
大気は、雲は、曇りてはまた晴るる日和(ひより)は
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
これによりて主はその造りまししものを育みたまふ
Laudato si, mi Signore, per sor'Acqua, ほむべきかな、わが主よ、やさしきはらから水は
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. いと役立ちて、低きにつき貴く清らなり
Laudato si, mi Signore, per frate Focu, ほむべきかな、わが主よ、はらから火は
per lo quale ennallumini la nocte: 夜のくらきを照らし
ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte. 美はし、たのし、たけくつよし
Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra,
ほむべきかな、わが主よ、はらから母なる大地は
la quale ne sustenta et gouerna, われらを育みわれらを治め、
et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba. 木の実を結び、花を装ひ、草をはぐくむ
Laudato si, mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
ほむべきかな、主よ、主の愛によりて人を許し
et sostengono infirmitate et tribulatione. 病にたへて憂き艱(くるしみ)忍ぶものは
Beati quelli ke 'l sosterranno in pace, めぐみあれ 主によって静かに耐ふるものに
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. いと高き主よ、主の冠はかれにあらん
Laudato si mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
ああほむべきかな わが主よ、はらから死は、
da la quale nullu homo uiuente pò skappare: 誰か死をのがれん いけるもの皆は。
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; いたはしきかな罪の死に滅ぶ者は
beati quelli ke trouarà ne le Tue sanctissime uoluntati,
されどほむべきかな 主の聖意にすむ者は
ka la morte secunda no 'l farrà male. 第二の死の害ふことはあらじ
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate 主を頌めたたへ、主に感謝せよ
e seruiteli cum grande humilitate. いとへりくだりて主に仕えよ
私は12世紀のイタリアの方言で書かれたこの「歌」の原語を正しく読めるという自信はないが、それでもアッシジの太陽の光のような清澄な音調を感じ取ることはできる。黒田氏の邦訳は、やや古めかしいが、もとの歌の醸し出す雰囲気を、可能な限り典雅な大和言葉で簡潔に再現しているような気がするのである。
しかし、この明るい響きで歌われる歌詞の終わりの四連の内容は、作者のフランシスがまさに重病で床につき、目もほとんど見えなくなった時期のものであることを如実に示している。
この詩の前半部分が、旧約聖書詩編148を踏まえていることは良く指摘されている。天と地、太陽と月と星など、創造されたすべてのものを通して主を賛美する「ハレルヤ」の歌は、旧訳の民の典礼の祈りであり、フランシスコの時代にも、とくに、夜明けの頃の祈りとして歌われていたであろう。現代の新共同訳聖書では、次のように訳されている詩編である。
ハレルヤ。天において主を賛美せよ。
高い天で主を賛美せよ。
御使いらよ、こぞって主を賛美せよ。
主の万軍よ、こぞって主を賛美せよ。
日よ、月よ主を賛美せよ。輝く星よ主を賛美せよ。
天の天よ 天の上にある水よ主を賛美せよ。 主の御名を賛美せよ。
主は命じられ、すべてのものは創造された。
主はそれらを世々限りなく立て越ええない掟を与えられた。
地において主を賛美せよ。海に住む竜よ、深淵よ 火よ、雹よ、雪よ、霧よ
御言葉を成し遂げる嵐よ 山々よ、すべての丘よ 実を結ぶ木よ、杉の林よ
野の獣よ、すべての家畜よ 地を這うものよ、翼ある鳥よ 地上の王よ、諸国の民よ
君主よ、地上の支配者よ 若者よ、おとめよ 老人よ、幼子よ。
主の御名を賛美せよ。主の御名はひとり高く 威光は天地に満ちている。
主は御自分の民の角を高く上げてくださる。
それは主の慈しみに生きるすべての人の栄誉。
主に近くある民、イスラエルの子らよ。
ハレルヤ。
詩編148は中世以来良く歌われていた賛歌であったが、アッシジのフランシスのLaudato Si には、全被造物に創造主の賛歌を呼びかけているに留まらない。
まず彼は、被造されたものたちを、すべて人格化して「兄弟姉妹」と呼びかけている。そして、「ほむべきかな、主よ、主の愛によりて人を許し、病にたへて憂き艱(くるしみ)忍ぶものは」「めぐみあれ 主によって静かに耐ふるものに、いと高き主よ、主の冠はかれにあらん」というキリスト者の受難と忍耐の歌を付け加えていることであろう。
伝承に拠れば、眼病で目の見えなくなったフランシスに手術のために灼熱した鉄の棒をあてる必要が生じたときに、彼は、十字を切って、「兄弟なる火よ、自分は汝を神の最も美しい被造物としてこよなく愛した。どうかあまり自分を痛めつけないで欲しい」と云ったという。そして、最後には最もおそるべき肉体の「死」にむかっても「はらから」と呼びかけている。
グレゴリオ聖歌で歌われる詩編のラテン語訳も併記しておこう。幸い、中世の頃を偲ばせる歌唱がYoutubeに掲載されている。
Alleluja.
1 Laudate Dominum de cælis; laudate eum in excelsis.
2 Laudate eum, omnes angeli ejus; laudate eum, omnes virtutes ejus.
3 Laudate eum, sol et luna; laudate eum, omnes stellæ et lumen.
4 Laudate eum, cæli cælorum; et aquæ omnes quæ super cælos sunt,
5 lauudent nomen Domini. Quia ipse dixit, et facta sunt; ipse mandavit, et creata sunt.
6 Statuit ea in æternum, et in sæculum sæculi;
præceptum posuit, et non præteribit.
7 Laudate Dominum de terra, dracones et omnes abyssi;
8 ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum, quæ faciunt verbum ejus;
9 montes, et omnes colles; ligna fructifera, et omnes cedri;
10 bestiæ, et universa pecora; serpentes, et volucres pennatæ;
11 reges terræ et omnes populi; principes et omnes judices terræ;
12 juvenes et virgines; senes cum junioribus, laudent nomen Domini:
13 quia exaltatum est nomen ejus solius.
14 Confessio ejus super cælum et terram; et exaltavit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis ejus; filiis Israël, populo appropinquanti sibi. Alleluja.