DIAMOND online (柯 隆:東京財団政策研究所主席研究員)
2024年6月20日

Photo:PIXTA
所得層に応じた住宅供給が充実している日本に対し、持ち家文化の根強い中国では公営住宅の整備が不十分で賃貸マーケットも育っておらず、低所得層の住む家が不足。さらにコロナ禍の横暴な隔離措置を目の当たりにし、共産党統治体制に絶望した人々が自由を求めて次々と“国外脱出”を試みているという。※本稿は、柯隆『中国不動産バブル』(文春新書)の一部を抜粋・編集したものです。
なぜ中国で賃貸マンションが敬遠されるのか
日本では、若者は大学を卒業して就職したら、自宅から通う人は別として、多くの人は賃貸のアパートを借りて住む。日本の賃金体系は今でも年功序列であるため、ある程度年数が経って給料が徐々に上がれば、結婚に向けてマンションを買う人が多い。なかには、結婚してからも賃貸マンションやアパートに住む人も少なくない。賃貸で家を借りるメリットには気楽さがあるだろう。
とくに財産形成を考えないのであれば、気楽に生活したい人にとって賃貸で家を借りるのは決して悪い選択ではない。また、低所得層の人々は家賃の安い公営住宅に申し込むこともできる。日本では、各々の所得層の多様化した需要に応える形で住宅の供給も多様化しているのだ。
それに対して、中国では不動産バブルの崩壊以降も、賃貸に乗り換える人が少なく、公営住宅も整備されていない。低所得層は住む家がなく、大都市の一角がスラム化している。数年前に北京市政府は街の景観をよくするため、「低端人口」(低所得層の人々)を本籍地に強制送還する措置を講じた。当時の北京市長は習政権常務委員の一人である蔡奇だ。
都市部にスラム街が出現すると、治安が悪くなるのは確かだが、だからといって住民を本籍地に強制送還するやり方は、明らかに乱暴すぎるといわざるを得ない。北京市の経済力であれば、日本の公営住宅のような住宅を整備して、抽選で入居者を受け入れることができるはずである。これらの「低端人口」と呼ばれる低所得層の人々は、大体が市内で飲食や宅配などのサービス業に従事していた。彼らが本籍地に強制送還されてから、北京市民の生活に支障が出るようになったと報道されている。
中国の都市部では公営住宅が整備されていないだけでなく、民間の賃貸マーケットも大きく育っていない。賃貸マーケットが育つには、貸すほうと借りるほうがいずれも契約をきちんと守らなければならない。しかし中国では、法律の整備は進んでいるものの、法の執行がきちんと行われていない。契約を一方的に破棄しても罪に問われないため、賃貸契約の文化が根付かないのだ。トラブルになって自分だけが損をすることを恐れ、部屋を貸そうとする人も借りようとする人もなかなか現れない。
資産形成としての不動産購入
中国人が賃貸を忌避するもう一つの理由は、資産形成ができないということである。仮に10年間、賃貸で家を借りた場合、せっせと毎月家賃を払っても、退去時には手元になんの財産も残らない。中国人は日本人に比べて財産形成に関心が高く、さらにマイホームはステータスシンボルであるため、なんとか家を購入しようとする。ただし、ビジネスを行う人、とりわけ、店を経営する人たちは例外である。彼らはたいてい不動産を買わずに、賃貸で店舗を借りる。ビジネスは失敗のリスクもあり、家賃は店の経費として計上できるからであろう。
総じていえば、中国人は自分が住む家としてマイホームを買う志向が強い。人口の多い国であるため、みんながいっせいにマイホームを購入しようとして、不動産ブームが一気に巻き起こった。実需と潜在需要を考えて、投資家も中国の不動産市況を楽観的に見通すようになった。一方で、経済発展とともに、所得格差は急速に拡大した。富裕層はマイホームを所有するだけではなく、投資目的で2戸目、3戸目の物件を買っていった。不動産ブームが過熱しすぎたため、中国政府は銀行に通達を出して、2戸目以上の物件を購入する個人に対して、頭金を引き上げたり、住宅ローンの金利優遇を引き下げたり、さまざまな措置を講じるよう命じた。
ただ、もっとも重要な固定資産税はいまだに導入していない。富裕層は投資目的で2戸目や3戸目の物件を購入するが、ほとんどの人はその物件を賃貸に出すことはない。物件の値上がりを待って転売し、キャピタルゲインを狙うのだ。一般的にマイホームの購入は実需であり、不動産バブルにはなりにくい。投資と投機が盛んになることで、バブルは大きく膨らむようになるのだ。
日本も中国も貯蓄率の高い国であるが、両者には異なる面がある。日本人はお金をためても、無理にリターンを求めず、多くの人は金利がゼロでもせっせと銀行に預金する。それに対して、中国人はリターンを求める傾向が強い。個人の金融資産は直接的ないし間接的に不動産市場に流れていき、不動産バブルを拡大させたといえる。
伝統的な家族観は崩壊し 若者の生活の西洋化が進む
中国人の伝統的な生活様式と家族意識といえば、大家族と親孝行である。伝統的な祝祭日といえば、春節(旧正月)、清明節、中秋節などであるが、いずれも家族団らんのためのものであると考えられている。日本のお正月に相当する春節は、家族が集まって一年の終わりを祝い、新たな一年の無事を祈るもっとも重要な祭日である。清明節は先祖を祭る祭日で、墓参りする人が多い。中秋節は中秋の名月を観賞しながら一家団らんする重要な祭日である。
しかし、40余年間の改革・開放を経て、中国人、とりわけ若者の生活は西洋化しており、核家族化も進んだ。中国社会では、伝統的な生活様式は徐々に消えていっている。伝統的な祭日は休みにこそなるが、家族が集まらないことも多くなっている。また、春節の風物詩である爆竹は環境汚染をもたらすとして、都市部を中心に多くの地域で禁止・制限された。若者にとって伝統的な祭日は、中身のない大型連休になっているようだ。とくに、独身の若者は実家に帰ると親に結婚を急かされるため、家族と集まるのを嫌がる人が少なくない。
かつて中国では、親孝行が儒教の美徳とされていた。今は「啃老(こうろう)」、すなわち、親に支援を仰ぐ若者が増えている。日本では若者は自立して実家を出た後、たまには顔を見せに帰ってくるが、基本的に経済的に自立しているのがほとんどである。中国では、むしろ親の支援を頼りにする若者が多い。
中国でも出生率は低下しており、子供を産まないか、産んでも1人だけである。その結果、中国の家庭の形は完全に変わってしまった。子供が多い大家族は過去のことで、今はほとんど「4─2─1」という逆三角形の構成になっている。4は高齢者で、2は現役の夫婦であり、1は子供である。公的な介護保険は整備されておらず、4人の高齢者を夫婦2人で介護することは現実的に不可能である。
コロナ禍が共産党統治体制への絶望をもたらした
こうしたなか、中国はコロナ禍に見舞われた。中国政府は厳格な隔離措置を軸とするゼロコロナ政策を3年にわたり実施した。当時、新型コロナウィルスの性質が十分に知られていなかったため、隔離措置を講じるのはやむを得なかった。ただ、ゼロコロナ政策を実施する現場では、1人の陽性者が見つかったら、エリア全体のすべての人を専用の施設に強制的に閉じ込めるなど暴力的な行為が多々あった。隔離施設に連れていかれた住民の家には、医療関係者や警察官とみられる人たちが許可なく侵入し、家中に消毒液をまき散らし、ペットも手あたり次第殺処分してしまった。こうした行動は中国の法律に違反する可能性がある。
上海などの大都市では数カ月にわたって隔離措置が実施され、食料の供給も停止させられた。病院は医療崩壊に陥り、持病のある患者が治療を受けられず、犠牲になった人はSNSなどでたくさん報告されている。中国のエリート層は政府に対し不信感を抱き、コロナ禍が終息する前に自宅マンションを含めて保有する物件をすべて売りに出し、海外へ移住した。
一方、低所得層の人々は先進国へ移住しようとしても、正規のビザを取得することが難しい。多くの人は中国のパスポート保持者に対してビザを免除するベネズエラなどの南米の国へ一旦入国し、そのあと陸路でメキシコに入り、アメリカへの入国を試みる。2023年に入ってから、メキシコからアメリカへ密入国する中国人が急増していると、アメリカのメディアは報道している。

『中国不動産バブル』(文春新書)柯隆 著
アメリカに密入国しようとする低所得層の多くは英語ができないはずである。アメリカに無事に着いたとしても、どのように生活をするのだろうか。なぜ彼らは祖国を捨てて、アメリカに渡ろうとするのか。中国人は幼いころから学校などで厳格な愛国教育を受けているにもかかわらず、どうして自分の国を捨てるようになったのか。
答えは一つしかない。彼らは祖国というより、共産党統治体制に心から絶望したのだろう。中国の諺には「哀莫大於心死」というものがあるが、どんな大きい悲しみも、心が死ぬことと比べると、たいしたことではないという意味である。心が死ぬというのは、まさに絶望だ。コロナ禍の3年間は、中国が40年にわたり築いた経済の奇跡と人々の幸せな生活を一変させ、すべてを壊してしまった。
*左横の「ブックマーク」から他のブログへ移動
















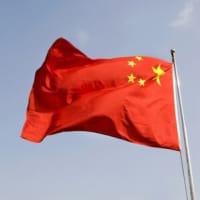



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます