PRESIDENT Online (高橋克英:株式会社マリブジャパン 代表取締役)
2024年5月6日
ついに国内1500人の早期退職募集
日本を代表する名門ブランド「資生堂」が、2024年2月、国内事業に関わる従業員約1500人の早期退職を募集すると発表した。
国内事業を手がける子会社「資生堂ジャパン」のうち、45歳以上で勤続年数20年以上の社員が対象だ。

写真=時事化粧品大手メーカーの資生堂のロゴマーク看板=2017年4月20日、東京・六本木
募集期間は同年4月17日から5月8日までで、①退職時年齢に応じた特別加算金を通常の退職金に加算し、②希望者には再就職支援サービスを提供する。
日本地域本社である資生堂ジャパンの従業員数は、1万人を超えており、今回、募集する早期退職はそのうちの1割を超える大規模なものになる。
大規模なリストラの背景には業績不振がある。資生堂の業績(2023年12月)は、売上高が前年比8.8%減の9730億円、コア営業利益が同22.4%減の398億円、営業利益が同39.6%減の281億円、純利益が36.4%減の217億円となり、2年連続の減収減益だ。コロナ禍が終わり化粧の機会も増え、インバウンドも復活しているにもかかわらず、なぜ業績が低迷しているのだろうか。
筆者は、名門ブランド「資生堂」の低迷は、①中国傾斜②EC遅れ③ブランド乱立の3つの根本的な問題によるものだとみている。こうした問題は、優良ブランドを抱えながら、生かし切れていない他の日本企業に共通する点も多そうだ。
売上高の25.5%を占める中国事業
① 地政学リスク高まる中国への傾斜
グローバル企業でもある資生堂において、日本事業の26.7%に次ぐ売上高25.5%を占めるのが中国事業だ。東京電力福島第1原子力発電所の処理水放出に伴う日本製品の買い控えもあり、中国事業の売上高は同4.0%減の2479億円、コア営業利益70億円の黒字(前期39億円の赤字)だった。
中国における地政学的リスクや反日的な対応は随分前から存在しており、何もプロ経営者でなくても、いまや一般の日本人であっても十分に認識できるような話だ。
経営判断、ビジネス判断として、この先も中国市場を大票田とする施策に問題はないのだろうか。自然災害など避けることが困難なリスクではなく、ある程度予測可能なリスクであるはずだ。事実、多くの日本企業が中国ビジネスからの撤退や縮小、他の市場への転換を検討したり、実行に移すなかで、足元の市場の大きさや成長性に目を奪われ、傾斜しすぎている面はないだろうか。
処理水放出に伴う不買運動だけでなく、同じような問題がこの先も繰り返される可能性は十分にあろう。万が一、日中間の対立がさらにエスカレートした場合のプランBを資生堂は持ち合わせているのだろうか。
化粧品の成分開示義務を強化するなど、中国政府の規制強化による技術流出懸念もあり、中国リスクはこの先も尽きることはない。因果関係は不明だが、他の業界でも起きたように、低価格ながら品質も向上してきた中国現地化粧品メーカーによるシェア拡大も進んでいる。
米国事業では買収と撤退を繰り返している
資生堂では、安定した成長が見込める米国事業も拡大するとしている。
確かに、米国は世界最大級の化粧品市場であり、安定性に加え成長性も見込める市場であるものの、エスティ ローダーやP&G、ユニリーバに加え、LVMHなど欧米の高級ファッションブランド系の化粧品などとの競争は熾烈であり、資生堂の米州事業の売上高は前年比20%減の1103億円にすぎない(2023年12月)。
このため、抜本的な規模拡大を目指し、2024年2月には、米国で高価格スキンケア化粧品事業を展開するDDGスキンケアホールディングスを4億5000万ドル(約640億円)で買収している。
しかしながら、米国での企業買収がうまくいくかどうかは不透明だ。資生堂は、過去何度も米国買収において高い授業料を払ってきたからだ。

※写真はイメージです
2010年に19億ドル(約1800億円)で買収した米国「ベアミネラル」は、業績不振から、2012年度と2017年度に累計900億円超の減損損失を計上した。最終的には、2016年に買収したものの同じく赤字続きの米国「ローラ メルシエ」などとともに、2021年に二束三文の7億ドル(約770億円)で米国の投資ファンドに売却している。2019年に8億4500万ドル(約895億円)で買収した米国「ドランク エレファント」もぱっとしないままだ。
対面販売は「文化」だが、時代はECに
② ECサイトの混在
名門ブランド「資生堂」低迷の根本的な問題の2つ目は、電子商取引(EC)の遅れだ。
高級ブランドを中心に、百貨店や化粧品専門店での美容部員によるカウンセリングを伴う対面での販売スタイルは、資生堂が長年顧客とともに培ってきた「文化」でもある。
一方で、既存の有人店舗での営業員による販売手法は、化粧品に限らず、あらゆる業種で、コストやスピードの面から従来の規模を維持することが困難となっている。いまや、ネット取引やSNSでの情報発信など、若い世代向けだけでなく、シニアや富裕層を含め全ての年代層に浸透している。また、ポイント獲得や優良顧客の会員化といった囲い込みも広がっている。
こうしたなか、資生堂では、化粧品専門店など得意先と連動しオンラインでのカウンセリングやチャットも可能なECサイト「Omise+(オミセプラス)」や、資生堂の公式ECサイト「watashi+(ワタシプラス)」、百貨店やイオンなど専門店のECサイトなどの強化・拡充により、国内Eコマース売上比率を現状の10%台前半から2025年には30%へ拡大するとしている。
「ネット上でどこでも買える」を解禁するか
実際、自社による公式ECサイト「watashi+(ワタシプラス)」では全品送料無料やポイントサービスもあり、アクセスしてみるとかなり充実した構成ではあるが、「知らなかった」「使ったことはない」という声も多く認知度は低い。
また、資生堂が誇る最高級ブランドの「クレ・ド・ポー ボーテ」は、EC販売チャネルを限定しているとはいえ、化粧品専門店や百貨店のECサイト、イオンスタイルなど複数のサイトからネット購入が可能だ。
既に資生堂が認定するオンラインショップは186(2024年4月30日時点)に上るが、この先、さらに拡大して「ネット上でどこでも買える」ようにするのか、逆に、限られた公式ECでしか購入できない形とするのか、取り扱いブランドごとに対応は変えるのか、など課題は山積だ。
いずれにせよ、公式サイトがいくつか乱立する現在のECサイトは認知度も低く分かりにくい。長年二人三脚でやってきた化粧品専門店などからは、資生堂によるECサイトにより顧客を奪われるとの不満が燻っている。「ネット上でどこでも買える」資生堂となることで、顧客の利便性は高まるものの、ブランド価値の毀損につながる危険性もはらむ。

写真=※写真はイメージです
顧客の奪い合いを招きかねないブランドの多さ
③ 32もあるブランド群
名門ブランド「資生堂」低迷の根本的な問題の3つ目は、ブランドの乱立だ。
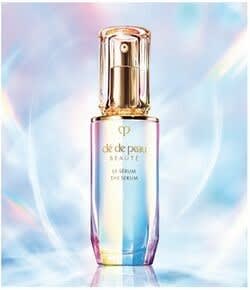
クレ・ド・ポー ボーテ ル・セラム(画像=プレスリリースより)
資生堂では、大きく「プレステージ」と「プレミアム」という2つのブランド群に分けられており、①「プレステージ」とされる高級ブランドには、SHISEIDO(シセイドウ)、Clé de Peau Beauté(クレ・ド・ポー ボーテ)、NARS(ナーズ)、IPSA(イプサ)、Drunk Elephant(ドランク エレファント)など16ブランドが名を連ねる。例えば、「Clé de Peau Beauté(クレ・ド・ポー ボーテ)」の美容液「セラムエクラS」が40ミリリットルで税込3万6300円、美容クリーム「ラ・クレーム」が30グラムで同6万8200円といった高額商品がそろう。
②「プレミアム」とされる中高価格帯ブランドには、ANESSA(アネッサ)、ELIXIR(エリクシール)、HAKU(ハク)、MAQuillAGE(マキアージュ)など13ブランドがある。
その他3ブランドとあわせ、実に合計32もの自社ブランドを抱えており、おのおのが美容液や美容クリームをはじめ多種多様な化粧品や関連商品を取りそろえている。
いまや、社員であってもブランド商品群の全てや相関関係を的確に把握できる者はほとんどいないのではないだろうか。新製品・新ブランドの乱発による開発費や販売費用の負担、商品ターゲット重複による顧客の奪い合いなどを招くことになる。
ブランド群の整理、統廃合が必要ではないか
こうした状況を踏まえ、資生堂では、自社ブランド群の選択と集中の一環として、2021年7月に「TSUBAKI(ツバキ)」や「uno(ウーノ)」などを扱うパーソナルケア事業を投資ファンドに売却している。さらに、国内での商品数を2022年末から2割の削減を目指す一方、主力ブランドである「Clé de Peau Beauté(クレ・ド・ポー ボーテ)」や「SHISEIDO(シセイドウ)」「ELIXIR(エリクシール)」に注力するなど、トランスフォーメーションを進めてはいる。
素朴な疑問ではあるが、資生堂の一番のブランドは「資生堂」ではないだろうか。「資生堂」はブランド自体確立されている一方、「銀座」「高価格」「伝統的」といった固定イメージもあり、こうした既存イメージを打破するため、あえて資生堂を冠しないさまざまなブランドを多角的に展開することで、若年層を含むあらゆる世代の取り込みを図ってきた側面はあろう。
いずれにせよ、エスティ ローダーやP&G、ユニリーバに加え、LVMHなど欧米の高級ファッションブランド系の化粧品と対抗するためにも、拡大し過ぎたブランド群の整理統廃合を急ピッチで進める段階にある。
もっともブランドの乱立は、日本企業の共通の課題かもしれない。化粧品に限らず、自動車や時計に装飾品にホテルなど、高品質・高評価にもかかわらず、なかなか、日本発の世界的なラグジュアリーブランドが誕生しない大きな原因の一つといえよう。
国内化粧品市場は拡大しているものの…
日本国内における、韓国ブランドなど低価格商品の広がりも、高価格帯をメインとする資生堂にとっては逆風だ。コロナ禍において、マスク着用が増え外出機会が減ったことで、化粧品にかける優先順位が下がり、低価格志向が定着。若年層においてSNSを介して、コンビニやドラッグストアに加え、ECサイトにて、韓国ブランドなど低価格商品が支持を得る状況が続いている。今や、日本においても、SNSでのインフルエンサーや口コミにより化粧品購入に至るケースは非常に多いとみられる。

写真=※写真はイメージです
なお、矢野経済研究所によると、2022年度の国内化粧品市場は前年比3.5%増加の2兆3700億円であり、2023年度は同3.4%増加の2兆4500億円を見込む。
製品カテゴリー別では、スキンケア市場が47.3%と全体の半分近くを占め、以下、ヘアケア市場20.3%、メイクアップ市場17.6%、男性用化粧品5.4%などとなっている。
このように、実は、日本市場自体は、拡大傾向にあるものの、市場拡大のパイを韓国ブランドにごっそり持って行かれてしまっているのだ。
資生堂もさまざまな手を打っているが、若年層のトレンドを捉え、振り向かせることに妙手はなく簡単ではない。
新たなる市場の開拓も簡単ではない
新たなる市場として、男性化粧品市場は拡大傾向にあるが、アラミス、クリニークなど欧米高級ブランドが先行する市場でもあり、キャッチアップできていない。
2024年4月には、資生堂は、美容や健康の改善をサプリや食品などで得る「インナーケア」事業の新ブランド、「SHISEIDO BEAUTY WELLNESS」を立ち上げた。カゴメと協働した飲料「ROOTINA(ルーティナ)」、ツムラと協働したサプリ「TUNE BEAUTE(チューンボーテ)」を販売するものの、こちらも国内においては、ファンケルやDHCなど既にプレゼンスを確保している競合先もあり簡単ではない市場だ。

写真=iStoc※写真はイメージです
働きやすい職場に「安住」していなかったか
最後にもう一つ気になる点がある。資生堂といえば、女性活用や働きやすい職場としても常に先端を行く企業だ。もっとも、社員に優しく居心地のいい環境が、大胆な変革や改革を停滞させ、仕事の既得権益化や細分化を生んだことが、①中国傾斜②EC遅れ③ブランド乱立を招いた側面はないだろうか。もしも、働きやすい職場に「安住」したことが、結果的に、減収減益や、早期退職募集の遠因となっているとしたら、由々しき事態だ。
当たり前だが、資生堂に限らず、ダイバーシティや働き方が尊重される令和の時代、女性にも男性にも優しく、人事制度や福利厚生が充実した働きやすい職場環境の向上に努めるのは、企業の責務である。一方で、営利企業として、社会や顧客の変化を捉えながらの社内競争や実力主義、コスト意識や採算性の確保といった点が、働く環境の前提にないと、ただおしゃれで居心地がいい職場になってしなうのではないだろうか。
高い技術力と豊富な人材を誇る名門ブランド企業の資生堂。①中国傾斜②EC遅れ③ブランド乱立、という3つの難題をいかに迅速かつ大胆に解決するのか。
これら問題の対応に、資生堂が先陣を切って成功すれば、同じように優良ブランドを抱えるものの、今一つ生かし切れていない他の日本企業にとっても好事例となり得よう。長期政権やガバナンスへの批判も社内外で燻り始めるなか、資生堂経営陣のさらなる大胆な決断が必要とされている。
株式会社マリブジャパン 代表取締役。金融アナリスト、事業構想大学院大学 客員教授。三菱銀行、シティグループ証券、シティバンク等にて銀行クレジットアナリスト、富裕層向け資産運用アドバイザー等で活躍。2013年に金融コンサルティング会社マリブジャパンを設立。世界60カ国以上を訪問。バハマ、モルディブ、パラオ、マリブ、ロスカボス、ドバイ、ハワイ、ニセコ、京都、沖縄など国内外リゾート地にも詳しい。映画「スター・ウォーズ」の著名コレクターでもある。
1993年慶應義塾大学経済学部卒。2000年青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科経済学修士。日本金融学会員。著書に『銀行ゼロ時代』(朝日新聞出版)、『いまさら始める?個人不動産投資』(きんざい)、『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』(講談社)、『地銀消滅』(平凡社)など多数。
*左横の「ブックマーク」から他のブログへ移動












