池袋テアトルダイヤで『東のエデン 劇場版II Paradise Lost』初日を見てきました。

構成的に見れば、ⅠとⅡをあわせてちょうど1本分かなーという印象。
劇場版Ⅰが笑いと動きによるつかみの前半とすれば、劇場版ⅡはTVから引っぱってきた
伏線の回収と、物語の決着を受け持つパートだったように思います。
TVでのアレがここでこうなるのか、という部分にはなかなか唸らされるところもあり、
あるいは「そういう落とし方?」と肩透かしに感じるところもありつつ、1年間に渡る
長くて短いような付き合いの総決算をしてまいりました。

そして見終わって感じたのは、いまさらだけど「映画って何だろう?」ということ。
それはただの物語なのか、それとも主義主張なのか。
一時の娯楽なのか、後に残る問いかけなのか。
理想を語る場所なのか、現実を直視させる場所なのか。
まあこれら全てであるとは言えますが、『東のエデン』においては、どのくらいの比率が
一番理想的なのか、そして劇場版ではその比率がどうだったのか?という点について、
自分でもまだ答えが出せてません。
少なくともTV版では「とてもいい案配」だと思ったんですが、劇場版にはやや疑問あり。
特にⅠとⅡの2本に分けてしまった点は、作品のバランスをやや悪くした一因にも思えます。
それでも『東のエデン』という、今の時代と正面から向き合い、進んで関わろうとする
強い意志が感じられるアニメに出会えたことは、とても価値ある経験でした。
劇場版の構成や落としどころには不満を感じるところもありますが、それを差し引いても
1年間見続けてきて本当によかった、と思っています。
この後は、作品のテーマについて少し踏み込んだ事を書いてみます。
ただし結構ネタばれっぽくなりますので、くれぐれもご注意ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、極めてフィクション寄りなガジェットである超AI(ジュイス)と100億の金を、
身近なリアリティである携帯電話と電子マネーに接合するというひねった発想によって、
ゲーム的な感覚で社会を変えることの可能性とその是非を問いかけた『東のエデン』。
しかし、物語の最終局面ではジュイスも100億円も主たるテーマから遠く離れてしまい、
残ったのは一人の青年による、半ば捨て身の主張でした。
しかし、いったい彼は何を変えたというのでしょうか?
彼が語ったのは、「国民主権」と「相互扶助」という、民主国家における基本的ルールの
再確認にしかすぎない、ともいえるでしょう。
確かに、いま全ての人々がそれを忘れつつあるのは間違いないし、もう一度その価値観を
取り戻そうという滝沢の主張は、まともすぎるほどに正しいと思います。
ただし、その言葉を現実の社会システムに置き換えてみるなら、それは「選挙」であり
あるいは「年金」や「社会保険」「終身雇用」となるのではないでしょうか。
そしてこれらの一部あるいは全部が、もはや古いシステムとして政治家や経済人、そして
多くの国民から拒絶され、否定され、打ち壊されようとする仕組みにほかならないのです。
ではフィクションとはいえ、『東のエデン』という物語はそれらに代わる新たな仕組みを
示せるのだろうか?というのが、私にとって最大の興味でした。
しかし劇場版Ⅱで示された「結論」は、それに答える性質のものではなかった。
たとえ嘘でもいいから、ジュイスと100億円で描ける美しい夢を見せて欲しかったし、
そこから覗くことができる可能性の扉を示して欲しかった、というのが、私の本音です。

例えば全国民にノブレス携帯を与えてジュイスを使わせることにより、国民投票を
より現実的にするとか、ジュイスをビッグ・ブラザーならぬ「リトル・シスター」として
社会に遍在させることで、支配/被支配とは違うAIとの共存を模索するという発想も
ありえたと思います。
あるいはここまで突拍子のない話でなければ、火浦院長の病院都市構想というように
作中で示されたアイデアもありました。
でも神山監督は、それらしく見える「嘘」を描く事を選ばず、(たぶん)自分の本音を
滝沢の口から語らせる、という真摯な道を選びました。
その正直さを尊いと思う一方、ここまで素の言葉を語らせてしまうことが「物語」としての
在るべき形なのかについては、やはり割り切れない気持ちも残ります。
詭弁であれ絵空事であれ、それによってしか示せない「理想」や「未来」もあるはずだし
そういうものを描くことで「ナマの現実」と対決することも、フィクションの役目のはず。
それをしなかった『劇場版Ⅱ』のクライマックスを「真摯なメッセージ」と受け止めるか
それとも「フィクションの敗北」と見るかで、評価は分かれるのではないでしょうか。
そしてこれを書いている自分は、この二つの気持ちの間でぐらぐらと揺れています。
TV版から見せてきた「生き金と死に金の違い」「個人レベルでの情報戦と情報漏えいの恐怖」
「電子的なアイデンティティと民主主義」そして「AIとの共存」」といった興味深いテーマたちが、
最後になって全て棚上げにされてしまったのは、正直なところ残念です。
でも滝沢の演説については、これまで人前で本音以外のことばかりを言わされてきた彼が、
最後にようやく本心(真実ではない)を話せてよかった、という気持ちもあるわけですよ。
キャラクターへの感情移入は大きくなったけど、物語に対して距離感は当初の感覚よりも
大きく離れてしまったという矛盾が、自分の中ではうまく整理できてない感じ。
そして、社会的なシステムへの言及が多かったTV版に比べ、劇場版(特にⅡ)では、
人と人(あるいは人とAI)の情緒的な挿話が、より多く見られたように思います。
特に血縁や人の縁といった「繋がり」に関する部分は、大きなウェイトを占めていました。
これは物部と滝沢を対決させたとき、システム論では物部の土俵になってしまうために、
別の切り口が必要であるという要求から来るものかもしれないし、あるいは製作の過程で
神山監督の心情が、よりウェットな方向に傾いた結果なのかもしれません。
ただし、そのウェットさが「21世紀に向けて切り捨ててきた日本らしさ」の系譜であり、
そこへ回帰することが容易な道ではないことも、強く指摘されるべきとも思います。
本来ならこういう難題をソフトランディングさせるための「道具」として、ジュイスとか
Mr.OUTSIDEの存在をうまく使うべきだとも思ったのだけれど、既に書いてきたとおり
『劇場版Ⅱ』においては、滝沢からの生々しい声でとりあえずの決着を迎えました。
たぶんこれが「いまの」神山監督の偽らざる気持ちなんだろうけれど、TV版と比べれば
ずいぶんと軌道修正がされてしまったのかな、とも推測されるところ。
といっても、滝沢自身は最初から一貫して「ぶれない人」で、逆に監督(とスタッフ)が、
滝沢の心情に引っぱられてしまったように見えるのも、またおもしろいところですが。
血縁の話といえば、物語のほぼ半分近くを裂いた滝沢の母親に関するエピソード。
これは、「滝沢朗とは誰か?」という疑問への答えとして用意された物だと思いますが、
個人的には「滝沢が誰でもかまわない」と思っていたことや、このエピソードのせいで
物語の軸が二つに割れてしまったという点もあり、あまり好ましいとは思えませんでした。
でもこれが入らなかったら、咲の出番がほとんどなくなっちゃたろうなぁ…。
それに大杉が一人前の男になることもできなかったろうし(^^;。

そうは言っても、滝沢母の金銭教育については、なかなか興味深いものがあります。
「お金の前では、人は平等」という考え方は「資本主義」と手を切れない我々にとって、
その枠内でいかに民主的なふるまいをするかのヒントになるという気がしたもので。
「金を持っている人が偉い」」のではなく、「金を仲立ちにして、人は平等になれる」と
読み替えていくことで、金を渡す側と受け取る側の間に「対等なコミュニケーション」を
確立できていければ、世の中もうちょっと住みやすくなるかもしれません。
これはあくまで心情的なモノですが、「クレーマー最強論」を唱える辻の考え方に従うと、
資本主義社会には加害者と被害者しか生まれないということになってしまいますからね。
理想論とはいえ、今の世の中で少しでも「持ちつ持たれつ」の関係を成立させていくには、
やはり辻の考えには立ち向かうべきだと思うし、子供のころからこういう心理を少しづつ
育てていくということも、今後に向けて大切なテーマかもしれません。
確かに、今の日本には金銭教育の土台がなさすぎると思います。
まあ、それは自分を含むほとんどの大人にも言えることだけど。
そういう意味で、滝沢が最後に配った1円は、いわば「逆Twitter募金」というシロモノ。
国民に対してつぶやくことで、聞いてくれた相手に1円ずつ払うというところでしょうか。
そしてこれは、国民への責任を果たすための「約束手形」という意味だけでなく、
たとえ1円分でもいいから、みんながこの国を救うための義務を果たして欲しいという
滝沢からの率直な願いのようにも受け取れます。
でもそれって、実はMr.OUTSIDEと同じ立場に立っちゃったという解釈もできるのか…。
だとすれば、エンドロール後のシーンを手放しで喜んでいいものだろうか。
またひとつ、考えるべき謎が増えてしまったような気もします。
あ、ここまであまり書かなかったけど、ヒロインである咲が失恋から立ち直る物語として
『東のエデン』を見るならば、これはこれでよかったんじゃないかと思いますよ。
「今も好きなのに思い切れない片思いの相手、しかも姉の旦那」という複雑な相手に対し
笑ってサヨナラできるようになっただけ、彼女も成長できたわけですからね。

そして今回の劇場版Ⅱ、一番の謎だったのは滝沢の母親かもしれません。
彼女の人生や滝沢を産んだ背景には、まだまだ多くの謎が横たわっています。
…ひょっとして彼女は、作品の枠を超えて現れた「けつねコロッケのお銀」なのでは?
そして滝沢は彼女の血を受け継ぐ「新世紀仕様の活動家」なのかもしれない…などと、
とりとめもなく思ったりもするのでした。
もしかして滝沢母も、かつて「東方革命学生連盟」のメンバーだったりして?
なにしろ大学の名前からして「相慈院」(アイジイン)ですからね~(笑)。
だからその上の「唾棄すべき世代」には、当然ながら押井師匠も含まれてるわけで、
彼らが掘ったトンネルをさらに神山監督の世代が掘り、次の世代に託していくというのが
『東のエデン 劇場版Ⅱ』の裏テーマでもあるのでしょう。
押井>神山(滝沢母)>滝沢の三世代へと受け継がれる闘争の系譜、なんちゃって。
整理しきれない、あるいは読みきれていない部分もあるとは思いますが、初見での感想は
だいたいこんな感じです。
なお、既に続編希望の声も出ているようですが、これまで作品を変えながらも一貫して
類似するテーマを追求してきた神山監督なだけに、私としては新しい舞台、新しい趣向で
『東のエデン』で掘り出したテーマを突き詰め、消化していって欲しいですね。
スピンアウトとか後日談はいいけど、シリーズ物については完全新作が見たいと思います。
まあその前に、少なくともあと1回は『劇場版Ⅱ』を見に行かなくてはならないのですが。
そんなわけで、自分の中で『東のエデン』が決着を迎えるのは、まだまだ先になりそうです。

構成的に見れば、ⅠとⅡをあわせてちょうど1本分かなーという印象。
劇場版Ⅰが笑いと動きによるつかみの前半とすれば、劇場版ⅡはTVから引っぱってきた
伏線の回収と、物語の決着を受け持つパートだったように思います。
TVでのアレがここでこうなるのか、という部分にはなかなか唸らされるところもあり、
あるいは「そういう落とし方?」と肩透かしに感じるところもありつつ、1年間に渡る
長くて短いような付き合いの総決算をしてまいりました。

そして見終わって感じたのは、いまさらだけど「映画って何だろう?」ということ。
それはただの物語なのか、それとも主義主張なのか。
一時の娯楽なのか、後に残る問いかけなのか。
理想を語る場所なのか、現実を直視させる場所なのか。
まあこれら全てであるとは言えますが、『東のエデン』においては、どのくらいの比率が
一番理想的なのか、そして劇場版ではその比率がどうだったのか?という点について、
自分でもまだ答えが出せてません。
少なくともTV版では「とてもいい案配」だと思ったんですが、劇場版にはやや疑問あり。
特にⅠとⅡの2本に分けてしまった点は、作品のバランスをやや悪くした一因にも思えます。
それでも『東のエデン』という、今の時代と正面から向き合い、進んで関わろうとする
強い意志が感じられるアニメに出会えたことは、とても価値ある経験でした。
劇場版の構成や落としどころには不満を感じるところもありますが、それを差し引いても
1年間見続けてきて本当によかった、と思っています。
この後は、作品のテーマについて少し踏み込んだ事を書いてみます。
ただし結構ネタばれっぽくなりますので、くれぐれもご注意ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、極めてフィクション寄りなガジェットである超AI(ジュイス)と100億の金を、
身近なリアリティである携帯電話と電子マネーに接合するというひねった発想によって、
ゲーム的な感覚で社会を変えることの可能性とその是非を問いかけた『東のエデン』。
しかし、物語の最終局面ではジュイスも100億円も主たるテーマから遠く離れてしまい、
残ったのは一人の青年による、半ば捨て身の主張でした。
しかし、いったい彼は何を変えたというのでしょうか?
彼が語ったのは、「国民主権」と「相互扶助」という、民主国家における基本的ルールの
再確認にしかすぎない、ともいえるでしょう。
確かに、いま全ての人々がそれを忘れつつあるのは間違いないし、もう一度その価値観を
取り戻そうという滝沢の主張は、まともすぎるほどに正しいと思います。
ただし、その言葉を現実の社会システムに置き換えてみるなら、それは「選挙」であり
あるいは「年金」や「社会保険」「終身雇用」となるのではないでしょうか。
そしてこれらの一部あるいは全部が、もはや古いシステムとして政治家や経済人、そして
多くの国民から拒絶され、否定され、打ち壊されようとする仕組みにほかならないのです。
ではフィクションとはいえ、『東のエデン』という物語はそれらに代わる新たな仕組みを
示せるのだろうか?というのが、私にとって最大の興味でした。
しかし劇場版Ⅱで示された「結論」は、それに答える性質のものではなかった。
たとえ嘘でもいいから、ジュイスと100億円で描ける美しい夢を見せて欲しかったし、
そこから覗くことができる可能性の扉を示して欲しかった、というのが、私の本音です。

例えば全国民にノブレス携帯を与えてジュイスを使わせることにより、国民投票を
より現実的にするとか、ジュイスをビッグ・ブラザーならぬ「リトル・シスター」として
社会に遍在させることで、支配/被支配とは違うAIとの共存を模索するという発想も
ありえたと思います。
あるいはここまで突拍子のない話でなければ、火浦院長の病院都市構想というように
作中で示されたアイデアもありました。
でも神山監督は、それらしく見える「嘘」を描く事を選ばず、(たぶん)自分の本音を
滝沢の口から語らせる、という真摯な道を選びました。
その正直さを尊いと思う一方、ここまで素の言葉を語らせてしまうことが「物語」としての
在るべき形なのかについては、やはり割り切れない気持ちも残ります。
詭弁であれ絵空事であれ、それによってしか示せない「理想」や「未来」もあるはずだし
そういうものを描くことで「ナマの現実」と対決することも、フィクションの役目のはず。
それをしなかった『劇場版Ⅱ』のクライマックスを「真摯なメッセージ」と受け止めるか
それとも「フィクションの敗北」と見るかで、評価は分かれるのではないでしょうか。
そしてこれを書いている自分は、この二つの気持ちの間でぐらぐらと揺れています。
TV版から見せてきた「生き金と死に金の違い」「個人レベルでの情報戦と情報漏えいの恐怖」
「電子的なアイデンティティと民主主義」そして「AIとの共存」」といった興味深いテーマたちが、
最後になって全て棚上げにされてしまったのは、正直なところ残念です。
でも滝沢の演説については、これまで人前で本音以外のことばかりを言わされてきた彼が、
最後にようやく本心(真実ではない)を話せてよかった、という気持ちもあるわけですよ。
キャラクターへの感情移入は大きくなったけど、物語に対して距離感は当初の感覚よりも
大きく離れてしまったという矛盾が、自分の中ではうまく整理できてない感じ。
そして、社会的なシステムへの言及が多かったTV版に比べ、劇場版(特にⅡ)では、
人と人(あるいは人とAI)の情緒的な挿話が、より多く見られたように思います。
特に血縁や人の縁といった「繋がり」に関する部分は、大きなウェイトを占めていました。
これは物部と滝沢を対決させたとき、システム論では物部の土俵になってしまうために、
別の切り口が必要であるという要求から来るものかもしれないし、あるいは製作の過程で
神山監督の心情が、よりウェットな方向に傾いた結果なのかもしれません。
ただし、そのウェットさが「21世紀に向けて切り捨ててきた日本らしさ」の系譜であり、
そこへ回帰することが容易な道ではないことも、強く指摘されるべきとも思います。
本来ならこういう難題をソフトランディングさせるための「道具」として、ジュイスとか
Mr.OUTSIDEの存在をうまく使うべきだとも思ったのだけれど、既に書いてきたとおり
『劇場版Ⅱ』においては、滝沢からの生々しい声でとりあえずの決着を迎えました。
たぶんこれが「いまの」神山監督の偽らざる気持ちなんだろうけれど、TV版と比べれば
ずいぶんと軌道修正がされてしまったのかな、とも推測されるところ。
といっても、滝沢自身は最初から一貫して「ぶれない人」で、逆に監督(とスタッフ)が、
滝沢の心情に引っぱられてしまったように見えるのも、またおもしろいところですが。
血縁の話といえば、物語のほぼ半分近くを裂いた滝沢の母親に関するエピソード。
これは、「滝沢朗とは誰か?」という疑問への答えとして用意された物だと思いますが、
個人的には「滝沢が誰でもかまわない」と思っていたことや、このエピソードのせいで
物語の軸が二つに割れてしまったという点もあり、あまり好ましいとは思えませんでした。
でもこれが入らなかったら、咲の出番がほとんどなくなっちゃたろうなぁ…。
それに大杉が一人前の男になることもできなかったろうし(^^;。

そうは言っても、滝沢母の金銭教育については、なかなか興味深いものがあります。
「お金の前では、人は平等」という考え方は「資本主義」と手を切れない我々にとって、
その枠内でいかに民主的なふるまいをするかのヒントになるという気がしたもので。
「金を持っている人が偉い」」のではなく、「金を仲立ちにして、人は平等になれる」と
読み替えていくことで、金を渡す側と受け取る側の間に「対等なコミュニケーション」を
確立できていければ、世の中もうちょっと住みやすくなるかもしれません。
これはあくまで心情的なモノですが、「クレーマー最強論」を唱える辻の考え方に従うと、
資本主義社会には加害者と被害者しか生まれないということになってしまいますからね。
理想論とはいえ、今の世の中で少しでも「持ちつ持たれつ」の関係を成立させていくには、
やはり辻の考えには立ち向かうべきだと思うし、子供のころからこういう心理を少しづつ
育てていくということも、今後に向けて大切なテーマかもしれません。
確かに、今の日本には金銭教育の土台がなさすぎると思います。
まあ、それは自分を含むほとんどの大人にも言えることだけど。
そういう意味で、滝沢が最後に配った1円は、いわば「逆Twitter募金」というシロモノ。
国民に対してつぶやくことで、聞いてくれた相手に1円ずつ払うというところでしょうか。
そしてこれは、国民への責任を果たすための「約束手形」という意味だけでなく、
たとえ1円分でもいいから、みんながこの国を救うための義務を果たして欲しいという
滝沢からの率直な願いのようにも受け取れます。
でもそれって、実はMr.OUTSIDEと同じ立場に立っちゃったという解釈もできるのか…。
だとすれば、エンドロール後のシーンを手放しで喜んでいいものだろうか。
またひとつ、考えるべき謎が増えてしまったような気もします。
あ、ここまであまり書かなかったけど、ヒロインである咲が失恋から立ち直る物語として
『東のエデン』を見るならば、これはこれでよかったんじゃないかと思いますよ。
「今も好きなのに思い切れない片思いの相手、しかも姉の旦那」という複雑な相手に対し
笑ってサヨナラできるようになっただけ、彼女も成長できたわけですからね。

そして今回の劇場版Ⅱ、一番の謎だったのは滝沢の母親かもしれません。
彼女の人生や滝沢を産んだ背景には、まだまだ多くの謎が横たわっています。
…ひょっとして彼女は、作品の枠を超えて現れた「けつねコロッケのお銀」なのでは?
そして滝沢は彼女の血を受け継ぐ「新世紀仕様の活動家」なのかもしれない…などと、
とりとめもなく思ったりもするのでした。
もしかして滝沢母も、かつて「東方革命学生連盟」のメンバーだったりして?
なにしろ大学の名前からして「相慈院」(アイジイン)ですからね~(笑)。
だからその上の「唾棄すべき世代」には、当然ながら押井師匠も含まれてるわけで、
彼らが掘ったトンネルをさらに神山監督の世代が掘り、次の世代に託していくというのが
『東のエデン 劇場版Ⅱ』の裏テーマでもあるのでしょう。
押井>神山(滝沢母)>滝沢の三世代へと受け継がれる闘争の系譜、なんちゃって。
整理しきれない、あるいは読みきれていない部分もあるとは思いますが、初見での感想は
だいたいこんな感じです。
なお、既に続編希望の声も出ているようですが、これまで作品を変えながらも一貫して
類似するテーマを追求してきた神山監督なだけに、私としては新しい舞台、新しい趣向で
『東のエデン』で掘り出したテーマを突き詰め、消化していって欲しいですね。
スピンアウトとか後日談はいいけど、シリーズ物については完全新作が見たいと思います。
まあその前に、少なくともあと1回は『劇場版Ⅱ』を見に行かなくてはならないのですが。
そんなわけで、自分の中で『東のエデン』が決着を迎えるのは、まだまだ先になりそうです。










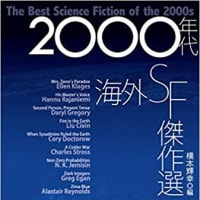


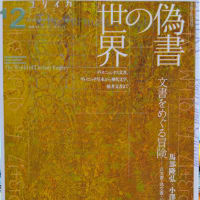









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます