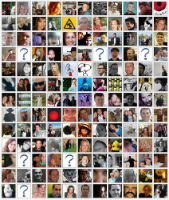自殺念慮のある若者は、唾液中の細菌に違いがあることが判明
自殺や鬱と関係する、
ある種の細菌の寡多が
遺伝子変異によるものならば、
なぜそのように遺伝子変異したかを
解明する必要がありますね。
後天的に遺伝子変異を起こす要因
(遺伝子のスイッチオンオフ)は、
生活習慣や食事、思考癖などの
日頃の過ごし方によるといわれています。
家系的に鬱病や自殺者が多いというのは、
実際にあるのですが、
つまり、遺伝子変異が起こって、
それが遺伝されているという事ですね。
でも、上記に記載した通り、
例え遺伝でも、後天的要素で遺伝的な負の側面を
発現させないようにする事が出来るのです。
それを家系の因縁をあなたの代で
断ち切るともいいますね。
考え方一つ、
過ごし方一つ、
生き方一つにより、
大きく変えることは可能なのです。
それには、
新しいソフトウェアを
インストールすれば良いのです。
新しいソフトは、
人によって齎される可能性が大きく、
例えば、結婚は新しいソフトツールとして
素晴らしい物だと思います。
結婚しない人は、
色々なタイプ、特にこれまでの自分とは
違うタイプの人との交流を通して
新しいソフトウェアの入手&
インストールが可能です。
引きこもっていては、
新しい風(ソフト)を入れる事はかなり難しいです。
失敗しても良い、人と違っていてよい。
なぜなら、地球環境そのものが、
進化し続ける命そのものであり、
その命を維持、発展させるために、
想像できないほどの
多様性を強く求めているのだから。
地球上にどれだけ多様な生物が存在しているか
知っていますか?
全世界の既知の総種数は約175万種で、
このうち、哺乳類は約6,000種、鳥類は約9,000種、
昆虫は約95万種、維管束植物は約27万種。
まだ知られていない生物も含めた地球上の総種数は
大体500万~3,000万種の間という説が多いようですね。
ちなみに、人種は色々な側面からの分け方がありますが、
一般的に、肌の色を特徴として、白色、黄色、赤色、黒色、茶色の
たったの5種しかありません。
上記のように、あなたが今、社会に適応できずに
引きこもっていたといても
それは寧ろ正常な反応の一つなのです。
人間社会は狭い範囲内に
人の生き方を押し込めているのですから、
窮屈さや息苦しさを感じて当たり前なのです。
それが当たり前の感覚と言って良いくらいです。
多かれ少なかれ、誰しもが持っている感覚です。
社会はもっと
懐が広く深くならないといけません。
特に日本は異種文化が入りにくく
閉鎖的な文化、思想が根強いです。
日本人は外国人からは
親切だけどフレンドリーではないと
見られがちで、
その言葉はとても的を得ていると思います。
日本で若者の自殺率が高いのは
そうゆう日本だからです。
つまり、若者が生き生きと暮らせるようになるには、
周りの温かな理解が必要不可欠なのです。
がん検診の誤解|早期発見しなくてよいがんがある?
NHKでもこんな記事を
書いてくださるようになりました。
癌は、過剰診断や偽陽性により、
早期治療がデメリットになるものもあるという事。
しなくても良い手術により
生涯後遺症に苦しむケースも。
ぜひ、皆さんにも知って欲しい部分です。
そして、糖尿病が癌リスクの最たるものですが、
そのリスクを分かっていない人が多いという事が
かかれてあります。
私は9年ほど前、妊娠中に妊娠性糖尿病になりました。
祖母が糖尿病の合併症で68歳で亡くなり、
兄弟にも糖尿病の人がいて、
とても心配し、強い危機感を抱いています。
それで、
ミトコンドリアを活性化させる
方法を探し出し、実践しています。
真相としては、糖尿病の真の原因は糖ではなく、
ミトコンドリアが細胞内外の水素イオン濃度の差を利用し、
糖と酸素からエネルギーを産生する際になくてはならない、
ビルビン酸脱水素酵素の働きを阻害する
多価不飽和脂肪酸(総じてプーファ)が
真の原因だと突き止めました。
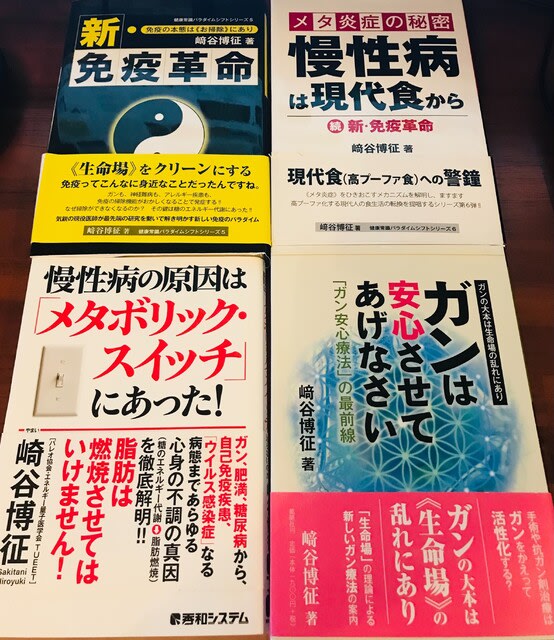
ですので、糖尿病は遺伝的リスクが大きい疾患と
言われていますが、
遺伝的な部分は勿論あるとは思いますが、
やはり、食習慣の継承、
つまり幼い頃からの食生活がどうだったか?
これに尽きるのだと思います。
私の場合、祖母と同居で祖母が食事を作る事が多く、
脂っこい揚げ物や炒め物の食事が多かったように思います。
ただ、私の場合は、自然療法家として
食事法も様々に実践してきた中で、
植物性健康神話にすっかり騙されており、
妊娠中は特に体の健康を考えていたため、
明らかにオリーブオイルとオメガ3や
脂の乗った美味しいお魚の食べ過ぎでした。
さて、多価不飽和脂肪酸は
酸素で飽和していない油脂ですから、
酸化しやすいオイルです。
特にオメガ6やオメガ3の植物性オイル魚油が代表格です。
ちなみに、植物性でもココナッツオイルは
飽和脂肪酸の含有量が多いので、
これに含まれません。
オメガ9はオメガ6やオメガ3と比べた場合は、
酸化しにくいといえますが、やはり不飽和脂肪酸に
変わりはないので出来るだけ控えた方が良いですね。
さて、食べ物から多価不飽和脂肪酸を排除するだけで
ミトコンドリアの代謝機能が
30%もアップする事が分かっています。
現代人は植物性油脂を摂りすぎています。
植物性オイルは、
オメガ6とオメガ3のバランスが
大切などと言われますが、
それ以前の問題で、
多価不飽和脂肪酸である事が
問題なのです。
どんなに揚げたての美味しい天ぷらでも
植物性オイルで揚げたのなら、
体内の消化過程でどんどん酸化が進みます。
なお、現在の現代西洋医学界でミトコンドリアは
全ての病に関わっている事が解明され、
ミトコンドリア移植法が大注目されています。
研究が進み臨床でも良い結果がでています。
糖尿病は老化であり、
その逆に、ミトコンドリアを活性化する事は、
若返りになります。
また、
ビルビン酸脱水素酵素を活性化させる食品が
そんなに多くはありませんが、
その中で特に貢献するものが、蜂蜜です。
そして、コエンザイムQ10とビタミンEの組み合わせ。
次にビタミンB群と、続きます。
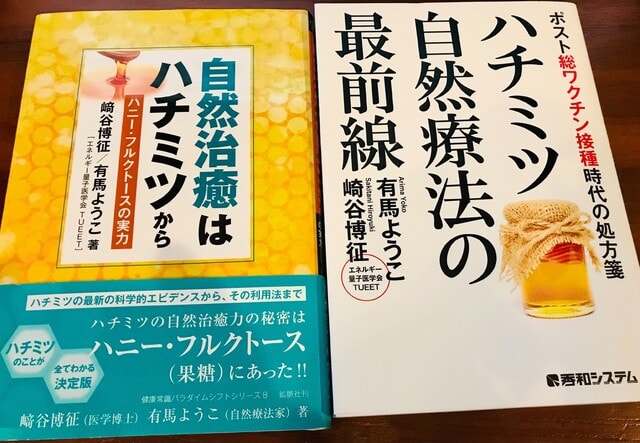
また、1ヶ月前からは
コエンザイムQ10とビタミンEを
常温核融合の技術で性質を変化させた
TQ製品を使っています。
TQ製品は、未知の可能性の塊で、
本当に物凄い力があり、
ミトコンドリアが更に活性化されるのが
良く分かります。
これまで、年齢的になかなかとれなかった
お腹周りの余分な皮下脂肪や中性脂肪が
ほんの1ヶ月でかなりスッキリし、
驚いている所です。
(ただし、TQ製品は
エネルギーレベルの高い人は、
好転反応が出やすいというお話しも
あります)
プーファフリーと蜂蜜により代謝を
これまでの脂質代謝から
ミトコンドリアの糖代謝に完全移行するのに、
3年〜5年ほどかかると言われていますが、
TQ製品を併用するなら、
もっと早く移行できると思います。
植物油脂は大体の加工品に入っていますので、
入っていない物を探すのが大変です。
でも、癌になりたくないのなら、
先ずは癌の温床となる糖尿病にならない事が
最も大事ですから、
なるべく控えるよにする努力が必要です。
癌は解糖系といって、
ミトコンドリアを介さない
低体温の環境で酸素を使わず
エネルギーを産生している細胞です。
その一方で、ミトコンドリアが
酸素を使いエネルギーを
産生する事をミトコンドリア系と言います。
ミトコンドリアが酸素を使って
エネルギーを産生する事自体、
体温が上がりますし、
癌にとって有害な酸素を使うわけなので、
癌細胞化はしません。
人のエネルギー代謝は
30代から徐々に解糖系からミトコンドリア系に移行し
40代ではミトコンドリア系が主体となるのが
自然な事なのですが、
今の中高年はミトコンドリア系に
移行出来てない人が多く、
それも中年以降は癌になりやすい
一つの理由に挙げられています。
脳も筋肉も、実はウイルスの助けでできている 最新研究で見えてきた世界
https://globe.asahi.com/article/13707574?fbclid=IwAR1w0AHCAQuRd0YVVQe2vZvLU38S9Ipf9oprQ9930h673O78jXGB6xfsxSY10年ほど前に人の胎盤がウイルスの介入で
今のように進化したと知った時は本当に驚いたものです。
現在は、数年まえからの新型コロナによって、
ウイルスと人間進化の関わりについての記事を
良く目にするようになりましたね。
ウイルス以外にも、ミトコンドリアも腸内細菌も人の中で
共生していますが、それぞれが生き物なので、
意識というものを持っています。
私という人は私一人の意識だけではなく、
共生している微小なナノレベルの生き物の意識も加わって、
私は存在しています。
実際、ある種の腸内細菌が人間の性格を左右している事が
研究により明らかにされていますし、
そもそも、腸は第二の脳などとも良く言われていますが、
今は、脳とは独立しているため、
第二の脳とは言えないとも言われていますね。
人の命の営みとは何と複雑なのでしょう。
正に神秘です



さて、私が人とウイルスとの関係を初めて知ったのは、
先に書いたように、胎盤の進化についての記事でしたが、
胎盤がウイルスによって出来たものだと知った時、
【ミトコンドリアのATP合成酵素が面白い!】
おはようございます!
色々と調べていて気付いたら一睡もせずにこんな朝に💦
さてさて、人間を含め、ありとあらゆる生命のエネルギー供給源のATPは、ATP合成酵素で作られています。
それがどこで合成されているかと言うと、細胞内の小器官であるミトコンドリア。これは元々プロテアバクテリアという原核生物の一つ、好気性細菌で、人間の細胞に取り込まれミトコンドリアとなり、人間の細胞内で共生するようになったのですね。
こんなに大事な役割を担っているミトコンドリアですが、実はまだ全部分かっていないのですよ。
しかも、ミトコンドリアでエネルギーを作り出しているATP酵素がモーターのように回転していることも、近年になり分かった事で、最初にそのことを提唱した博士も大変な目にあっていたのです!
前後しまますが、私は、ホメオパシー(自然医学)の学校ではアデノシン三リン酸(ATP)をアデノシン二リン酸(ADP)とリン酸に分解する事でエネルギーを作っているという、簡単な事しか教えて貰ってないのですが、ミトコンドリアは生きていく為に最重要な仕事をしているので、最近、詳しく調べてその働きを勉強しています。
ミトコンドリアは細胞内外の水素イオンの濃度の差によりATP合成酵素が回転してエネルギーを作っているのですが、上記に書いたように、最初にこの仮説を立てた、ボール・ボイヤーさん、あまりにも型破りな仮説の提唱で、長らく学会で相手にされなかったらしいのですよ💦
いやはや。
長い間の冬を越えて、後に正しいことが立証され、
このATP合成酵素に関する研究は大変重要なものであるとして、1997年秋にボイヤー、ウォーカー、スコウの3名はノーベル化学賞を受賞しました。
それで、全ての生命現象に不可欠なエネルギーのATPですが、実は人間の体内には僅か数十グラム、3分間分のATPしかないという・・・😳😳😳😳😳
でも、心配はご無用!
ATPが分解されてできたADPとリン酸は食べ物を燃焼して得られるエネルギーを使って、再びATPになることで、結果的に一日に体重に相当するATPが作られているのだとか。
なお、水素イオン濃度が細胞内で上がるのを防ぐために、細胞呼吸(食べ物を燃焼する)を使って、細胞外に水素イオンを汲み出す仕組みが常に働いているので、ATP合成酵素は回転し続けることができるのだそう!
全身にある37兆個(昔は60兆といわれていた)の細胞内のナノレベルで
こうやってエネルギーを作り出しているなんてね、、、、
自分にご苦労様って、頭が下がりますね。
徹夜もご苦労様でした😅
こちらの動画も分かりやすかったです
↓
https://youtu.be/R2n3MEtviOU

今日は今、研究が盛んにおこなわれ、ガン細胞の転移の原因としても注目されている、
エクソソームについてのお話しです。
エクソソームに関しては、
こちらの北海道大学大学院医学研究院の南保明日香准教授らの研究グループの報告が分かりやすいと思います。
「EB ウイルス感染細胞がまき散らす粒子の性質を解明」
~EB ウイルスが引き起こすがん発症の解明と診断への応用に期待
【用語解説】
*1 エクソソーム … 様々な細胞から体液中に放出される微小な粒子。放出する細胞に由来する様々な
たんぱく質や核酸を含んでいる。エクソソームを取り込んだ細胞にこれらの因子を輸送することで,
細胞の性質を変える。近年では,がんをはじめとした疾患に関わることが解明されつつある。
*2 マイクロ RNA … 約 20 塩基から構成される RNA であり,細胞の遺伝子発現を調節する機能をも
つ。近年,がん細胞が放出するエクソソームが特定のマイクロ RNA を内包し,がんの悪化や転移の
原因となることが報告されている。
用語解説を読むだけでも、大体わかるかと思いますが、健康な細胞がなぜガン化するかについては、
ガン化した細胞が放出したエクソソーム内のガン細胞由来のmRNA遺伝子細胞によって、ガン化するという事です。
ガンの全てがウィルス由来ではありませんし、
全ての疾患にしても、そうですよね。
現在の多くの疾患は生活習慣病だといわれいますが(ガンも今では生活習慣病の一種ともいわれていますね)、
つまり、それらは、血液の汚れによるものです。
つまり、血液の汚れによりたまった、細胞内の不要なゴミが細胞を傷つける事で異常細胞になり、
その異常細胞由来のmRNAを含んだエクソソームが排出され、
そのエクソソームが健康な細胞を病気にするという事です。
例えば、糖尿病であれば、血液中の高血糖状態が長く続いた事により、
すい臓のランゲルハンス島の細胞が異常化し、異常化した細胞が増えるほど、
インシュリンホルモンを生産できなくなるという事ですね。
(血液に大量に糖分が流れ込み、その処理に追い付かず、
細胞が疲れ切ってしまうとインシュリンホルモンが出なくなります。
初期はすい臓の臓器が疲れているだけなので、
食事療法でまたホルモンがでるようになりますが、
遺伝子自体が異常化するとホルモン自体を生産できなくなります)
改めて、健康な細胞とはなんでしょうか?
細胞としての役割を全うする細胞の事ですよね。
それは遺伝子の設計図により、
細胞が複製される時に寸分の狂いもなくしっかりと複製されるという事です。
遺伝子の複製に間違いがあると、ガン化他、病気が発生する事になります。
(細胞が複製される時、一定の割合で異常な細胞が発生していますが、
免疫細胞が異常細胞を処理しているので、普通、病気を発症する事はありません。
ですが、免疫細胞は子供の教育と同じで、生まれた場所から胸腺に移動し、
そこで大人の免疫細胞になるための教育をうけます。
このため、胸腺は免疫細胞養成機関ともいわれる部分です。
この時、大人になりきらない免疫細胞が生まれてしまう場合があります。
このような未熟な免疫細胞が多い人ほど、免疫力も弱いのです。
免疫力が弱くなる原因については様々あり、長くなるので、またの機会に譲ります)
遺伝子の複製に間違いが起こるという事は、
傷ついた細胞が作られるという事ですが、
細胞を傷つけるものとして、
この地上で最たるものは、放射線被ばくです。
放射線被ばくしなくても、病気になる人は沢山います。
電磁波も細胞を傷つけますし、ウィルス感染以外にも、
体内にたまった微量な重金属も細胞の正常な複製を阻害します。
それらは、添加物として摂取したり、
ヘアースプレ-や洗剤などにも入っていますし、
ドライヤーを使う時にも発生しているケミカルなものです。
微量な重金属は神経細胞にたまりやすいという特徴があり、
アルミニウムと認知症の関係などは、割と良くしられたお話しです。
エクソソームの働きが分かったいま、
私達は細胞の複製が正常に行われるよう、
生活していかなければなりませんね。
皆さん、こんにちは。
今日はとっても涼しいですね。
急に気温がさがりましたので、
体調管理にはくれぐれも
お気をつけてお過ごしくださいね。
さて、
今日は人間の脳の発達に関する事についてです。
私はライフコーチとしての知見を深めるべく、
人間を知るために、人類に関係する
形質人類学、言語学、遺伝学、考古学などに関する書物も
読みます。
今日は私が読んだもので面白く、大変参考になったものを二つ、
ご紹介させていただきます。
一つはSNSに関係する事。
もう一つは、人間性の起源についてです。
(後半に記載しましたが、こちらがかなり面白いです)
先ず初めに、
現代では他者とのコミュニケーションの手段の一つに
ソーシャルネットワークがあります。
ある研究では、FBでお友達が多い人は、少ない人よりも
偏桃体などが大きいという相関関係がある事が分かりました。
偏桃体などが大きいから友達が多いのか、
友達が多くなったから偏桃体などが大きくなったのか、
それはこれからの研究で明らかにされるようです。
いずれにしても、
人と関わる事は脳に良い影響がある様です。
確かに、色々な人がいて、
時には大きなストレスと感じる場合もありますが、
脳の偏桃体などが大きくなる可能性があるのです。
もしかしたら、
自らの脳が持っている以上の
脳の可能性を広げる事が出来るのかもしれません。
そう考えると、
SNSで関わる人が増える事は、
それと同時にストレスが増える事にもなりますが、
自分自身の未知なる脳の可能性を引き出すためにも、
努力と工夫をしながら上手に関わっていきたいものですね。
―――――――――――――――――――――――――――――
元記事はこちらです⇓
「Facebookの友達多い人、脳の一部領域が大きい」英研究者が報告
Facebook上の友達の数と、脳の特定領域の大きさに相関関係があると報告された。
Facebook上の友達の数と、脳の特定領域の大きさには関係があると、英国の研究者が報告した。友達が多い人ほど、扁桃体などが大きいという。
ユニバーシティカレッジロンドン(UCL)のジェレイント・リーズ教授らが、Facebookを使っている125人の大学生の脳をスキャンしたところ、Facebookの友達の数と、いくつかの脳の領域の灰白質の量に強い関連が見られたという。関連が見られた領域は、扁桃(へんとう)体、右上側頭溝、左中側頭回、右内嗅皮質。
advertisement
扁桃体は記憶の処理や情動反応に関係し、最近の研究で、扁桃体の灰白質の量が多い人は、現実世界での友達の数が多いと示されている。
上側頭溝は生物の動きの動きを認識でき、中側頭回は社会的手掛りの読み取りに、右内嗅皮質は記憶やナビゲーションに関連するという。
これら3つの領域の大きさは、Facebook上の友達の数とは関連があったが、現実の友人の数とは相関はなかったという。
研究者らは、この研究で発見されたのはあくまでも相関関係であり、因果関係ではないと強調している。
今回のデータからは、Facebookの友達が多いことで脳の一部を大きくしたのか、生得的に友達をたくさん作る特性がある人がいるのかがは分からないと説明している。
「友人の数と関連があるとみられる脳の領域を見つけた。次の疑問は、その構造が時間とともに変わるかどうかだ。それが、インターネットが脳を変えるかどうかの答えを見つける助けになる」
研究では、オンラインでの友達の数と現実での友達の数にも関連があることが示唆されたという。
「研究結果は、Facebookのほとんどのユーザーは、既存の交友関係を補強するために同サイトを使っているという見方を裏打ちしている」
研究結果は「Proceedings of the Royal Society B」に掲載されている。
―――――――――――――――――――――――――――――
そして、もう一つはこちら!!!!かなりおすすめです!!!
これはもう大変読み応えがあり、本当に面白く読めます。
読んだ後に内面の充実を感じられるシンポジウムの特集記事です。
もう今日はこれでおしまい!はい、おやすみなさい~でも
全然良いくらいです。
ぜひお読みいただけたらと思います。!!
紙で印刷して読みたい方はこちらからどうぞ⇓
https://www.jstage.jst.go.jp/article/asj/122/1/122_122.76/_pdf
76 山極 寿一 Anthropol. Sci. (J-Ser.) シンポジウム特集記事 総説 人間性の起源を探求する重要性 山 極 寿 一 1 * 1 京都大学大学院理学研究科 (平成 26 年 5 月 12 日受付,平成 26 年 5 月 19 日受理)
要 約 人類学は,現在私たちが生きている社会や,それを維持するために必要な人間の特性が何に由来するの かを教えてくれる重要な学問である。
人間の形態的特徴と同じく,社会の特徴も,人類の進化史の中に正 しく位置づけないと,現在の人間の行動特性を誤って解釈することになる。
たとえば,集団間の戦いは定 住生活と農耕が登場してから発達したもので,人間の本性とは言えない。
人間の高い共感能力は,捕食圧 の高い環境で多産と共同保育によって鍛えられ,家族と共同体の形成を促した。
その進化史を人間に近縁 な類人猿と比較してみるとよく理解できる。
最近の自然人類学の成果をぜひ高校教育に生かしてほしい。
京都大学大学院理学研究科
〒606–8502 京都市左京区北白川追分町
人類学の重要性 77
はじめに 国政選挙の投票権や狩猟免許などさまざまな許認可が 18歳まで引き下げられようとしている昨今,人類学が高 校の教科書できちんと教えられていないというのは,は なはだお粗末な話だと思う。
そもそも進化論さえまとも に教えられていないのだから,数百万年にわたる壮大な 人類の進化史のなかで創り出された人間性を考察するこ となどできようはずがない。
生物学や医学の分野から人 間の体の仕組みや生理的な特徴が詳しく解明されようと している時代,責任ある成人になる前に人間性について 正しい理解を深めておくことはこの上なく重要である。
人間性を進化の視点から探究する方法には二つの視点 がある。
化石から過去の生活を復元して,進化の歴史を 再構成する方法と,人間に近縁な現存の種と比較しなが ら共通祖先の時代まで遡る方法である。
化石は断片的に しか残らないし,そこから推測できることには限りがあ る。生理生態や行動などは化石からは判断しにくいから だ。
一方,現存種との比較からは,進化の時間が隔たる ほど,共通祖先の姿を復元しにくくなる。祖先がどの種 の特徴を色濃く残していたか,根拠を持って類推するの が難しいからである。そのため,二つの方法を補完的に 用いて,なるべく確からしい祖先の特徴を探りあてるし かない。 それでも,類推するための証拠が増えれば,これまで の誤解が解けて,人間の進化の足跡が明らかになってく る。
これまでそういうことが何度もあった。有名な事件 は,1911 年のチャールズ・ドーソンによるピルトダウ ン人の発見である。それまで欧米の学者の多くは,人類 の祖先がまず脳を拡大し,その大きな脳を支えるために 二足で立って歩きはじめたと考えていた。そして,その 特徴をもつ化石はアジアやアフリカではなく,ヨーロッ パで見つかるはずだと信じていた。脳容量が現代人並み に大きく,顎骨が類人猿に似ていたピルトダウン人の頭 骨は,当時の人類学者が待望していた特徴を備えていた。 そのため,この頭骨は人類の直系の祖先と見なされ, 1953 年にそれがまがいものと発覚するまで大英博物館 に鎮座し続けた。
実はこの頭骨は,現代人の頭部とオラ ンウータンの下顎骨を巧みに組み合わせて作られていた のである。その後,人類の祖先は時代を遡ればのぼるほ ど,脳は類人猿並みに小さくなることが判明した。逆に, いくら遡っても祖先は直立して二足で歩いていた。しか も,200 万年以上遡ると人類の化石はアフリカにしか出 土しないことがわかってきた。20 世紀初頭の人類学者 の臆測に反して,人類の祖先は当時暗黒大陸と見なされ ていたアフリカに誕生し,脳の拡大ではなく,直立二足 歩行から進化の足跡を刻み始めたのである。
人間性に関する大きな誤解 人間の本性についても,実は現在もなお誤解され続け ていることがある。アメリカ合衆国のバラク・オバマ大 統領は,2009 年 12 月 19 日にオスロで行われたノーベル 平和賞の受賞式で,「戦争はどのような形であれ,昔から 人類とともにあった」,「平和を維持する上で戦争という 手段にも果たす役割がある」,「戦争は時には必要であり, 道徳的にも正当化できると判断できることがある」と述 べている。
これは,明らかにかつて人類学者が唱えた説 をもとにしている。それは,1950年代に出された「骨歯 角文化」と「狩猟仮説」である(山極,2007)。1924 年 に南アフリカでアウストラロピテクス・アフリカヌスと いう 160 万年前の化石を発掘したレイモンド・ダートは, 第二次大戦後に同じ場所でヒヒの頭骨に決まって同じよ うなへこみがあることを発見した。彼はそのへこみが, カモシカの上腕骨を使ってアフリカヌスが狩猟した跡だ とみなし,この時代の人類がすでに組織的な狩猟を行っ ていたと考えた。また,近くで発見されたアフリカヌス の頭骨にも同じようなへこみがあることから,アフリカ ヌスどうしが獣骨を武器として殺し合った証拠だとし た。まだ類人猿並みの小さな脳をもっていたアウストラ ロピテクスの時代に,すでに狩猟具を用いて肉食を常習 化させ,それを武器に置き換えて仲間どうしで戦いを始 めていたというのである。
この仮説は,アメリカの人気劇作家ロバート・アード レイによって数冊の本になった(アードレイ,1973)。 霊長類の集団が示すなわばり防衛の行動特性を受け継い だ人類の祖先が,森林から草原へ出て行って狩猟能力を 高め,狩猟具を武器にして集団間の戦いを始めたという 内容である。
しかも,この殺戮能力は現代人にまで受け 継がれ,人類は古い昔から武器と戦争によって秩序と平 和をもたらしてきたというのである。この説は一般社会 に急速に受け入れられた。第二次大戦で人類史上もっと も大規模な殺戮を経験した人々にとって,戦争が人間の 本性であり,自由と平和を築く有効な手段であると見な すことが,心の傷を癒す効果を持ったからに違いない。
そして,この説は 1965 年にアーサー・クラークとスタ ンリー・キューブリックによって制作された映画「2001 年宇宙の旅」に見事に反映されることになる。この映画 で「夜明け前」と名付けられた冒頭のシーンには,アウ 78 山極 寿一 Anthropol. Sci. (J-Ser.) ストラロピテクスと思われる,道具をもたない猿人たち が登場する。あるとき,宇宙から突然降り立った直方体 の物体に霊感を与えられた猿人の一人は,サバンナに散 らばっている動物の骨を狩猟具として用いる考えを抱 く。狩猟に成功した猿人たちは,やがてその道具を仲間 の猿人たちに向けて,水場争いに勝利をおさめ,集団ど うしの戦いが激化していくというシナリオである。この 映画を見て,人類の進化史を理解できたと感じた人々は 多かったのではないだろうか。
しかし,ダートの仮説はそもそも大きな間違いであっ た。その後,アウストラロピテクスの化石や肉食動物の 古生態を詳しく調査したチャールズ・ブレインによって, ヒヒやアウストラロピテクスの頭骨にあったへこみは, ヒョウの犬歯にぴったり合うことが判明した。アウスト ラロピテクスの狩猟の獲物と見なされた動物の骨も, ヒョウやハイエナによって運び込まれたものだった。ア ウストラロピテクスは狩猟者ではなく,ヒョウやハイエ ナに狩猟される獲物だったのである(ハート&サスマン, 2007)。
もちろん,彼らが狩猟具を武器に替えて戦いを 始めたという証拠もない。そもそも人類の祖先が殺傷力 のある道具を用いて狩猟をした証拠は,50 万年前の南 アフリカや 40 万年前のドイツで見つかっている先をと がらせた槍が最古である(クライン&エドガー,2004)。 この槍を人間との戦いに用いた形跡はない。最古の石器 は 260 万年前のエチオピアで発見されているが,狩猟具 として使ったのではなく,肉食獣が食べ残した獲物の骨 から肉をはがしたり,骨を割って骨髄を取り出すのに用 いられたようである。700 万年にわたる人類の進化史の なかで,武器を用いた戦いはわずか 1 万年前ぐらいに始 まった出来事であり,とても人間の本性とは言えない。 人間性を形作る主な特徴は,戦いが始まる前にすでに完 成しており,戦いが人間の社会に平和をもたらす手段で あり続けてきたなどとはとても考えられないのである。
人間以外の霊長類との比較による考察 戦いが人間の本性ではないことは,人間以外の霊長類 がどのように社会を作っているかを考察してみるとよく わかる。現在,地球上には約 300 種の霊長類が生息して おり,このうち昼行性の霊長類は夜行性の種に比べて体 が大きく,大半が 2 頭以上の群れを作って暮らしている。 1980年代から社会生態学という学問分野で,サルたちが 群れを作って暮らす理由についてさまざまな議論が展開 された(Sterck et al., 1997)。
その結果,まず繁殖に大き なコストをかけるメスが,栄養価の高い食物を効率よく 摂取し,捕食者から身を守るために,集合して暮らす性 質を発達させたと考えられた。一方,オスにとっては繁 殖を成功に導くためにはメスの近くにいることが有利に なる。そのため,メスが群がるとそこにオスも参加して 群れが形成される。しかし,自分で子どもを産むことが ないオスは,より多くのメスを妊娠させることが子孫を 多く残すことにつながるので,交尾相手をめぐって他の オスと競合を高める。その結果,群れに参加できずに単 独で行動するオスや,メスのいないオス集団,1頭のオス が複数のメスと作る単雄複雌群,複数のオスが複数のメ スと共存する複雄複雌群といった,集団構成に大きな変 異が生じる。
また,体が大きく力の強いオスにメスがハ ラスメントを受けたり,生まれたばかりの子どもを殺さ れたりする。子殺しは授乳期間の長い種に多く,子ども を殺すことによって授乳を止めて発情を再開させ,その メスと交尾をして自分の子どもを残そうとするオスの繁 殖戦略の一つと見なされている。そのため,子殺しを防 止しようとしてメスは力の強いオスを選んで安定した関 係を築こうとする傾向が強まる。この社会生態モデルで は,狩猟や仲間との戦いが群れを作る要因となっていな い。人類の祖先が進化の初期,他の霊長類と似たような 能力で同じような暮らしをしていたとすれば,狩猟や戦 いが人間の社会性を育んだとはとても言えないのである。
ではいったい,人間の本性とは何か。それはどんな背 景で,どんな必要性から生まれたのだろう。それを考え るためには,人間と近縁な類人猿の社会と比較してみる ことが必要になる。社会や行動は化石に残らないし,類 人猿と人間は近過去に共通の祖先から分かれて,同じ進 化の時間を経てそれぞれの社会に特有な特徴を発達させ ていると考えられるからだ。
つまり,類人猿と人間との 間で共通な特徴は,おそらく共通祖先が持っていたと思 われるし,異なる特徴は祖先が分岐してから新たに発達 したと見なせる場合が多いからである。 共通な特徴の好例が,多様な文脈で現れる対面交渉や 自己主張するときのディスプレイである。
類人猿とは系 統的に離れるオナガザル科のサルで,地上をよく用いて 暮らすヒヒやマカクにとって,相手を注視するのは軽い 威嚇にあたる。優位なサルに見つめられれば,劣位なサ ルは視線を避け,採食場所をゆずったり,交尾相手から 離れたりしなければならない。
ところが,類人猿では注 視が威嚇を意味するとは限らず,グルーミングや抱擁な どの宥和的交渉,遊びや交尾の誘いであったりする。し かも,目を合わせることによって優劣関係が露呈しない ので,対面することが多くなる。食物を分配する行動や Vol. 122,2014 人類学の重要性 79 対面交尾が多くみられるのも類人猿の特徴といっていい だろう。
これは人間にも通じる特徴である。また,人間 に近縁なアフリカの類人猿は,地上で二足で立って胸や 物をたたいたり,枝を引きずって走る行動が共通してい る。これはおとなのオスに多く,自己主張のための誇示 行動として,型にはまったディスプレイになっている。
ゴリラの胸たたきが最も定式的で,群れどうしが距離を 取り合うときやオスどうしが張り合うとき,出発の合図 や求愛などに使われる。一方,チンパンジーでは最優位 のオスが自分の社会的地位を誇示するときに使われ,ボ ノボでは出発の合図としてのみ用いられる。この違いは, オスが対等に張り合うゴリラ,群れ内で共存するオス間 に優劣の順位のあるチンパンジー,メスより弱い立場で 攻撃性が低いボノボの社会の特徴を反映している。
すな わち,共通祖先にあったディスプレイが,それぞれの社 会の特徴に合わせて変形して来た歴史を表しているのだ ろうと考えられる。人間にも二足で立って正面を向き, 胸を張ったり,手を振り上げたり,柏手を打ったりして 自己主張する表現が男に多く見られる。アフリカの類人 猿と共通な形態特徴だけでなく,共通の行動特性に人類 独自の社会性を反映させた結果だろうと思う。
異なる特徴は,性に関連する形態や行動に見ることが できる。チンパンジーのメスは発情すると性皮が大き く腫れ,複数のオスと立て続けに乱交的な交尾をする。 オスは頻繁に多量の精子を放出するので睾丸が大きい (Harcourt et al., 1981)。オランウータンやゴリラはメス が顕著な発情徴候を示さず,オスの睾丸も小さい。これ は特定のオスとメスが排他的な交尾をするためであると 考えられる。人間の性の特徴はオランウータンやゴリラ に近い。おそらく,人類の祖先が家族をつくり,特定の 雌雄のペアに性交渉を限定したことがこの特徴に反映さ れているのだろうと考えられる。
人間の特異な生活史から人間性の起源を探る 人間は家族をつくり,複数の家族が集まって共同体を 形成し,生計,繁殖,教育などの活動をそのなかで行う。 この家族と共同体という重層構造をもつ点が,他の霊長 類と異なると考えられる(Grueter et al., 2012; Chapais, 2013)。人間以外の霊長類には家族的な群れか,家族を もたない大きな群れしか見当たらないし,重層的な構造 をもつヒヒの群れでもその中の集団が協力し合うという 現象はめったに見られないからだ。
その理由は,家族と 集団が拮抗する原理で作られているからである。家族は 互いに仲間を思いやり,仲間のために犠牲もいとわない 行為によって支えられている。
一方,集団は安定した個 体どうしの関係を認知することによって支えられてい る。優劣の関係があれば,劣位な個体が自分の行動を抑 制する。対等な関係であれば,対等なやり取りが期待さ れる。物を譲れば,別の機会にそのお返しがある。
だか ら,血縁関係にある仲間をえこひいきし見返りを求めな い家族と,安定した社会関係に則って行動する集団とは 相いれなくなり,二つを両立させることができなくなる のである。
ではなぜ,人間は原理の異なる家族と共同体を両立さ せることができたのだろう。それは,類人猿と人間の子 どもの成長や子育ての方法を比べてみるとよくわかる。
人間の赤ちゃんは 3 キログラムを超える重い体重で生ま れ,わずか 1 歳前後で離乳してしまう。にもかかわらず, 離乳した幼児は華奢な乳歯でおとなと同じような硬い食 物を食べることができない。人間はどの文化や社会でも, 20 歳ぐらいまで他人に食物を供給してもらって育つの である。
ところが,ゴリラでもチンパンジーでも出生時 の体重は 2 キログラムに満たず,3 ~ 5 歳まで乳を吸っ ている。離乳したときはすでに永久歯が生えており,お となと同じ自然の食物を食べることができ,すぐに仲間 に頼らずに自分で食物をさがして育つようになる。 この不思議な人間の子どもの成長は,多産と大きな脳 という特徴を獲得する過程で備わったものである(山極, 2012)。
初期人類は,類人猿の生息したことのない樹木 の少ない草原へと進出した。そこで直面した課題は,広 く分散した食物を探し歩くことと,強力な地上性の肉食 動物から身を守ることだった。直立二足歩行は,おそら く広く歩き回って体力の劣る仲間に栄養価の食物を運ぶ ために発達した。ヒヒのように,特定の安全な寝場所に 複数の集団が集まって夜を過ごすことで,樹上の安全な ベッドを作れない草原で身を守ったのだろうと思う。
や がて,肉食獣が食べ残した獲物から肉や骨髄を取って食 べるようになり,多大な栄養を確保できたおかげで脳は 大きくなりはじめた。社会脳として進化した人間の脳は, 集団規模が大きくなるに従い,社会的複雑さに対処でき るように新皮質の割合が増えることによって類人猿の 3 倍以上の容量になったと考えられる(ダンバー,1998)。
脳が大きくなり始めたのは,ホモ属が初めて登場した 200 万年前である。しかし,人類はこのとき,脳の大き い赤ちゃんを産んで類人猿と同じ成長速度で子どもが育 つ道を選択できなかった。
脳が大きくなる前の 500 万年 間に直立二足歩行が完成し,その歩行様式に合うように 骨盤が変形して産道の大きさが制限されてしまったから 80 山極 寿一 Anthropol. Sci. (J-Ser.) である。
そこで,胎児の状態の赤ちゃんを産んで,脳を はやい速度で発達させ,12 ~ 16 歳で完成させるように なった。類人猿の脳は離乳時までに大人の大きさになる ので,現代人は 3 倍の時間を脳の成長に費やしているこ とになる。脳の成長には多大なエネルギーを費やすので, その分人類は身体の成長を遅らせて,必要なエネルギー を脳に回すようにした(Bogin, 1999)。
これが,人間の 子どもの成長が類人猿より遅れる理由である。その結果, 人類は脳が大きく成長の遅い子供をたくさん抱えること になった。 こういった生活史戦略の変化が,共同育児という行動 を発達させ,人間に独特な社会性を育んだのだろうと思 う。
類人猿は共同で育児をしない。単独生活のオランウー タンは母親だけが子どもを育てるし,群れで暮らすチン パンジーは他のメスが子育てを手伝うことがあるがオス は参加しない。ゴリラのオスは離乳後の幼児の面倒を見 るが,メスといっしょに子どもを育てたりはしない。
し かし,こうした子育てに母親以外の手が加わる程度に応 じて,離乳年齢に差ができることは興味深い。離乳年齢 はふつう体の大きさに応じて高くなると考えられるの に,最も体の大きなゴリラが低く(3 ~ 4 歳),続いて チンパンジー(5 ~ 6 歳),オランウータン(7 ~ 9 歳) が最も高いのである。おそらく,人類の離乳年齢が低く なったのも,子育てに多くの人が関わるようになったか らだろうと考えられるのだ。
では,共同保育はどういった社会性を育んだのだろう。 これにはいい例がある。人類や類人猿とは系統的に遠く 離れた南米のマーモセットやタマリンは,人類顔負けの 共同保育をする。これらのサルは双子や三つ子を産む多 産という特徴を持ち,生まれたばかりの赤ちゃんを年上 の子どもやオスが参加して共同で育てる。養育者になっ たおとなのサルは子供に頻繁に食べ物を分け与える。
実 は最近の報告で,おとなの間に食物の分配が見られる種 には,必ずこういった養育者から子供に食物が分け与え る行動が見られることが分かった(Jaeggi & van Schaik, 2011)。
つまり,子どもを養育するために発達した行動 が大人の間に普及し,別の意味を持つ社会行動となった ということが考えられるのである。
チンパンジーのおと などうしの間には,交尾相手を確保するためや同性間で 連帯するために食物の分配行動が見られる。こういった 行動はもともと養育者と子どもの間から大人の間に広 がったのかもしれない。
こういった視点に立つと,人類が共同保育を通じて得 た特徴が見えてくる。それは共感と同情,そして見返り を求めない奉仕の精神である(山極,2012)。成長の遅 い子どもに食物を分け与え,生活上の様々な便宜を図る のに,そのお返しを期待したりはしない。脳の増大とと もに成長過程が長引いたおかげで,養育者と子どもの間 にあった共感や同情などの感情を大人の間にまで普遍す ることができたのではないだろうか。
もちろん,共感や 同情の能力は,熱帯林の外という類人猿の経験していな い過酷な環境を生き延びるために大きな力を発揮したに 違いない。南米の熱帯雨林に暮らすタマリン,マーモセッ トは脳を大きくすることも,熱帯雨林を出る必要もな かったので,子どもの成長が早く,人類のように共感能 力を高めるには至らなかったのだろう。
家族と共同体を組み合わせて社会を作ることができた のは,本来血縁者に限られていた感情を人類が他者にも 抱くことができるようになったからである。状況によっ て他者との関係を臨機応変に作り変えながら,安定した 社会関係を維持できる能力こそ,この重層社会に必要な 能力である。
それを育てたのは,霊長類を育んだ熱帯雨 林の外で,食料の供給と子育てに多彩な協力関係を結ん で生き延びた結果,人類が採用した生活史戦略であった のだと考えられる。
おわりに 私がこれまで述べてきた進化のストーリーはまだ仮説 にすぎない。社会や行動は化石に残らないから,タイム マシンでも発明しない限り,この 700 万年の間に人類が どんな社会で暮していたか,確実な証拠は決して得られ ないからだ。だが,現代の私たちが共通に持つ人間性が どのようなものであるのか,何に由来するのか,どんな 目的のために発達したのかに思いを巡らすことは,現代 の社会を理解するために,私たちが抱えるさまざまな社 会問題を解決するために重要である。
過去の人間性を誤 解することは,現代の私たちの行動を間違って解釈する ことにつながるからだ。これまでにも多くの思想家たち がこの問いに答えを与えようとしてきた。少なくとも自 然人類学は,それを科学的証拠と視点に基づいてより確 実なものにしようとしている。それをまだ証明されてい ないからといって等閑に付し,今行われている議論を紹 介しないのは高校生にとって明らかにマイナスだろうと 思う。
社会に出て責任ある立場を担おうとしている若者 たちは,もっと人間性について関心を持つべきだからで ある。人間性の由来について知識を豊かに持ち,人間に ついて深い洞察力を持った次世代の若者たちに,未来を 託したいと思う。
Vol. 122,2014 人類学の重要性 81 参考文献 アードレイ,R.(1973)アフリカ創世記.徳田喜三郎・森 本圭樹・伊澤紘生訳,筑摩書房. Bogin B. (1999) Evolutionary perspective on human growth. Annual Review of Anthropology, 28: 109–153. Chapais B. (2013) Monogamy, strongly bonded groups, and the evolution of human social structure. Evolutionary Anthropology, 22: 52–65. ダンバー,R.I.M.(1998)ことばの起源―猿の毛づくろい, 人のゴシップ.松浦俊輔・服部清美訳,青土社。 Grueter C.C., Chapais B., and Zinner D. (2012) Evolution of multilevel social systems in nonhuman primates and humans. International Journal of Primatology, 33: 1002–1037. Harcourt A.H., Harvey P.H., Larson S.G., and Short R.V. (1981) Testis weight, body weight, and breeding system in primates. Nature, 293: 55–57. ハート,D.・サスマン,R.(2007)ヒトは食べられて進化 した.伊藤伸子訳,化学同人。 Jaeggi A.V. and van Schaik C.P. (2011) The evolution of food sharing in primates. Behavioral Ecology and Sociobiology, 65: 2125–2140. クライン,R.G.・エドガー,B.(2004)5 万年前の人類に何 が起きたか? 意識のビッグバン.鈴木淑美訳,新書館. Sterck E.H.M., Watts D.P., and van Schaik C.P. (1997) The evolution of female social relationships in nonhuman primates. Behavioral Ecology and Sociobiology, 41: 291–309. 山極寿一(2007)暴力はどこからきたか:人間性の起源を 探る.NHK ブックス. 山極寿一(2012)家族進化論.東京大学出版会.
さて、今日は、最先端の遺伝子研究である「エピジェネティクス」と健康についてです!
遺伝子は人体設計図だという事は皆様もご存知だと思いますが、その設計図を作る別の遺伝子がある事が分っていて、これを研究する新たな学問が「エピジェネティクス」です。
近年、遺伝子の働きをオン、オフにするエピゲノムが、加齢やストレス、食生活の影響を受けやすい事がわかってきています。
現代正統医学の分野では、薬によってエピゲノムを操作することで、遺伝子を正常な状態に戻せるとして新たな治療法の開発を目指しています。
最先端のエピゲノムの解析装置が普及した2000年代半ばから研究が国内外で急速に進み、まずがんの分野で先行しました。既に日本、欧米でがん治療薬が開発され使われています。
糖尿病などの生活習慣病やうつ病などの精神疾患でも、エピゲノムとの関係が明らかになるにつれ、今後は、治療薬の開発競争が本格化する見通しだという事です。
このエピゲノムについて、私も昨年から色々と情報を集めるなどしており、とても注目しています。
そして、自然療法家の私は、当然の事ながら、加齢、ストレス、食生活の影響の方に重要性を感じています。
なお、ロシアで行われた言語学者や遺伝学者も加わった研究により、DNAそのものである、遺伝子コードのアルカリ列は規則的な文法に従っており、私達の言語のような一連の基本ルールに従っている事が見出されました。
つまり、人間の言語は、本来のDNAの反映なのだそうです。
これにより、遺伝子を切断したり、置き換えたりせずに言葉や周波数でDNAに影響を与えられる新しいタイプの医学を構築できる証拠が見つかったという事なんです。
日本でも、2011年 瑞宝中綬章を受章された、遺伝子工学で世界をリードされてきた村上和雄先生が代表を務める「心と遺伝子研究会」で研究されています。
という事で、私が何をお伝えしたいのか、もうお察しですね。
全ての人は、ご自分の生活習慣を見直す事やストレス管理、そして言葉を利用して、健康をコントロールしていく事が出来るといえるんです!
特に、言葉は最初、擬音語として生まれ、雨が降ってきたよ~というのを「ザーザー」などと口頭で伝える為に発生したのが始まりなんですね。
言葉は自然から生まれた音ですので、建設的・肯定的・循環的な要素で満たされている自然界を表現する言葉だけが本当の意味で正しい言葉といえますね。
だから、暴言など否定的な言葉は、本当の意味では言葉ではないのですね。
人間のDNAに良い影響を及ぼす事が出来るのは、自然界から生まれ出た良い言葉だけなのです。
ありがとうや、愛や感謝などはDNAにとって(心にとっても!)、最も栄養になる言葉といえますね。
暴言で人の心は傷つきますが、傷ついているのは心だけではなく、DNAそのものも大きなダメージを受けているのです。
遺伝子の働きをオン、オフにするエピゲノムの役割、それに、私達の言語のような一連の基本ルールに従っているという遺伝子コード、
これらに、影響を与えるという加齢やストレス、食生活、言葉・・・・
自らの責任において、ある程度は健康管理・維持ができるのですから、出来る事から始め、病気予防・健康維持に努めていきたいですね。
 ・・・皆さまがいつも温かな幸せにつつまれますように・・・
・・・皆さまがいつも温かな幸せにつつまれますように・・・
一昨日、「言葉と周波数でDNAが変わる事を科学者が発見」という記事を掲載しました。
その研究をしたロシアの科学者は、ゴミとされている90%のゲノムを研究し、人間のDNAは、肉体の形成だけではなく、データの蓄積と通信にも用いられている事を発見しました。
そして、DNAに情報が蓄積される仕組みについても、書かれていましたね。
また、ロシアの言語学者は、遺伝子コード、とくに、明らかに90%に満たない部分が人間の言語と同じルールに従っていることを見出したとの事でしたね。
私がことさらこのロシアの科学者の研究に興味があるのは、アメリカによる情報操作がされていないという事と、ホメオパシーのレメディがなぜ情報を保持する事が出来ているのか。そして、なぜ、レメディによって、人間、動物、植物の生命力を高める事ができるのか。そのヒントになる研究だと思っているからです。
という事で、私が注目している遺伝子関連の記事が経済新聞に掲載されていたので、皆様にもお伝えしますね。
■ゲノムの8割に役割 理研など国際チームが解明 2012年9月11日付 経済新聞
理化学研究所などが参加する国際研究プロジェクト「エンコード計画」は、人間のゲノム(全遺伝情報)の8割以上が何らかの機能を持つことをつきとめた。無用と思われていた部分が遺伝子の働きを調節するなど生命活動に必要な役割を担っていた。生命の大きなナゾを解明するととともに、創薬にもつながる成果という。
人間のゲノムは2003年に解読された。その結果、生命活動に不可欠なたんぱく質の設計図に当たる遺伝子は全体の約2%しかなく、残りは働きが不明だった。
ゲノムを詳細に調べたところ、80.4%が遺伝子を動かせるスイッチなどの役割を果たしていることが判明。スイッチに関係する異常でタンパク質がうまくできないと、病気になることがわかってきた。がんや認知症、糖尿病や高血圧などとの関連が指摘されている。
成果は、英科学誌ネイチャーに発表した。エンコード計画には、日本のほか、米英など32の研究機関が参加している。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
私は、上記の日経の記事と、ロシアの科学者の研究を掲載した記事から
「やはり言葉と周波数が遺伝子を動かせるスイッチの役割の一つなのね・・・・・・・」と思いました。
それを踏まえ、心と体の関係を遺伝子レベルで研究している「心と遺伝子研究会」のHPをご紹介したいと思います。
今回のブログ記事にご興味を持たれた皆様にとっては、有益な情報が得られると思いますので、是非、みてみてくださいね
(HPより引用転載)
生命科学分野の研究は大変な勢いで進歩してきており、2000年6月にはヒト・遺伝子の全配列が解明されました。そして、遺伝子に関するいろいろなことが良く分かってきました。
遺伝子の大切な働きの一つは、その情報を親から子、子から孫へと伝達することですが、他に外界からの刺激によってON/OFFし我々の体を正常に維持するという機能もあります。
遺伝子スイッチのON/OFFは我々を取り巻く外部環境からの物理的・化学的刺激に反応して起こりますが、精神的ストレスや感動・興奮・喜びなどの内部要因によっても起こります。
このプロジェクトは、これらの陽性ストレスや感情が我々の体にどのように影響しているかを遺伝子スイッチのON/OFFという全く新しい視点から解明することを目的としております。
(転載終了)
☆メモ
遺伝子に関するエビジェネティックスという新しい学問があります。
DNAは確かに生物を作る基本骨格ですが、DNAの情報はDNAの上を覆う化学物質の層にコントロールされている事が明らかになっています。
これを受けて、分子生物学を考える上で基本的方向転換が起こり、遺伝子を包んでいる部分を研究するエピジェネティックスという新たな学問が誕生し、ここ十数年で研究活動が活発化しています。
ヒトゲノムが一であっても、エピゲノムは数百倍に及びますが、風変わりな仮説とは違い、既にエピジェネティック治療が開始されています。エピジェネティック薬の効果はまだ10%や20%程度と低いものの、効果は臨床で証明されています。
なお、ショウジョウバエの研究から、喫煙や食事の習慣などによる一代でのエピジェネティック的変化が孫の代まで影響を及ぼす事が判っています。
そのため、メンデルの法則に逆らうどころか、ダーウインの進化論(現実的には、世界では宗教家が圧倒的に多いので、ダーウインの進化論を支持する人の割合は少ないが、日本人のほとんどはダーウイン進化論信者である)をも揺るがす事になる為に発言には慎重さが求められ、これまでエピジェネティックスの情報は公の場にはほとんどでてこないものでした。
今回、当ブログに掲載した日経の記事は、詳細な事まで書いていないので、定かではありませんが、おそらくエピジェネティクスの分野の新しい研究報告の事を書いているのではないでしょうか。
また、心と遺伝子研究会や、当ブログの「言葉と波長でDNAが変わる・・・」の記事に掲載したロシアの科学者の研究も、おそらくエピジェネティックスの分野の話だと思います。
そして、私はひそかに思っています。ホメオオパシーの遺伝マヤズム理論はエピジェネティクッスの研究により解明されるのではないかと・・・・・
参考HP:Newsweek
 ・・・皆さまがいつも温かな幸せにつつまれますように・・・
・・・皆さまがいつも温かな幸せにつつまれますように・・・