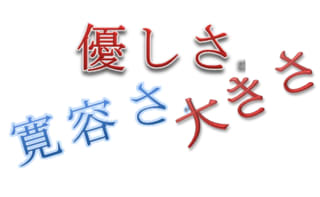にほんブログ村
にほんブログ村
戸石小3年 歩花

夏休みに、さくらとゆうなは、海に行きました。
すなはまで、貝がら集めをしていると、おりたたんだ紙が落ちていました。
ひろげてみると、宝島の地図だったのです。
さくらとゆうなは、そこらへんに落ちている木を使って、船を作りました。
二人は、さっそく、その船に乗って、宝島へ出かけました。
そして、宝島にたどりつき、しばらく歩いていると、一本の橋がありました。
その橋の手前には、とても大きなダイジャがいて、ゆうなとさくらの方をじっと見ています。
二人は、「どうやってあの大きなダイジャをにがすの?」と話し合いました。
すると、さくらがいい考えを思いつきました。
さくらが、「リュックに入れておいたおにぎりを出来るだけとおくになげるので、ダイジャが、おにぎりを追いかけて行くうちに、この橋をわたろう。」そう言うと、ゆうなは、「うん!」と言うように、深くうなづきました。
ゆうなが、「よくそんないい考えを思いついたね。」と言うと、さくらは、「こんな動物、へっちゃらだよ。」と言いました。
ふたりは、しんちょうに橋をわたりました。
二人が、またしばらく歩いていくと、大きな池がありました。
その池には、とても大きな魚が一ぴき泳いでいます。
すると、とても強い風がふいて、上から大きな木が落ちてきました。
さくらとゆうなが、思わず大きなひめいをあげると、その木は、ちょうど池のところでとまりました。
その木を橋のかわりにして、さくらとゆうなは、とても用心して木の橋を渡って池をこえました。
さくらとゆうなは、「木が橋になるとは思いもしなかったね。」と話していました。
そしてまた、二人がしばらく歩いていくと、こんどはチーターがあらわれました。
チーターは二人の方をじっと見つめています。
すると、さっき、さくらがおにぎりをあげたダイジャが助けにきてくれました。
そして、ダイジャは、宝ばこのある場所までつれて行ってくれました。
さくらとゆうなは、ダイジャにお礼を言いました。
宝ばこの中は、しんじゅやほうせきでいっぱいです。
二人は宝島から家に帰ることができました。
ー感想ー
明日はもう二学期の終業式、いよいよクリスマスや正月をはさむ楽しい冬休みが始まる。
小学三年生の孫娘が、二学期に『ものがたり』作りに挑戦した成果を冬休みを前に、学校から持ち帰った。
野暮用で娘宅を訪問すると、その成果を見せてもらった。
『小学三年生はこんなに書けるのか』というのが正直な感想だ。
授業の中での取り組みなら、決して時間をかけて準備して書いたわけではないだろう。
自分の小学三年生の頃の記憶はあいまいだが、ものがたりを書くなどといった経験はなく、運動会や遠足などの学校行事の後に作文を命じられ、創作的意欲などないまま『なにか書く。』といったところだったろう。
孫娘の作品の評価はできないが、小学三年生にしては、全体を通して工夫した表現ができているように思う。
思い出として、わたしの感想を添えて、ブログ公開しておきたい。