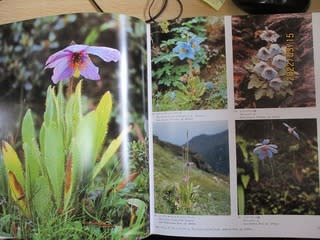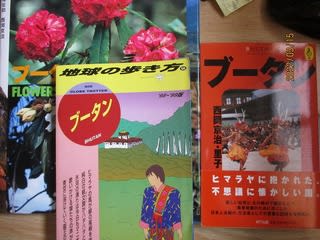雨もやいの変わりやすい天気が続く。今日で三日目か。この頃、わたしは病院で『頚椎症性神経根症』と診断されていて、体を動かす起居動作が難しくて重苦しい日常生活を送っている。まあ病い多き立派な後期高齢者でもある。
雨もやいの変わりやすい天気が続く。今日で三日目か。この頃、わたしは病院で『頚椎症性神経根症』と診断されていて、体を動かす起居動作が難しくて重苦しい日常生活を送っている。まあ病い多き立派な後期高齢者でもある。それはともあれ、ある方からの要望でここに ヒロハカツラ の現在の生育状況の生の画像を載せる。ヒロハカツラ(広葉桂)という樹木自体は珍しいので、あまり一般的ではなく稀少種で専門の植木苗市場でも入手難かな。無論、園芸用のホームセンターでは無理だろう。これは雌雄異株、ちなみに植物分類上はヒロハカツラは植生的には隔離分布で、カツラの突然変異種かな、とわたしは思っている。


ここでは二年前の画像の記録だが、原生地の母樹からの実生木の鉢上げなどの入手の由来、経過、栽培状況などの過去の記事はR5/5/4付けをご覧ください。
植物(樹木・花木・山菜・草花・種子)の品種ごとの単価一覧表や、入手方法は、R6/9/18付けのこのブログで公開しています。(緑字下線部分を左クリックすると、別画面を開くことができます。)











 6月23日午後2時過ぎ、わたしは郷里での喜寿祝同窓会があり、その帰途、この際にと思い みちのくアジサイ園 に行く。栽培場所は北限ともみなされているが、東北では珍しい岩手県一関市内の山中である。アジサイの満開時期にはまだ早いのは分かっていたが初めてである。現在、一部のヤマアジサイ類が咲いている。ここは、既存の推定樹齢80年以内の杉林で、間伐や除伐によって出現した林床を利用したアジサイ園である。この日、曇天のなかで中途から時雨れる天候になったが、わたしは主に山本コレクションを見て回る。
6月23日午後2時過ぎ、わたしは郷里での喜寿祝同窓会があり、その帰途、この際にと思い みちのくアジサイ園 に行く。栽培場所は北限ともみなされているが、東北では珍しい岩手県一関市内の山中である。アジサイの満開時期にはまだ早いのは分かっていたが初めてである。現在、一部のヤマアジサイ類が咲いている。ここは、既存の推定樹齢80年以内の杉林で、間伐や除伐によって出現した林床を利用したアジサイ園である。この日、曇天のなかで中途から時雨れる天候になったが、わたしは主に山本コレクションを見て回る。









 今の時期、ユリノキ(百合の木)が開花を迎える。
今の時期、ユリノキ(百合の木)が開花を迎える。