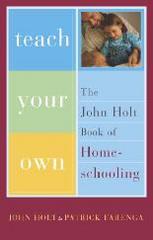
Teach your own - A Hopefull Path for Education by John holt ―アメリカのホームスクール運動の推進者であったJohn Holt(ジョン・ホルト)の著書のタイトルです。(邦訳は『なんで学校へやるの』一光社刊)
「学校」を変革することは可能か?―という問いに、「否」の答えを返す前に、私はより根底的な疑問を抱くようになりました。「学校」とは、たとえそれがうまく運営されるとしても、一体全体、なくてはならないものなのか、と。「学校」は学習の場として最善のところではないのではないか、と否定的な見解を持つようになったのです。ある特殊な技能教育の分野を除けば、「学校」などたいして存在価値がないのではないか、と。
私自身の胸に聞いてみても、現に私が知っている知識の大半は、「学校」で習ったことではないのです。集会、ワークショップ、セミナーなど、いわゆる「学習環境」とか「学習経験」という言葉で総称される場所なり機会のおかげで身につけたものでも全然ないのです。
時間が経つにつれて、私の疑いはさらに深まり、「学習(ラーニング)」という言葉それ自体にも、ある種のうさん臭さを感じるようになりました。(『なんで学校へやるの』)
学校をめぐる議論の大筋は、大きく二つに分かれているようです。
①嫌なことは無理にしなくて(させなくて)もいいじゃないか。
②生徒が嫌だといっても、やるべきことはし(させ)なければいけない。
問題は<学校>という<学習>環境の性格なんですね。さらにいえば、子どもの自由―学校の強制的性格―をどのように考えるかということになるでしょう。
ジョン・ホルトは大学を卒業して小学校の教師になったひとです。熱心な教師であった彼は、だんだんと「学校改革」にエネルギーを注ぐようになりました。「<学校>をなんとか変えなければ?」「子どもが生き生きするような学校はどのようにしたら作れるか?」
そしてついには「教育(学校・学習)に代わるもの」を求め続け、全米でも屈指のホームスクーラーとなったのです。1970年代から80年代ににかけてのことでした。
彼の立場はじつに明確です。「物事を成し遂げる、すなわち、主体的で目的に満ち、意味に溢れた生活および仕事」というものと、「教育、すなわち、脅しや褒美、恐怖や欲望の圧力下で行われる、人生から切り離された学習」とはまったく別物だということです。
彼は特別のことをいっているのではありません。いまどき、だれでもいいそうなことです。しかし、そこまでは同じでも、その先一歩を踏みだすかどうかで決定的なちがいが生じるのです。
ここからイリイチのような「義務制の学校はなくしてしまえ」(Deschooling)といった提案が生みだされました。たしかに学校無用論は続出しましたが、現にあいかわらず学校は存在しています。この先も今と同じように存在し続けるでしょう。でも、学校という<学習>環境は様変わりしたし、今後も変わりつづけるだろうとわたしは思います。
いまや、私たちの社会は学校(子ども)をもてあましているのではないでしょうか。
中高一貫だとか、小中一貫だとか、高大一貫だとか、なんとも「一貫」ばやりですが、それはいったいどういうことですか?「一を以て貫く」とはだれかの言でしたが、はたして、子どもの仕合わせにつらなる「一貫」性が学校なんかにあるのかいな。(一缶小人)
「学校」を変革することは可能か?―という問いに、「否」の答えを返す前に、私はより根底的な疑問を抱くようになりました。「学校」とは、たとえそれがうまく運営されるとしても、一体全体、なくてはならないものなのか、と。「学校」は学習の場として最善のところではないのではないか、と否定的な見解を持つようになったのです。ある特殊な技能教育の分野を除けば、「学校」などたいして存在価値がないのではないか、と。
私自身の胸に聞いてみても、現に私が知っている知識の大半は、「学校」で習ったことではないのです。集会、ワークショップ、セミナーなど、いわゆる「学習環境」とか「学習経験」という言葉で総称される場所なり機会のおかげで身につけたものでも全然ないのです。
時間が経つにつれて、私の疑いはさらに深まり、「学習(ラーニング)」という言葉それ自体にも、ある種のうさん臭さを感じるようになりました。(『なんで学校へやるの』)
学校をめぐる議論の大筋は、大きく二つに分かれているようです。
①嫌なことは無理にしなくて(させなくて)もいいじゃないか。
②生徒が嫌だといっても、やるべきことはし(させ)なければいけない。
問題は<学校>という<学習>環境の性格なんですね。さらにいえば、子どもの自由―学校の強制的性格―をどのように考えるかということになるでしょう。
ジョン・ホルトは大学を卒業して小学校の教師になったひとです。熱心な教師であった彼は、だんだんと「学校改革」にエネルギーを注ぐようになりました。「<学校>をなんとか変えなければ?」「子どもが生き生きするような学校はどのようにしたら作れるか?」
そしてついには「教育(学校・学習)に代わるもの」を求め続け、全米でも屈指のホームスクーラーとなったのです。1970年代から80年代ににかけてのことでした。
彼の立場はじつに明確です。「物事を成し遂げる、すなわち、主体的で目的に満ち、意味に溢れた生活および仕事」というものと、「教育、すなわち、脅しや褒美、恐怖や欲望の圧力下で行われる、人生から切り離された学習」とはまったく別物だということです。
彼は特別のことをいっているのではありません。いまどき、だれでもいいそうなことです。しかし、そこまでは同じでも、その先一歩を踏みだすかどうかで決定的なちがいが生じるのです。
ここからイリイチのような「義務制の学校はなくしてしまえ」(Deschooling)といった提案が生みだされました。たしかに学校無用論は続出しましたが、現にあいかわらず学校は存在しています。この先も今と同じように存在し続けるでしょう。でも、学校という<学習>環境は様変わりしたし、今後も変わりつづけるだろうとわたしは思います。
いまや、私たちの社会は学校(子ども)をもてあましているのではないでしょうか。
中高一貫だとか、小中一貫だとか、高大一貫だとか、なんとも「一貫」ばやりですが、それはいったいどういうことですか?「一を以て貫く」とはだれかの言でしたが、はたして、子どもの仕合わせにつらなる「一貫」性が学校なんかにあるのかいな。(一缶小人)









