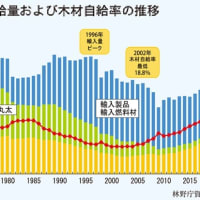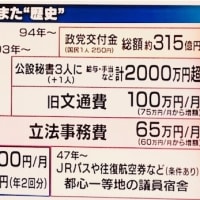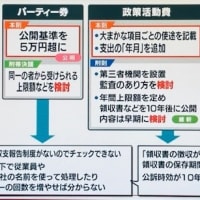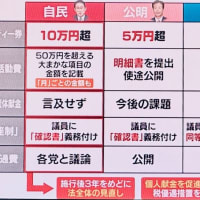『世界の半分がなぜ飢えるのか」(食料危機の構造)朝日新書を読んでから、もうすでに30年経つだろうか。著者のスーザン・ジョージ女史は、世界各地を飛び回って、食料問題を提起していた。私の食糧問題に対する原点ともいえる本である。調べてみると1976年刊とある。女史の提言から世界の食糧事情は全く変わっていない。むしろ悪化している。
地球の人口は当時より10億人増えた。だから飢餓人口が増えるのも当然という、直感的な一面では問題を理解できない。食糧そのものは、この間着実に伸びているからである。女史の訴えは、富の偏在にある。北(先進国)が、南(後進国)の食糧と資源を収奪するからである。その世界的なシステムを作ったのが、北であるから当然である。
北が作ったシステムとは、世界銀行をはじめとした自らが富を得るシステムであり、食料の市場をグローバル化する市場原理である。女史の提言から変わって来たのは、環境の悪化と南の国々が富を蓄え始めたことである。富は国家間から国家内に偏在し始めた。
インドは2億人の飢餓人口を持ちながらも20億ドルもの、小麦や米を輸出している。飢餓の象徴的な国のバングラディッシュさえ、食料は不足してはいないのである。ブラジルも同様である。世界最大の穀物生産国のアメリカでも、常時3000万人が飢えているのである。
日本など先進国の食糧援助で救われるのは、国内の供給する側にある人たちである。援助物資は飢える人まで回っていないのが現状である。海外援助よりも南の国に押し付けた、債務を帳消しにする方がよっぽど現実的である。が、債務を押し付けることで援助がなりたつ以上、それはかなわないことだとスーザン女史の指摘は健在である。
国家間の賃金に格差がある限り、富を求める資本は彼らを利用し詐取する。自由経済がこれを促進させる。先進国の農民の賃金は、途上国の農民の賃金と競争させられるのである。TPPは食糧問題に最悪の結論をもたらすことになる。
食糧は援助ではなく、彼らが自賄いすることでしか未来がない。仮に援助が一時上手く行っても、生産構造やそれに伴う流通などが整備されない限り、食料問題は解決しないのである。