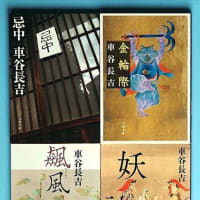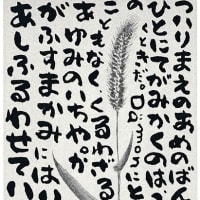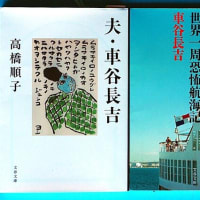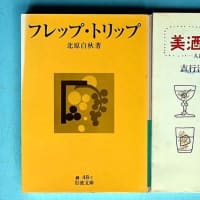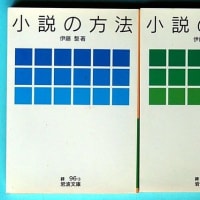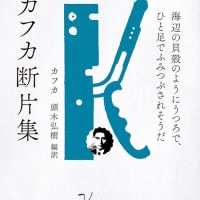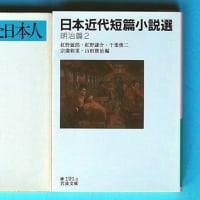■中条省平「カミュ伝」集英社インターナショナル新書(2021年刊)
しばらくアメリカ文学を読んできたけれど、少々疲れたので、BOOK OFFでお安く手に入れたこの伝記を読むことにした。
コロナウィルスがはやったため、だれからともなくカミュの「ペスト」が記憶の底から掘り出され、書店に平積みとなって、マンガなど関連本もふくめ、「ペスト」から教訓を引き出そうとする動きがマスコミなどを通じて流布された。
アルベール・カミュというと、わたしは高校時代のことを思い出す。
友人が電話してきて「話があるんだけど、喫茶店にでもいかないか」といわれ、当時有名だった高崎の“あすなろ”で会った。
たぶん2時間ほど一方的に聞き役をつとめたはず(^^;;)
彼もわたしも、小生意気なまじめ一方の高校生だった。窪田啓作訳の「異邦人」は、はっきりとは覚えていないが、会う直前か、直後に読んでいる。
友人Oさんはなかなかの秀才で、わたしは一目置いていたから、神妙な面持ちで話を訊いたはず。
話題の中心は「異邦人」ではなく、「シーシュポスの神話」であった。
何だか思弁的哲学的で、Oさんのいうことが、どの程度理解できたか、心もとない。
「読んだらそのあとで、また会おう」
カミュは当時の文学青年あるいは哲学青年にとって、輝かしい先駆者であったのではないか?
60年代末期の田舎の高校生は、“徒労”とか“虚無”とかいうことばを核に堂々巡りしただけ・・・のような気がする。
結局わたしは、そのあと、ドストエフスキーを読むことになり、カフカの短編に傾倒し、カミュからは離れてしまった・・・と思う。
「現代詩手帖」「ユリイカ」など、1960年代詩からももろに影響を受けていたが、まあ、そういったことはどうでもいい(´ω`*)
《コロナ禍の中、大きな反響を呼ぶ小説『ペスト』の原作者アルベール・カミュ。フランスが生んだ不世出の作家の全貌にせまる評伝の決定版が登場!
「フランス支配下のアルジェリアでの生い立ち」「第二次世界大戦中、パリでのレジスタンス活動」「『異邦人』など代表作の執筆過程」「プレイボーイとしての華麗なる女性遍歴」「サルトルとの論争」「ノーベル文学賞受賞の経緯」「突然の自動車事故死」など、多くのエピソードをちりばめながら、カミュの生涯・思想・哲学について多角的に論じる。》BOOKデータベースより
カミュがこれほどのプレイボーイだったとは、はじめて知った(ˊᗜˋ*)
われわれ気まじめな高校生は、不条理の神話に、やや欺かれていたような気がする。もっともサルトルだって、女には手がはやかったのだ。
中条省平さんのものは、NHKの100分de名著のカミュも読んで、多少は感心した。
「カミュ伝」は、それを基礎にしたもの。いたって平明で、60年代70年代の文芸評論や思想書を予想して身構えていると、肩透かしをくらう。
第10章「早すぎた晩年」によると、本書のキーワードの一つは「ものいわぬ人々」であり、このあたりはなかなか読ませる。
「ペスト」はもちろん、最近光文社古典新訳文庫から新訳が発売となった「転落」にも、興味はある^ωヽ*
だけど、第1章「アルジェの青春 -太陽と死の誘惑」、第2章「闘う新聞記者 -現実へのコミットメント」は飛ばし読みしてしまった。
「シーシュポスの神話」「反抗的人間」は、新潮文庫で持っているはずだけど、優先順位はずっと先である。
この「カミュ伝」も、読者を虜にするほどの迫力は残念ながら備えてはいない。いまどきの大学の教員なら、失礼ながらだれでも書くレベルであろう。

(本書にも収められている、カルティエ=ブレッソンのスナップポートレイト)
評価:☆☆☆☆
しばらくアメリカ文学を読んできたけれど、少々疲れたので、BOOK OFFでお安く手に入れたこの伝記を読むことにした。
コロナウィルスがはやったため、だれからともなくカミュの「ペスト」が記憶の底から掘り出され、書店に平積みとなって、マンガなど関連本もふくめ、「ペスト」から教訓を引き出そうとする動きがマスコミなどを通じて流布された。
アルベール・カミュというと、わたしは高校時代のことを思い出す。
友人が電話してきて「話があるんだけど、喫茶店にでもいかないか」といわれ、当時有名だった高崎の“あすなろ”で会った。
たぶん2時間ほど一方的に聞き役をつとめたはず(^^;;)
彼もわたしも、小生意気なまじめ一方の高校生だった。窪田啓作訳の「異邦人」は、はっきりとは覚えていないが、会う直前か、直後に読んでいる。
友人Oさんはなかなかの秀才で、わたしは一目置いていたから、神妙な面持ちで話を訊いたはず。
話題の中心は「異邦人」ではなく、「シーシュポスの神話」であった。
何だか思弁的哲学的で、Oさんのいうことが、どの程度理解できたか、心もとない。
「読んだらそのあとで、また会おう」
カミュは当時の文学青年あるいは哲学青年にとって、輝かしい先駆者であったのではないか?
60年代末期の田舎の高校生は、“徒労”とか“虚無”とかいうことばを核に堂々巡りしただけ・・・のような気がする。
結局わたしは、そのあと、ドストエフスキーを読むことになり、カフカの短編に傾倒し、カミュからは離れてしまった・・・と思う。
「現代詩手帖」「ユリイカ」など、1960年代詩からももろに影響を受けていたが、まあ、そういったことはどうでもいい(´ω`*)
《コロナ禍の中、大きな反響を呼ぶ小説『ペスト』の原作者アルベール・カミュ。フランスが生んだ不世出の作家の全貌にせまる評伝の決定版が登場!
「フランス支配下のアルジェリアでの生い立ち」「第二次世界大戦中、パリでのレジスタンス活動」「『異邦人』など代表作の執筆過程」「プレイボーイとしての華麗なる女性遍歴」「サルトルとの論争」「ノーベル文学賞受賞の経緯」「突然の自動車事故死」など、多くのエピソードをちりばめながら、カミュの生涯・思想・哲学について多角的に論じる。》BOOKデータベースより
カミュがこれほどのプレイボーイだったとは、はじめて知った(ˊᗜˋ*)
われわれ気まじめな高校生は、不条理の神話に、やや欺かれていたような気がする。もっともサルトルだって、女には手がはやかったのだ。
中条省平さんのものは、NHKの100分de名著のカミュも読んで、多少は感心した。
「カミュ伝」は、それを基礎にしたもの。いたって平明で、60年代70年代の文芸評論や思想書を予想して身構えていると、肩透かしをくらう。
第10章「早すぎた晩年」によると、本書のキーワードの一つは「ものいわぬ人々」であり、このあたりはなかなか読ませる。
「ペスト」はもちろん、最近光文社古典新訳文庫から新訳が発売となった「転落」にも、興味はある^ωヽ*
だけど、第1章「アルジェの青春 -太陽と死の誘惑」、第2章「闘う新聞記者 -現実へのコミットメント」は飛ばし読みしてしまった。
「シーシュポスの神話」「反抗的人間」は、新潮文庫で持っているはずだけど、優先順位はずっと先である。
この「カミュ伝」も、読者を虜にするほどの迫力は残念ながら備えてはいない。いまどきの大学の教員なら、失礼ながらだれでも書くレベルであろう。

(本書にも収められている、カルティエ=ブレッソンのスナップポートレイト)
評価:☆☆☆☆