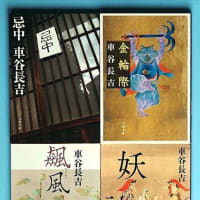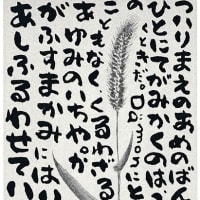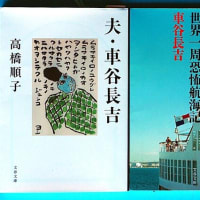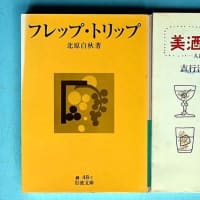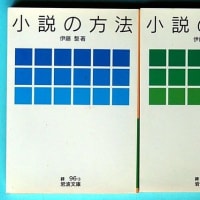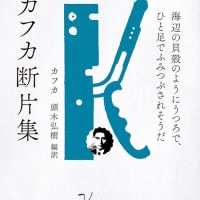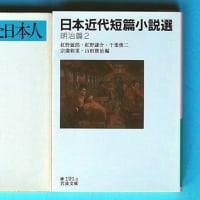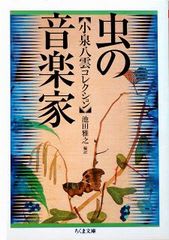
ラフカディオ・ハーン、日本名小泉八雲とは、じつに個性的な不思議な文学者である。いちばん読まれているのは「耳なし芳一」「雪女」「むじな」等に代表される怪談・奇談であろう。
水木しげるさんの劇画や宮崎アニメの世界では、妖怪たちは現代風にアレンジされて復活し、縦横に活躍をする人気キャラクターに育っている。
ギリシア生まれ。父はプロテスタントアングロ・アイリッシュ、母は富裕なギリシア人の娘であった。年譜を見ると、両親が離婚し、大叔母に引取られたが、その大叔母が破産。また16歳で左目失明。
19歳で移民船でアメリカへ渡り、黒人女性と結婚し、離婚したいきさつがある。米国で新聞記者として働いているとき、服部一三の知遇を得て、その紹介で島根県松江市の尋常師範学校(現松江大学)の英語教師として来日したことにより、日本との関係が生じた。
来日してすぐ、士族小泉湊の娘節子(セツ)と結婚。日本に帰化し、やがて小泉八雲と名のることになる。来日したのは1890年であるから、日本での活動期間は14年間ということになる(詳しくは→ウィキペディアを参照)。
熊本第五高等中学で教諭、東京帝大で英語講師もやっていて、いずれも夏目漱石の前任者であったことは有名。
なんとなく「マイナーな文人」との印象を持っていたが、1930年代に第一書房から全18冊、また1980年代には恒文社から全15冊の全集が刊行されている。
現在手にはいりやすい本としては、新潮文庫「小泉八雲集」岩波文庫「心」はじめ、講談社学術文庫として、平川祐弘編で「光は東方より」「神々の国の首都」「明治日本の面影」など5冊がある。
未知であった日本にやってきて、アカデミックな教育をあまり受けていない八雲がわずか14年で、これだけの業績を残したのは、節子夫人の尽力があったにしても、そのすぐれた資質を思いみるべきであろう。
民話や伝承に通じていたばかりでなく、日本や中国の中世、近世の文学にも驚くべき該博な知識を持っていたのである。そういったある意味で古色蒼然たる世界が、八雲というプリズムを通過すると、別種な美しい光をおびて、きらきらと輝きはじめるのは手品を見ているようである。
この書評を書くにあたって、ウェブで小泉八雲を検索し、その略年譜もはじめて読んだが、前半生は波乱にとんだ、困難な人生だったことが想像される。
八雲を考えるにあたって、看過しえないのは、世界有数の「漂泊の民」として知られるギリシア人の血が流れていたこと、若年で眼に傷害を負っていたことのふたつである。
漂泊の民としてあくなき好奇心の源泉をもっていたが、眼の傷害は、彼に神秘家としての側面を付与するにいたったのではないかと、推測するからである。
さて、書きたいのは「虫の音楽家」についてである。ここで八雲はこれまでわたしが知らなかった想像力の持ち主としてあらわれている。
本書冒頭におかれた、すばらしく繊細な「霜の幻想」の一節を引用してみよう。
<時に十二月の太陽は、こうした霜の炎の輝きをことさらにきらめかせ、燃え盛る太陽の鋭い光線が、水晶の鎧のつづれ織りに当たって砕けては、無数の火花をまき散らし、ハチドリの胸の柔毛のあたりに輝く、妖精のようなほのかな虹色で、一面にきらめく霜の模様を彩るのであった。>
写真の世界に「マクロ撮影」というジャンルがあるのは、現代では大抵の人が知っているだろう。マクロレンズは、顕微鏡のような拡大はむりだが、小さな被写体をのぞき込むようにして撮影できる便利なアイテムで、八雲の眼は、まさにマクロの眼と化して、その美しさをことばに置き換えている。
「冬ざれ」の景色は、日本画の先人たちが愛してやまなかった画材のひとつだが、イメージ豊かにそれをことばで表現した人はいなかった。
「露のひとしずく」「夢を食うもの」「草雲雀」など、どれも散文詩の傑作である。「微細なもの」に向かい合う八雲の眼は、詠嘆に流れることなく研ぎ澄まされ、観察の精度を深めていく。
われわれの近代文学は、徳富蘆花の「自然と人生」や国木田独歩の「武蔵野」などのすぐれた随想を持っている。
「自然との対話」の記録としていずれも傑出した業績だが、八雲の文学は、英語で書かれているため、よき訳者を得ると、見違えるような現代文として蘇ってくるのだ。
本書は三章にわかれ、第一章はより幻想性の色濃い「夢を食うもの」第二章は昆虫をめぐるエッセイ「生きものたちのコスモロジー」、第三章は海を主要なモチーフとしてあつかった「海の文学」の三部構成になっていて、それら全21編と、ご子息小泉一雄さんの「父八雲を憶う」の抜粋が収録されている。
編訳の池田さんによると、晩年に書かれたものばかりだという。
わたしがいちばん楽しみにしていたのは、第二章の「生きものたちのコスモロジー」であった。蝶、蚊、蟻、蛍、蛙などについて、その該博な知識を披露し、こまやかな観察を交えながら書いている。
どれもユニークで、きらきら輝く散文詩だったり、漂泊者の呟きだったり、伝統文化におさまりきらないあたらしい「美」の発見だったりする。
タイトルになった「虫の音楽家」は圧巻で、スズムシ、松虫、邯鄲、金雲雀、クツワムシ、キリギリス、馬追など、日本人がある地域で古来から愛玩してきた「秋の音楽家」について、八雲先生のいわば「思いのたけ」が縷々とつづられ、読み応え十分。
わたし自身、春から夏、秋の終わりにかけて、カメラを手にしてチョウを追いかける趣味をもっている。
「俳句に詠われた蝶」を調べてみたいと思ったことがあるので、八雲の「蝶」を読んだときには、わが意を得たりと膝をたたいた。
そこにはつぎのような俳句が集められている。
・脱ぎかくる羽織すがたの胡蝶かな ・・・乙州
・起きよ起きよわが友にせん寝(ぬ)る胡蝶 ・・・芭蕉
・落花枝にかへると見れば胡蝶かな ・・・守武
・蝶々や女の足の後や先 ・・・素園
・追われても急がぬふりの胡蝶かな ・・・我楽
・蝶とぶやこの世に望(のぞみ)ないように ・・・一茶
・睦まじや生まれかわらば野辺の蝶 ・・・一茶
キアゲハ、モンシロチョウ、ヤマトシジミ、トラフシジミ、ミドリヒョウモンなどと現代のわれわれは分類学的に整備された「昆虫図鑑」的な眼でチョウを眺めている。
近世の俳人にどの程度チョウの区別がついたのか心もとないが、それはまあ、いいとしよう。
「生活のなかにいる昆虫」に、俳人たちは胸の思いを託したのだ。
八雲のような外国人にこういった伝統文化が、深く、美しく根をはったのは、まったくのところ希有な出来事といわねばならない。
八雲というプリズムを通過して、そういった光景は鮮度をまし、あたらしく色揚げされた。
「読書の快楽」とは、わたしにいわせれば、こういう本にひそんでいるのである。
ラフカディオ・ハーン(1850~1904年)
小泉八雲コレクション「虫の音楽家」池田雅之編訳 ちくま文庫>☆☆☆☆★
水木しげるさんの劇画や宮崎アニメの世界では、妖怪たちは現代風にアレンジされて復活し、縦横に活躍をする人気キャラクターに育っている。
ギリシア生まれ。父はプロテスタントアングロ・アイリッシュ、母は富裕なギリシア人の娘であった。年譜を見ると、両親が離婚し、大叔母に引取られたが、その大叔母が破産。また16歳で左目失明。
19歳で移民船でアメリカへ渡り、黒人女性と結婚し、離婚したいきさつがある。米国で新聞記者として働いているとき、服部一三の知遇を得て、その紹介で島根県松江市の尋常師範学校(現松江大学)の英語教師として来日したことにより、日本との関係が生じた。
来日してすぐ、士族小泉湊の娘節子(セツ)と結婚。日本に帰化し、やがて小泉八雲と名のることになる。来日したのは1890年であるから、日本での活動期間は14年間ということになる(詳しくは→ウィキペディアを参照)。
熊本第五高等中学で教諭、東京帝大で英語講師もやっていて、いずれも夏目漱石の前任者であったことは有名。
なんとなく「マイナーな文人」との印象を持っていたが、1930年代に第一書房から全18冊、また1980年代には恒文社から全15冊の全集が刊行されている。
現在手にはいりやすい本としては、新潮文庫「小泉八雲集」岩波文庫「心」はじめ、講談社学術文庫として、平川祐弘編で「光は東方より」「神々の国の首都」「明治日本の面影」など5冊がある。
未知であった日本にやってきて、アカデミックな教育をあまり受けていない八雲がわずか14年で、これだけの業績を残したのは、節子夫人の尽力があったにしても、そのすぐれた資質を思いみるべきであろう。
民話や伝承に通じていたばかりでなく、日本や中国の中世、近世の文学にも驚くべき該博な知識を持っていたのである。そういったある意味で古色蒼然たる世界が、八雲というプリズムを通過すると、別種な美しい光をおびて、きらきらと輝きはじめるのは手品を見ているようである。
この書評を書くにあたって、ウェブで小泉八雲を検索し、その略年譜もはじめて読んだが、前半生は波乱にとんだ、困難な人生だったことが想像される。
八雲を考えるにあたって、看過しえないのは、世界有数の「漂泊の民」として知られるギリシア人の血が流れていたこと、若年で眼に傷害を負っていたことのふたつである。
漂泊の民としてあくなき好奇心の源泉をもっていたが、眼の傷害は、彼に神秘家としての側面を付与するにいたったのではないかと、推測するからである。
さて、書きたいのは「虫の音楽家」についてである。ここで八雲はこれまでわたしが知らなかった想像力の持ち主としてあらわれている。
本書冒頭におかれた、すばらしく繊細な「霜の幻想」の一節を引用してみよう。
<時に十二月の太陽は、こうした霜の炎の輝きをことさらにきらめかせ、燃え盛る太陽の鋭い光線が、水晶の鎧のつづれ織りに当たって砕けては、無数の火花をまき散らし、ハチドリの胸の柔毛のあたりに輝く、妖精のようなほのかな虹色で、一面にきらめく霜の模様を彩るのであった。>
写真の世界に「マクロ撮影」というジャンルがあるのは、現代では大抵の人が知っているだろう。マクロレンズは、顕微鏡のような拡大はむりだが、小さな被写体をのぞき込むようにして撮影できる便利なアイテムで、八雲の眼は、まさにマクロの眼と化して、その美しさをことばに置き換えている。
「冬ざれ」の景色は、日本画の先人たちが愛してやまなかった画材のひとつだが、イメージ豊かにそれをことばで表現した人はいなかった。
「露のひとしずく」「夢を食うもの」「草雲雀」など、どれも散文詩の傑作である。「微細なもの」に向かい合う八雲の眼は、詠嘆に流れることなく研ぎ澄まされ、観察の精度を深めていく。
われわれの近代文学は、徳富蘆花の「自然と人生」や国木田独歩の「武蔵野」などのすぐれた随想を持っている。
「自然との対話」の記録としていずれも傑出した業績だが、八雲の文学は、英語で書かれているため、よき訳者を得ると、見違えるような現代文として蘇ってくるのだ。
本書は三章にわかれ、第一章はより幻想性の色濃い「夢を食うもの」第二章は昆虫をめぐるエッセイ「生きものたちのコスモロジー」、第三章は海を主要なモチーフとしてあつかった「海の文学」の三部構成になっていて、それら全21編と、ご子息小泉一雄さんの「父八雲を憶う」の抜粋が収録されている。
編訳の池田さんによると、晩年に書かれたものばかりだという。
わたしがいちばん楽しみにしていたのは、第二章の「生きものたちのコスモロジー」であった。蝶、蚊、蟻、蛍、蛙などについて、その該博な知識を披露し、こまやかな観察を交えながら書いている。
どれもユニークで、きらきら輝く散文詩だったり、漂泊者の呟きだったり、伝統文化におさまりきらないあたらしい「美」の発見だったりする。
タイトルになった「虫の音楽家」は圧巻で、スズムシ、松虫、邯鄲、金雲雀、クツワムシ、キリギリス、馬追など、日本人がある地域で古来から愛玩してきた「秋の音楽家」について、八雲先生のいわば「思いのたけ」が縷々とつづられ、読み応え十分。
わたし自身、春から夏、秋の終わりにかけて、カメラを手にしてチョウを追いかける趣味をもっている。
「俳句に詠われた蝶」を調べてみたいと思ったことがあるので、八雲の「蝶」を読んだときには、わが意を得たりと膝をたたいた。
そこにはつぎのような俳句が集められている。
・脱ぎかくる羽織すがたの胡蝶かな ・・・乙州
・起きよ起きよわが友にせん寝(ぬ)る胡蝶 ・・・芭蕉
・落花枝にかへると見れば胡蝶かな ・・・守武
・蝶々や女の足の後や先 ・・・素園
・追われても急がぬふりの胡蝶かな ・・・我楽
・蝶とぶやこの世に望(のぞみ)ないように ・・・一茶
・睦まじや生まれかわらば野辺の蝶 ・・・一茶
キアゲハ、モンシロチョウ、ヤマトシジミ、トラフシジミ、ミドリヒョウモンなどと現代のわれわれは分類学的に整備された「昆虫図鑑」的な眼でチョウを眺めている。
近世の俳人にどの程度チョウの区別がついたのか心もとないが、それはまあ、いいとしよう。
「生活のなかにいる昆虫」に、俳人たちは胸の思いを託したのだ。
八雲のような外国人にこういった伝統文化が、深く、美しく根をはったのは、まったくのところ希有な出来事といわねばならない。
八雲というプリズムを通過して、そういった光景は鮮度をまし、あたらしく色揚げされた。
「読書の快楽」とは、わたしにいわせれば、こういう本にひそんでいるのである。
ラフカディオ・ハーン(1850~1904年)
小泉八雲コレクション「虫の音楽家」池田雅之編訳 ちくま文庫>☆☆☆☆★