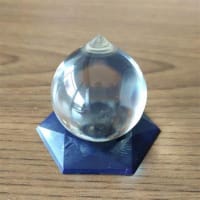人の俳句からいろいろな刺激をいただいている。
本日の讀賣俳壇の小澤實選、第3席、
絵は我にあらず踏めよと神の声 徳永松雄(八王子市)
この句に目をみはった。
まず季語の「踏絵」を分解して全体に散らして季語性を出したこと。そして内容の濃さにである。
小澤さんは、
「踏絵を踏むキリスト教徒の内面を描いた。絵は自分ではない、踏みなさいと神の声が響いている。江戸時代、踏絵は春先に行われた。」
との評を寄せている。
若いころキリスト教にいたくひかれて関係書を乱読したことがある。小説では遠藤周作の『沈黙』を何度も読んだ。また四十代、五十代はヨーロッパへ旅しては教会などいくつも訪ねた。バチカンなどローマカトリック教会に限らず、東欧・ロシアのギリシャ正教系の教会やイコンなども相当数見て歩いたりし、また本も読んだ。
イコンは神を形にしたものであり踏絵に通じる邪の道かもしれぬが、総じてあちらのキリスト教者は踏絵を日本人キリスト教者ほど問題にするのであろうか、という疑惑を強く持ったのである。
踏めばいいじゃないか、たんなる絵なんだもの。
『沈黙』を読んでいてそのへんに疑問を持ち出すとだんだん全体が滑稽に思えてきた。
遠藤さんは日本は外国の文化をまるで別な物に変える泥沼のようなものだという。
また山本七平は日本人は全員日本教徒であり向こうの文化を向こうのありようで理解していない、と説く。日本人でほんとうの意味のキリスト教を理解できている率は低いのではないかという指摘である。
徳永さんの句は、日本のキリスト教者の根っこを問うような切れ味がありユニークな踏絵の句である。これほど内容がおもしろいと、「踏絵」を分解し季語を全体に散らしたことも許せるのである。
=================================
一方、4月3日付の讀賣俳壇の正木ゆう子選の第3席、
おひなさまというねむいという夕日 松本みゆき(館林市)
一読してよく3席にしたな、自分なら採らないな、と思った。すぐに正木さんの評を読んだ。
【評】敢えて俳句的な表現を外し、独特のニュアンスを出した句。幼い女の子の言葉を書き留めたのかも。時にはこんな冒険も応援したい。
正木さんの指摘するように「冒険句」である。
ひこばえ句会のNさんが「センセイは正木ゆう子選に納得しませんよね」と穿ったことをいう。ぼくの俳句の嗜好を知っているのである。
たしかに、ぼくは、石田波郷の「霜柱俳句は切字響きけり」という美しい立ち姿の句を目指している。
それは動かせないのであるが、冒険はしないといけないと常に思っている。ぼくは正木さんから選句も冒険することが大事だとのメッセージを受け取っていて冒険する選句は自分の句会で生かそうとしている。
冒険をして自分が今まで使わなかった抽斗を引き出さないと美意識はすぐ轍にはまってしまい、予定調和の句を量産することになる。
正木さんは選を冒険している。
するとそれに応じて作る方も冒険をする。冒険は失敗も非常に多いが新たな地平を切り開く。選句により人を揺さぶる、揺さぶられるということが精神の活性化に通じる。
正木さんは従来の俳句にかなり飽きているのでありそれは理解できる。
しかし並選では、穏当な調和的な内容の句も採ってバランスを取っている。
Nさんが正木ゆう子特選句に異論を持ってぼくに話題を持ってくるということが俳句の発展になるのである。
複数の選者がいろいろな選をする。その結果、山にいろんな木が生息するように俳句がある。入選した、落選した、ということを超えて俳句は楽しいのである。