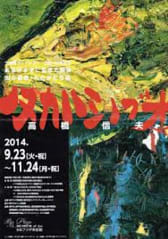歴史社会学者の小熊英二さんが『世界』で父親の半生を聞き取っている(「生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後」2014年10月~)。小熊健二さんは1925年生まれ。1944年19歳で召集、中国大陸に送られ、現地で敗戦。ソ連軍によりシベリアに抑留され4年間強制労働に従事させられる。多くの仲間が死に絶える中で「生きて帰ってきた」。筆舌に尽くしがたい世界を生き抜いてきた人の証言は、人間が二度とそのような世界を生み出してはならないとの教訓でとても大事である。ホロコーストからの生還者、日本軍慰安婦、そしてカンプチアでポル・ポト時代を生き抜いた人たち。
「消えた画」監督のリティ・パニュは実際13歳のときポル・ポト派の政策によって親兄弟とともに過酷な集団生活を強いられた。親とも兄弟とも引き離され、ただ「番号」によって呼ばれ、意味のない開墾作業に従事する日々。極度の飢えと容赦ない「粛清」で親も兄弟も失う。しかし彼は生き抜いた。小熊健二さんのように。そして難民キャンプを経てフランスに渡り、映画監督して大成する。パニュ監督が描くのはポル・ポト派の時代ばかり。
日本の商業ベースで公開された作品は多くはないが、それでも何本かドキュメンタリー作品が知られているらしい。今回「消えた画 クメール・ルージュの真実」が広く公開されたことによって、言わば名作「キリングフィールド」のトラウマが溶解されるのではないかと感じた。一つひとつ説明したい。
まず「キリングフィールド」が名作であるかどうか。映画上映後、国連広報官としてカンプチア国際法廷に関わっていた前田慶子さんのお話を伺う機会を得た。前田さんの話では「キリングフィールドはポル・ポト派時代を知るためのバイブル的映画」だという。たとえばプノンペンのいたるところで上映されているとも。「キリングフィールド」が街のいたるところで上映されているというのも驚くが、85年当時はポル・ポト派(ひいては中国共産党)に対する悪辣なプロパガンダだと指弾された「キリングフィールド」は今やその時代を知る有用なアイテムとなっているのだ。前田さんは言う。「キリングフィールド」の記者は、国連の法廷設置委員会でも証言したと。
トラウマとは言うまでもない。「キリングフィールド」の評価と同時に、あのような時代を生きた人たちが実際にそれを語るのかできるのかということ。日本軍の従軍慰安婦であった金学順さんが1991年にはじめて自身の告白したことによって、「慰安婦問題」は日の目を見ることになったが、当然、金さんをはじめ「従軍慰安婦」経験のある人たちには語りがたいトラウマがあるし、「慰安婦」を「買った」日本兵の中にもそれもある人もあるだろう。
「溶解」は難しい。本作で、あるいはこれまでの作品でパニュ監督が描きたかったのは何か、映画の力で何を目指そうとしたのか。ポル・ポト派の下級兵士は都会から強制移住させられた農村の普通の人々であった。だから、ポル・ポト派が敗走、瓦解したあともその地に住まい、迫害された都会の「新人民」と近くで暮らした人たちだ。「新人民」と「(旧)人民」との間に和解はあるのか、そう、両者の間に心の溶解はあるのか。
実は、パニュ監督が描くのはトラウマであるし、溶解であるし、「キリングフィールド」の再解釈でもあるし、そうではない。あの時代に実際生きた者の実相、それだけだ。おぞましいことにはちがいない。体験は過酷を極めたが、やさしい―あえて言う―泥人形で表現することによって、むしろ、過酷さへのイマジネーションが広がる。生き永らえたのが不思議、奇跡の体験。肉体も、精神も。
パニュ監督も「生きて帰ってきた」。その映画に託された証言は、二度とあのような時代を到来させないための「語り(部)」なのだ。
先ごろ世界中で現在でも奴隷的拘束下にある人の割合がNGOによって発表された。最大数はインドであったそうだが、日本も0ではなかった。その意思に反して労働を強いられ、人間的思惟を許されない環境。残念ながら、「豊かな」日本でも「明日」のない「生きる」だけのために働き続ける被用者層が存在し、それらの層を生み出す構造はシベリア抑留やポル・ポト派のそれに無縁ではないように見える。
「消えた画」は決して「消した画」であってはならないのである。
「消えた画」監督のリティ・パニュは実際13歳のときポル・ポト派の政策によって親兄弟とともに過酷な集団生活を強いられた。親とも兄弟とも引き離され、ただ「番号」によって呼ばれ、意味のない開墾作業に従事する日々。極度の飢えと容赦ない「粛清」で親も兄弟も失う。しかし彼は生き抜いた。小熊健二さんのように。そして難民キャンプを経てフランスに渡り、映画監督して大成する。パニュ監督が描くのはポル・ポト派の時代ばかり。
日本の商業ベースで公開された作品は多くはないが、それでも何本かドキュメンタリー作品が知られているらしい。今回「消えた画 クメール・ルージュの真実」が広く公開されたことによって、言わば名作「キリングフィールド」のトラウマが溶解されるのではないかと感じた。一つひとつ説明したい。
まず「キリングフィールド」が名作であるかどうか。映画上映後、国連広報官としてカンプチア国際法廷に関わっていた前田慶子さんのお話を伺う機会を得た。前田さんの話では「キリングフィールドはポル・ポト派時代を知るためのバイブル的映画」だという。たとえばプノンペンのいたるところで上映されているとも。「キリングフィールド」が街のいたるところで上映されているというのも驚くが、85年当時はポル・ポト派(ひいては中国共産党)に対する悪辣なプロパガンダだと指弾された「キリングフィールド」は今やその時代を知る有用なアイテムとなっているのだ。前田さんは言う。「キリングフィールド」の記者は、国連の法廷設置委員会でも証言したと。
トラウマとは言うまでもない。「キリングフィールド」の評価と同時に、あのような時代を生きた人たちが実際にそれを語るのかできるのかということ。日本軍の従軍慰安婦であった金学順さんが1991年にはじめて自身の告白したことによって、「慰安婦問題」は日の目を見ることになったが、当然、金さんをはじめ「従軍慰安婦」経験のある人たちには語りがたいトラウマがあるし、「慰安婦」を「買った」日本兵の中にもそれもある人もあるだろう。
「溶解」は難しい。本作で、あるいはこれまでの作品でパニュ監督が描きたかったのは何か、映画の力で何を目指そうとしたのか。ポル・ポト派の下級兵士は都会から強制移住させられた農村の普通の人々であった。だから、ポル・ポト派が敗走、瓦解したあともその地に住まい、迫害された都会の「新人民」と近くで暮らした人たちだ。「新人民」と「(旧)人民」との間に和解はあるのか、そう、両者の間に心の溶解はあるのか。
実は、パニュ監督が描くのはトラウマであるし、溶解であるし、「キリングフィールド」の再解釈でもあるし、そうではない。あの時代に実際生きた者の実相、それだけだ。おぞましいことにはちがいない。体験は過酷を極めたが、やさしい―あえて言う―泥人形で表現することによって、むしろ、過酷さへのイマジネーションが広がる。生き永らえたのが不思議、奇跡の体験。肉体も、精神も。
パニュ監督も「生きて帰ってきた」。その映画に託された証言は、二度とあのような時代を到来させないための「語り(部)」なのだ。
先ごろ世界中で現在でも奴隷的拘束下にある人の割合がNGOによって発表された。最大数はインドであったそうだが、日本も0ではなかった。その意思に反して労働を強いられ、人間的思惟を許されない環境。残念ながら、「豊かな」日本でも「明日」のない「生きる」だけのために働き続ける被用者層が存在し、それらの層を生み出す構造はシベリア抑留やポル・ポト派のそれに無縁ではないように見える。
「消えた画」は決して「消した画」であってはならないのである。