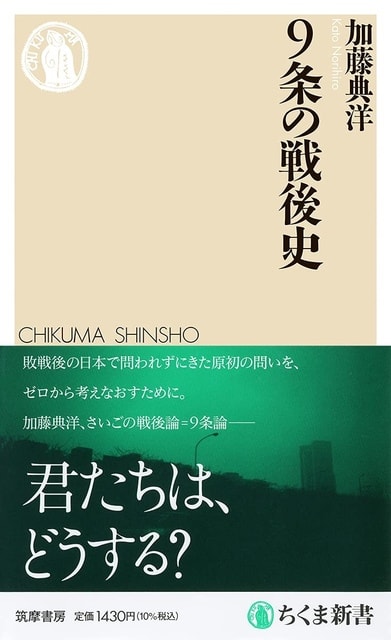井上ひさしさんが、「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」と語っていたことを思い出した。
日本国憲法改正という議論は、憲法9条を変えるか変えないかという議論のことだ。そこには日本が自前の軍隊を持つことの是非はもちろん、自前の軍隊を持って他国を侵略した大日本帝国憲法をどう評価するかや、9条の出自がそもそもアメリカ由来であることをどう捉えるか、さらにはすでに自衛隊という大きな軍隊を持つ実態との乖離をどう考えるかと議論は多岐にわたる。そしてそれはすなわち戦後日本の歴史そのものである。
2019年若くして惜しまれながら亡くなった加藤典洋は、これらの難題を整理づけ、課題を提示する。そのためには新書版とはいえ500頁を超える大部が必要であった。そして、その整理づけのためには、9条、いや護憲派のうち少なからずの中には、筆者もそうであるが、丸山眞男といった戦後リベラルを象徴する知識人の言説、意見を言わば丸呑み、時に金科玉条のごとく盲信する姿勢をも突き崩さざるを得なかった。それは9条が抱えてきた時代背景を基礎とするその役割と、その扱い方を政治的立場も踏まえて歴史的に整理することにつながる。一方、9条をタテにアメリカからの軍事増強や更なる中国やソ連に対する政策の変更を拒み続けてきた自民党ハト派は、引き換えに日米安保体制の拡大を引き受ける。また、自主憲法制定を目指す自民党タカ派は、安保体制は自前の立派な軍隊を持つまでの一時的な仕組みと捉える。今日から考えると奇妙なねじれにも見えるが、結局55年体制とは、護憲勢力が必ず3分の1以上国会を占める奇妙な安定体制でもあったのだ。しかし、それが護憲側の「安穏」を助け、自民党内でも経済重視のハト派的流れから、憲法9条をどうするのか、といった根本的課題にも「向き合わずに」済んだというのだ。
護憲派の「教条主義的」姿勢に疑問を呈しつつ、護憲の立場から9条の活かし方を提言し続けたためにリベラル派から批判を受けてきた加藤も、安倍政権の誕生によって政権と9条の関係が根本的、劇的に変わったとする。それは天皇を元首とするなど明治憲法の復活と見紛う憲法草案の発表と、そうであるのになりふり構わぬ対米盲従の両立というあり得ない選択を示したからである。そうであるから、加藤も現行憲法のまま、2015年の集団的自衛権の行使を可能にした安全保障法制や、その理屈づけには反対した。そして、その暴挙をなした安倍晋三はまたもやコロナ禍の中、2020年に政権を投げ出し、安倍のコピー政権である菅政権も確実にそれらを引き継ぎ、そして2021年夏に政権を投げ出した。その跡を継いだのが、ハト派の象徴であったはずの宏池会の岸田文雄政権誕生となったのだが、その岸田も安倍・菅の方向性を何ら正そうとしない。しかし、加藤はこれらの政権与党内の腐敗も知らずに世を去ったのであった。
冒頭に、井上ひさしの言葉を紹介したが、加藤の仕事は、9条という、戦後日本が、有権者たる日本国民の誰もが逃れられない、向き合わざるを得ないアメリカとの関係、国民国家の自立とは何かといったアポリアを「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく」説き起こしたことに他ならない。もうすぐ任期満了が僅かであるのに岸田政権がわざと解散した上での衆議院選挙がある。日本の有権者の半数はまた棄権するのだろうか。加藤の一番の危惧はそこではなかったか、との思いも拭えない。(2021年 ちくま新書)