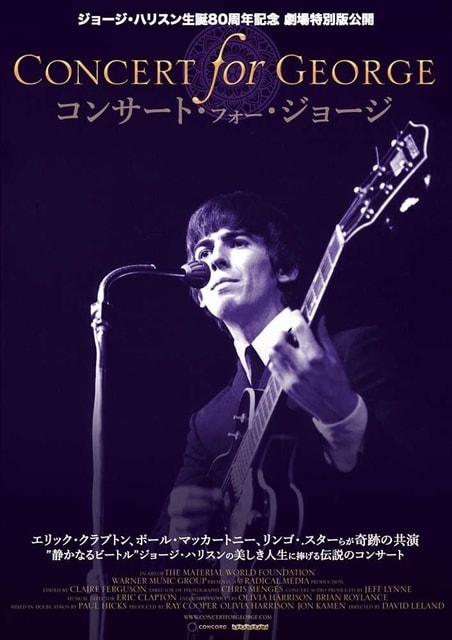「シモーヌ フランスに最も愛された政治家」は欧州議会議長に女性として初めて選出されたシモーヌ・ヴェイユの生涯を綴る物語だが、その大きく占める枢要部分はアウシュヴィッツなど強制収容所の体験談である。そして「アウシュヴィッツの生還者」は、主人公の戦後の人生に強制収容所での体験がフラッシュバックする描き方だ。
かくも映画ではホロコーストが幾度も描かれてきたし、たくさん観てきた。なぜ、幾度も描かれるのだろう。そして何度も観てしまうのだろう。人類史上最悪とも言うべき大量殺戮を可能にした経緯と、そこに至る差別や優生思想の発露など歴史の汚点を最大限追体験できるからだろうか。その戒めによって、もうあのような歴史を繰り返してはならないというヒューマニズムの発露なのだろうか。そう言う面ももちろんあるが、自分自身を振り返るともう少し別の意味もあるように思う。
1944年、16歳で捕えられたシモーヌは母、姉ミルーとともにアウシュヴィッツに送られる。しかし、ソ連の進軍でナチス・ドイツが敗退を重ねていた時期、別の収容所への死の行進。次々と斃れゆく中でも親子三人は生き流れえるが母はついに事切れる。解放後、男性社会を懸命に生きたシモーヌはやがて法務官として刑務所改革に取り組み、国会議員として中絶合法化を成立させる。そんなシモーヌがアウシュヴィッツを訪れ、その頃の経験を詳しく語り出したのは2004年。78歳。その時点ではまだ政界を引退していなかった。
一方、「アウシュヴィッツの生還者」では、ボクサーのハリー・ハフトの現実に強制収容所での体験が挟み込まれ、彼はその記憶に苛まされている。ポーランド系ユダヤ人のハフトは「生還者」として英雄視されるが、なぜ生還できたのか。それは彼がナチスの軍高官の余興で開かれた収容所でのボクシング・マッチに勝ち続けたからだった。敗れたユダヤ人はその場で殺された。そのような過去を明らかにしたのは収容所送りで生き別れた恋人レアに自分の無事を伝えたいからだった。しかし、名を売るために挑戦したとんでもなく格上の相手にコテンパンにされて、レアを探すのを諦め引退を決める。しかし、戦時トラウマは拭いきれなかった。
シモーヌに加害体験はないが、目の前で母を助けられなかったサバイバーズ・ギルトの思いはあるだろう。ましてや、ハフトは多くの同胞を死なせ、また彼を支えた妻にも打ち明けられなかった収容所での壮絶な体験は、解放後彼を苛むに十分だ。ボクシングしか教えることのないハフトは、肉体戦には向かなそうな息子にトレーニングを強要し、息子もまた父親と距離があり疎ましいようだ。けれど、レアと再会できたハフトはやっと息子アランに全てを打ち明ける。アランが書いた父親の体験談が映画となった。だから「アウシュヴィッツの生還者」は全くの創作ではない。ホロコーストは描ききれていない。いや、描くには個々の物語がありすぎるのだ。
現在、自身を顧みてもホロコーストのような生か死かといった究極の選択を迫られる状況にはもちろんなかった。けれど、個々の関係で他者への思慮を欠いた言動は、ときにその時の思惑以上に他者を蔑んだり、傷つけたりしたことがあるはずだ。だから、それを思い出すことで苦しくなる。ましてやホロコーストだ。
戦時のPTSDは、やっとアメリカのイラク戦争帰還兵で明らかになり、ベトナム戦争時のそれも後追いで明らかになりつつある。
人を傷つける、あるいは、傷つけてしまったという悔悟を大事にしたいと思う。
(「シモーヌ フランスに最も愛された政治家」は2022、フランス。「アウシュヴィッツの生還者」は、2021年、カナダ・アメリカ・ハンガリー作品)