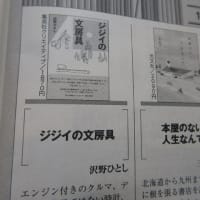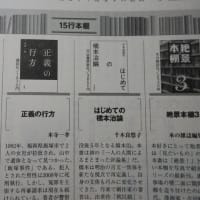「週刊新潮」の書評ページのために書いてきた文章で振り返る、この1年に読んだ本たちです。
2012年 こんな本を読んできた(10月編)
モーリス・ルブラン:著 平岡敦:訳『ルパン、最後の恋』
早川書房 1365円
モーリス・ルブランが70年前に書いた「アルセーヌ・ルパン」の物語を“新作”として読める。それだけで十分事件ではないだろうか。ルブランが亡くなったのは1941年、真珠湾攻撃の年だ。以来、遺族のもとで封印されてきた幻の遺稿が、今年になってフランス本国で出版された。その日本語版が本書である。
舞台は1920年代のパリ郊外。ルパンの“最後の恋”の相手は、自殺したレヌエ大公の娘・コラだ。次の英国王候補オックスフォード公の婚約者である彼女は、後見人とも言える4人の男たちに囲まれて暮らしている。実はその中の一人、サヴリー大尉こそ正体を隠したルパンであり、その胸の内にはコラへの恋心が秘められていた。
やがてルパンに危機が迫る。原因は一冊の古い本だった。その時、彼を助けて大活躍するのが、日ごろ勉強を教えている貧しい子供たちだ。その関係はどこか明智小五郎と少年探偵団を思わせる。マリ・アントワネットの血を引く美女。3人の殺し屋。暗躍する謎の組織。緊張の中にユーモアを織り交ぜつつ、物語はクライマックスへと向かう。
巻末に置かれた、単行本初収録となるルパン・シリーズ第1作も貴重だ。
(2012.08.20発行)
柳 美里『沈黙より軽い言葉を発するなかれ~柳美里対談集』
創出版 1470円
「話すことは、聴くことから始まる」と言う著者の、本書は初の対談集である。登場するのは映画監督・岩井俊二、漫画家・山本直樹、詩人・和合亮一、女優・寺島しのぶなど8人。いずれも著者が「本当に逢いたいひと」であり、規範や基準から外れている、もしくはそれに疑義を呈している表現者たちだ。
自らエロマンガと呼ぶ性を描く作品の一方で、連合赤軍事件を素材にした長編漫画『レッド』を描き続けている山本。「僕は小さい物語しか描けないし、描きたくない」というスタンスだからこそ、連合赤軍を「好きになったとか、嫌いになったとか、何を食ったとか、そういう目線」で語ることができるのだ。
映画に関して、「最初から人には習わないと決めていました」と岩井。高校時代から教育を拒否し、すべて独学でやると決めた少年は今、誰とも似ていない独自の美学に満ちた映像作品を撮っている。
寺島は歌舞伎の家に生まれた女の子という境遇の特異性を淡々と語る。父(七代目尾上菊五郎)との関係を「今でもすごく息苦しい」と告白する娘が、スクリーンの中では男たちと激しく渡り合ってきた。仕事の上では自分に妥協を許さない姿勢が著者と重なってくる。
(2012.08.30発行)
小玉 武 『佐治敬三~夢、大きく膨らませてみなはれ』
ミネルヴァ書房 2940円
「『洋酒天国』とその時代」で開高健や山口瞳を擁した寿屋(現・サントリー)宣伝部とその時代を活写した著者。本書は彼らを生かし切った二代目社長、佐治敬三の生涯を追った人物評伝の力作である。ひたすら「個」を開くことに専心した男の80年を知る。
(2012.08.30発行)
白川浩司 「遥かなる『文藝春秋』」
小学館 1890円
前著「オンリー・イエスタデイ1989」は、著者の「諸君!」編集長時代を回想したものだ。本書では、同じく編集長を務めた「文藝春秋」を通じて向き合った人間と社会を語っている。特に興味深いのは細川政権誕生の舞台裏。それは現在の政治状況に繋がるからだ。
(2012.09.05発行)
新津 きよみ 『彼女の時効』
光文社 1470円
殺人の時効は廃止されたが、死亡事故を起こしたひき逃げ犯は5年で時効だ。その理不尽さが遺族を苦しめ続ける。夫を奪われた久子が事故現場で出会った奇妙な女性もまた犠牲者だった。2人は助け合いながら、互いの運命を変えた事故の真相を究明していく。
(2012.09.20発行)
石持浅海 『扇動者』
実業之日本社 1470円
テロ、もしくはテロリストと聞けば、多くの人は暴力という言葉を想起する。しかし、本書に登場するテロ組織は一風変わっている。何しろ血を流すことなく、国民の政府への不信感をあおることで政権交代を成し遂げようというのだから。
舞台は軽井沢に置かれた施設だ。宿泊と作業が可能な閉じられた空間である。集まったのは7人男女。コードネーム「春日」をはじめ、全員が普段は一般市民として生活しながら、裏で反政府活動に参加している。週末になると集合して作業を行うが、互いの本名や素性は知らないままだった。
このグループの役割は兵器開発。今回のミッションは「子供という切り口で政府を揺さぶる」兵器を作り出すことだ。白熱した議論が行われ、一旦休憩した後で夕食をとる。だが、女性メンバーの「千歳」だけが食堂に現れない。探してみると、彼女は部屋で殺害されていた。
施設は一種の密室。外部からの侵入者もいない。犯人は内部にいる可能性が高い。誰が、なぜ、どうやって実行したのか。しかも兵器の製作は中止することができない。そのリミットも迫る。本格推理の密室殺人とテロリズムという意外な組み合わせから生まれた、異色ミステリーである。
(2012.09.20発行)
佐々木美智子・岩本茂之 『新宿、わたしの解放区』
寿郎社 2625円
破天荒な女性がいたものだ。北海道の根室に生まれ、高校を卒業して就職し、結婚。離婚してキャバレーに勤め、札幌ススキノ経由で上京。新宿でおでんの屋台を引き、日活撮影所で映画の編集者となる。次いで写真を学んだかと思うと新宿ゴールデン街でバーを開く。
時代は騒乱の60年代後半である。羽田空港闘争、三里塚闘争、日大闘争、そして東大安田講堂の攻防戦。著者はカメラを持って、また時には体ひとつで現場に立ち続ける。その最中に出会ったのが日大全共闘議長・秋田明大だ。2人は行動を共にする仲となる。
これだけでも十分に波乱万丈な人生だが、著者の真骨頂はここからだ。単身ブラジルへと渡り、アマゾンでレストラン・バーを開店。現地のマフィアから銃弾を撃ち込まれても怯まず、店を繁盛させる。やがて帰国するが、まるでトランジットの如く東京に滞在しただけで、今度は大島へと移り住むのだ。現在78歳。代々木で行われた反原発集会にも参加している。
ここには誰もが知る映画監督、俳優、作家など多彩な人物たちが登場する。しかもその多くが世を去った。本書が一人の女性の半生記であると同時に、貴重な昭和現代史となっているのはそのためだ。
(2012.09.20発行)
関川夏央 『東と西 横光利一の旅愁』
講談社 2310円
横光利一の小説『旅愁』は、昭和11年に実行した欧州旅行での体験がベースとなっている。本書ではこの作品を軸に、横光の精神の軌跡をたどる。そこにあるのは戦前という時代であり、当時の日本社会であり、欧州文化である。明かされる作家と作品の関係が興味深い。
(2012.09.28発行)
五十嵐恵邦 『敗戦と戦後のあいだで~遅れて帰りし者たち』
筑摩書房 1785円
敗戦により外地に取り残された日本人は686万人だ。やがて続々と引き揚げてきたが、大幅に遅れて帰国を果たした者もいた。たとえば『人間の條件』の五味川純平、横井庄一、小野田寛郎などだ。彼らの戦いと戦後を追うことで見えてくる戦争体験の意味。
(2012.09.15発行)
佐々木玲仁 『結局、どうして面白いのか~「水曜どうでしょう」のしくみ』
フィルムアート社 1785円
北海道のローカル番組でありながら、いつしか全国区の存在となった「水曜どうでしょう」。それはいかに作られ、人気の秘密はどこにあるのか。著者は気鋭の臨床心理学者。作り手たちへのインタビューを手掛かりに、この空前絶後の番組を分析していく。
(2012.09.14発行)
なぎら健壱 『町の忘れもの』
ちくま新書 998円
著者がフォークシンガーであることを知らない世代も増えてきた。テレビの「タモリ倶楽部」で居酒屋巡りをしている口ひげ男は、ただのオジサンではない。下町探索をさせたら日本一という大変な人物なのだ。
本書は新聞に書き溜めた、いわば「懐かしいもの」大全である。共同アパート、コンクリートのごみ箱、リアカー、原っぱ、銭湯の番台、手動式エレベーター、デパートの屋上遊園地などなど。失われたもの、消えゆくものへの愛着と感謝を込めたエッセイに唸り、著者自らレンズを向けた写真にこころ和ませる。
(2012.09.10発行)
本城雅人 『希望の獅子』
講談社 1785円
80年代初頭、横浜に3人の高校生がいた。少しワルの志龍(ジーロン)、運動では誰にも負けない亮仔(リャンジャイ)、そして日本人の母親をもつ将一。中華街を自分たちの庭のように駆け回っていた彼らの友情の証が中国式獅子舞だ。互いの信頼がなければ不可能な技を軽々と決める最強チームだった。ところが、ある日を境に3人の姿が消えてしまう。そして歳月だけが中華街を通り過ぎた。
2012年、横浜で男の死体が発見される。亮仔だった。捜査にあたるのは県警の若手である山下と、加賀町署のベテラン刑事・樋口だ。30年もの間、消息不明だった男の出現。どこでどう暮していたのか。誰になぜ殺されたのか。さらに残りの2人、志龍と将一はどうなったのか。生きた亮仔を最後に目撃したのは、かつての彼らを彷彿とさせる獅子舞の練習に励む高校生だった。30年という時間を隔てて、過去と現在とが交錯していく。
3年前の松本清張賞候補作『ノーバディノウズ』以来、斬新な野球小説で評価を高めてきた著者。書き下ろし長編となる本書は、時間軸だけでなく日本と中国にまたがるスケールの大きな物語だ。裏社会の闇と恋と友情。慟哭の結末が待っている。
(2012.09.27発行)
松岡正剛 『松丸本舗主義~奇蹟の本屋、3年間の挑戦。』
青幻舎 1890円
東京駅北口近くにある丸善丸の内本店。その4階の一角に、“書店内書店”とでも言うべき「松丸本舗」が出現したのは3年前だ。まず驚かされたのは書棚。変形エスカルゴ型、もしくはチェコのプラハ的迷路といった風情で、うねるような書棚が延々と続いていた。
また、並んでいる本たちも、一般的な分類ではなく、あるキーワードやイメージによって集められ、関連づけられていた。それはまるで松岡正剛という“知の司祭”の頭の中か、個人図書館に迷い込んだようなスリルと興奮を与えてくれた。
さらに「本は三冊で読む」という著者の読書コンセプトを具現化すべく、ジャンルやサイズや選者の異なる三冊がバンドでくくられ、売られていた「三冊屋」など、多彩なコーナー企画も刺激的だった。
その「松丸本舗」が幕を閉じた。65坪、各1冊、10万種、289棚、1074日間。本書は多くの人に支持され、惜しまれながら消えていった稀代のリアル書店の記録である。選書の仕方、本棚の在り方と並べ方をはじめ、「歴史や人生の中のつながりとして、本を見る」ことの意味が解き明かされている。書店としては存在しなくても、松丸本舗が深めた「本の持つ極上の愉悦」は今後も消えない。
(2012.10.23発行)
大橋博之 『SF挿絵画家の時代』
本の雑誌社 1890円
こんなアプローチがあったのか、と感嘆すべき一冊。SF小説を読む者の想像力を刺激する挿絵画家たちの列伝である。小松崎茂、真鍋博、金森達、深井国など、名前と共に画風の記憶が甦る71名が並ぶ。原画はもちろん印刷という“公開”の形も大切にした人たちだ。
(2012.09.25発行)
木村伊兵衛ほか 『昭和の記憶~写真家が捉えた東京』 クレヴィス 2520円
名写真家たちが伝える昭和という時代、街、そして人。昭和12年の銀座、千人針の風景は土門拳だ。田沼武能が撮ったのは街頭テレビの前に並ぶ無数の笑顔。昭和30年代のサラリーマンの表情は長野重一である。モダン東京から高度成長に至る34年間のドキュメントだ。
(2012.09.20発行)
逢坂剛・川本三郎
『さらば愛しきサスペンス映画』七つ森書館 2310円
「あらゆる映画や小説はサスペンスである」。巻頭に掲げられた逢坂の名言だ。またDVDや衛星放送も大いに活用すべし、と川本。ストーリー、監督、そして女優の魅力もサスペンス映画の楽しみだ。同世代の2人が語りつくす名作、傑作、異色作の数々に圧倒される。
(2012.10.05発行)
木内 昇『ある男』
文藝春秋 1680円
舞台は明治時代初期。諸藩がそれぞれ“国”だったものが、いきなり中央政府が統括する国家となった。そこに生じる無理や矛盾を背負わされたのは地方の人々だ。直木賞作家が4年ぶりに送り出すこの短編集は、7人の無名の男たちを通して描く歴史の軋みである。
巻頭の「蝉」では、南部の銅山で働く金工(かなこ・鉱山労働者)が東京へと向かう。政府の要職にある井上馨に会うためだった。男たちの生きる場である銅山を、自らの利権のために奪う極悪人。男が命がけの直訴の果てに見たものは。
「実は、紙幣を、造っていただきたいのです」と懇願されるのは、引退を決意した老細工師だ。相手は新政府の転覆を企てる一党。依頼された贋金はその軍資金となるという。男は彼らを指導しながら仕事を進めるが、職人としてどうしても譲れない一線があった(「一両札」)。
他に、中央からやってきた県知事と地元住民との軋轢に翻弄される地役人(「女の面」)。福島県令・三島通庸が押し付ける重い税負担に怒る農民たち。それを抑える男はかつての京都見廻組だった(「道理」)。いずれも時代の変わり目に遭遇した男たちの悲惨にして滑稽、重厚にして軽妙な物語が楽しめる。
(2012.09.30発行)
園 子温(その・しおん)『非道に生きる』
朝日出版社 987円
著者は『冷たい熱帯魚』『ヒミズ』などの作品で知られる映画監督。本書は自らの生い立ちから演出法までを語った“自伝的映画論”ともいうべき一冊である。
著者によれば、映画には2種類ある。一つは観客の政治や社会、人生に対する欲求不満を解消する「満足させる映画」。そしてもう一つが、人を怒らせ苛立たせ、感情を逆なでして緊張感を生み出す「覚醒させる映画」だ。自身はその両方を撮っていきたいと言うが、実際には後者の作品が圧倒的に多い。たとえば『自殺サークル』では、新宿駅のホームで女子高生54人が集団飛び込み自殺をするシーンが観客の度肝を抜いた。
また最近の主流である「製作委員会方式」の映画作りを嫌い、リサーチやマーケティングなどから作品を発想することを禁じ手としている。その結果、最低最悪の映画になっても、自分の欲望を映画に焼きつければよしとする。さらに「これは映画ではない」と非難されようと、その「ではない」部分を極北まで突き詰めるのが面白いと言うのだ。自分の本音で映画を撮る監督が少ない中では異色中の異色。腹が据わっている。
最新作は原発事故に翻弄される家族を描いた『希望の国』。目指しているのは世界標準の映画だ。
(2012.10.05発行)
一橋文哉『となりの闇社会~まさかあの人が「暴力団」?』PHP新書 798円
一読して驚くのは、普通の市民のすぐ近くに暴力団がいるということだ。企業どころか震災や生活保護制度を利用して行政にも食い込んでいる。さらに「手渡し詐欺」という新手で家庭にまで触手を伸ばす。「人間の欲望あるところに闇はある」の言葉がリアルだ。
(2012.10.02発行)
孫崎 享『アメリカに潰された政治家たち』
小学館 798円
『戦後史の正体』で注目された著者の最新刊。日本の主要な政治家たちがいかにしてアメリカを激怒させ、その報復を受けてきたか。登場するのは岸信介、鳩山一郎、田中角栄、小沢一郎など。“対米追随”の総決算ともいうべき現政権までの流れが一目瞭然だ。
(2012.10.02発行)
大野左紀子『アート・ヒステリー』
河出書房新社 1575円
アートのヒストリーではない。「これこそアート」「いや、こっちだ」と叫び合う様相を、元アーティストの著者はヒステリーと呼ぶ。民主主義と資本主義と美術教育が生んだ現代のモンスターの正体とは何なのか。キーワードは「父」「傷」そして「異物」だ。
(2012.09.30発行)
斎藤貴男 『私がケータイを持たない理由』
祥伝社新書 819円
電車内の光景を見よ。誰もが掌中の機器を見つめ、指先で画面に触れ、その呆けたような表情を隠そうともしない。ケータイは利便性と引き換えに多くの代償を求める。対面している相手を無視。交通事故を誘発。監視社会の助長。またいじめの道具でもある。
そんな指摘を並べる著者だが、ケータイを憎んでいるのではない。ケータイによって露呈される人間の醜さ、その本性を見て、「こんな道具を使う資格があるのか」と憤っているのだ。未熟な現代人にもできそうな、「休ケータイ日」を試してみたくなる。
(2012.09.30発行)