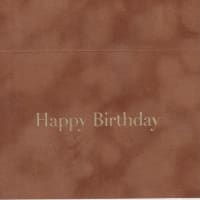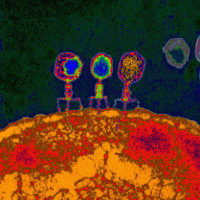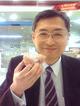IT技術を使うと、国内外のどこにいても情報にアクセスできるという手軽さがあります。
また低コストであることも魅力です。
それはよい側面です。
難しい側面もあります。
それはざっくりいえばセキュリティです。ざっくりすぎると危険な話なので、ひとつひとつ検討をして、主催者や情報提供者がそれに同意(責任をもつ)ことが重要になります。
「そのことに権限があり、責任をもつといったのは誰か、それを保証する仕組みに可能な範囲の準備をしたか」です。
例えば、若手医師セミナーは、特定の回線だけでラインをつなぐ方式をとっており、結果としてファイザー社員のPCがないと映写できないようになっています。
インターネットで自由にみれるようにしてほしいという要望があるのですが、セミナーの主旨や講義の意図の理解のない視聴者に誤解されることもあり、また各講師の講義のコンテンツは講師に著作権があり、無断での録画を防止するためのセキュリティを重視しています。
このことにより講師の発言の自由度が高まります。これもセキュリティです。
中継会場を増やして欲しい、自分の病院でやってくれという依頼もあるのですが、MRさんの数に限界があり、また回線を増やすと不安定になるリスクがあり、これも難しい状況にあります。
病院のシステムに入ると問題が生じたときの影響がとてもおおきいので、トラブルなく専用回線で通信する、これもセキュリティです。
医学書院で行うティアニー先生の症例検討会、これもUstreamなどで遠方の人が見ることができたらいいなとおもうのですが、実際の症例を用いる場合は、プレゼンターの医師・所属施設名とセットになるとかなり個人情報が危うくなります。
このため、完全公開にすることは難しいと判断しました。
このような制約があるため、いつもブログでアナウンスする際には極力、病院名やプレゼンター名をいれないようにしていますし、配付資料は会場で回収する工夫をする主催者もあります。
最近は、医師(医療機関)によっては学会や講義などで公開をする場合に、患者さんやご家族の了解を得ている場合もありますし、積極的に「役立ててください」という方も少なくありません。(入院時や受診時に、学会等で匿名の形ですが情報を活用させていただくことがあります、というような一括同意をとっている病院もあります)
これもセキュリティの工夫のひとつ。
クローズドの勉強会の場合でも個人情報については配慮がなされるのは当然ですが、その場の約束事項を聞くことのない不特定の第三者が見られるようなシステムにはセキュリティ上の課題があります。
少しセキュリティレベルをあげるには、ライブ中継ではなく、録画で修正をかけて(発言者に了解を得て)公開するという方法もあります。かなりたいへんな作業ですが。
そう考えると、生の症例ではなく、時期や施設、主治医の特定がされないような表記、その他、教育コンテンツのために少し改変したようなものがインターネット公開にあたって必要な配慮といえます。
では、症例ではなく講義はどうでしょうか?
一番の問題は(マナー違反ではありますが)録画をされて、その先よくわからない形で拡散してしまうことです。しゃべったそのときは妥当な内容が、ある時期から「それでは不足」「すでに古い」になります。
免責事項とあわせて見てもらう工夫もあるのですが、どこまでそれをセットにしてもらえるかが難しいところです。
ときどき新しい情報にUpdateする必要があるのですが、公開しっぱなしでメンテナンスをされない場合、それは発信者側のセキュリティ意識が問われます。
こう考えてくると、約束事項を読んだ上で同意をするような契約メンバー制、課金制のシステムにおいてセミ公開式にするものが妥協点のように思います。
それはまたそれでお金や手間がかかりますが。
特定の人にだけURLを教える(検索では探せない)、パスワードをかける、等です。
教育プログラム上の問題としては、「第三者の目の存在を気にして」発言が抑制され、フロアとのインタラクティブ性が落ちる可能性があります。
某大手インターネットメディアに誘われた、ネット上症例検討会を辞退したのはこの最後の理由によるところが大きかったです。
また低コストであることも魅力です。
それはよい側面です。
難しい側面もあります。
それはざっくりいえばセキュリティです。ざっくりすぎると危険な話なので、ひとつひとつ検討をして、主催者や情報提供者がそれに同意(責任をもつ)ことが重要になります。
「そのことに権限があり、責任をもつといったのは誰か、それを保証する仕組みに可能な範囲の準備をしたか」です。
例えば、若手医師セミナーは、特定の回線だけでラインをつなぐ方式をとっており、結果としてファイザー社員のPCがないと映写できないようになっています。
インターネットで自由にみれるようにしてほしいという要望があるのですが、セミナーの主旨や講義の意図の理解のない視聴者に誤解されることもあり、また各講師の講義のコンテンツは講師に著作権があり、無断での録画を防止するためのセキュリティを重視しています。
このことにより講師の発言の自由度が高まります。これもセキュリティです。
中継会場を増やして欲しい、自分の病院でやってくれという依頼もあるのですが、MRさんの数に限界があり、また回線を増やすと不安定になるリスクがあり、これも難しい状況にあります。
病院のシステムに入ると問題が生じたときの影響がとてもおおきいので、トラブルなく専用回線で通信する、これもセキュリティです。
医学書院で行うティアニー先生の症例検討会、これもUstreamなどで遠方の人が見ることができたらいいなとおもうのですが、実際の症例を用いる場合は、プレゼンターの医師・所属施設名とセットになるとかなり個人情報が危うくなります。
このため、完全公開にすることは難しいと判断しました。
このような制約があるため、いつもブログでアナウンスする際には極力、病院名やプレゼンター名をいれないようにしていますし、配付資料は会場で回収する工夫をする主催者もあります。
最近は、医師(医療機関)によっては学会や講義などで公開をする場合に、患者さんやご家族の了解を得ている場合もありますし、積極的に「役立ててください」という方も少なくありません。(入院時や受診時に、学会等で匿名の形ですが情報を活用させていただくことがあります、というような一括同意をとっている病院もあります)
これもセキュリティの工夫のひとつ。
クローズドの勉強会の場合でも個人情報については配慮がなされるのは当然ですが、その場の約束事項を聞くことのない不特定の第三者が見られるようなシステムにはセキュリティ上の課題があります。
少しセキュリティレベルをあげるには、ライブ中継ではなく、録画で修正をかけて(発言者に了解を得て)公開するという方法もあります。かなりたいへんな作業ですが。
そう考えると、生の症例ではなく、時期や施設、主治医の特定がされないような表記、その他、教育コンテンツのために少し改変したようなものがインターネット公開にあたって必要な配慮といえます。
では、症例ではなく講義はどうでしょうか?
一番の問題は(マナー違反ではありますが)録画をされて、その先よくわからない形で拡散してしまうことです。しゃべったそのときは妥当な内容が、ある時期から「それでは不足」「すでに古い」になります。
免責事項とあわせて見てもらう工夫もあるのですが、どこまでそれをセットにしてもらえるかが難しいところです。
ときどき新しい情報にUpdateする必要があるのですが、公開しっぱなしでメンテナンスをされない場合、それは発信者側のセキュリティ意識が問われます。
こう考えてくると、約束事項を読んだ上で同意をするような契約メンバー制、課金制のシステムにおいてセミ公開式にするものが妥協点のように思います。
それはまたそれでお金や手間がかかりますが。
特定の人にだけURLを教える(検索では探せない)、パスワードをかける、等です。
教育プログラム上の問題としては、「第三者の目の存在を気にして」発言が抑制され、フロアとのインタラクティブ性が落ちる可能性があります。
某大手インターネットメディアに誘われた、ネット上症例検討会を辞退したのはこの最後の理由によるところが大きかったです。