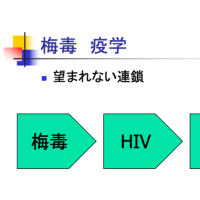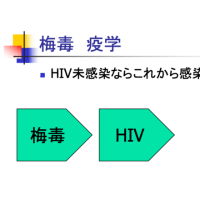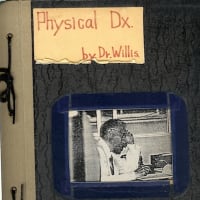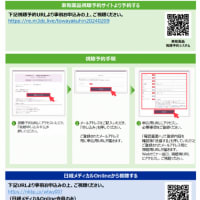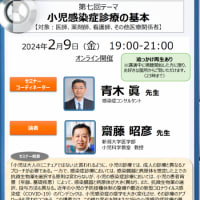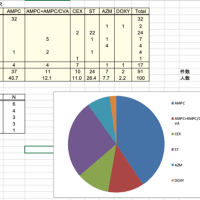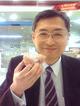2006年に世界で承認販売が始まってから、ことしで10年目。臨床試験中のデータを含めると10年以上のデータがあります。新しいワクチン、思春期のワクチン、女性に接種するワクチンということで各国で導入初期には副反応に関連する話題も熱かったですが、さすがに9年もたったところで、○○が問題だという「騒動」はごく一部の話になっています。
いっときフィーバーしていた米国でもメディアの扱いが小さくなると有害事象の報告も減っています。
現時点では、このワクチンの接種の安全性は他のワクチンと変わらないレベルと評価されています。
WHO、世界の専門機関も(恵まれた国でのアクセスの話ですが)推奨をしています。
【整理の仕方】
「よくある副反応」
「まれな副反応」
「とてもまれな副反応」
「副反応とは考えにくい紛れ込みの症例」
「有害事象だが副反応とは考えにくいもの」 といったかたちで整理ができます。
刺したところが痛い、という原因、結果、その機序が「ワクチン接種のせいだろう」とわかりやすいものと
接種した日に熱が出た、という「そうかもしれない」けれど「他の原因でもおこりうる」判断にちょっと困るもの(でもすぐ治るので問題にはならない)
接種して1年後に麻痺症状が出たという「そんなに後に出るの?」「他のことが原因の可能性はないの?」と慎重に検討をしないと何もいえないものと、ワクチンというよりは、他の疾患の可能性が高いんじゃないの?(これまでの医学的知見から)というものがあります。
この検討はとても重要で、よくわからない時点で○○のせいだ!と決めつけてしまうと、その時点で間違うと治療自体がずれていくという不利益につながるからです。
100%確実なものはない、という謙虚さが必要な分野で、確立していない検査や診断がないなかで、○○のせいと決めて話を展開しているメディアは支援とは反対のことをしている自覚はないのかもしれませんね。
(「○○じゃない」というのも「○○だ」というのも"決めつける"おかしさは一緒です。自分の考えだけゴリ押しするのがおかしいことに気づけない時点で???です)
今年の7月にデンマーク政府が「再度、安全性についての評価をしてくれないか」とEMAに依頼をしたのは、CRPSとPOTSについてです。
因果関係の検討、このワクチン導入後、接種群だけ有意に増えていないか?という疫学的な評価を接種した人(分母)が数年後に増えた時点でもう一度評価をしてほしいということです。
CRPSとPOTS以外は問題になっていない、ともいえます。
この2つは、HPVワクチンの導入前から知られている症状ですので、まさに導入後どうなのか?なのですが、
CRPSは交通事故や手術、採血など外傷や鋭利な器具を用いた処置のあとなどにもおこりうるので、特定のHPVワクチン(薬液)そのものが問題というよりは、その「行為で」一定の頻度で起こると想像できます。
POTSもその症状が、非特異的なのと、この年齢の女性でよくある症状が含まれることから、「そうかもしれない」的に思う人が受診をすれば疑い例じたいが増えます。
(テレビでセンセーショナルに扱ったりすると)
そこで、接種群と非接種群での比較、長期のコホート観察等でアラートというほどに増えているのかの検討が行われました。
そして。副反応で残る話が、医師でジャーナリストの村中璃子氏の連載でも紹介があった、医学的には説明がつかない(テレビでよく流される)不随意運動や多様で変化に富む複数の症状がHPVワクチンそのものの原因なのか?ということです。
多様な症状をHPVワクチン接種後の症候群としてHANSと名付けて展開している医師も複数いるそうです。
(このあたりについては、ティアニー先生はじめ米国の専門家等とも議論済み〜)
この時点で、多発、とか数千人いる重篤な副反応の被害者という表記を続けることができるのかは記者自身にご検討いただきたいです(調べればわかりますので)。
村中さんの記事の中で指摘のあった関連情報はこちらにあります。
慶応義塾大学病院 医療・健康情報サイト 【身体表現性障害】
間接的、直接的に参考になりそうな専門医らの情報も紹介しておきます。
2013年7月12日 Neurology 興味を持った「神経内科」論文 「機能性(心因性)不随意運動の病名と治療」
2014年7月3日 神経内科 一歩前進 子宮頸癌ワクチン副反応
中村ゆきつぐのブログ
2014年10月26日 HPVワクチンについて 副作用と言われるものがこれなら、私は自信を持って娘に打たせます
2015年9月5日 子宮頸癌ワクチン副作用 調べることが必用
医師は医師として誠実に情報を提供している。それが役割ですね。
さて。今回のテーマは原因が何かの検証ではありません。それは専門的な知識や経験をもつ先生方が検討しています。
問いは「誰が本当の支援者か?」です。
支援においては「真実追求」が最終ゴールではなく、「科学的な妥当性」でもありません。
苦痛な症状、不快な状況、困っている日常を改善することが、メディアの好きな「寄り添う」とか「救済」のはずですが、回復につながるような情報を報道しないのはなぜでしょう?
政治的な活動やアピール、症状固定につながりかねない陰性情報ばかり流し続けて支援も救済もないのではないかと思うわけです。
インターネットには当事者や支援者によって、回復事例やその手がかりが紹介されています。
報道アカウントがその情報をみていることもわかっています。
この時点ではワクチンが"原因"なのか"被害者"という言葉が適切なのかを厳密に検討することは目的ではないのでおいておきます。
"被害者"は絵になるし、対製薬会社、対厚労省という図式もニュースになりやすいのではないかとおもいますが、それが問題だというならば、回復する情報はなぜ扱わないのでしょう?
それが、機序が不明確とか、自助努力あるいは医療以外の介入で回復することを疑問視する人もいなくはないとおもいますが、実際に治っている、当事者が「これでよくなったのだ」「治せるのだ」というフェーズにたどりつき、副反応のない方法/高い費用をかけずとりくめる方法でよくなっていることを前向きにとらえ励ますことを「支援者」とか「自分は寄り添っている」つもりのひとたちはなぜしないのだろう?と思って眺めています。
遠回りのようですが、そういった事例のつみかさねが実は「原因」や「機序」の理解や「その先」にもつながると思うのですけどね。
村中さんも指摘していますが、利用されたり、安全性がわからない薬を投薬されたり処置されたり、という状況が早く改善されますように。
(医療側にも「おかしいな」案件が複数ありますので、別の記事で紹介します)
いっときフィーバーしていた米国でもメディアの扱いが小さくなると有害事象の報告も減っています。
現時点では、このワクチンの接種の安全性は他のワクチンと変わらないレベルと評価されています。
WHO、世界の専門機関も(恵まれた国でのアクセスの話ですが)推奨をしています。
【整理の仕方】
「よくある副反応」
「まれな副反応」
「とてもまれな副反応」
「副反応とは考えにくい紛れ込みの症例」
「有害事象だが副反応とは考えにくいもの」 といったかたちで整理ができます。
刺したところが痛い、という原因、結果、その機序が「ワクチン接種のせいだろう」とわかりやすいものと
接種した日に熱が出た、という「そうかもしれない」けれど「他の原因でもおこりうる」判断にちょっと困るもの(でもすぐ治るので問題にはならない)
接種して1年後に麻痺症状が出たという「そんなに後に出るの?」「他のことが原因の可能性はないの?」と慎重に検討をしないと何もいえないものと、ワクチンというよりは、他の疾患の可能性が高いんじゃないの?(これまでの医学的知見から)というものがあります。
この検討はとても重要で、よくわからない時点で○○のせいだ!と決めつけてしまうと、その時点で間違うと治療自体がずれていくという不利益につながるからです。
100%確実なものはない、という謙虚さが必要な分野で、確立していない検査や診断がないなかで、○○のせいと決めて話を展開しているメディアは支援とは反対のことをしている自覚はないのかもしれませんね。
(「○○じゃない」というのも「○○だ」というのも"決めつける"おかしさは一緒です。自分の考えだけゴリ押しするのがおかしいことに気づけない時点で???です)
今年の7月にデンマーク政府が「再度、安全性についての評価をしてくれないか」とEMAに依頼をしたのは、CRPSとPOTSについてです。
因果関係の検討、このワクチン導入後、接種群だけ有意に増えていないか?という疫学的な評価を接種した人(分母)が数年後に増えた時点でもう一度評価をしてほしいということです。
CRPSとPOTS以外は問題になっていない、ともいえます。
この2つは、HPVワクチンの導入前から知られている症状ですので、まさに導入後どうなのか?なのですが、
CRPSは交通事故や手術、採血など外傷や鋭利な器具を用いた処置のあとなどにもおこりうるので、特定のHPVワクチン(薬液)そのものが問題というよりは、その「行為で」一定の頻度で起こると想像できます。
POTSもその症状が、非特異的なのと、この年齢の女性でよくある症状が含まれることから、「そうかもしれない」的に思う人が受診をすれば疑い例じたいが増えます。
(テレビでセンセーショナルに扱ったりすると)
そこで、接種群と非接種群での比較、長期のコホート観察等でアラートというほどに増えているのかの検討が行われました。
そして。副反応で残る話が、医師でジャーナリストの村中璃子氏の連載でも紹介があった、医学的には説明がつかない(テレビでよく流される)不随意運動や多様で変化に富む複数の症状がHPVワクチンそのものの原因なのか?ということです。
多様な症状をHPVワクチン接種後の症候群としてHANSと名付けて展開している医師も複数いるそうです。
(このあたりについては、ティアニー先生はじめ米国の専門家等とも議論済み〜)
この時点で、多発、とか数千人いる重篤な副反応の被害者という表記を続けることができるのかは記者自身にご検討いただきたいです(調べればわかりますので)。
村中さんの記事の中で指摘のあった関連情報はこちらにあります。
慶応義塾大学病院 医療・健康情報サイト 【身体表現性障害】
間接的、直接的に参考になりそうな専門医らの情報も紹介しておきます。
2013年7月12日 Neurology 興味を持った「神経内科」論文 「機能性(心因性)不随意運動の病名と治療」
2014年7月3日 神経内科 一歩前進 子宮頸癌ワクチン副反応
中村ゆきつぐのブログ
2014年10月26日 HPVワクチンについて 副作用と言われるものがこれなら、私は自信を持って娘に打たせます
2015年9月5日 子宮頸癌ワクチン副作用 調べることが必用
医師は医師として誠実に情報を提供している。それが役割ですね。
さて。今回のテーマは原因が何かの検証ではありません。それは専門的な知識や経験をもつ先生方が検討しています。
問いは「誰が本当の支援者か?」です。
支援においては「真実追求」が最終ゴールではなく、「科学的な妥当性」でもありません。
苦痛な症状、不快な状況、困っている日常を改善することが、メディアの好きな「寄り添う」とか「救済」のはずですが、回復につながるような情報を報道しないのはなぜでしょう?
政治的な活動やアピール、症状固定につながりかねない陰性情報ばかり流し続けて支援も救済もないのではないかと思うわけです。
インターネットには当事者や支援者によって、回復事例やその手がかりが紹介されています。
報道アカウントがその情報をみていることもわかっています。
この時点ではワクチンが"原因"なのか"被害者"という言葉が適切なのかを厳密に検討することは目的ではないのでおいておきます。
"被害者"は絵になるし、対製薬会社、対厚労省という図式もニュースになりやすいのではないかとおもいますが、それが問題だというならば、回復する情報はなぜ扱わないのでしょう?
それが、機序が不明確とか、自助努力あるいは医療以外の介入で回復することを疑問視する人もいなくはないとおもいますが、実際に治っている、当事者が「これでよくなったのだ」「治せるのだ」というフェーズにたどりつき、副反応のない方法/高い費用をかけずとりくめる方法でよくなっていることを前向きにとらえ励ますことを「支援者」とか「自分は寄り添っている」つもりのひとたちはなぜしないのだろう?と思って眺めています。
遠回りのようですが、そういった事例のつみかさねが実は「原因」や「機序」の理解や「その先」にもつながると思うのですけどね。
村中さんも指摘していますが、利用されたり、安全性がわからない薬を投薬されたり処置されたり、という状況が早く改善されますように。
(医療側にも「おかしいな」案件が複数ありますので、別の記事で紹介します)