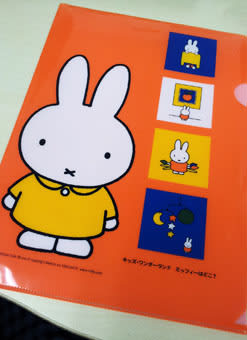最近、小学生が書いた作文を大量に読む機会に恵まれた。みんなが学校や家庭での出来事をいきいきと書いていて楽しい。しかし、サッカー大会や修学旅行、運動会のことなど、書く内容が重なる場合が多くて、もっといろんなテーマに目を向けたらいいのになと思ったりする。
このブログ「日刊イオ」の内容も、最近、編集会議のこと、特集で取り上げた結婚問題のことが続いて、ちょっとうんざりしているので、今日は他のことを書こうと思う。
2年前、イオの取材で長崎の軍艦島(正式名称は端島)へ行ってきた。そのときのことは、月刊イオはもちろん、このブログでも報告した。2010年6月10日ブログ「軍艦島」 http://blog.goo.ne.jp/gekkan-io/e/a9edce75b3f9c721f011896c07921d96
軍艦島は炭鉱の島で、朝鮮が日本の植民地だったときに、多くの朝鮮人が強制的に連れてこられ過酷な労働を強いられた。そして多くの朝鮮人が死んでいる。ブログでは、軍艦島ツアーでの説明で、朝鮮人の強制連行や犠牲についてひとことも触れられていないということを書き、最後に次のように締めくくっている。
「長崎港に戻り船を降りるとき、「軍艦島上陸証明書」をもらいました。その裏に「今ここに新たな歴史の扉を開く」と書かれてました。まず、過去の歴史を清算してもらいたいものです。いま軍艦島を世界遺産に登録しようという動きがあります。過去に軍艦島に住んでいた人たちが中心になって活動しているようです。事前にその人たちが書いた「軍艦島の遺産」という本を読んだのですが、石炭生産のことや日本人の暮らしのことばかりで、朝鮮人のことは、たった5行しか書かれてありませんでした。それも「強制連行」「強制労働」という言葉は一言もありません。世界遺産にするのは良いですが、日本の過去の国家犯罪を後世に伝えるための世界遺産にすべきです。」
現実に「NPO軍艦島を世界遺産にする会」というものもあり、日本は世界遺産登録へと向けて様々な動きを行っているようである。
そのことに関し、最近、朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮中央通信社が論評を発表した。タイトルは「犯罪の歴史を遺産とする国」(10月27日発)。論評のところどころの要旨を以下に紹介する。
「最近、日本が九州の端島を「日本近代化の象徴」としてユネスコ世界文化遺産に登録しようとしている。問題は、同島が前世紀に朝鮮人民に対する日帝の野獣のような蛮行が公然と行われていた強制懲役場、殺人現場であったというところにある」
「日帝の苛酷な蛮行によって同島で悲惨に死んだ朝鮮人の数は明らかになっただけでも120人を超える」
「内外に悪名だけをとどろかしている端島、身震いするこの犯罪の現場を日本は「近代化に貢献した産業遺産」とし、2015年ユネスコ世界文化遺産に登録するというのである。言い換えれば、日帝の過去の犯罪史を示す血の痕跡を絹の風呂敷で覆い、自分らのいわゆる「文明」の宣伝に利用するつもりである」
「これは、朝鮮人民に対するもうひとつの我慢できない特大の冒とく行為、歴史わい曲行為である」
「NPO軍艦島を世界遺産にする会」のホームページを見てみると、会は2003年3月に設立されている。ホームページには理事長の書いた「軍艦島を世界遺産にする会とは」という文章や「世界遺産への提起書」が掲載されているのだが、朝鮮人強制労働について一言も触れられていない。そして、朝鮮中央通信の論評に対して、ホームページのトップページで次のような開き直ったひどい文章を載せている。
「かつて軍艦島にいわゆる強制連行があり、暴虐の歴史を軍艦島に抱き合せた形で既成事実化しようとしているようです。歴史の捏造と歪曲で日本を貶めることに利用するにあたっては許容しかねるものです。他国にとっての怨念があるものだから価値を認めるなという、内政干渉に到っては言葉がありません。いかなる誹謗中傷がでてきたとして、世界遺産の構成資産からしぼるということはありません。「物議を醸しだすものをいれるな」とおっしゃる国内の学者もいます。しかし、隠し事をしたり、また逆に変に韓国や北朝鮮の厳しい怨念に対して、宥めすかすために、嘘の自白をしてその場逃れをしようという安易なこともしたくありません。要は歴史は歴史として淡々と受け止め、歴史を歪曲せず向き合っていきます。正々堂々と歴史的事実をつみかさねた公正な資料を基に準備をしていきたいと思っています。双方が理解をするためにはそれなりの理論と歴史の精査が必要であると思います。」
https://sites.google.com/a/hayabusa-studio.com/gj/
この文章を発見し読んだとき、あまりの破廉恥さにこちらの顔が赤くなった。多くの人にさらすべきだと、今日のブログのテーマを軍艦島にしたのだ。しかし、このような考えは現在の日本社会の大勢を占めるものであろう。
軍艦島の炭鉱は三菱のものだった。長崎市の産業における三菱の占める位置はいまも大きい。戦時中、三菱は軍艦などの兵器を作り、いまも日本の軍需企業のトップとして兵器を作り続けている。日本軍「慰安婦」制度犠牲者のハルモニたちを撮った安世鴻さんの写真展「重重~中国に残された朝鮮人元日本軍「慰安婦」の女性たち」を中止したニコンは三菱グループの会社だ。写真展中止に当たって、三菱の圧力があったことを多くの人たちが指摘している。
軍艦島の世界遺産登録の動きにも三菱が関わっている。

長崎港から軍艦島に向かう途中にある三菱の巨大ドック。昔ここで軍艦が製造されていたと軍艦島クルーズで説明されていた
前回のブログでも書いたが、世界遺産にするのなら、日本の過去の国家犯罪を後世に伝えるための世界遺産にすべきである。(k)