「人類の足跡10万年全史」 スティーヴ・オッペンハイマー 草思社 2007
"Out of Eden: the peopling of the world" Stephen Oppenheimer 2003
人類の起源はアフリカにあると言う
それは単なる仮説に過ぎないのか、それとも説得力と根拠のある説なのか、真理なのか
知的な冒険へと誘ってくれる、羅針盤
本書では、人類の起源はアフリカにあり、そして「出アフリカ」がなされ、そのアフリカを飛び出した我々の祖先が地球上のあらゆる人間たちの祖先であるということを証明してくれる。ミトコンドリアDNAを使い、遺伝子の系統樹を見せてくれて。著者本人のフィールド・ワーク、先人たちの膨大な研究をふまえ、図表をふんだんに使い、素人にも分かりやすい言葉で語りかけてくれる。
そもそもなぜアフリカが人類の起源と言えるのだろう?一昔前まで、ヨーロッパ人たちは自分たちこそが全人類の祖先であると信じていた。なぜそれが間違っていると言えるのだろう?アフリカから地球全体に人類の祖先が移動して行った?アジアや、オーストラリア、アメリカはとても遠いぞ。どうやって移動することが出来たのだ?
そんな疑問は全て一掃してくれる。
こう信じたいから、それに理由をくっつけた上でそれが正しいと思い込むことが愚行であることも教えてくれる。
サイエンス本は、我々読者が個人で収集できるような情報の集積を大きく超えて、先人たちが残した膨大な文献(も含めて)を自分で読まないで、読んだのと同じ効果が得られるという意味で、「お得」な本と言える。
以下、自分用覚書
・自然淘汰が、大きな脳を造り出したのではなく、まず初めに大きな脳ありき。という仮説
・密林が氷期にサバンナ化したたことによって、4足歩行から2足歩行になったという仮説は根拠薄弱。「脳を冷やすため」「遠くを見るため」に頭部が上にいくようになったと言う者がいるが。
・ネアンデルタール人や、ホモ・エレクトスは我々の祖先ではない。途中で絶滅した。
・我々の脳は、250万年前から100万年前にかけて猛スピードで大きくなった。しかし、最近ではむしろ脳は小さくなっている。これは、出産のリスクを減らすためだろうか?説得力ある説明はまだない。
・脳の大きさはだいぶ前に大きくなることをやめてしまった。しかし我々の行動的進化は留まることを知らない。脳の進化と行動的進化を説明する「共進化」という概念は面白い。
・言語は単なるうわさ話にすぎない意味で登場したという説は違うと著者は言う。言語が氷期に生き延びることを可能にした手段だったと。
・「人は文化で判断できない」(120ページ)とは至言

最後に、この「人類の足跡10万年全史」の旅を締めくくるべく、エピローグに多様性の重要さについて説く箇所があるので引用す。
では変種の審美的な側面をのぞいて、多様性の何がそれほど重要なのだろうか。その答えは生きのびていくことにある。無作為の多様性は、自然と進化の燃料倉庫だ。ランダムに生じる遺伝的多様性がないと、種は生存し、ふりかかるさまざまなストレスに適応する柔軟さを失う。繁殖する一つがいから無作為の多様性が発展していくには多くの世代を要するので、極端な遺伝子の瓶首効果を経た種が多様性を取り戻すのは大変なことになる。(387ページより引用)
多様性が我々にとってとても大事なことであると、自分自身が考えていたので、この箇所ががっつりと入り込んで来た。多様性がなぜ重要なのか述べ始めると長くなるので、いつか機会があったら別記事にしてみたい。簡単に言えば、多様性を認めることが、「差別」が無駄な行為であると考える道につながる。あるいは、与えられる権利という意味では男女は平等であるべきだが、男女同質ではない。違うのだ。違うからいいのだ。また、人と違うということに何かプラスの意味が存在し、人と同じであるということに安心を感じてしまうことが、多様性の観点からするとあまり好ましくないとか・・・・・・ うーむ。アホの俺が語ると、へそが茶を沸かしそうだ。
今日の教訓
え?
あたしの祖先は
お星さまだけどね。
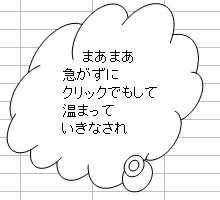
人気blogランキングへ
自作面白ネタブログランキング















こちらは主に1万3000年の文化的な変遷を語る内容のものではありましたが。
10万年のという人類史的な視点も興味深いですね。
そんな私は懸案出るたーる人
銃・病原菌・鉄 読みましたねー。でもほとんど覚えていないことに今気がつきました。
タイトルに10万年とありますが、正確には19万年全史だと思います。キリが悪いから10万年にしたんですかね。