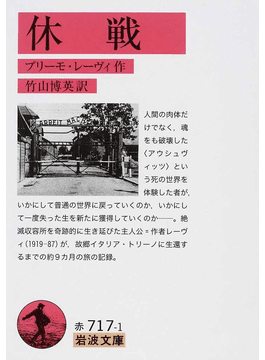先日プリーモ・レーヴィの「溺れるものと救われるもの」を再読したとき、12年前に初めて読んだときよりも細部がよく頭に入ってくる感覚があったので、引き続き「休戦」をもう一度読みたくなった。「休戦」も12年前に読んだのだが、そのときは「これが人間か アウシュヴィッツは終わらない」(以下「アウシュヴィッツ‥」)を読んだ直後だったので、著者のアウシュヴィッツ体験に打ちのめされて、それとは異質の一種の明るさをもつ「休戦」の世界に入っていけなかった。
「休戦」はアウシュヴィッツ強制収容所が1945年1月にソ連軍によって解放された後、著者が紆余曲折を経てイタリアのトリノに帰還するまでの経験を書いたものだ。その意味では「アウシュヴィッツ‥」の後日談になるが、死の恐怖がなくなった(=ナチス・ドイツがいなくなった)という決定的な要因があり、「アウシュヴィッツ‥」の緊迫した世界とは違って、どこか明るくのんびりした作品になった。
その帰還は果てしなく漂流するような旅になるのだが、その中で著者が出会ったさまざまな人物、焦燥、倦怠、冒険、その他のさまざまな出来事が描かれる。著者はその帰還をギリシャ神話のオデュッセウスの帰還になぞらえている節があるが、読み手もその漂流の感覚をつかみ、それに身を委ねれば、本書は波のように心地よいリズムを打ちながら、波間に人間への洞察を垣間見せる。
本書の基本的な性格はそのようなもので、わたしは今回再読して、それを楽しむことができた。以下ではわたしが今回とくに注目した点を二つあげたい。一つは著者をふくむ総勢1400人のイタリア人を祖国に送還したソ連軍のことだ。ソ連軍は著者たちに一日一キロのパンを支給し、毎日「カーシャ」(ラードと粟といんげん豆と肉と香料の固まり)を支給し、週に3~4回は魚も支給した。また「イデオロギー教育をしようというばかげた野望は持たなかった」。
ソ連軍のその厚遇は、戦後シベリアに抑留された日本人への冷遇、酷使そして思想教育とはなんという違いだろう。その違いはいったいなぜなのか、という点。
もう一つは帰還の途中で立ち寄ったミュンヘンのことだ。「彼ら(引用者注:ドイツ人たち)は廃墟の中にこもっていたが、それはあたかも責任回避の要塞に意図的に閉じこもっているかのようだった。」。著者はこの部分に次のような注を付けている。「ドイツ人が少し前に被った苦痛と服喪は、彼らの個人的、集団的過ちを意識するのを不可能にし、「責任回避的」にした。」と。
ドイツ人のこの描写は、敗戦直後の日本人の姿と二重写しにならないだろうか。
「休戦」はアウシュヴィッツ強制収容所が1945年1月にソ連軍によって解放された後、著者が紆余曲折を経てイタリアのトリノに帰還するまでの経験を書いたものだ。その意味では「アウシュヴィッツ‥」の後日談になるが、死の恐怖がなくなった(=ナチス・ドイツがいなくなった)という決定的な要因があり、「アウシュヴィッツ‥」の緊迫した世界とは違って、どこか明るくのんびりした作品になった。
その帰還は果てしなく漂流するような旅になるのだが、その中で著者が出会ったさまざまな人物、焦燥、倦怠、冒険、その他のさまざまな出来事が描かれる。著者はその帰還をギリシャ神話のオデュッセウスの帰還になぞらえている節があるが、読み手もその漂流の感覚をつかみ、それに身を委ねれば、本書は波のように心地よいリズムを打ちながら、波間に人間への洞察を垣間見せる。
本書の基本的な性格はそのようなもので、わたしは今回再読して、それを楽しむことができた。以下ではわたしが今回とくに注目した点を二つあげたい。一つは著者をふくむ総勢1400人のイタリア人を祖国に送還したソ連軍のことだ。ソ連軍は著者たちに一日一キロのパンを支給し、毎日「カーシャ」(ラードと粟といんげん豆と肉と香料の固まり)を支給し、週に3~4回は魚も支給した。また「イデオロギー教育をしようというばかげた野望は持たなかった」。
ソ連軍のその厚遇は、戦後シベリアに抑留された日本人への冷遇、酷使そして思想教育とはなんという違いだろう。その違いはいったいなぜなのか、という点。
もう一つは帰還の途中で立ち寄ったミュンヘンのことだ。「彼ら(引用者注:ドイツ人たち)は廃墟の中にこもっていたが、それはあたかも責任回避の要塞に意図的に閉じこもっているかのようだった。」。著者はこの部分に次のような注を付けている。「ドイツ人が少し前に被った苦痛と服喪は、彼らの個人的、集団的過ちを意識するのを不可能にし、「責任回避的」にした。」と。
ドイツ人のこの描写は、敗戦直後の日本人の姿と二重写しにならないだろうか。