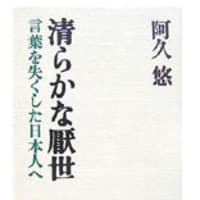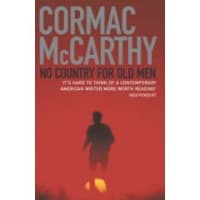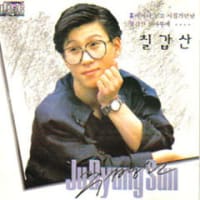「人の世の仲秋無月芋食ひて」山口青邨
芋名月は陰暦8月15日、今年は9月13日だった。
芋名月をWEBで調べてみると、御所勤めの女官たちが書いた当番日記の〈御湯殿記〉には「名月御祝、三宝に芋ばかり高盛り」とあるように、新芋を掘り、水炊きのまま月前に供えたりして秋の収穫を祝ったものだとある。
信心の足りない我が家では、お月様に供えるのではなくもっぱら自家消費用の〈赤柄芋〉や〈月見だんご〉を食卓に供した。もちろん、三宝に高く盛り上げるほどはない。赤柄芋は隣県遠州が主産地の芋。柔らかいが煮崩れをしない肉質や甘みのある食味のよさが評判で、家人の好物である。
里芋といえば炊くのが一般的だろう。先週の日曜日(9月15日)には、山形の秋の風物詩〈日本一の芋煮会〉が行われて、今年も多くの芋煮ファンを集めたというニュースをNHK山形が流している。芋煮が山形の郷土料理だというのはこちらも承知しているが、遠い東北まで遠征をして味わったことはないのが残念だ。
〈日本一の芋煮会〉というのは「鍋太郎」と名付けられた直径6.5Mもある大鍋で大量の芋煮をつくることからそう云われるのだろう。
迎えて31回目の今年は去年より5千食多い3万5千食分を準備したという。里芋4トン、長ねぎ5千本、牛肉1.4トン、こんにゃく5500枚、醤油820リットル、地酒80升、砂糖200キロ、山形の水6トンなど、大量の食材が用意されて次々と大鍋に投入され、作業員たちが醤油や砂糖などで味を付け、大柄杓でかき混ぜて仕上げ、大型ショベルカーを使って掬う作業を繰り返した。見るからに工業生産だが、最近ではギネスに挑戦する大規模な食イベントが世界的になっているから、山形が唯一無二ということではないのだろう。それでも、そんな製造現場を目撃できれば感激ものだ。
朝9時半から配食ということだが、中には夜明け前の4時半ころから鍋を持って待ったという芋煮ファンもいたらしい。列を作った参加者たちは300円の協賛金を払って芋煮を受け取り、河川敷の芝生の上でできたての芋煮を味わっていたとある。大鍋で作ったほくほくの芋煮だ。さぞや美味しかったことだろう。行かずとも想像はできる。
ウイキで読むと、山形の芋煮会はすでに江戸時代に源流があると書かれている。最上川の舟運にかかわる人たちが野外で鍋料理を始めたことだとあるから、神仏に奉る秋の収穫祭ということでもなかったのだろう。意外に庶民的な始まりというのが面白いではないか。
里芋はこれからが盛りになるのだから、庶民としては、シーズン中にもう一度くらいは美味い里芋を食べさせてもらいたいなと、このブログを書きながら考えた。
最新の画像[もっと見る]