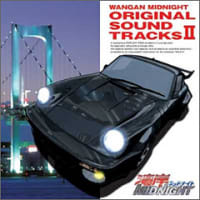『おしいれのぼうけん』などで有名な古田足日氏の童話に
『大きい一年生と小さな二年生』という作品がある。
幼少の頃読書好きだった私は、今でもこの童話のストーリーをはっきりと覚えている。
体が大きいのに弱虫な一年生の「まさや」と
まさやの家の近所に住む、背が小さいけれど勝気な二年生の女の子「あきよ」
あきよの同級生で団地に住んでいるのんびり屋のまりこの3人が織り成す、成長と冒険の物語。
まさやのことを「一年生のくせに私より体が大きいなんて生意気!」と思っていたあきよだけれど、学校への通学路である暗い森の中の道が恐くて学校に行きたくないと泣いていたまさやを誘って学校へ登校するようになり、次第に3人で遊ぶようにもなっていく。
ある日3人で、あきよの好きな花「ホタルブクロ」を遠くの古い神社まで取りに行った帰り道、いじめっ子に遭遇。せっかく取ってきたホタルブクロを折られてしまう。
今まで、けんかしてもどんなときでも泣かなかったあきよが、目の前で涙を見せた―
そして、お母さんからさまざまな事で叱られっぱなしだったまさやの思いが頂点に達し、
まさやは、あきよに「持ちきれないくらいのホタルブクロを取ってあげる」ために、
わずかなお小遣いとあきよとの思い出の品を持って、家出(という名の冒険)をする。
かなり前に書かれた作品で、カラーテレビが(登場していたものの)まだ普及していなかったり、パンが5円で買えたりする時代背景だが、
思春期を迎える前の幼少時代は女の子の方がおてんばだけど強気だった頃―
男の子が泣き虫だった頃を懐かしがりながら、
まさやが作中に出会う人たちから学ぶことや、彼の成長ぶりなど
さまざまなことに感動して読める本である。
自分は、弱虫で泣き虫だったし、特に小学校低学年の頃は友達がいなかったこともあり、まさや・あきよ・まりこの関係がとても羨ましかった。
歯を食いしばり、強気にけんかする(というより、悪いことは悪いことと面と向かって立ち向かう)あきよ。
のんびりやだけどまさやのこともあきよのことも大切に思うまりこ。
まさやのクラスメイトにみどりという名の妹を持つあきよの同級生に、教室内でのまさやの一件(失敗談)を聞いたときも、あきよもまりこもまさやの味方だった。
ある日あきよは言う。
「まさやくんがしっかりしないんだったら、もういっしょに学校にいってあげないから」
まさやは答える。
「ぼく、しっかりするよ」
あきよはうれしくなった。
しかし、あきよにしっかりする、と答えたまさやは困ってしまう。
「しっかりする」とはどういうことか?
それがまさやにはわからなかったのだ。
机の上に座ってずーっとずーっと考えたまさやが導き出した答え―
『あきよちゃんはほんとうにしっかりしてるわね』というお母さんの言葉からひらめいた。
「わかった!あきよちゃんのようになればいいんだ!」
それからあとはかんたんだった。あきよのようになるには、あきよのしていることを見ていればいい、と。
けど、やはりまさやは困惑する。
強気な態度の男の子にも面と向かって言いたいことをはっきりと言い、時にけんかする。
「しっかりするっていうのはけんかするってことなのかなぁ」
前述の、ホタルブクロの花を取りに行った日の帰りまで、涙を見せなかったあきよのことを思い出し
「しっかりするっていうのは泣かないことなのかなぁ」
親の教育と愛情をまだまだ沢山注がれる幼少時代には、学校の内外で出会う子供たちが交流の中心であり、近所やさまざまなところで出会い、ほんの少しだけど心を通わせる大人たちは、見方を変えれば子供とは別の世界の人間である。
そんな中、大人ではなく、「あの子みたいにしっかりした子になりたい!」という、目指す姿があるというのはとても意味深いものであると思う。
30歳を越えた大人の私でも、今まで出会った人の中で、忘れられない人、こんな風なモノの考え方ができる人になりたい、もっとしっかりしたい、という欲求はある。
しかし、私はまさやのような小学生ではない。
「30歳にもなるんだから・いいオトナなんだから、それなりに社会経験してきているだろう」=「もっとしっかりしろ!」
と言われてしまうのが常だ。
それに、今目指すべき人が居ない。
もちろん、まったくのゼロという意味ではない。生き方や考え方において、参考になる人は沢山いる。
問題は、すぐ近くに居ないこと。
まさやにとって、生活のメインの場である学校や放課後に会うあきよのように、生活のメインの場=仕事において、そーゆう人が居ない、ということである。
今は仕事も失ってしまったから、居る・いない以前の問題なのだが…
仕事の中において、「この人についていけばいいんだ」というキーパーソンのような、かけがえのない存在となる人が居るということは、本当に幸福なことだと思う。
もちろんそれは普段の生活全般においても言えることで、
たとえば結婚して家庭を持つことや、好きな人と一緒に居ること―それはもちろん幸せなことだけどそれは私にとっては不可能に近いことで、私はそれを望まない―「この人と生きていける」「この人がそばに居るだけで、自分が自分になれる」という人。
単なる甘えや寄りかかりではなく、もっと高い次元において
そーゆう人の存在がとても大きな意味を持つのではないかと思う。
今の私は、まさやと同じ気持ちを胸に抱いている。
「しっかりするとはどういうこと?」
まさやのように、「しっかりするために『このひとこそ!』と参考になる人」が近くに居ればいいが―
自分でどれだけ考えてもわからないのなら、一緒に仕事していく中で・一緒に何かを成し遂げる中で、そんな人が近くに居て、自分にないものを見て盗める・教えてもらえる、そして切磋琢磨できることができたら、これほど幸せなことはない。
久しぶりに、この童話のことを思い出すきっかけがあり
お話の内容のことよりも、自分にとって「親以外の」大切な人のありがたさを考え、思い出したきっかけになった。
繰り返し問い続ける
「しっかりするとはどういうこと?」
時々質問が変わる
「私、ただノンベンダラリと年齢を重ねてしまったダメ男?」
と
そんなことを未だに考えているようじゃ
私は社会人として赤店満点ってことだナ―
(童話は今でも注文可能。興味のある方は読んでみてほしい)
拙い文章ですみません。
『大きい一年生と小さな二年生』という作品がある。
幼少の頃読書好きだった私は、今でもこの童話のストーリーをはっきりと覚えている。
体が大きいのに弱虫な一年生の「まさや」と
まさやの家の近所に住む、背が小さいけれど勝気な二年生の女の子「あきよ」
あきよの同級生で団地に住んでいるのんびり屋のまりこの3人が織り成す、成長と冒険の物語。
まさやのことを「一年生のくせに私より体が大きいなんて生意気!」と思っていたあきよだけれど、学校への通学路である暗い森の中の道が恐くて学校に行きたくないと泣いていたまさやを誘って学校へ登校するようになり、次第に3人で遊ぶようにもなっていく。
ある日3人で、あきよの好きな花「ホタルブクロ」を遠くの古い神社まで取りに行った帰り道、いじめっ子に遭遇。せっかく取ってきたホタルブクロを折られてしまう。
今まで、けんかしてもどんなときでも泣かなかったあきよが、目の前で涙を見せた―
そして、お母さんからさまざまな事で叱られっぱなしだったまさやの思いが頂点に達し、
まさやは、あきよに「持ちきれないくらいのホタルブクロを取ってあげる」ために、
わずかなお小遣いとあきよとの思い出の品を持って、家出(という名の冒険)をする。
かなり前に書かれた作品で、カラーテレビが(登場していたものの)まだ普及していなかったり、パンが5円で買えたりする時代背景だが、
思春期を迎える前の幼少時代は女の子の方がおてんばだけど強気だった頃―
男の子が泣き虫だった頃を懐かしがりながら、
まさやが作中に出会う人たちから学ぶことや、彼の成長ぶりなど
さまざまなことに感動して読める本である。
自分は、弱虫で泣き虫だったし、特に小学校低学年の頃は友達がいなかったこともあり、まさや・あきよ・まりこの関係がとても羨ましかった。
歯を食いしばり、強気にけんかする(というより、悪いことは悪いことと面と向かって立ち向かう)あきよ。
のんびりやだけどまさやのこともあきよのことも大切に思うまりこ。
まさやのクラスメイトにみどりという名の妹を持つあきよの同級生に、教室内でのまさやの一件(失敗談)を聞いたときも、あきよもまりこもまさやの味方だった。
ある日あきよは言う。
「まさやくんがしっかりしないんだったら、もういっしょに学校にいってあげないから」
まさやは答える。
「ぼく、しっかりするよ」
あきよはうれしくなった。
しかし、あきよにしっかりする、と答えたまさやは困ってしまう。
「しっかりする」とはどういうことか?
それがまさやにはわからなかったのだ。
机の上に座ってずーっとずーっと考えたまさやが導き出した答え―
『あきよちゃんはほんとうにしっかりしてるわね』というお母さんの言葉からひらめいた。
「わかった!あきよちゃんのようになればいいんだ!」
それからあとはかんたんだった。あきよのようになるには、あきよのしていることを見ていればいい、と。
けど、やはりまさやは困惑する。
強気な態度の男の子にも面と向かって言いたいことをはっきりと言い、時にけんかする。
「しっかりするっていうのはけんかするってことなのかなぁ」
前述の、ホタルブクロの花を取りに行った日の帰りまで、涙を見せなかったあきよのことを思い出し
「しっかりするっていうのは泣かないことなのかなぁ」
親の教育と愛情をまだまだ沢山注がれる幼少時代には、学校の内外で出会う子供たちが交流の中心であり、近所やさまざまなところで出会い、ほんの少しだけど心を通わせる大人たちは、見方を変えれば子供とは別の世界の人間である。
そんな中、大人ではなく、「あの子みたいにしっかりした子になりたい!」という、目指す姿があるというのはとても意味深いものであると思う。
30歳を越えた大人の私でも、今まで出会った人の中で、忘れられない人、こんな風なモノの考え方ができる人になりたい、もっとしっかりしたい、という欲求はある。
しかし、私はまさやのような小学生ではない。
「30歳にもなるんだから・いいオトナなんだから、それなりに社会経験してきているだろう」=「もっとしっかりしろ!」
と言われてしまうのが常だ。
それに、今目指すべき人が居ない。
もちろん、まったくのゼロという意味ではない。生き方や考え方において、参考になる人は沢山いる。
問題は、すぐ近くに居ないこと。
まさやにとって、生活のメインの場である学校や放課後に会うあきよのように、生活のメインの場=仕事において、そーゆう人が居ない、ということである。
今は仕事も失ってしまったから、居る・いない以前の問題なのだが…
仕事の中において、「この人についていけばいいんだ」というキーパーソンのような、かけがえのない存在となる人が居るということは、本当に幸福なことだと思う。
もちろんそれは普段の生活全般においても言えることで、
たとえば結婚して家庭を持つことや、好きな人と一緒に居ること―それはもちろん幸せなことだけどそれは私にとっては不可能に近いことで、私はそれを望まない―「この人と生きていける」「この人がそばに居るだけで、自分が自分になれる」という人。
単なる甘えや寄りかかりではなく、もっと高い次元において
そーゆう人の存在がとても大きな意味を持つのではないかと思う。
今の私は、まさやと同じ気持ちを胸に抱いている。
「しっかりするとはどういうこと?」
まさやのように、「しっかりするために『このひとこそ!』と参考になる人」が近くに居ればいいが―
自分でどれだけ考えてもわからないのなら、一緒に仕事していく中で・一緒に何かを成し遂げる中で、そんな人が近くに居て、自分にないものを見て盗める・教えてもらえる、そして切磋琢磨できることができたら、これほど幸せなことはない。
久しぶりに、この童話のことを思い出すきっかけがあり
お話の内容のことよりも、自分にとって「親以外の」大切な人のありがたさを考え、思い出したきっかけになった。
繰り返し問い続ける
「しっかりするとはどういうこと?」
時々質問が変わる
「私、ただノンベンダラリと年齢を重ねてしまったダメ男?」
と
そんなことを未だに考えているようじゃ
私は社会人として赤店満点ってことだナ―
(童話は今でも注文可能。興味のある方は読んでみてほしい)
拙い文章ですみません。