豊浦宮跡の石碑を後に、次に向かったのは石神遺跡。
ここからは須弥山石や石人像が発掘されたそうですが、現在は田んぼに戻ってた…よね?
自転車こぐのでいっぱいいっぱいでちょっと記憶の景色がぼんやりなんだわ。
毎年田んぼを1枚ずつ買っては発掘作業を行っていると聞きました。
地道な作業なんだな、って思うのと同時に、この田園風景の下には古代の遺跡が静かに眠っているんだと思うと、そんな場所に自分が立っているなんて夢のようでした。

次に水落遺跡へ。
ここは中大兄皇子が造った、日本初の漏尅(水時計)の跡。
飛鳥資料館に模型があったけど、それを見ても仕組みが理解仕切れていないワタクシ…。
サイフォンと同じだって言われたんだけど。

次に飛鳥寺へ。
今は小さなお寺となってしまってますが、ここが日本最古の本格的寺院があった所。
真ん中に塔があり、塔を囲むように東西と北に金堂があった、一塔三金堂って造りの壮大な伽藍があったそうです。
この造りだと塔が何の為に造られたのかが良く分かるなと思った。
西門跡のさらに西側に蘇我入鹿の首塚がありました。
飛鳥大仏は法隆寺の釈迦三尊像を作った鞍作止利の作。
鎌倉時代の落雷で火災に合い、大幅な補修はされているけれど、飛鳥時代に作られた時からずっと同じ場所に安置されているそうです。
この仏様を厩戸王子(聖徳太子)や蘇我毛人も拝んだのかと思うと…っ!!

水落遺跡や飛鳥寺近辺はこんな風景が広がってました。
田んぼの稲の緑に彼岸花の赤が良く映えてました。
これが中ツ道って教えられたけど本当?
次に訪れたのは「飛鳥宮跡苑池遺構」という1999年に発掘された、飛鳥浄御原宮の宮廷庭園跡。
…とは言え現在は埋め戻されてただ一面の草っ原で、道路から見ると飛鳥川へ向かって土地が低くなっている場所にあり、田んぼのあぜ道を少し歩いて向かうようになるので、普通の観光客はまず間違いなく訪れない場所。
第一、苑池跡へ向かう為の案内板一つ無かったもの。
でもここを訪れたお陰で飛鳥浄御原宮跡の広大さを体感できました。
もし次回ここへ行ったとしても、自力ではたどり着けないよ(苦笑)
そして板蓋宮跡へ。
板蓋宮は大化の改新で蘇我入鹿が中大兄皇子や中臣鎌足に殺された場所。
…でも現在復元整備されているのは飛鳥浄御原宮跡で、板蓋宮はその下層にあるらしい。
板蓋宮跡として整備されているのは、飛鳥浄御原宮の大井戸の跡。
ちなみに明日香村役場のある場所が南門です。
地面は石敷きとなっていて、素晴らしい宮があったんだろうなと想像してました。
ここでおっちゃんに“エビノコ大殿”のあった場所も教えてもらったのですが、エビノコ大殿が何なのか咄嗟に思い出せなかった。
昨日博物館で見てきただろう、一体何を見てきたんだ?!って言われたけど、だって火焔土器の話しで盛り上がったんだもん、なんて言えない(笑)
その後にようやくエビノコ大殿の模型があったのを思い出せたけど。
次にとっても有名な石舞台古墳へ。

元々が明日香村でも一番有名な観光地で、しかも“彼岸花祭り”の期間中で、お祭りのメイン会場があって、前日夜も道路が大混雑していたけど、この日もやはり大混雑。

石舞台古墳の周囲は空掘となっていて、水が入っていない堀って部分で大王(天皇)の墓では無いって分かるのだそうです。
それで蘇我馬子の墓と言われていると。

内部もとても広いんですね~。
人が多くて埃っぽくて、長居すると咳き込みそうだったので早々に出てしまいました。
石室内部の足元に雨水を排水する溝があるのですが、これは新たに作ったのではなくて、古墳が作られた当時から存在する排水溝で、空堀に流れるようになっているそうです。
ちゃんと考えて作られているんですね。
石舞台古墳の西側の下った場所にある駐車場、そこのレストハウスが島庄遺跡のある場所。
ここが蘇我馬子の邸宅跡と言われているそうです。
島庄って地名の場所に邸宅があったから嶋大臣(しまのおおおみ)と呼ばれたのかと思ってたけど、邸宅の池に島があったから嶋大臣って呼ばれて、その邸宅があったから地名が島庄になったのか、どっちなんだろう?
墓も邸宅も真神原を見下ろせる高台にあって、馬子の権力の一端を垣間見た気分になりました。
ここからは須弥山石や石人像が発掘されたそうですが、現在は田んぼに戻ってた…よね?
自転車こぐのでいっぱいいっぱいでちょっと記憶の景色がぼんやりなんだわ。
毎年田んぼを1枚ずつ買っては発掘作業を行っていると聞きました。
地道な作業なんだな、って思うのと同時に、この田園風景の下には古代の遺跡が静かに眠っているんだと思うと、そんな場所に自分が立っているなんて夢のようでした。

次に水落遺跡へ。
ここは中大兄皇子が造った、日本初の漏尅(水時計)の跡。
飛鳥資料館に模型があったけど、それを見ても仕組みが理解仕切れていないワタクシ…。
サイフォンと同じだって言われたんだけど。

次に飛鳥寺へ。
今は小さなお寺となってしまってますが、ここが日本最古の本格的寺院があった所。
真ん中に塔があり、塔を囲むように東西と北に金堂があった、一塔三金堂って造りの壮大な伽藍があったそうです。
この造りだと塔が何の為に造られたのかが良く分かるなと思った。
西門跡のさらに西側に蘇我入鹿の首塚がありました。
飛鳥大仏は法隆寺の釈迦三尊像を作った鞍作止利の作。
鎌倉時代の落雷で火災に合い、大幅な補修はされているけれど、飛鳥時代に作られた時からずっと同じ場所に安置されているそうです。
この仏様を厩戸王子(聖徳太子)や蘇我毛人も拝んだのかと思うと…っ!!

水落遺跡や飛鳥寺近辺はこんな風景が広がってました。
田んぼの稲の緑に彼岸花の赤が良く映えてました。
これが中ツ道って教えられたけど本当?
次に訪れたのは「飛鳥宮跡苑池遺構」という1999年に発掘された、飛鳥浄御原宮の宮廷庭園跡。
…とは言え現在は埋め戻されてただ一面の草っ原で、道路から見ると飛鳥川へ向かって土地が低くなっている場所にあり、田んぼのあぜ道を少し歩いて向かうようになるので、普通の観光客はまず間違いなく訪れない場所。
第一、苑池跡へ向かう為の案内板一つ無かったもの。
でもここを訪れたお陰で飛鳥浄御原宮跡の広大さを体感できました。
もし次回ここへ行ったとしても、自力ではたどり着けないよ(苦笑)
そして板蓋宮跡へ。
板蓋宮は大化の改新で蘇我入鹿が中大兄皇子や中臣鎌足に殺された場所。
…でも現在復元整備されているのは飛鳥浄御原宮跡で、板蓋宮はその下層にあるらしい。
板蓋宮跡として整備されているのは、飛鳥浄御原宮の大井戸の跡。
ちなみに明日香村役場のある場所が南門です。
地面は石敷きとなっていて、素晴らしい宮があったんだろうなと想像してました。
ここでおっちゃんに“エビノコ大殿”のあった場所も教えてもらったのですが、エビノコ大殿が何なのか咄嗟に思い出せなかった。
昨日博物館で見てきただろう、一体何を見てきたんだ?!って言われたけど、だって火焔土器の話しで盛り上がったんだもん、なんて言えない(笑)
その後にようやくエビノコ大殿の模型があったのを思い出せたけど。
次にとっても有名な石舞台古墳へ。

元々が明日香村でも一番有名な観光地で、しかも“彼岸花祭り”の期間中で、お祭りのメイン会場があって、前日夜も道路が大混雑していたけど、この日もやはり大混雑。

石舞台古墳の周囲は空掘となっていて、水が入っていない堀って部分で大王(天皇)の墓では無いって分かるのだそうです。
それで蘇我馬子の墓と言われていると。

内部もとても広いんですね~。
人が多くて埃っぽくて、長居すると咳き込みそうだったので早々に出てしまいました。
石室内部の足元に雨水を排水する溝があるのですが、これは新たに作ったのではなくて、古墳が作られた当時から存在する排水溝で、空堀に流れるようになっているそうです。
ちゃんと考えて作られているんですね。
石舞台古墳の西側の下った場所にある駐車場、そこのレストハウスが島庄遺跡のある場所。
ここが蘇我馬子の邸宅跡と言われているそうです。
島庄って地名の場所に邸宅があったから嶋大臣(しまのおおおみ)と呼ばれたのかと思ってたけど、邸宅の池に島があったから嶋大臣って呼ばれて、その邸宅があったから地名が島庄になったのか、どっちなんだろう?
墓も邸宅も真神原を見下ろせる高台にあって、馬子の権力の一端を垣間見た気分になりました。












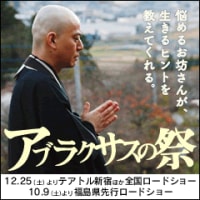







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます