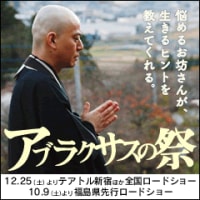京都旅行1日目、最初の訪問地は大阪府羽曳野市。
近鉄南大阪線の上ノ太子駅で下車して、駅前のレンタサイクルで自転車を借りて散策。
そこそこ乗客が降りたなって思ったのに、私以外はみんなみかん狩り目当ての人だった。
みかん狩りってこの時期なんですね…知らなかった。
思っていた以上のアップダウンと道の細さに、何度も停まっては地図を確認する作業の繰り返し。
多分ここだろうと思った穴穂部皇子御廟も、案内板が無かったので思わずスルー。
最初に向かったのは壺井八幡宮。

このあたりは壺井の香炉峰といわれ、河内源氏発祥地として知られており、平安時代中期の寛仁4年(1020年)、源頼信が河内守に任官してこの地に私邸を営み、康平7年(1064年)に前九年の役を平定した頼義(頼信の子)が石清水の神を私邸の東側に勧請したのが本宮の起源である。
また、左側にある壺井権現社、源義時(義家の五男)が河内源氏の祖神として天仁2年(1109年)に創祀したものである。
現社殿は、両社とも元禄14年(1701年)に徳川綱吉の命で柳澤吉保が再建したものである。(案内板より)

こっちが壺井権現社ですね。
この後通法寺跡へ。

羽曳野市壺井は河内源氏の発祥地として知られていますが、この壺井通法寺は、長久4年(1043年)に河内国司であった源頼信が小堂を建てたことからはじまります。
前九年の役(1051~62年)の時、東北地方で活躍した源頼義が浄土教に帰依し阿弥陀仏を本尊としてから河内源氏の菩提寺となり源氏の隆栄と共に栄えました。
南北朝時代(約700年前)には、戦火にあい建物を焼失しましたが、江戸時代になって源氏の子孫・多田義直が5代将軍綱吉に願い出て、柳沢吉保らが普請奉行となって再建しました。
ところが、明治時代の廃仏毀釈により現在のように山門・鐘楼などを残すだけとなってしまいました。(案内板より)
この通法寺跡に源頼義の墓があります。

源頼義っていったら、藤原経清を錆刀で鋸引きにした人よ!
ちょっと心の中でギリッとか思っちゃった。
もちろんちゃんと墓前で手を合わせたけれどね。
この通法寺跡から少し離れた所に源頼信と源義家の墓もあります。

源義家の墓。
小高い丘の上に、さらに一際高い位置にお墓がありました。
イノシシ注意って看板があって、人っ子一人居らずちょっと怖かった(苦笑)
源頼信の墓はここから更に歩くようで、こっちまでは行きませんでした。
往年には河内源氏の本拠地として栄えたのでしょうけれど、今ではひっそりとしたというか殆ど人に出会わないくらいに静かな所でした。
自転車のブレーキ音が酷くて辺りに響き渡り、あまりの恥ずかしさに下りも押して歩いたほど静かだった…。
近鉄南大阪線の上ノ太子駅で下車して、駅前のレンタサイクルで自転車を借りて散策。
そこそこ乗客が降りたなって思ったのに、私以外はみんなみかん狩り目当ての人だった。
みかん狩りってこの時期なんですね…知らなかった。
思っていた以上のアップダウンと道の細さに、何度も停まっては地図を確認する作業の繰り返し。
多分ここだろうと思った穴穂部皇子御廟も、案内板が無かったので思わずスルー。
最初に向かったのは壺井八幡宮。

このあたりは壺井の香炉峰といわれ、河内源氏発祥地として知られており、平安時代中期の寛仁4年(1020年)、源頼信が河内守に任官してこの地に私邸を営み、康平7年(1064年)に前九年の役を平定した頼義(頼信の子)が石清水の神を私邸の東側に勧請したのが本宮の起源である。
また、左側にある壺井権現社、源義時(義家の五男)が河内源氏の祖神として天仁2年(1109年)に創祀したものである。
現社殿は、両社とも元禄14年(1701年)に徳川綱吉の命で柳澤吉保が再建したものである。(案内板より)

こっちが壺井権現社ですね。
この後通法寺跡へ。

羽曳野市壺井は河内源氏の発祥地として知られていますが、この壺井通法寺は、長久4年(1043年)に河内国司であった源頼信が小堂を建てたことからはじまります。
前九年の役(1051~62年)の時、東北地方で活躍した源頼義が浄土教に帰依し阿弥陀仏を本尊としてから河内源氏の菩提寺となり源氏の隆栄と共に栄えました。
南北朝時代(約700年前)には、戦火にあい建物を焼失しましたが、江戸時代になって源氏の子孫・多田義直が5代将軍綱吉に願い出て、柳沢吉保らが普請奉行となって再建しました。
ところが、明治時代の廃仏毀釈により現在のように山門・鐘楼などを残すだけとなってしまいました。(案内板より)
この通法寺跡に源頼義の墓があります。

源頼義っていったら、藤原経清を錆刀で鋸引きにした人よ!
ちょっと心の中でギリッとか思っちゃった。
もちろんちゃんと墓前で手を合わせたけれどね。
この通法寺跡から少し離れた所に源頼信と源義家の墓もあります。

源義家の墓。
小高い丘の上に、さらに一際高い位置にお墓がありました。
イノシシ注意って看板があって、人っ子一人居らずちょっと怖かった(苦笑)
源頼信の墓はここから更に歩くようで、こっちまでは行きませんでした。
往年には河内源氏の本拠地として栄えたのでしょうけれど、今ではひっそりとしたというか殆ど人に出会わないくらいに静かな所でした。
自転車のブレーキ音が酷くて辺りに響き渡り、あまりの恥ずかしさに下りも押して歩いたほど静かだった…。