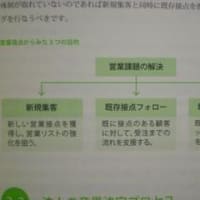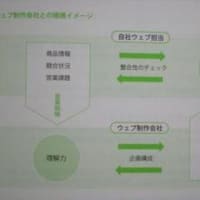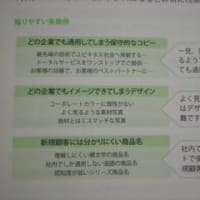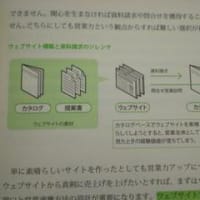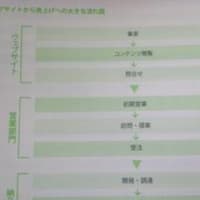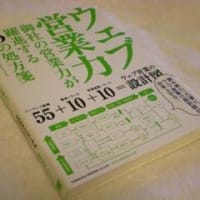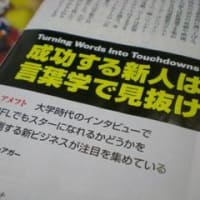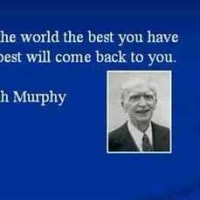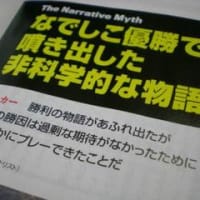「考えるということは、本来個人的になされる作業なのである」
著者/立花 隆 出版社名/講談社 777円
日本を代表する知識人の一人、立花隆氏の著作です。
「田中角栄研究~その金脈と人脈」では、当時強大な権勢を誇っていた田中角栄の“錬金術”について大手マスコミが報道しない事実を膨大な取材によって積み上げ、ついに失脚にまで追い込んだのは特筆に値すると思います。
そんな立花氏が、自分の経験も踏まえ、情報の取り方、情報の取捨選択の仕方等を伝授してくれるのが、この『「知」のソフトウェア 』です。
インターネットの急速な発達によって、この本が発行された当時に比べて外的環境は大きく変わりましたが、“知的生産術の本質”は変わっていません。
本書で著者は、こう語っています。
「考えるということは、本来個人的になされる作業なのである」
重い言葉だと思います。
著者のプロフィールを以下に記します。
◆立花隆
立花 隆(たちばな たかし、本名:橘 隆志 1940年5月28日 - )は、日本のジャーナリスト・ノンフィクション作家・評論家。
◆来歴
1940年 長崎県長崎市に生まれる。父は長崎の女学校教師で後に編集者を務め、母は羽仁もと子の信奉者で、クリスチャンの家庭。戦前の右翼思想家・橘孝三郎は、父のいとこに当たる。
1942年(昭和17年) 父が文部省職員として北京の師範学校副校長となったため、一家で中国へ渡る。
1946年 6歳の時、引揚げで日本へ戻り、一時母方の茨城郡那珂西に住み、のちに父の郷里茨城県水戸市に移る。
茨城師範学校(茨城大学)付属小学校、中学校を経て、1956年(昭和31年)に水戸一高、千葉県に移ったため東京都立上野高等学校への転入を経る。小学校時代から読書に熱中し、自らの読書遍歴を記した文章を残している(『ぼくはこんな本を読んできた』で紹介)また、中学時代は陸上競技にも熱中。俳優の梅宮辰夫・モータージャーナリストの徳大寺有恒は同級生で、三人とも陸上競技選手であり優秀な力を持っていた。
1959年(昭和34年) 理系志望であったが色弱のために諦め、東京大学文科二類へ入学。在学中は小説や詩も書き、イギリスで開かれた反核会議にも参加。卒論はフランスの哲学者メーヌ・ド・ビラン。
1964年 文学部仏文科を卒業し、文藝春秋に入社、「週刊文春」に配属されるが、もっともやりたくない仕事であるプロ野球の取材をさせられたことから退職を決意。2年後のことである。
1967年(昭和42年) 東京大学文学部哲学科に学士入学。哲学科在学途中から文筆活動に勤しむようになり、ジャーナリストとして活躍する。創刊時の雑誌『諸君!』に「生物学革命」、「宇宙船地球号」「石油」などのテーマをノンフィクションや評論を書く。
1968年 「立花隆」のペンネームで文藝春秋増刊号「素手でのし上がった男たち」を発表。『諸君!』の初代編集長田中健五(のちの文藝春秋編集長)との交友が後の「角栄研究」に繋がる。
1970年 東京大学を中退。
1972年 イスラエルをはじめ中東各地、ヨーロッパ諸国を放浪する。また一時期バーも経営していた。
1974年(昭和49年) 『文藝春秋』に「田中角栄研究~その金脈と人脈」を発表。大手マスメディアの警察の発表を元にした記事とは一線を画し、自らの足で膨大な資料をかき集めた詳細な記事は大きな反響を呼び、田中退陣のきっかけを作ったとされる。文藝春秋は角栄批判から手を引くが、その後も発表場所を変え、折に触れて田中金脈問題を取り上げ、ロッキード事件で田中が逮捕された後は東京地裁での同事件の公判を欠かさず傍聴し、一審判決まで『朝日ジャーナル』誌に傍聴記を連載した。また同誌上で「ロッキード裁判批判を斬る」を連載し、俵孝太郎、渡部昇一ら田中角栄擁護論者を“イカサマ論法にして無知”と批判した。なお、渡部は後年、立花のことを高く評価するコラムを雑誌に発表している。朝日ジャーナルでの担当者は筑紫哲也。以後しばし筑紫の番組に出演するなど公私ともに親交がある。
1976年(昭和51年)には『文藝春秋』に『日本共産党の研究』を連載。これに対して党側が組織的な反立花キャンペーンを展開して反論し、大論争に発展する。また、「総合商社」、「農協」、「中核・革マル」、脳死問題など巨大な権力、組織の徹底究明のジャーナリズム活動を行う。
政治関係の記事を執筆する一方で、『諸君!』時代に書いていたサイエンス関係のテーマにも手を広げ、1981年には『中央公論』に「宇宙からの帰還」を発表。平凡社『アニマ』に連載された「サル学の現在」、ノーベル賞受賞者利根川進との対談『精神と物質』、『科学朝日』に連載された「サイエンス・ナウ」「電脳進化論」「脳を究める」、など数多くのテーマを手がける。また、NHKやTBSなどにおいてドキュメンタリー番組制作にも携わり、連動した臨死体験などの著作もある。これらの業績で1983年に菊池寛賞、1998年に司馬遼太郎賞をそれぞれ受賞。
1995年公開のアニメ映画、「耳をすませば」で主人公の父親役を演じ、作品の話題作りに貢献。
1996年 - 1998年には、東京大学教養学部で「立花ゼミ」を主催。ゼミは2005年に再開され、現在も続いている。立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科教授も務める。
1998年 神戸連続児童殺傷事件の検事調書を文藝春秋社が入手。これを雑誌に掲載するか否かについて当時の編集長平尾隆弘から緊急に相談を受け、「どんなことがあっても掲載すべき」との判断を下す。少年法61条に抵触するか否かについては、この法令が報道することを禁じているのは、あくまで、本人のアイデンティティを推知できるような要素であって、それ以上ではない-従って、この調書を載せること自体は少年法61条に抵触することは全くないと判断。掲載を推薦し「文藝春秋」(1998年3月特別号)に掲載された。立花隆自身バッシングが起こることは確実と予想してのことであった。
2007年12月に膀胱癌の手術を受け、『文藝春秋』(2008年4月号)に手記「僕はがんを手術した」を発表した。
◆人物
幼少期より一貫して人の生と死の問題に関心を持ってきた。あるいは人間存在の本質に興味を抱き続けてきた。そのため、他人の目には一見すると結びつかないような多方面のことをテーマに考え、書いてきた。したがって、その仕事ぶりは行き当たりばったりで大きなグランドデザインはないようにも見える。これについて立花自身は次のように述懐している。「人生というのは、いつでも予期せぬことに満ち満ちている。計画など立てたところで、計画通りの人生など生きられるはずがないのである。もし自分の計画通りの人生を生きた人がいるとしたら、それはたぶん、つまらない人生を生きた人なのだ…(略)」(『生、死、神秘体験』)。
前述のように、立花の関心の中心には生と死の問題があると言えるかもしれない。臨死体験、脳死、異常性格者、超能力など、およそアカデミックではなかった分野にまで科学的な視点から切り込んでいくことも多く、したがって一部ではオカルト主義者との評価も生まれた。
猫好きで、東京都文京区小石川に「猫ビル」(巨大な猫の顔が壁に描かれている)の別名で呼ばれる地上三階地下一階建の事務所兼書庫を保有。数万冊にも上る蔵書を抱える。地下にはワインセラーを設置しており、無類のワイン好きである。猫ビルについては、妹尾河童が「ぼくはこんな本を読んできた」で図解で紹介している。
兄は元朝日新聞社監査役の橘弘道(たちばな ひろみち、1938年 - )。
◆エピソード
文藝春秋社「週刊文春」の記者時代、プロ野球にだけは全く興味が無いため、その関係の仕事だけはさせないでほしいと宣言したにもかかわらず「あの野郎は生意気だ」ということで、見せしめにプロ野球の取材を1週間にもわたってさせられ、退社する決意を固めた。
自分がやりたくもないことを上司の命令というだけでやらねばならない事実に我慢ができなかった。ちなみに、プロ野球には昔も現在も一切の関心はなく、「なぜあんなものに多くの人が夢中になれるのか全く理解できない」と自著に記している。
(※ウィキペディアより抜粋)
 知的刺激に富む一冊
知的刺激に富む一冊 ブ◯◯◯で救われるのは芸人だけではない
ブ◯◯◯で救われるのは芸人だけではない 内容が物足りません
内容が物足りません 知的生産活動の名著のひとつ。何をしたら無駄になるかも実体験を通して教えてくれる本。
知的生産活動の名著のひとつ。何をしたら無駄になるかも実体験を通して教えてくれる本。 アウトプットとインプットの間を見つめて
アウトプットとインプットの間を見つめて
この商品を買った人は、こんな本も買っています☆
▼
 ■中学生・高校生向け■
■中学生・高校生向け■ 認知心理学に基づく読み・書きの本
認知心理学に基づく読み・書きの本
 勉強法というより学問への入門書
勉強法というより学問への入門書
 「教えられる側」よりも「教える側」が読む本じゃないかな。
「教えられる側」よりも「教える側」が読む本じゃないかな。
 間違った知識を、正しい知識に修正する方法が書かれた貴重な本。
間違った知識を、正しい知識に修正する方法が書かれた貴重な本。
著者/立花 隆 出版社名/講談社 777円
日本を代表する知識人の一人、立花隆氏の著作です。
「田中角栄研究~その金脈と人脈」では、当時強大な権勢を誇っていた田中角栄の“錬金術”について大手マスコミが報道しない事実を膨大な取材によって積み上げ、ついに失脚にまで追い込んだのは特筆に値すると思います。
そんな立花氏が、自分の経験も踏まえ、情報の取り方、情報の取捨選択の仕方等を伝授してくれるのが、この『「知」のソフトウェア 』です。
インターネットの急速な発達によって、この本が発行された当時に比べて外的環境は大きく変わりましたが、“知的生産術の本質”は変わっていません。
本書で著者は、こう語っています。
「考えるということは、本来個人的になされる作業なのである」
重い言葉だと思います。
著者のプロフィールを以下に記します。
◆立花隆
立花 隆(たちばな たかし、本名:橘 隆志 1940年5月28日 - )は、日本のジャーナリスト・ノンフィクション作家・評論家。
◆来歴
1940年 長崎県長崎市に生まれる。父は長崎の女学校教師で後に編集者を務め、母は羽仁もと子の信奉者で、クリスチャンの家庭。戦前の右翼思想家・橘孝三郎は、父のいとこに当たる。
1942年(昭和17年) 父が文部省職員として北京の師範学校副校長となったため、一家で中国へ渡る。
1946年 6歳の時、引揚げで日本へ戻り、一時母方の茨城郡那珂西に住み、のちに父の郷里茨城県水戸市に移る。
茨城師範学校(茨城大学)付属小学校、中学校を経て、1956年(昭和31年)に水戸一高、千葉県に移ったため東京都立上野高等学校への転入を経る。小学校時代から読書に熱中し、自らの読書遍歴を記した文章を残している(『ぼくはこんな本を読んできた』で紹介)また、中学時代は陸上競技にも熱中。俳優の梅宮辰夫・モータージャーナリストの徳大寺有恒は同級生で、三人とも陸上競技選手であり優秀な力を持っていた。
1959年(昭和34年) 理系志望であったが色弱のために諦め、東京大学文科二類へ入学。在学中は小説や詩も書き、イギリスで開かれた反核会議にも参加。卒論はフランスの哲学者メーヌ・ド・ビラン。
1964年 文学部仏文科を卒業し、文藝春秋に入社、「週刊文春」に配属されるが、もっともやりたくない仕事であるプロ野球の取材をさせられたことから退職を決意。2年後のことである。
1967年(昭和42年) 東京大学文学部哲学科に学士入学。哲学科在学途中から文筆活動に勤しむようになり、ジャーナリストとして活躍する。創刊時の雑誌『諸君!』に「生物学革命」、「宇宙船地球号」「石油」などのテーマをノンフィクションや評論を書く。
1968年 「立花隆」のペンネームで文藝春秋増刊号「素手でのし上がった男たち」を発表。『諸君!』の初代編集長田中健五(のちの文藝春秋編集長)との交友が後の「角栄研究」に繋がる。
1970年 東京大学を中退。
1972年 イスラエルをはじめ中東各地、ヨーロッパ諸国を放浪する。また一時期バーも経営していた。
1974年(昭和49年) 『文藝春秋』に「田中角栄研究~その金脈と人脈」を発表。大手マスメディアの警察の発表を元にした記事とは一線を画し、自らの足で膨大な資料をかき集めた詳細な記事は大きな反響を呼び、田中退陣のきっかけを作ったとされる。文藝春秋は角栄批判から手を引くが、その後も発表場所を変え、折に触れて田中金脈問題を取り上げ、ロッキード事件で田中が逮捕された後は東京地裁での同事件の公判を欠かさず傍聴し、一審判決まで『朝日ジャーナル』誌に傍聴記を連載した。また同誌上で「ロッキード裁判批判を斬る」を連載し、俵孝太郎、渡部昇一ら田中角栄擁護論者を“イカサマ論法にして無知”と批判した。なお、渡部は後年、立花のことを高く評価するコラムを雑誌に発表している。朝日ジャーナルでの担当者は筑紫哲也。以後しばし筑紫の番組に出演するなど公私ともに親交がある。
1976年(昭和51年)には『文藝春秋』に『日本共産党の研究』を連載。これに対して党側が組織的な反立花キャンペーンを展開して反論し、大論争に発展する。また、「総合商社」、「農協」、「中核・革マル」、脳死問題など巨大な権力、組織の徹底究明のジャーナリズム活動を行う。
政治関係の記事を執筆する一方で、『諸君!』時代に書いていたサイエンス関係のテーマにも手を広げ、1981年には『中央公論』に「宇宙からの帰還」を発表。平凡社『アニマ』に連載された「サル学の現在」、ノーベル賞受賞者利根川進との対談『精神と物質』、『科学朝日』に連載された「サイエンス・ナウ」「電脳進化論」「脳を究める」、など数多くのテーマを手がける。また、NHKやTBSなどにおいてドキュメンタリー番組制作にも携わり、連動した臨死体験などの著作もある。これらの業績で1983年に菊池寛賞、1998年に司馬遼太郎賞をそれぞれ受賞。
1995年公開のアニメ映画、「耳をすませば」で主人公の父親役を演じ、作品の話題作りに貢献。
1996年 - 1998年には、東京大学教養学部で「立花ゼミ」を主催。ゼミは2005年に再開され、現在も続いている。立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科教授も務める。
1998年 神戸連続児童殺傷事件の検事調書を文藝春秋社が入手。これを雑誌に掲載するか否かについて当時の編集長平尾隆弘から緊急に相談を受け、「どんなことがあっても掲載すべき」との判断を下す。少年法61条に抵触するか否かについては、この法令が報道することを禁じているのは、あくまで、本人のアイデンティティを推知できるような要素であって、それ以上ではない-従って、この調書を載せること自体は少年法61条に抵触することは全くないと判断。掲載を推薦し「文藝春秋」(1998年3月特別号)に掲載された。立花隆自身バッシングが起こることは確実と予想してのことであった。
2007年12月に膀胱癌の手術を受け、『文藝春秋』(2008年4月号)に手記「僕はがんを手術した」を発表した。
◆人物
幼少期より一貫して人の生と死の問題に関心を持ってきた。あるいは人間存在の本質に興味を抱き続けてきた。そのため、他人の目には一見すると結びつかないような多方面のことをテーマに考え、書いてきた。したがって、その仕事ぶりは行き当たりばったりで大きなグランドデザインはないようにも見える。これについて立花自身は次のように述懐している。「人生というのは、いつでも予期せぬことに満ち満ちている。計画など立てたところで、計画通りの人生など生きられるはずがないのである。もし自分の計画通りの人生を生きた人がいるとしたら、それはたぶん、つまらない人生を生きた人なのだ…(略)」(『生、死、神秘体験』)。
前述のように、立花の関心の中心には生と死の問題があると言えるかもしれない。臨死体験、脳死、異常性格者、超能力など、およそアカデミックではなかった分野にまで科学的な視点から切り込んでいくことも多く、したがって一部ではオカルト主義者との評価も生まれた。
猫好きで、東京都文京区小石川に「猫ビル」(巨大な猫の顔が壁に描かれている)の別名で呼ばれる地上三階地下一階建の事務所兼書庫を保有。数万冊にも上る蔵書を抱える。地下にはワインセラーを設置しており、無類のワイン好きである。猫ビルについては、妹尾河童が「ぼくはこんな本を読んできた」で図解で紹介している。
兄は元朝日新聞社監査役の橘弘道(たちばな ひろみち、1938年 - )。
◆エピソード
文藝春秋社「週刊文春」の記者時代、プロ野球にだけは全く興味が無いため、その関係の仕事だけはさせないでほしいと宣言したにもかかわらず「あの野郎は生意気だ」ということで、見せしめにプロ野球の取材を1週間にもわたってさせられ、退社する決意を固めた。
自分がやりたくもないことを上司の命令というだけでやらねばならない事実に我慢ができなかった。ちなみに、プロ野球には昔も現在も一切の関心はなく、「なぜあんなものに多くの人が夢中になれるのか全く理解できない」と自著に記している。
(※ウィキペディアより抜粋)
「知」のソフトウェア (講談社現代新書 (722))
posted with amazlet at 09.09.15
立花 隆 講談社 売り上げランキング: 22823
おすすめ度の平均: 

 知的刺激に富む一冊
知的刺激に富む一冊 ブ◯◯◯で救われるのは芸人だけではない
ブ◯◯◯で救われるのは芸人だけではない 内容が物足りません
内容が物足りません 知的生産活動の名著のひとつ。何をしたら無駄になるかも実体験を通して教えてくれる本。
知的生産活動の名著のひとつ。何をしたら無駄になるかも実体験を通して教えてくれる本。 アウトプットとインプットの間を見つめて
アウトプットとインプットの間を見つめてこの商品を買った人は、こんな本も買っています☆
▼
読む心・書く心―文章の心理学入門 (心理学ジュニアライブラリ)
posted with amazlet at 09.10.20
秋田 喜代美 北大路書房 売り上げランキング: 44688
おすすめ度の平均: 

 ■中学生・高校生向け■
■中学生・高校生向け■ 認知心理学に基づく読み・書きの本
認知心理学に基づく読み・書きの本じょうずな勉強法―こうすれば好きになる (心理学ジュニアライブラリ)
posted with amazlet at 09.10.20
麻柄 啓一
北大路書房
売り上げランキング: 18352
北大路書房
売り上げランキング: 18352
おすすめ度の平均: 

 勉強法というより学問への入門書
勉強法というより学問への入門書 「教えられる側」よりも「教える側」が読む本じゃないかな。
「教えられる側」よりも「教える側」が読む本じゃないかな。 間違った知識を、正しい知識に修正する方法が書かれた貴重な本。
間違った知識を、正しい知識に修正する方法が書かれた貴重な本。