
全体についての説明と、登場人物名の史実との対応一覧は、
「序段」ページにありますよ。
三段目に出てきた、塩治判官(えんや はんがん 浅野内匠守ですよ)の家来の若侍、早野勘平(はやの かんぺい)くんが
この段の主人公です。
恋人の腰元お軽ちゃんにさそわれたので、つい職場放棄していたら、その間に主君の判官が城中で刃傷沙汰、
お城の外でフラフラしていた勘平は城中にも入れず、塩治(えんや)のお屋敷にも戻れず、切腹しようとしますが思いとどまり、
お軽ちゃんの実家に身を寄せて、折を見てお詫びをしてみることにします。
という経過は三段目で語られるのですが、現行、「通し上演」で出しても、三段目のこの勘平に関するくだりはおおむねカットされます。お軽ちゃんに誘われるあたりも含めて全部。
刃傷事件のあとにある「裏門外の場」も、「道行」の所作に変化してしまい、清元の歌うような文句で語られるようになったために、込み入った事情が聞き取りにくいです。
なのでこの五段目、何の説明もなく、イキナリ山の中に猟師が出てきて、それが塩治の浪人の早野勘平くんなのです。わかんねえよ。
ましてやああた、五、六段目だけ出すときなんてああた。
「これのどこが忠臣蔵なの?」と聞きたくなるのもムリはありません。
そういうわけで、申し訳ありませんが、↑のような事情です、お含みおき下さい。
今、勘平は山崎というところにいます。名前の通り山の中ですよ。
ここにあるお軽ちゃんの実家に身を寄せています。
お父さんは与一兵衛(よいちべえ)さんといいます。お百姓さんです。あまりお金持ちじゃありません。
勘平、生活費のために猟師をしていますよ。お侍だから銃器類や刃物の扱いは慣れてるしね。
山道です。夜です、真っ暗ですよ。季節は水無月、旧暦の6月ですから今だと7月ごろです。
折からの夕立に降られて火縄銃の火口(ほくち)をしめらせてしまった勘平、銃が撃てませんよ、通りかかった旅人に「火を貸してくれ」と頼みます。
よくみれば旅人は、塩治の家来、千崎弥五郎(せんざき やごろう)さんです。
ここからセリフのみのやりとりになりますが、かなり重要な事を言っているので聞き取れないと後で困ったことになります。
勘平は過去の失敗を取り戻したいと思っている。
チマタでほの聞く塩治浪人たちの討ち入り計画のウワサ、何とか仲間に入れてもらいたい。
千崎弥五郎に会ったのを幸い、「まぜて」と頼みますが、
千崎も外部の人間にそんな極秘事項をもらせませんよ、
弥五郎、「そんな計画はないが、死んだ判官様のために石塔を建立する計画があり、今金を集めている。
と、そんな表向きの計画に事寄せて「討ち入り資金集めてる」と暗に勘平に教えます。
勘平、なんとか金作ってみるから、と言います。
ふたりは分かれます。
ここまで前半です。「鉄砲渡し」と呼ばれる場です。
勘平が弥五郎に火を借りるとき、武器である鉄砲を渡して害意のない事を示す、その潔い態度からこの呼び名が付けられています。
後半、
「二つ玉」と呼ばれる場面です。
さてまあ、討ち入りのウワサは前々からあったわけで、勘平やお軽はなんとか資金の一部を調達して、それをお詫びの印として討ち入りに参加したいと思っていました。
暗い夜道を老人が歩いてきますよ、お軽のお父さんの与一兵衛です。
山の中のお百姓、まとまった百両とかのお金は作れませんよ、なので、色々考えて、婿の勘平には内緒で娘のお軽を祇園の茶屋に百両で売ったのです。
今契約がすんで、金を半分受け取って帰る途中です。
という事情を現行上演では与一兵衛さんが夜、真っ暗な山の中で独り言で語るのでちょっと不自然です。
と、
後ろの稲むらからイキナリ手が出て、与一兵衛さんが刺されて死にますよ。刺したのは浪人風の若い男です。
与一兵衛の独り言を聞いて、金欲しさに刺したのです。
死体から財布をとって手探りで金を数えます。「五十両」。
よろこぶ男。
というのが現行演出です。
一応書くと、もとのカタチは、
夜道を歩く与一兵衛に声をかけて「夜道は危ないぞ」と連れだって行こうとする若い男。
強盗に決まっているのでなんとか追い払おうとする与一兵衛ですが、刺されて金を取られます。
婿の出世ために娘を売った大事な金、と事情を話して返してもらおうとする与一兵衛ですが、
男「俺を恨むな金が敵(かたき)じゃ」と言って与一兵衛を刺し殺します。
このほうが自然だしわかりやすいです。明治ごろまではこの流れが残っていたはずです。文楽はいまもこうです。
もとの演出の定九郎は、上方の田舎の荒くれ者らしい、みすぼらしい身なりなのですが、
現行演出ですと黒紋付で着流しの、いかにも浪人ものらしい衣装です。
顔も白塗りで二枚目風になり、
死ぬまでの動きもスタイリッシュに計算されています。
この演出は、江戸中期に2代目中村仲蔵(なかむら なかぞう)が考え付き、完成させました。画期的でした。
ただ、非常に見栄えもよく、たのしいこの演出ですが、「仮名手本忠臣蔵」のストーリーを客が把握していることが前提となる、ある意味サービス場面です。
ストーリーをちゃんと知らない今日びの客にはわかりにくくて逆効果な部分もあるとは思います。
まあとにかく金を奪ってニンマリする男、斧定九郎(おの さだくろう)。
ここに正体不明のカブリモノの生き物が花道から走って来ます。よける定九郎、次の瞬間、バンと音がして定九郎のけぞり、血を吹いて倒れます。
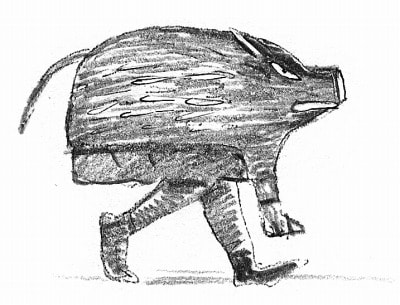
何が起きたのかというと、走ってきたのはイノシシです。この「イノシシに見えね~~」さ加減は江戸時代からネタにされているので、もう「イノシシが出るぞ」とココロの準備をして、そのつもりで見る以外に仕方ありません。
イノシシは、早野勘平に撃たれて追われていたのでした。勘平が撃った2発目の玉が、定九郎に当たったのです。
死ぬ定九郎。
♪心地よしとぞ 見えにける~ と浄瑠璃。
あと、この「斧 定九郎」という男は全段読んでもここにしか出ないのですが、四段目に出てきた、塩治判官の家来で性格が悪いほうの、「斧 九太夫(おの くだゆう)」の息子です。
あまりに素行が悪いので勘当されて、こんな山のなかで追いはぎをしているのです。
昔も今もこういうキレた若者はいたのですねー。恐ろしい話です。
与一兵衛が死ぬところからここまで、セリフらしいセリフもなく、どんどん話が展開するので予備知識がないとおそらく意味不明ですよ。
ていうか浄瑠璃が事細かにナレーションしているから本当は問題ないのです。聞き取れないかたが多いのはしかたありません。
まあ、こんな展開ですよ。
イノシシを追って出てきた勘平、
ところで今は夜です。山の中、雨が降ったり止んだりの天気なので月も出ず、真っ暗ですよ。街灯なんかないですから。
何か倒れているのでイノシシだと思い、獲物ゲット、とよろこんで近寄る勘平。でもよくさわってみると倒れているのは人間ですよ、ぎゃああ。
そうこうするうちにサイフに気付き、天の恵みに違いないと、金を持ってて走り去ります。
五段目ここまでです。
本来は六段目への前フリのための場面なのですが、何が起きるのかあらかじめ全て確認してから見に行かないと意味わからないので、
現代では「前フリ説明をする」という機能は果たしていません。
そもそもこの段自体が、説明がないと意味わからないです。
今はここは、細かい動きに至るまで段取りが決まっている、歌舞伎の中でもトップレベルの完成度である様式美を楽しむだけの段です。
本当は夏の夜、雨が降っている山道のむせかえるような季節感、何が飛び出してくるかわからない暗闇の不便さや恐怖、
など、いろいろと感じたいところなのですが、
現代人には、ムリ。風情ねえなあ。
とりあえず、この段で何がおきたかはアタマに入れていってください。六段目で困るから。
タイトルの「二つ玉」というのは鉄砲の呼び名です。2連発銃のことです。
バンバンと続けて2発出るのではなく、一度火縄に点火すると2回撃てる構造、ということです。
1発目はイノシシに当たりましたがとどめはさせず。
そして2発目は…。
というようなデンジャラスな緊張を予感させるタイトルです。
「2発の弾丸」みたいなサスペンス風のタイトルだと思えばわかりやすいかもですね。
=六段目へ=
=全段もくじ=
=50音索引に戻る=
「序段」ページにありますよ。
三段目に出てきた、塩治判官(えんや はんがん 浅野内匠守ですよ)の家来の若侍、早野勘平(はやの かんぺい)くんが
この段の主人公です。
恋人の腰元お軽ちゃんにさそわれたので、つい職場放棄していたら、その間に主君の判官が城中で刃傷沙汰、
お城の外でフラフラしていた勘平は城中にも入れず、塩治(えんや)のお屋敷にも戻れず、切腹しようとしますが思いとどまり、
お軽ちゃんの実家に身を寄せて、折を見てお詫びをしてみることにします。
という経過は三段目で語られるのですが、現行、「通し上演」で出しても、三段目のこの勘平に関するくだりはおおむねカットされます。お軽ちゃんに誘われるあたりも含めて全部。
刃傷事件のあとにある「裏門外の場」も、「道行」の所作に変化してしまい、清元の歌うような文句で語られるようになったために、込み入った事情が聞き取りにくいです。
なのでこの五段目、何の説明もなく、イキナリ山の中に猟師が出てきて、それが塩治の浪人の早野勘平くんなのです。わかんねえよ。
ましてやああた、五、六段目だけ出すときなんてああた。
「これのどこが忠臣蔵なの?」と聞きたくなるのもムリはありません。
そういうわけで、申し訳ありませんが、↑のような事情です、お含みおき下さい。
今、勘平は山崎というところにいます。名前の通り山の中ですよ。
ここにあるお軽ちゃんの実家に身を寄せています。
お父さんは与一兵衛(よいちべえ)さんといいます。お百姓さんです。あまりお金持ちじゃありません。
勘平、生活費のために猟師をしていますよ。お侍だから銃器類や刃物の扱いは慣れてるしね。
山道です。夜です、真っ暗ですよ。季節は水無月、旧暦の6月ですから今だと7月ごろです。
折からの夕立に降られて火縄銃の火口(ほくち)をしめらせてしまった勘平、銃が撃てませんよ、通りかかった旅人に「火を貸してくれ」と頼みます。
よくみれば旅人は、塩治の家来、千崎弥五郎(せんざき やごろう)さんです。
ここからセリフのみのやりとりになりますが、かなり重要な事を言っているので聞き取れないと後で困ったことになります。
勘平は過去の失敗を取り戻したいと思っている。
チマタでほの聞く塩治浪人たちの討ち入り計画のウワサ、何とか仲間に入れてもらいたい。
千崎弥五郎に会ったのを幸い、「まぜて」と頼みますが、
千崎も外部の人間にそんな極秘事項をもらせませんよ、
弥五郎、「そんな計画はないが、死んだ判官様のために石塔を建立する計画があり、今金を集めている。
と、そんな表向きの計画に事寄せて「討ち入り資金集めてる」と暗に勘平に教えます。
勘平、なんとか金作ってみるから、と言います。
ふたりは分かれます。
ここまで前半です。「鉄砲渡し」と呼ばれる場です。
勘平が弥五郎に火を借りるとき、武器である鉄砲を渡して害意のない事を示す、その潔い態度からこの呼び名が付けられています。
後半、
「二つ玉」と呼ばれる場面です。
さてまあ、討ち入りのウワサは前々からあったわけで、勘平やお軽はなんとか資金の一部を調達して、それをお詫びの印として討ち入りに参加したいと思っていました。
暗い夜道を老人が歩いてきますよ、お軽のお父さんの与一兵衛です。
山の中のお百姓、まとまった百両とかのお金は作れませんよ、なので、色々考えて、婿の勘平には内緒で娘のお軽を祇園の茶屋に百両で売ったのです。
今契約がすんで、金を半分受け取って帰る途中です。
という事情を現行上演では与一兵衛さんが夜、真っ暗な山の中で独り言で語るのでちょっと不自然です。
と、
後ろの稲むらからイキナリ手が出て、与一兵衛さんが刺されて死にますよ。刺したのは浪人風の若い男です。
与一兵衛の独り言を聞いて、金欲しさに刺したのです。
死体から財布をとって手探りで金を数えます。「五十両」。
よろこぶ男。
というのが現行演出です。
一応書くと、もとのカタチは、
夜道を歩く与一兵衛に声をかけて「夜道は危ないぞ」と連れだって行こうとする若い男。
強盗に決まっているのでなんとか追い払おうとする与一兵衛ですが、刺されて金を取られます。
婿の出世ために娘を売った大事な金、と事情を話して返してもらおうとする与一兵衛ですが、
男「俺を恨むな金が敵(かたき)じゃ」と言って与一兵衛を刺し殺します。
このほうが自然だしわかりやすいです。明治ごろまではこの流れが残っていたはずです。文楽はいまもこうです。
もとの演出の定九郎は、上方の田舎の荒くれ者らしい、みすぼらしい身なりなのですが、
現行演出ですと黒紋付で着流しの、いかにも浪人ものらしい衣装です。
顔も白塗りで二枚目風になり、
死ぬまでの動きもスタイリッシュに計算されています。
この演出は、江戸中期に2代目中村仲蔵(なかむら なかぞう)が考え付き、完成させました。画期的でした。
ただ、非常に見栄えもよく、たのしいこの演出ですが、「仮名手本忠臣蔵」のストーリーを客が把握していることが前提となる、ある意味サービス場面です。
ストーリーをちゃんと知らない今日びの客にはわかりにくくて逆効果な部分もあるとは思います。
まあとにかく金を奪ってニンマリする男、斧定九郎(おの さだくろう)。
ここに正体不明のカブリモノの生き物が花道から走って来ます。よける定九郎、次の瞬間、バンと音がして定九郎のけぞり、血を吹いて倒れます。
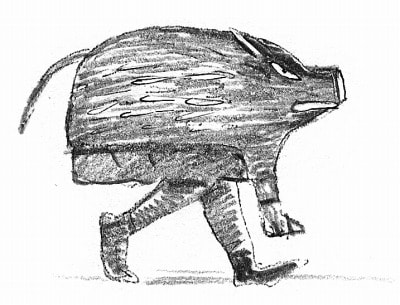
何が起きたのかというと、走ってきたのはイノシシです。この「イノシシに見えね~~」さ加減は江戸時代からネタにされているので、もう「イノシシが出るぞ」とココロの準備をして、そのつもりで見る以外に仕方ありません。
イノシシは、早野勘平に撃たれて追われていたのでした。勘平が撃った2発目の玉が、定九郎に当たったのです。
死ぬ定九郎。
♪心地よしとぞ 見えにける~ と浄瑠璃。
あと、この「斧 定九郎」という男は全段読んでもここにしか出ないのですが、四段目に出てきた、塩治判官の家来で性格が悪いほうの、「斧 九太夫(おの くだゆう)」の息子です。
あまりに素行が悪いので勘当されて、こんな山のなかで追いはぎをしているのです。
昔も今もこういうキレた若者はいたのですねー。恐ろしい話です。
与一兵衛が死ぬところからここまで、セリフらしいセリフもなく、どんどん話が展開するので予備知識がないとおそらく意味不明ですよ。
ていうか浄瑠璃が事細かにナレーションしているから本当は問題ないのです。聞き取れないかたが多いのはしかたありません。
まあ、こんな展開ですよ。
イノシシを追って出てきた勘平、
ところで今は夜です。山の中、雨が降ったり止んだりの天気なので月も出ず、真っ暗ですよ。街灯なんかないですから。
何か倒れているのでイノシシだと思い、獲物ゲット、とよろこんで近寄る勘平。でもよくさわってみると倒れているのは人間ですよ、ぎゃああ。
そうこうするうちにサイフに気付き、天の恵みに違いないと、金を持ってて走り去ります。
五段目ここまでです。
本来は六段目への前フリのための場面なのですが、何が起きるのかあらかじめ全て確認してから見に行かないと意味わからないので、
現代では「前フリ説明をする」という機能は果たしていません。
そもそもこの段自体が、説明がないと意味わからないです。
今はここは、細かい動きに至るまで段取りが決まっている、歌舞伎の中でもトップレベルの完成度である様式美を楽しむだけの段です。
本当は夏の夜、雨が降っている山道のむせかえるような季節感、何が飛び出してくるかわからない暗闇の不便さや恐怖、
など、いろいろと感じたいところなのですが、
現代人には、ムリ。風情ねえなあ。
とりあえず、この段で何がおきたかはアタマに入れていってください。六段目で困るから。
タイトルの「二つ玉」というのは鉄砲の呼び名です。2連発銃のことです。
バンバンと続けて2発出るのではなく、一度火縄に点火すると2回撃てる構造、ということです。
1発目はイノシシに当たりましたがとどめはさせず。
そして2発目は…。
というようなデンジャラスな緊張を予感させるタイトルです。
「2発の弾丸」みたいなサスペンス風のタイトルだと思えばわかりやすいかもですね。
=六段目へ=
=全段もくじ=
=50音索引に戻る=




















さて、重箱の隅で恐縮ですが、塩「冶」ですよ?! 「冶金」で「やきん」です! (合金とかの技術ですね)
とは言え、管理人さまのお力を考えますと、貴重な執筆能力は新しい記事を書くことに振り向けられるべきで、直すのは無駄なお手間なのでお勧め致しかねますが...
古典からは、どうしても逃げられませんね。また機会がありましたら、よろしくお願いします。お元気で
11段あるので時間がかかっちゃうかもしれませんが、がんばります。
新規作成もがんばりますー。
定九郎を現在のようにしたのは初代の仲蔵ではないでしょうか?