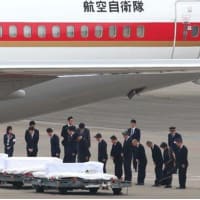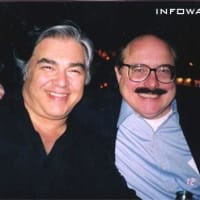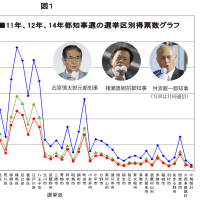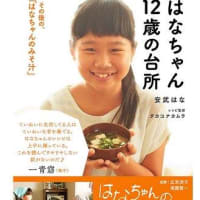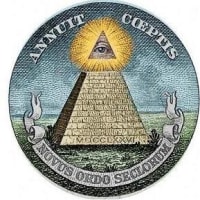菅首相はマニフェストにも書かれていない「TPP参加」を突然持ち出し今年の6月を目途に正式決定したいと言い出しました。
菅首相は「TPP参加」は日本の「第三の開国」に当たり「江戸幕府末期の第一の開国と同じように「鎖国状態の日本を世界に開くのだ」という説明をダボス会議で
表明しました。
菅首相の「TPP第三開国論」は歴史を真剣に学んだこともなく側近官僚や取り巻き学者の意見をそのまま受け売りした全くの「嘘」であり無知蒙昧の 典型です。
大手マスコミは今回もまた米国支配層と日本の経団連の利益のために、菅首相の「全くの嘘」を一切批判せず「TPPに参加しないと日本は世界の孤児 になる」などと
国民の無知につけ込んだ脅迫で世論操作を行っています。
菅首相が江戸幕府末期の「第一の開国」をあたかもポジティブで素晴らしいことのように言っているのは全くの間違いでなのです。
「第一の開国」は江戸幕府が欧米列強から隷従的・片務的な「不平等条約」を押し付けられて開国を強制されたものなのです。
「開国日本」は独立国家の当然の権利である関税自主権を奪われ手いました。
「開国日本」は領事裁判権を認めさせられ犯罪を犯した外国人を日本の法律で裁けない治外法権を強制されたのです。
1945年の敗戦の「第二の開国」では、米国によって「日米安保条約」という不平等軍事条約を強制され日本の国内に現在でも124の駐留米軍基地 と
毎年6000億円以上の駐留経費の負担を強いられているのです。
「第二の開国」で米国に強制された「日米地位協定」によって、犯罪を犯した米国軍人を日本の法律で裁けない治外法権状態が今でも続いているので す。
菅首相が日本の「第三の開国」を真剣に希求するのであれば、「日米安保条約」と「日米地位協定」を真っ先に破棄して日本の「独立」を図るべきなの です。
日本がTPPに参加すれば関税が撤廃されあらゆる保護規制が撤廃される結果、少数の米国と日本のグローバル企業が市場を独占し、日本の農業・林 業・漁業と
中小零細企業と地方は壊滅するでしょう。
日本がTPPに参加すれば、日本人の生活のあらゆる分野(雇用、所得、年金、医療、介護、社会福祉、家族関係など)に米国流の新自由主義=市場原 理主義が導入され、
今以上に貧富の差が拡大し分断された「大格差社会」が出現刷るでしょう。
日本がTPPに参加すれば、日本は米国の完全な植民地となるでしょう。
TPPはオバマ政権が作り出した米国による「非軍事による世界支配」の罠であり、日本は絶対に参加してはならないのです。
賢明な国民は菅首相と財界と大手マスコミの「嘘」に騙されてはいけません。
【参考記事】
▼ 異様な「TPP開国論」歴史の連続性を見抜け 内橋克人氏
2011年2月8日 内橋克人氏講演会
http://www.jacom.or.jp/tokusyu/2011/tokusyu110208-12482.php
むき出しの市場原理主義に対抗思潮を
TPPについて東京発マスコミの「開国」一辺倒論ぶりは異様なものです。例えば去年秋の日比谷での大規模な反対集会について1行も報道していませ ん
。
これに対して、地域社会に密着するジャーナリズムは違っておりまして、私が書いた『TPP開国論を問う』『市場原理主義 再び』といった反対論 を
大きく掲載しています。お手許に配ってあります資料をご覧ください(中国新聞、北海道新聞)。すでに崖っぷちに立たされている日本農業の背中をさ らに押す、
というような圧力が出てきた時、中央紙とはまるで違う対応をする。それがコミュニティ・ペーパーの特徴でもあるでしょう。
ともあれ、いまやTPPをめぐって「国論二分」の状況になってきました。
協同組合の中にもいまだTPPに関して態度を決めかねている方がいます。「まだ情報を収集中」などという、ある協同組合トップの方に私は率直に
「情報が集まった時にはもう手遅れですよ」と申し上げた。
菅直人首相は歴史上、幕末・明治を第一の開国、あたかも輝かしい開国であったかのごとく信じているようですが、蒙昧とはこのことをいうのでしょ う。
第一の開国こそは欧米列強への隷従的・片務的な「不平等条約」でした。相手国は一方的に関税を決め、日本は独立国家の当然の権利である関税自主権 さえ
奪われた。それから領事裁判権という名のもと、犯罪を犯した外国人を日本の法律で裁けない治外法権も強制されました。対等な関係における日本の 「開国」が
やっと実現したのは、第一の開国から60数年も経った第1次大戦後のことです。近代日本がいかに苦悶を迫られたか、それを菅氏はご存じない。
「開国」という「政治ことば」に秘められた大きな企みが人々を間違った方向へ導いていく。「規制緩和」「構造改革」がそうでした。
これに反対するものは「守旧派」と呼び、少数派として排除しましたが、今回も同じ構図です。「改革」とか「開国」とか、一見、ポジティブな響き の、
前向きの言葉の裏に潜む「政治ことば」の罠、その暗闇に目を注ぎながら言葉の真意を見抜いていかなければなりません。
「国を開く」などといいますが、その行き着くところ、実質はまさに「国を明け渡す」に等しい。「城を明け渡す」とは落城のことです。
光り輝く近代化というイメージ、その実態は?と問わなければなりません。「第一の開国」についての詳細はお手許の資料に詳述してあります。
◆“四つの異様”
TPPにつきまして事情はすでにご存じの通りです。シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイといった4カ国に始まる多国間協定への経 緯、
またこれにアメリカ、カナダなどが参加表明するに至ったそもそもの理由など、基礎的、常識的な事情は省略いたしまして、なぜいまアメリカは
「米主導のアジア圏」形成に向けて動き出したのか。TPPにかけるアメリカのしたたかな戦略性ということについて、考えを述べたいと思います。
昨年10月、米国際戦略問題研究所(CSIS)と日本経済新聞社共催のシンポジウムで前原誠司外相は「(日本の第1次産業の割合は)1.5%。
そのために(これを守るために)残り98.5%が犠牲になっている」と発言しました。場所も内容も不適切です。が、これを問題にするジャーナリズ ムは
皆無でした。
私はこれを「三つの異様」と呼び、第一に菅首相の開国論の異様、第二に前原発言の異様、そして第三に新聞・メディアの異様、
三つを揃えて批判の論拠を書きました。こうしたあり方になびく日本社会全体の異様、これを含みますと「四つの異様」となります。
ところで、CSISとはいったい何を研究するシンクタンクなのか。ワシントンのジョージタウン大学のなかにある。1960年代から長期間、
アメリカの世界戦略に携わってきたこのシンクタンクをめぐっては、さまざまな説がありますが、今日はその部分は控えておきましょう。
前原氏はこの機関と日本の大手マスコミとの共催シンポジウムの場で30分ほどの基調講演をし、そのなかで先程のような発言をした。
アメリカにとってはまさに「舌なめずり」したくなるような言葉です。
1990年代半ば、「多国間投資協定」(MAI)をめぐる大きな騒動がありました。
米国のクリントン政権がこの協定を“21 世紀における世界経済の憲法”とまで称して、多国間で資本、マネーに関する協定を結ぼうと
画策していたのです。
市民、NGOが気付いたときには、すでに、通商交渉に関して議会の承認なく大統領の一存ですべてを決めることのできる「ファストトラック」
という手続き開始の直前。物事は進んでおりました。
以後、全世界1000を超えるNGОが猛烈な反対運動を展開して結局、クリントン大統領は構想の撤回に追い込まれた。フランスのNGO・ ATTAC
はじめ世界中の市民あげての一大反対運動が盛り上がったからです。1997年のことでした。日本から声を上げたのは「市民フォーラム2001」
というNGОだけで、
いってみれば日本は“ただ乗り”の形で難を逃れたことになります。だから、今回、市民も無防備なのかも知れません。
◆MAI蘇る
このMAIの狙いがTPPに姿を変えていまに蘇った、と私は考えています。長い歴史の連続性をきちんと認識できるジャーナリストがいなくなって
しまいました。
もし今回のTPP騒動にヨーロッパが巻き込まれておれば、とっくの昔にNGОが反対運動を立ち上げ、世界中に広げていたことでしよう。
MAIの狙いはマネーにとって障壁なき「バリアフリー社会」を世界につくるということでした。協定批准国が外資に内国民待遇を与えることを
義務付けます。
重要な点を挙げますと、まず第1に、例えば日本の自治体が不況対策として地場の中小企業に制度融資などを行った場合、これを協定違反とみなしま す。
国内企業への公的支援、優遇策はすべて外資に対する差別であるとするのです。
第2は、投資に対する絶対的自由の保障で、外資に対して天然資源の取得権まで含めて投資の自由を保障する。つまり国土の切り売りを認めなさい
ということです。
今、外資による森林や水源の買収が問題になっていますが、すでに南米などでは国土を切り売りしている国もたくさんあります。
第3は、外国人投資家に相手国政府を直接、提訴できる損害賠償請求権を与えるとしたことでした。例えば地場産業育成のための公的支援を差別待遇 だと
外国人投資家が判断すれば、当該国政府を相手取って賠償を求めることができるのです。
以上は、外国資本への“逆差別”の奨励であり、徹底した外資優遇策です。その背景にウォール街の意思、マネーの企みがあること、
いうまでもありません。
13年ほど前、こういう協定が結ばれようとしていた事実を認識していただきたい。もし実現していたらどうなっていたか。いずれにせよ、
こうした長期の国際戦略を研究し、政策提言するシンクタンクは、たとえ大統領が何代変わろうとも、生き続けているのです。
今、形を変えてMAIの戦略性が息を吹き返した、それがTPPに盛り込まれた高度の戦略性です。ここを見抜かなければなりません。
関税ゼロはその一つに過ぎない。
米国の狙いは対中国戦略にもあります。中国はいまなお社会主義市場経済を名乗り、アングロサクソン型市場経済とはルールが違います。
◆協調と緊張
例えば中国には個人に土地所有権はありません。資本主義市場経済の最も重要な要素は私的所有権、つまり財産権です。その一部がないという
中国のルールを変えて完全な私的財産権を確立させる、これによって、アメリカ覇権による「グローバル・スタンダード」を世界に普遍化していく、 と。
TPPの真意の一つは中国経済への対抗力、包囲力というものを日本を巻き込んで日米共同で形成していく、これが米国の狙いの一つです。
TPP加盟予定、参加表明国も含めた環太平洋9カ国の合計GDPの95%が日米二国で占められています。実質は日米FTAといわれるのも、
その故ですが、FTAなどとは比較にならないほど、重大なアメリカの対アジア戦略がTPPには込められています。
その一つが、いまいいました対中国戦略です。
中国はEUとFTAを結び、むろんアジアでも覇権を確立しようとしています。ルールの違うものが大変な勢いで伸びていることに米国が
脅威を感じないはずはありません。
軍事的にはもちろん、経済的にも米中間には協調と緊張の両側面があり、米国のシンクタンクはこれを両立させていくために、
“協調的対決”あるいは“対決型協調”をもって、世界に広がっていく中国の勢いを喰い止めようと政策提言を重ねてきました。
米国の多国籍企業、超国家企業にとって中国市場こそは人口規模の大きさ、今後の成長力からして、まさに舌なめずりしたい利益機会です。
しかし、他方で戦略的緊張関係は増大する。この二律背反のなか、米中のルールの調整が大きなテーマになってきました。
どちらのルール(法的・経済的諸制度)に合わせるのか。むろんのこと、アングロ・サクソン型ルールへの呑み込み(吸収的等質化)をはかること が、
アメリカの長期の戦略なのであり、その目的の実現に向けてあらゆる手法を採ろうとするでしょう。
イラク攻撃ではアメリカは対テロ戦という大義を掲げましたが、その真意がイスラム社会のルールを変えさせることにあったことが、
いまや歴史的にも明らかにされてきました。イスラム世界でも中国の土地と同じように財産権の概念が薄い。アングロ・サクソン型資本主義市場経済の
基礎的条件である「私的財産権の絶対化」というインフラは、こと少なくとも正統なイスラム圏には存在しない。
◆マネーの意思
イスラムでは「正当な労働の報酬以外は受け取ってはならない」という戒律があります。当然ながら「利が利を生むマネー」を正当化したり、
壮大な不労所得を是認したり、というマネー資本主義は、少なくとも正面玄関から入っていくことはできません。利子を取らないイスラム銀行が世界中 で
伸びています。マネー資本主義にとってこれは大きな障壁です。マネーは運動できる場の領域が広ければ広いほど、利が利を呼び、高い蓄積を可能にす る。
こうしたマネーの意思はイラク・アタックのさなか、各所で実現に向けて展開されていたことが、いま明らかになってきました。世界のNGOが
伝えています。
たとえば米軍がバグダッドを攻めた時、彼らの戦車は汚水を飲み水に浄化できる「逆浸透膜」という精緻な技術の浄化装置を積み込んで進みました。
バクダッドの南、ウムカスルスという街に米軍の部隊が入ったとき、その街では米空軍の猛爆のため水道水はじめほとんどのインフラが破壊されてい て、
住民は飲み水にもこと欠き、渇(かつ)えていた。やってきた米軍は真っ先に何をするか、それを現地にとどまったNGOが逐一、見届けた。
米軍はまずその街の人びとに声をかけ、タンクローリー車の所有者を探した。給水車ですね。タンクローリーをもっている、というのは、むろんのこと
富裕層です。
名乗りを上げた富裕層に米軍は何を指示したか。「街の人びとは水に飢えているでしょう。ここに水があります。これを皆さんに無料で差し上げます。
皆さんはこれを街の人びとに与えなさい。ただし、条件がある」と。それが「代金をとって売りなさい」ということでした。つまり飲み水を「商品」と して
売らせよう、ということです。
タンクローリーの所有者たちは最初、「もらった水を売るということはイスラムの戒律からしてできない」と。しかし、目の前に喉の渇えた人びとが
たくさんいる。給水された水を代金をとって売ってみる。すると、苦労しなくてもカネは入ってくる。「あ、これはいいな」と。次第に感覚が麻痺し て、
これはいい商売だ、と。つまり市場経済の餌付けですね。
こうしたやり方はヘリテージ財団系のシンクタンクがマニュアルを作成した。レッスン1からレッスン10まで明示されている。米軍は忠実に実行し ていった。
こうして先般、米軍はイラクから撤退しましたが、その後にはかつてのイスラム世界とは違う市場化されたイラク経済が残りました。国有企業の民営化 が進み、
銀行には外資が入り、それまで禁じられていた利益の海外送金も自由になった。
こうした歴史からも明らかなように、経済的ルールの違う中国経済圏への対抗力(一面協調・他面敵対)をどう保つか、アメリカにとっては最重要の
グローバル・ポリシーです。TPPに込められた戦略性、その網のなかに日本はからめとられていくでしょう。
◆大黒柱を抜く
以上、TPP構想に込められた、これまで触れられていない、しかし重大な側面を指摘しました。TPPについてはひとまずこれくらいにして次の テーマです。
日本経済を振り返りますと、昭和30年代後半から「貿易・資本自由化」が実施に移され、モノとカネの自由化がどんどん進められました。
日米安保改定のもう一つの顔が日本市場の開放にあったことを知る人が少ないのに驚きます。小麦も大豆も粗糖も飼料用トウモロコシも、すべて自由化 の対象
として開放を迫られた。日本農業の大黒柱が、このとき、抜かれたのです。穀物すべてにわたる低い低い自給率への道が掃き清められた。
いま、最後の砦、コメが狙いであること、そして背後にアメリカの長期にわたるグローバル・ポリシーがあること。何も、景気回復に必死のオバマ政権 に
始まったことではないこと、重ねて強調しておかなければならないでしょう。
お配りした『TPP開国論を問う』に、前原発言の虚妄について具体的な数字を挙げて反論しておりますので、じっくりお読み頂ければ、と思います。
さて、いま、日本の自動車は25%以上が海外生産です。日本経済がこういう日本型多国籍企業、私は「グローバルズ」と呼んできましたが、わずか 百社ほどの
グローバルズにおんぶしておれば、国内での雇用力は衰退し、高度失業化社会に至ること、目に見えています。完全失業者350万人、雇用調整助成金 で
辛うじて保たれている雇用が199万人。そのほかに「雇用保蔵」が600万人超(GDPの需給ギャップから推計)。表に出た数字からは想像もつか ない
大量失業の現実です。
誰が日本国内における雇用を守るのか。私は「ローカルズ」と呼んでおりますが、日本列島に固着して生きる中小企業、農業、そして協同組合などを
措いてない
こと、明らかなところでしょう。国内の地域社会に密着して生きていくほかにない日本人、そして地域に固着する社会的企業です。私たちはこれからま すます
“シンク・スモール・ファースト”(小さきもの、弱きものの利益から先に考える)という、ヨーロッパでは常識の思想性を深めていかなければならな いと
思います。
私は地域社会に根ざした人間中心の経済について「人間主語の経済」、あるいは「理念型経済」と呼んできました。「市場」が主語でなく「市民」が
市場を制御する社会です。そういう社会は可能かと、多くの実例を挙げて問うてきました。
◆自覚的消費者
例えば北欧における「自覚的消費者」の積極的な育成が挙げられます。家電製品の場合、全ての商品にエネルギー・マークが貼ってある。 ABCD・・・と。
当初は価格の安い、しかし、エネルギー効率の悪いAが売れます。値段が安いから。ところが消費者のうちの自覚的な人びとが、いや、値段はやや高い けれども、
電力消費の少ない、効率的なDのほうがよい、こちらを選択すべきだ、と。すると一般の消費者もDを選ぶようになる。Dの価格の中には地球環境を守 る
コストが込められている、とそう理解して選ぶ消費者が増えていく。するとDに量産効果が出てきて、AよりDのほうが安くなる。Dが一般化していく と、
今度はさらにEという次の、もっと省エネの商品を開発する、といった具合です。そういう形で市場を市民社会的制御の下に置くわけです。
またデンマークでは一般家庭の電気代に上乗せしてグリーン料金というのが課せられる。これを出資金として風力発電を行う市民共同発電方式が大き く育った。
配電会社は市民共同方式による電力を高く買う一方、企業からは安く買う制度になっており、政策的に優遇している。市民の出資金は「グリーン証書」 という
証券となって流通していきます。
また同国は原油価格の国際相場が下がっても国内の石油製品価格は下げないという二重価格制をとったこともありました。そのようにしてオイル ショック時には
1.5%だったエネルギー自給率がいまや180%となり、実力ある電力輸出国になった。因みに同国の食料自給率は300%です。
ワイルドな資本主義、むき出しの市場原理主義、新自由主義の時代を超克していくためには、これに歯止めをかける「対抗思潮」というものを盛り上 げて
いかなければならないでしょう。そのために協同組合の力の結集、内部の革新、そして「協同の協同」(協同組合間連携)が必要なのです。
最後に「賢さをともなわない勇気は乱暴なだけであり、勇気をともなわない賢さなどはくそにもならない」というドイツの作家エーリッヒ・ケスト ナーの
言葉を紹介しておきたいと思います。ナチに弾圧されたケストナーは「賢さをともなった勇気」だけが人間社会を幸せにできる、と書き遺しました。
いま、ケストナーの言葉のなかにこそ「協同組合人」が備えるべき資質の核心が込められているのではないか、そう信じています。
こうした認識をいっそう深めるため、皆様のお手許にありますように、価値高い2本の論文が宇沢弘文先生から寄せられました。
心から御礼申し上げる次第です。
(終わり)
--
菅首相は「TPP参加」は日本の「第三の開国」に当たり「江戸幕府末期の第一の開国と同じように「鎖国状態の日本を世界に開くのだ」という説明をダボス会議で
表明しました。
菅首相の「TPP第三開国論」は歴史を真剣に学んだこともなく側近官僚や取り巻き学者の意見をそのまま受け売りした全くの「嘘」であり無知蒙昧の 典型です。
大手マスコミは今回もまた米国支配層と日本の経団連の利益のために、菅首相の「全くの嘘」を一切批判せず「TPPに参加しないと日本は世界の孤児 になる」などと
国民の無知につけ込んだ脅迫で世論操作を行っています。
菅首相が江戸幕府末期の「第一の開国」をあたかもポジティブで素晴らしいことのように言っているのは全くの間違いでなのです。
「第一の開国」は江戸幕府が欧米列強から隷従的・片務的な「不平等条約」を押し付けられて開国を強制されたものなのです。
「開国日本」は独立国家の当然の権利である関税自主権を奪われ手いました。
「開国日本」は領事裁判権を認めさせられ犯罪を犯した外国人を日本の法律で裁けない治外法権を強制されたのです。
1945年の敗戦の「第二の開国」では、米国によって「日米安保条約」という不平等軍事条約を強制され日本の国内に現在でも124の駐留米軍基地 と
毎年6000億円以上の駐留経費の負担を強いられているのです。
「第二の開国」で米国に強制された「日米地位協定」によって、犯罪を犯した米国軍人を日本の法律で裁けない治外法権状態が今でも続いているので す。
菅首相が日本の「第三の開国」を真剣に希求するのであれば、「日米安保条約」と「日米地位協定」を真っ先に破棄して日本の「独立」を図るべきなの です。
日本がTPPに参加すれば関税が撤廃されあらゆる保護規制が撤廃される結果、少数の米国と日本のグローバル企業が市場を独占し、日本の農業・林 業・漁業と
中小零細企業と地方は壊滅するでしょう。
日本がTPPに参加すれば、日本人の生活のあらゆる分野(雇用、所得、年金、医療、介護、社会福祉、家族関係など)に米国流の新自由主義=市場原 理主義が導入され、
今以上に貧富の差が拡大し分断された「大格差社会」が出現刷るでしょう。
日本がTPPに参加すれば、日本は米国の完全な植民地となるでしょう。
TPPはオバマ政権が作り出した米国による「非軍事による世界支配」の罠であり、日本は絶対に参加してはならないのです。
賢明な国民は菅首相と財界と大手マスコミの「嘘」に騙されてはいけません。
【参考記事】
▼ 異様な「TPP開国論」歴史の連続性を見抜け 内橋克人氏
2011年2月8日 内橋克人氏講演会
http://www.jacom.or.jp/tokusyu/2011/tokusyu110208-12482.php
むき出しの市場原理主義に対抗思潮を
TPPについて東京発マスコミの「開国」一辺倒論ぶりは異様なものです。例えば去年秋の日比谷での大規模な反対集会について1行も報道していませ ん
。
これに対して、地域社会に密着するジャーナリズムは違っておりまして、私が書いた『TPP開国論を問う』『市場原理主義 再び』といった反対論 を
大きく掲載しています。お手許に配ってあります資料をご覧ください(中国新聞、北海道新聞)。すでに崖っぷちに立たされている日本農業の背中をさ らに押す、
というような圧力が出てきた時、中央紙とはまるで違う対応をする。それがコミュニティ・ペーパーの特徴でもあるでしょう。
ともあれ、いまやTPPをめぐって「国論二分」の状況になってきました。
協同組合の中にもいまだTPPに関して態度を決めかねている方がいます。「まだ情報を収集中」などという、ある協同組合トップの方に私は率直に
「情報が集まった時にはもう手遅れですよ」と申し上げた。
菅直人首相は歴史上、幕末・明治を第一の開国、あたかも輝かしい開国であったかのごとく信じているようですが、蒙昧とはこのことをいうのでしょ う。
第一の開国こそは欧米列強への隷従的・片務的な「不平等条約」でした。相手国は一方的に関税を決め、日本は独立国家の当然の権利である関税自主権 さえ
奪われた。それから領事裁判権という名のもと、犯罪を犯した外国人を日本の法律で裁けない治外法権も強制されました。対等な関係における日本の 「開国」が
やっと実現したのは、第一の開国から60数年も経った第1次大戦後のことです。近代日本がいかに苦悶を迫られたか、それを菅氏はご存じない。
「開国」という「政治ことば」に秘められた大きな企みが人々を間違った方向へ導いていく。「規制緩和」「構造改革」がそうでした。
これに反対するものは「守旧派」と呼び、少数派として排除しましたが、今回も同じ構図です。「改革」とか「開国」とか、一見、ポジティブな響き の、
前向きの言葉の裏に潜む「政治ことば」の罠、その暗闇に目を注ぎながら言葉の真意を見抜いていかなければなりません。
「国を開く」などといいますが、その行き着くところ、実質はまさに「国を明け渡す」に等しい。「城を明け渡す」とは落城のことです。
光り輝く近代化というイメージ、その実態は?と問わなければなりません。「第一の開国」についての詳細はお手許の資料に詳述してあります。
◆“四つの異様”
TPPにつきまして事情はすでにご存じの通りです。シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイといった4カ国に始まる多国間協定への経 緯、
またこれにアメリカ、カナダなどが参加表明するに至ったそもそもの理由など、基礎的、常識的な事情は省略いたしまして、なぜいまアメリカは
「米主導のアジア圏」形成に向けて動き出したのか。TPPにかけるアメリカのしたたかな戦略性ということについて、考えを述べたいと思います。
昨年10月、米国際戦略問題研究所(CSIS)と日本経済新聞社共催のシンポジウムで前原誠司外相は「(日本の第1次産業の割合は)1.5%。
そのために(これを守るために)残り98.5%が犠牲になっている」と発言しました。場所も内容も不適切です。が、これを問題にするジャーナリズ ムは
皆無でした。
私はこれを「三つの異様」と呼び、第一に菅首相の開国論の異様、第二に前原発言の異様、そして第三に新聞・メディアの異様、
三つを揃えて批判の論拠を書きました。こうしたあり方になびく日本社会全体の異様、これを含みますと「四つの異様」となります。
ところで、CSISとはいったい何を研究するシンクタンクなのか。ワシントンのジョージタウン大学のなかにある。1960年代から長期間、
アメリカの世界戦略に携わってきたこのシンクタンクをめぐっては、さまざまな説がありますが、今日はその部分は控えておきましょう。
前原氏はこの機関と日本の大手マスコミとの共催シンポジウムの場で30分ほどの基調講演をし、そのなかで先程のような発言をした。
アメリカにとってはまさに「舌なめずり」したくなるような言葉です。
1990年代半ば、「多国間投資協定」(MAI)をめぐる大きな騒動がありました。
米国のクリントン政権がこの協定を“21 世紀における世界経済の憲法”とまで称して、多国間で資本、マネーに関する協定を結ぼうと
画策していたのです。
市民、NGOが気付いたときには、すでに、通商交渉に関して議会の承認なく大統領の一存ですべてを決めることのできる「ファストトラック」
という手続き開始の直前。物事は進んでおりました。
以後、全世界1000を超えるNGОが猛烈な反対運動を展開して結局、クリントン大統領は構想の撤回に追い込まれた。フランスのNGO・ ATTAC
はじめ世界中の市民あげての一大反対運動が盛り上がったからです。1997年のことでした。日本から声を上げたのは「市民フォーラム2001」
というNGОだけで、
いってみれば日本は“ただ乗り”の形で難を逃れたことになります。だから、今回、市民も無防備なのかも知れません。
◆MAI蘇る
このMAIの狙いがTPPに姿を変えていまに蘇った、と私は考えています。長い歴史の連続性をきちんと認識できるジャーナリストがいなくなって
しまいました。
もし今回のTPP騒動にヨーロッパが巻き込まれておれば、とっくの昔にNGОが反対運動を立ち上げ、世界中に広げていたことでしよう。
MAIの狙いはマネーにとって障壁なき「バリアフリー社会」を世界につくるということでした。協定批准国が外資に内国民待遇を与えることを
義務付けます。
重要な点を挙げますと、まず第1に、例えば日本の自治体が不況対策として地場の中小企業に制度融資などを行った場合、これを協定違反とみなしま す。
国内企業への公的支援、優遇策はすべて外資に対する差別であるとするのです。
第2は、投資に対する絶対的自由の保障で、外資に対して天然資源の取得権まで含めて投資の自由を保障する。つまり国土の切り売りを認めなさい
ということです。
今、外資による森林や水源の買収が問題になっていますが、すでに南米などでは国土を切り売りしている国もたくさんあります。
第3は、外国人投資家に相手国政府を直接、提訴できる損害賠償請求権を与えるとしたことでした。例えば地場産業育成のための公的支援を差別待遇 だと
外国人投資家が判断すれば、当該国政府を相手取って賠償を求めることができるのです。
以上は、外国資本への“逆差別”の奨励であり、徹底した外資優遇策です。その背景にウォール街の意思、マネーの企みがあること、
いうまでもありません。
13年ほど前、こういう協定が結ばれようとしていた事実を認識していただきたい。もし実現していたらどうなっていたか。いずれにせよ、
こうした長期の国際戦略を研究し、政策提言するシンクタンクは、たとえ大統領が何代変わろうとも、生き続けているのです。
今、形を変えてMAIの戦略性が息を吹き返した、それがTPPに盛り込まれた高度の戦略性です。ここを見抜かなければなりません。
関税ゼロはその一つに過ぎない。
米国の狙いは対中国戦略にもあります。中国はいまなお社会主義市場経済を名乗り、アングロサクソン型市場経済とはルールが違います。
◆協調と緊張
例えば中国には個人に土地所有権はありません。資本主義市場経済の最も重要な要素は私的所有権、つまり財産権です。その一部がないという
中国のルールを変えて完全な私的財産権を確立させる、これによって、アメリカ覇権による「グローバル・スタンダード」を世界に普遍化していく、 と。
TPPの真意の一つは中国経済への対抗力、包囲力というものを日本を巻き込んで日米共同で形成していく、これが米国の狙いの一つです。
TPP加盟予定、参加表明国も含めた環太平洋9カ国の合計GDPの95%が日米二国で占められています。実質は日米FTAといわれるのも、
その故ですが、FTAなどとは比較にならないほど、重大なアメリカの対アジア戦略がTPPには込められています。
その一つが、いまいいました対中国戦略です。
中国はEUとFTAを結び、むろんアジアでも覇権を確立しようとしています。ルールの違うものが大変な勢いで伸びていることに米国が
脅威を感じないはずはありません。
軍事的にはもちろん、経済的にも米中間には協調と緊張の両側面があり、米国のシンクタンクはこれを両立させていくために、
“協調的対決”あるいは“対決型協調”をもって、世界に広がっていく中国の勢いを喰い止めようと政策提言を重ねてきました。
米国の多国籍企業、超国家企業にとって中国市場こそは人口規模の大きさ、今後の成長力からして、まさに舌なめずりしたい利益機会です。
しかし、他方で戦略的緊張関係は増大する。この二律背反のなか、米中のルールの調整が大きなテーマになってきました。
どちらのルール(法的・経済的諸制度)に合わせるのか。むろんのこと、アングロ・サクソン型ルールへの呑み込み(吸収的等質化)をはかること が、
アメリカの長期の戦略なのであり、その目的の実現に向けてあらゆる手法を採ろうとするでしょう。
イラク攻撃ではアメリカは対テロ戦という大義を掲げましたが、その真意がイスラム社会のルールを変えさせることにあったことが、
いまや歴史的にも明らかにされてきました。イスラム世界でも中国の土地と同じように財産権の概念が薄い。アングロ・サクソン型資本主義市場経済の
基礎的条件である「私的財産権の絶対化」というインフラは、こと少なくとも正統なイスラム圏には存在しない。
◆マネーの意思
イスラムでは「正当な労働の報酬以外は受け取ってはならない」という戒律があります。当然ながら「利が利を生むマネー」を正当化したり、
壮大な不労所得を是認したり、というマネー資本主義は、少なくとも正面玄関から入っていくことはできません。利子を取らないイスラム銀行が世界中 で
伸びています。マネー資本主義にとってこれは大きな障壁です。マネーは運動できる場の領域が広ければ広いほど、利が利を呼び、高い蓄積を可能にす る。
こうしたマネーの意思はイラク・アタックのさなか、各所で実現に向けて展開されていたことが、いま明らかになってきました。世界のNGOが
伝えています。
たとえば米軍がバグダッドを攻めた時、彼らの戦車は汚水を飲み水に浄化できる「逆浸透膜」という精緻な技術の浄化装置を積み込んで進みました。
バクダッドの南、ウムカスルスという街に米軍の部隊が入ったとき、その街では米空軍の猛爆のため水道水はじめほとんどのインフラが破壊されてい て、
住民は飲み水にもこと欠き、渇(かつ)えていた。やってきた米軍は真っ先に何をするか、それを現地にとどまったNGOが逐一、見届けた。
米軍はまずその街の人びとに声をかけ、タンクローリー車の所有者を探した。給水車ですね。タンクローリーをもっている、というのは、むろんのこと
富裕層です。
名乗りを上げた富裕層に米軍は何を指示したか。「街の人びとは水に飢えているでしょう。ここに水があります。これを皆さんに無料で差し上げます。
皆さんはこれを街の人びとに与えなさい。ただし、条件がある」と。それが「代金をとって売りなさい」ということでした。つまり飲み水を「商品」と して
売らせよう、ということです。
タンクローリーの所有者たちは最初、「もらった水を売るということはイスラムの戒律からしてできない」と。しかし、目の前に喉の渇えた人びとが
たくさんいる。給水された水を代金をとって売ってみる。すると、苦労しなくてもカネは入ってくる。「あ、これはいいな」と。次第に感覚が麻痺し て、
これはいい商売だ、と。つまり市場経済の餌付けですね。
こうしたやり方はヘリテージ財団系のシンクタンクがマニュアルを作成した。レッスン1からレッスン10まで明示されている。米軍は忠実に実行し ていった。
こうして先般、米軍はイラクから撤退しましたが、その後にはかつてのイスラム世界とは違う市場化されたイラク経済が残りました。国有企業の民営化 が進み、
銀行には外資が入り、それまで禁じられていた利益の海外送金も自由になった。
こうした歴史からも明らかなように、経済的ルールの違う中国経済圏への対抗力(一面協調・他面敵対)をどう保つか、アメリカにとっては最重要の
グローバル・ポリシーです。TPPに込められた戦略性、その網のなかに日本はからめとられていくでしょう。
◆大黒柱を抜く
以上、TPP構想に込められた、これまで触れられていない、しかし重大な側面を指摘しました。TPPについてはひとまずこれくらいにして次の テーマです。
日本経済を振り返りますと、昭和30年代後半から「貿易・資本自由化」が実施に移され、モノとカネの自由化がどんどん進められました。
日米安保改定のもう一つの顔が日本市場の開放にあったことを知る人が少ないのに驚きます。小麦も大豆も粗糖も飼料用トウモロコシも、すべて自由化 の対象
として開放を迫られた。日本農業の大黒柱が、このとき、抜かれたのです。穀物すべてにわたる低い低い自給率への道が掃き清められた。
いま、最後の砦、コメが狙いであること、そして背後にアメリカの長期にわたるグローバル・ポリシーがあること。何も、景気回復に必死のオバマ政権 に
始まったことではないこと、重ねて強調しておかなければならないでしょう。
お配りした『TPP開国論を問う』に、前原発言の虚妄について具体的な数字を挙げて反論しておりますので、じっくりお読み頂ければ、と思います。
さて、いま、日本の自動車は25%以上が海外生産です。日本経済がこういう日本型多国籍企業、私は「グローバルズ」と呼んできましたが、わずか 百社ほどの
グローバルズにおんぶしておれば、国内での雇用力は衰退し、高度失業化社会に至ること、目に見えています。完全失業者350万人、雇用調整助成金 で
辛うじて保たれている雇用が199万人。そのほかに「雇用保蔵」が600万人超(GDPの需給ギャップから推計)。表に出た数字からは想像もつか ない
大量失業の現実です。
誰が日本国内における雇用を守るのか。私は「ローカルズ」と呼んでおりますが、日本列島に固着して生きる中小企業、農業、そして協同組合などを
措いてない
こと、明らかなところでしょう。国内の地域社会に密着して生きていくほかにない日本人、そして地域に固着する社会的企業です。私たちはこれからま すます
“シンク・スモール・ファースト”(小さきもの、弱きものの利益から先に考える)という、ヨーロッパでは常識の思想性を深めていかなければならな いと
思います。
私は地域社会に根ざした人間中心の経済について「人間主語の経済」、あるいは「理念型経済」と呼んできました。「市場」が主語でなく「市民」が
市場を制御する社会です。そういう社会は可能かと、多くの実例を挙げて問うてきました。
◆自覚的消費者
例えば北欧における「自覚的消費者」の積極的な育成が挙げられます。家電製品の場合、全ての商品にエネルギー・マークが貼ってある。 ABCD・・・と。
当初は価格の安い、しかし、エネルギー効率の悪いAが売れます。値段が安いから。ところが消費者のうちの自覚的な人びとが、いや、値段はやや高い けれども、
電力消費の少ない、効率的なDのほうがよい、こちらを選択すべきだ、と。すると一般の消費者もDを選ぶようになる。Dの価格の中には地球環境を守 る
コストが込められている、とそう理解して選ぶ消費者が増えていく。するとDに量産効果が出てきて、AよりDのほうが安くなる。Dが一般化していく と、
今度はさらにEという次の、もっと省エネの商品を開発する、といった具合です。そういう形で市場を市民社会的制御の下に置くわけです。
またデンマークでは一般家庭の電気代に上乗せしてグリーン料金というのが課せられる。これを出資金として風力発電を行う市民共同発電方式が大き く育った。
配電会社は市民共同方式による電力を高く買う一方、企業からは安く買う制度になっており、政策的に優遇している。市民の出資金は「グリーン証書」 という
証券となって流通していきます。
また同国は原油価格の国際相場が下がっても国内の石油製品価格は下げないという二重価格制をとったこともありました。そのようにしてオイル ショック時には
1.5%だったエネルギー自給率がいまや180%となり、実力ある電力輸出国になった。因みに同国の食料自給率は300%です。
ワイルドな資本主義、むき出しの市場原理主義、新自由主義の時代を超克していくためには、これに歯止めをかける「対抗思潮」というものを盛り上 げて
いかなければならないでしょう。そのために協同組合の力の結集、内部の革新、そして「協同の協同」(協同組合間連携)が必要なのです。
最後に「賢さをともなわない勇気は乱暴なだけであり、勇気をともなわない賢さなどはくそにもならない」というドイツの作家エーリッヒ・ケスト ナーの
言葉を紹介しておきたいと思います。ナチに弾圧されたケストナーは「賢さをともなった勇気」だけが人間社会を幸せにできる、と書き遺しました。
いま、ケストナーの言葉のなかにこそ「協同組合人」が備えるべき資質の核心が込められているのではないか、そう信じています。
こうした認識をいっそう深めるため、皆様のお手許にありますように、価値高い2本の論文が宇沢弘文先生から寄せられました。
心から御礼申し上げる次第です。
(終わり)
--