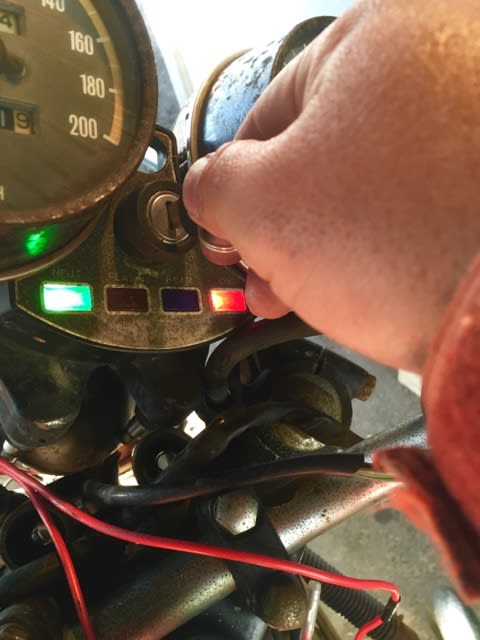新品のICレギュレーターを取り付けたところ、
チャージランプが消灯せず充電されなくなった650RS。
なんと、
ozakiの配線ミスでした。
ショボーン(。-_-。)
プラス→赤
黒→黒
黄色→黄色
緑→空色
だと思い込んでいました。
遠い目( ̄◇ ̄;)
配線図を再度確認して
ちゃんと配線し直しました。

左のピカピカ銀色が新品レギュレーター。
右の色褪せた金色が純正当時物レギュレーター。
黄色→緑へ
空色→黄色へ繋ぎます…

黄色→黄色じゃないよ。
思い込み厳禁で‼︎
エンジン始動。

あれ?やっぱり消えません。
いえいえ。
エンジンの回転を上げると消灯して、正常に充電されていることを確認しました。
やっぱりozakiの配線ミスでした。
♪───O(≧∇≦)O────♪
そしてまた再び、
純正当時物レギュレーターに繋いでみました。

ビシッと消えます。900回転。
新品。

んー。
消えそで、消えないよ。
んと。
1100回転で、消えます。
ん~と。
とりあえず、
やっぱり、
古いのを使おうと。
♪( ´θ`)ノ
ですよね!
交換は、壊れてからでも遅くない。
それにしても、
43年前の電子機械、
純正当時物レギュレーター。
ザ・昭和。
made in NIPPON
デキる奴です。
まだまだ働く43歳。
凄いね!
チャージランプが消灯せず充電されなくなった650RS。
なんと、
ozakiの配線ミスでした。
ショボーン(。-_-。)
プラス→赤
黒→黒
黄色→黄色
緑→空色
だと思い込んでいました。
遠い目( ̄◇ ̄;)
配線図を再度確認して
ちゃんと配線し直しました。

左のピカピカ銀色が新品レギュレーター。
右の色褪せた金色が純正当時物レギュレーター。
黄色→緑へ
空色→黄色へ繋ぎます…

黄色→黄色じゃないよ。
思い込み厳禁で‼︎
エンジン始動。

あれ?やっぱり消えません。
いえいえ。
エンジンの回転を上げると消灯して、正常に充電されていることを確認しました。
やっぱりozakiの配線ミスでした。
♪───O(≧∇≦)O────♪
そしてまた再び、
純正当時物レギュレーターに繋いでみました。

ビシッと消えます。900回転。
新品。

んー。
消えそで、消えないよ。
んと。
1100回転で、消えます。
ん~と。
とりあえず、
やっぱり、
古いのを使おうと。
♪( ´θ`)ノ
ですよね!
交換は、壊れてからでも遅くない。
それにしても、
43年前の電子機械、
純正当時物レギュレーター。
ザ・昭和。
made in NIPPON
デキる奴です。
まだまだ働く43歳。
凄いね!