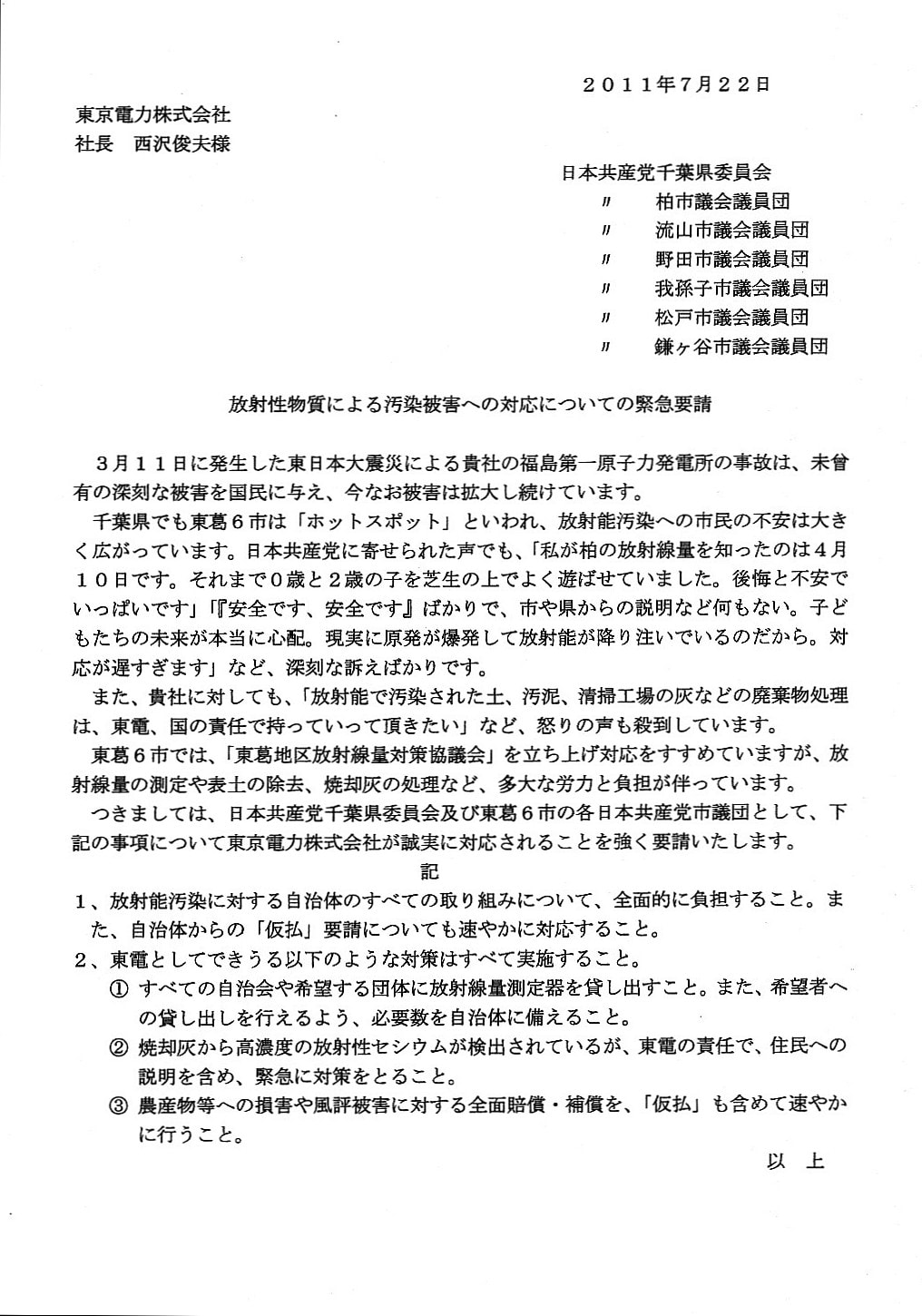「松戸の未来を取り戻す会」(通称:MMT)のブログはこちらです。
松戸市の放射線レベルのライブ配信はこちらです。
測定結果地図へのリンクを変更しました。こちらをご覧下さい。
これはgooglemapに各自治体が公表した測定値をプロットしたもののようです。(私が作成したものではありません)
今日は、市立病院問題で県の担当課と懇談しました。

事前にいくつかの質問を提出しておき、それに対する回答もいただきました。
現在、東葛北部医療圏では9600床の基準病床数(必要数)に対して現有9052床と、548床のベッド不足の状態であり、この基準病床数は高齢化にともなって増加傾向にあるとのことです。
その東葛北部医療圏にあって中核的な役割を担う松戸市立病院は、第三次救急、地域がん連携拠点病院、災害拠点病院などの機能に加え、小児救急、周産期医療などの機能を有し、県としても非常に重要な役割をもった病院であるという認識が示されました。
市長が推奨した構想案6および7(8も含む)では、新病院の病床数は450床に減少させるとしていますが、松戸市立病院と同レベルの機能を有する千葉大学医学部付属病院が835床、旭中央病院が956床であることを考えると、松戸市立病院の613床という病床数を450床に減少させることは、現在の病院機能を維持することが困難となることは明白です。
一部の市長派議員が、「金がかかりすぎるから、身の丈にあった病院を」という主張をしていますが、市長の推奨する450床の「超急性期病院」は、入院期間を極端に短く(現在の14日程度→9日前後に)して患者の回転を上げ、「超急性期」・・・すなわち「死ぬか生きるかの瀬戸際」の人たちのための専門医集団の病院をつくるという構想です。
市民が気軽にかかることができない「超急性期病院」の、いったいどこが「身の丈にあった病院」なのか・・・大いに疑問です。
もちろん「お金は可能な限り安く」というのは基本です。前回の特別委員会では、「構想1~5についても、工夫をすれば安くすることができる」という考えが、市長の方から示されています。
また今日は県の担当者に対しても、「県の保健医療計画では、9600床の必要ベッド数に対して、548床も不足している。松戸市立病院では建設費を安くするためにベッド数を減らそうという案が市長から出され、これでは現在の病院機能が維持できなくなる可能性がある」「必要な病床数を確保するため、そして松戸市立病院の重要な医療機能を維持するためにも、建設費の補助を増額するなど特別な配慮はあって然るべきではないか」という指摘をしました。
・・・詳しいことは8月7日に開催されるシンポジウム「どうする市立病院建替え」でも示されると思います。ぜひこちらもご参加下さい。
とき:8月7日(日)14:00~
ところ:松戸市民劇場ホール
市内在住の方で「ご自宅」を測定希望の方がおられましたら、時間のあるときにですが出張測定しますので、ご希望の日時(複数候補)とご連絡先を明記してメールをお送り下さい。(ご希望に添えない場合があるかも知れませんが、その際はご容赦下さい)
*****
松戸市の放射線レベルのライブ配信はこちらです。
*****
測定結果地図へのリンクを変更しました。こちらをご覧下さい。
これはgooglemapに各自治体が公表した測定値をプロットしたもののようです。(私が作成したものではありません)
*****
今日は、市立病院問題で県の担当課と懇談しました。

事前にいくつかの質問を提出しておき、それに対する回答もいただきました。
現在、東葛北部医療圏では9600床の基準病床数(必要数)に対して現有9052床と、548床のベッド不足の状態であり、この基準病床数は高齢化にともなって増加傾向にあるとのことです。
その東葛北部医療圏にあって中核的な役割を担う松戸市立病院は、第三次救急、地域がん連携拠点病院、災害拠点病院などの機能に加え、小児救急、周産期医療などの機能を有し、県としても非常に重要な役割をもった病院であるという認識が示されました。
市長が推奨した構想案6および7(8も含む)では、新病院の病床数は450床に減少させるとしていますが、松戸市立病院と同レベルの機能を有する千葉大学医学部付属病院が835床、旭中央病院が956床であることを考えると、松戸市立病院の613床という病床数を450床に減少させることは、現在の病院機能を維持することが困難となることは明白です。
一部の市長派議員が、「金がかかりすぎるから、身の丈にあった病院を」という主張をしていますが、市長の推奨する450床の「超急性期病院」は、入院期間を極端に短く(現在の14日程度→9日前後に)して患者の回転を上げ、「超急性期」・・・すなわち「死ぬか生きるかの瀬戸際」の人たちのための専門医集団の病院をつくるという構想です。
市民が気軽にかかることができない「超急性期病院」の、いったいどこが「身の丈にあった病院」なのか・・・大いに疑問です。
もちろん「お金は可能な限り安く」というのは基本です。前回の特別委員会では、「構想1~5についても、工夫をすれば安くすることができる」という考えが、市長の方から示されています。
また今日は県の担当者に対しても、「県の保健医療計画では、9600床の必要ベッド数に対して、548床も不足している。松戸市立病院では建設費を安くするためにベッド数を減らそうという案が市長から出され、これでは現在の病院機能が維持できなくなる可能性がある」「必要な病床数を確保するため、そして松戸市立病院の重要な医療機能を維持するためにも、建設費の補助を増額するなど特別な配慮はあって然るべきではないか」という指摘をしました。
・・・詳しいことは8月7日に開催されるシンポジウム「どうする市立病院建替え」でも示されると思います。ぜひこちらもご参加下さい。
とき:8月7日(日)14:00~
ところ:松戸市民劇場ホール
*****
市内在住の方で「ご自宅」を測定希望の方がおられましたら、時間のあるときにですが出張測定しますので、ご希望の日時(複数候補)とご連絡先を明記してメールをお送り下さい。(ご希望に添えない場合があるかも知れませんが、その際はご容赦下さい)